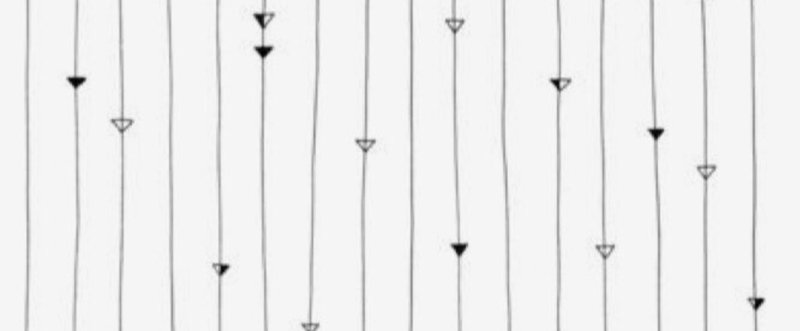
0.3ミリ
タナベ君はいつも、うぐいす色の細長い筆箱からシャープペン、消しゴム、付箋、蛍光ペン、定規、シャープペンの芯。必ずその順番で物を机に置く。
無意識のものなのか、高校入試に向けての願掛けなのかは分からないけれど、私の知る限りではずっとこの順番だった。それに気づいたのは一か月ほど前のことで、塾の席替えで私の席がタナベ君の左斜め後ろになったからだった。できることなら本当は隣の席が良かったのだけれど、斜め後ろの方が相手にも周りにも気づかれずに、こっそりとナタベ君を観察できるからこれはこれで良かったのかもしれない。
といっても私はタナベ君のことをよく知らない。
タナベ君は他校の生徒で、名前はユウタという。
目が合ったことぐらいはあるけれど、その他のことはよくわからない。
知っているのは筆箱から文房具を取り出す順番と、あまり主流ではない0.3ミリのシャープペンを使っていること。塾に持ってくるリュックは登山系のアウトドアブランドでセンスがいいこと。授業中は決してあくびをしないこと。読んでいる本はいつもハードカバーがかけられていること。後ろから見る彼のつむじが白いこと。帰りは一人で歩いて帰り、傘を忘れたのであろう雨の日はそのまま濡れて帰ること。黒板の小さな文字が見えない時はメガネをかけること。
少し注意して見ていれば誰でも気づいてしまうような、そんなことばかりだった。
通っている塾がたまたま同じだというだけで、共通の友人も居ない。話すきっかけなんて到底思いつかなかった。私は異性に積極的に話かける方でもないし、それはきっとタナベ君も同じだと思う。
まず彼が他の誰かとおしゃべりしているところを私は見たことがなかった。先生とテキストのことについて話しているところは何度か見かけたことがあるけれど、同じ中学であろう男の子とも顔すら知らない他人のような立ち振る舞いで過ごしている。でも「イジメ」や「シカト」といった陰湿で暗い雰囲気は感じられなかった。
ただそういう風になっているだけのように感じる。特別なきっかけもなく、空気のように流れでそうなってしまったのかもしれない。
これは私の知っているタナベ君の情報の一つなのだけれど、彼は授業のある日、誰よりも早く塾の教室に来て自分の席に座っている。そして静かに、本を読んだりテキストを解いて時間をつぶしている。お金を出して塾に通っているのだから当たり前なのだけれど、そうすることで話しかけるなと、周りに壁を作っているようにも見える。けれど、参考書を見つめて、張りつめたような、力のこもっている横顔を見ると少しだけ胸が痛くなる。
どうにかしてあげたいなとすら思ってしまう。
そのことを私は友人のチエに相談することにした。
いや、相談と言ったら少し大げさになってしまう。ただなんとなく、会話の隙間を埋めるために「気になる男子が居るんだよね」とチエに言葉をこぼしたのがきっかけだった。
タナベ君のことでそこまで真剣に悩んでいるわけではなかったけれど、少なからずここ最近の私の頭の片隅にはタナベ君が居て、日を追うごとに成長しているのが感じられた。
それに同じ塾に通う友人よりも、塾とは無関係のチエの方が話やすいと思ったのもある。
「それって恋っていうより、なんていうか」
うーん。と、そこでチエは言葉を詰まらせ、大げさに腕を組んだ。
もう部活を引退しているというのに、黒くすすけたエナメルバックをいつも肩から下げている。部の後輩からもらったのであろう手作りのフェルトのキーホルダーが彼女と一緒に跳ねるように揺れている。
ハンドボール部を引退したチエは、地元の私立高校にスポーツ推薦が決まっている。受験勉強に取り組んでいる他の部員にもかまってもらえず、毎日のように打ち込んでいた部活の時間がすっぽりとなくなったのもあいまって、暇を持て余しているように見えた。
頭で考えるよりも先に身体が動いてしまう古典的な体育会系のチエに相談を持ち掛けるのは少しためらわれたけれど、ほどよい刺激だったのか思いのほか私の話に食いついてきた。そしていま熱心に頭を抱えている。何事にも全力で答えてくれるのがチエの一番いいところだと思う。
「恋っていうより、なによ?」
うなり続けているチエに視線を投げかける。少し間を置いてから彼女は、はっとしたように顔を上げた。
「保護者っぽいよね!」
組んでいた腕を風を切るほどの勢いで解きながら、チエはそう言ったのだ。屈託のない眩しい笑顔には自信が満ち溢れているようだった。
「え!そうなの!?この胸の痛みは保護者目線から来ているものなの?」
「絶対そうだよ!だって女の子が恋をするのは、相手に何かしらの魅力を感じているからでしょ?今のノドカの話だと、息子が心配なお母さんみたいだよ。ワタナベ君だっけ?ん?まぁ、名前はいいや。とりあえずその人の魅力が全く感じられないんだよね」
「ワタナベ君じゃなくて、タナベ君、ね。いやいや彼にだって魅力の一つや二つあるはずだよ。たぶんだけど」
「えー例えば?」
チエは首をかしげながらまっすぐに私を見つめてきた。
私はその視線から逃れるように、顔を上へそらした。並木通りのイチョウはもうすっかり葉がなくなっている。枝がてのひらのような形で青い空に向かって伸びていた。その隙間に秋と冬が混ざり合ったような風が吹いている。
タナベ君は今頃何をしているのだろうと、そんなことを思った。
「うーん。まぁ特に思いつかないんだけどね」
少しだけ考えを巡らせたあと、笑いながら言うとチエは大きな目をくるりと回して深呼吸のようなため息をついた。
「ノドカは優しいから、独りぼっちの彼が気にかかるだけなんだよ」
チエはそういうけれど、私は決して特別に優しいわけではない。
負の物をあしらうのが人より自然に見えるだけであって、困っている人を見境なく助けたいとは思わない。興味がなかったり、自分では手に負えないと感じたら、気づいていない振りをすればいいのだ。知らんぷり、見ない振り、人に悟られないように、うまく表に出さずにしまい込む。それは優しさとはまったく別物のはずだ。
私はタナベ君を独りぼっちから助けたいわけでも、ましてやタナベ君の彼女になりたいわけでもない。
なんとなく気になって、なんとなくそれがタナベ君で、なんとなく偶然に異性で、そういった「なんとなく」の連鎖が今の私のもやもやに繋がっている。
もしかしたらチエの言っていることは正しいのかもしれない。
私が優しいか、優しくないのかは別として、受験勉強というただでさえ孤独な闘いの中で、タナベ君には好きな音楽の話をしたり、わからない問題を一緒に解いたり、文房具のおすすめ合いをしたりできないのかと思うと、かわいそうだと勝手に気にかけてしまうのだ。
だったらこれは「恋」なんて浮ついたものではなくて「同情」という身勝手で暴力的な迷惑行為なのかもしれない。
並木通りを過ぎ、住宅街に入ってすぐのところでチエとは別れた。彼女の家はもう少し先のところにある。
「じゃ!保護者活動頑張って!」
最後にそう言い残して、彼女は大股で歩いて行った。
保護者活動もなにも、私はタナベ君と一度も会話をしたことがないのだ。だから何も頑張れることがない。できることと言えば今までと同じで、タナベ君の机に同じ順番で置かれてゆく文房具を眺めたり、くせ毛なのか寝癖なのか分からない後ろ髪を今日はどんな形だろうかとチェックすることしかできない。
なんだか自分が非力のように思えた。
間抜けだと言ってもいいのかもしれない。
きっと受験が終わって高校に通うようになったら私はあの塾へは通わなくなる。そうすると何も残らないのだ。
タナベ君に抱いているこの感情や、発見した癖、眺めていた間のわずかばかりの幸福のような時間がないものとなってしまう。
それはとっても惜しいような気がする。
そして、気が付いたら私は0.3ミリ芯のシャープペンを買っていた。
塾の教室のドアを開けるとタナベ君が居た。まだ授業までは1時間ほど時間がある。他の生徒はまだ誰も来ていないようだった。
タナベ君はいつものように席に座っていた。私がドアを開けた時、目が合ったけれど、特に挨拶するわけでもなく視線は参考書に移されてしまった。
私は自分の席に座り、そして誰も見ていないのに筆箱の中にシャープペンの芯が入っていない演技のようなものを丁寧にした後、席を立って斜め向かいに座るタナベ君の背後にそろそろと近づいて行った。
「あぁ!それ!0.3ミリのシャープペン!よかったぁ、芯持ってる?」
タナベ君は十分すぎる間のあと、機敏な動きで顔を向けて私のことをじっと見つめた。
血が頭に集中してゆくのが分かる。少しわざとらしかったかもしれない。「あぁ!それ!」だなんて、シャーペンの芯一つで大袈裟にもほどがある。もう少し自然に話かければよかった。
もうこのまま立ち去ってしまおう。
「ごめんなさい」
そう言いかけた時、タナベ君の手が上がった。彼はその手でタナベ君自身を指した。
「自分に話かけたの?」
というようなジェスチャーだった。目は驚いたように見開かれていた。
緊張しながら私はすぐに頷いた。
タナベ君は一度大きな瞬きをして、視線を下げた。
長い睫毛が頬に影を落としている。
細長い指先がやけにゆっくりと動いているように見えた。
あのうぐいす色のペンケースの中からシャープペンの芯が取り出される。
少しの振動で折れてしまいそうなほどの線が、蛍光灯を反射させて銀色に光っている。
まるで繊細な植物を渡すような仕草で彼は私にそれを差し出した。
口元には笑みが浮かんでいた。
しっとりとした落ち着きのある表情の変化に、目が離せない。
「恋」とは言い切れない不思議な感情の延長線上に、タナベ君は居る。
でもなぜだろう、彼のことがとても気になってしまう。
もっと知りたいとすら思う。
あぁ、タナベ君は私とどんな声で話すのだろう。
開きかかった唇を見て、そう思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
