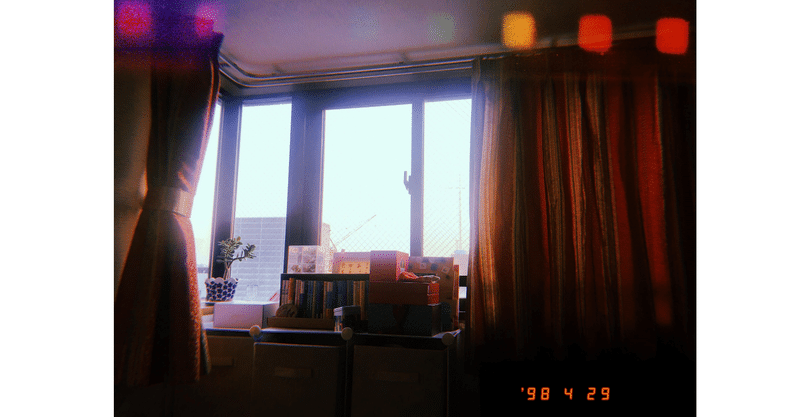
わたしの4人目のおじいちゃんー離婚再婚に苦しんだ子どもが、大人になって知ったこと
わたしにはお母さんがふたりいる。だから、お父さんのお父さん、お母さんのお父さん、お継母さんのお父さんで、おじいちゃんは3人いる。と、思っていた。しかし、おじいちゃんは4人いたらしい。
両親が離婚したのはわたしが6歳の頃のことだった。急にお母さんがいなくなり、大きなオレンジ屋根の一軒家から、お父さんとお兄ちゃんとわたしの3人でちいさなアパートに引っ越した。離婚の理由は分からなかった。現在、26歳になったわたしも、正直、よく分かっていない。本当の理由を聞くのが怖いままこの年齢まできてしまって、もはやそれはどうでもいいことに変った。
離婚理由がなにか聞かされなかったが、お父さんの再婚相手であるお継母さんは、ヒステリックを起すとあらゆる角度から暴言を繰り出し、「お前の母親は不倫した!」だの「お金を持ち出して遊びほうけた!」だの言っていた。それがどういうことか、まだ幼かったわたしには1ミリも理解できなかったが、悪意をもって放たれていることは子ども心に理解ができていた。「とても悪いことをしたんだろう」と感じていた。そして、お継母さんは「あんな女の子どもだから、あなたも同じことをする」と何度も何度も叫んだ。
「同じ血が流れている」からそうなるという理論。血。お継母さんはお父さんの親族たちのことも心底嫌っていて、わたしに流れる全部の血が憎くて堪らなかったんだろう。自分の皮膚の下を流れる液体によって、なぜこんな仕打ちをうけるのか到底理解できやしなかった。ただじっと耐えながら、「いつかこんな家から抜け出してやる」という思いを胸の内でぐつぐつと滾らせていた。
中学生に上がっても、暴言は続いた。ある日、こんなことを言われた。「あんたは結婚したって幸せになれない。お前の母親が離婚したのは、その母親も離婚しているからだ!」と。「そいう血なんだ!」と。何年も何年も繰り返される言葉の暴力に、わたしはすっかり自分を空っぽの人形にしてしまう術を覚えていたが、その言葉には引っ掛かった。お母さんのお母さん、つまりおばあちゃんは、離婚していないからだ。わたしはおじいちゃんを知っている。おじいちゃんの葬式にも行った。どういうこと?じゃあ、あれは誰だったの?
疑問が芽生えたまま、だけど、「黙る」ことで自分の心を保ってきたわたしがそれを解消する術はなく、「きっと継母の思い込みだ、なにかの間違いだ」と言い聞かせ、時間が過ぎていった。
大学を卒業して、ライターを志し上京したわたしは、おばあちゃんの家に転がり込むことになる。おばあちゃんと会った記憶は、両手で数えられるくらいしか持ってなかった。離婚してからお母さんとの面会は月に1回だけだったし、おばあちゃんは関東に住んでいたので年に1度会えるかどうかというレベルのつながりだった。
「おばあちゃんと暮らすって、どういう日々になるのかなあ」と、最初は不安もあった…のだろうか、いまとなってはあまりにこの生活が気に入っていて、そんな気持ちどこへやら。おばあちゃんと、その日の天気や今日のごはん、EXITの兼近(おばあちゃんはイケメンが好きで、目がとても悪いのに、兼近だけは短いCMカットでも「兼近!」と声を上げる。兼近すごい。)の話を繰り返す日々はとても穏やかだ。毎晩喧噪だらけで怯えて寝ていた子ども時代より心身ともに休まった。
毎日三食、一緒にキッチンに立ってごはんを用意する。おばあちゃんのみそ汁がめちゃくちゃ美味しくて、みそ汁はいつもおばあちゃんが担当。そしてたまに、近所の商店街にある回転寿司屋さんに行く。「わたしもう大人だし、働いているんだから」と、お金を出させてくれと申し出るが、それをおばあちゃんは毎回丁寧に断る。負い目はあるがなんだかんだ言って、甘やかされている、という感覚がここちよくて好きなわたしがいた。
上京して2か月経った頃、お腹いっぱいの帰り道。商店街に立ち並ぶ出店や、親子連れを眺めながら(この商店街は春から秋にかけて毎週ちいさなお祭りをするくらい地域が賑わっていた)おばあちゃんに合わせてのんびりゆったり歩いていた。なんの話をしていたってけな。確か、戦争で熊本に疎開したことや、新卒で福岡の商社で勤めていたことを聞いた。おばあちゃんからそんな話を聞くのははじめてで、おばあちゃんはわたしが生まれたときからおばあちゃんだけど、それ以前の長い長い歴史があるんだと改めて感じ入っていた。
「お父さんが死んじゃって、あなたのお母さんをひとり抱えて…」
「え?」
「そのあとおじいちゃんに出会って再婚して…」
「おばあちゃん!ちょっと待って。初めて聞いたんだけど…」
「あら、そう?」
おばあちゃんは遠くを見つめるようにし、変わらずのんびりと言った。「お前の母親が離婚したのは、その母親も離婚しているからだ!」継母のヒステリックな暴言を思い出す。あれは間違いだった。だけど、すこしだけ本当が混じっていたのだ。お母さんにもお父さんがふたりいた。本当のお父さんは、死んでしまっていたんだ。
会ったことがないわたしのおじいちゃんは、商社の受付嬢兼、電話交換手をしていたおばあちゃんと出会った。おばあちゃんは18歳。高校を卒業したばかり。彼は4歳年上の、下請け会社の営業の人だったという。よく会社に出入りしていたその人とのお付き合いは秘密のもの。しかし、バイクで遊びにいった小倉にある公園で、おばあちゃんは足を骨折し、入院。怪我のいきさつとともに交際はみんなに知れ渡ることになる。「恥ずかしかったわあ」とおばあちゃんははにかみながら両手で顔を覆った。
ひとり娘だったおばあちゃんの結婚を、両親は反対したらしい。何度も何度も話し合っては断られ、結局、彼が婿入りするということで了承を得た。その後、出産。わたしのお母さんが生まれる。しかし、すぐに彼が発病。はじめは結核だと疑われ、感染しないように隔離生活を強いられてしまう。その後、誤診が分かり、癌として別の病院へ。そのまま家に帰ることはなかった。お母さんはまだたったの2歳。おばあちゃんは23歳という若さで、未亡人になる。
25歳まで育児に専念し、4歳になった娘の面倒を両親に頼んで、おばあちゃんは再就職をする。前職と同じく電話交換手だった。会社の作業室の隣は応接室になっていて、関連会社の若い男性社員たちが終業時間を過ぎるとぞろぞろ集まり、麻雀に講じていたらしい。その中の一人と、後におばあちゃんは再婚をする。これが、わたしが知っていたおじいちゃん。「いつも壁を、コンコン、とノックしてくるの。”もう!まだ仕事中なんですからね!”って怒っていたわ。でも、本当は照れていただけなの」25歳のおじいちゃんと、27歳で二度目の結婚をしたおばあちゃんは、二女と、三女をもうけた。
「おじいちゃんは、3人とも分け隔てなく育て、可愛がってくれたわ」
そのおじいちゃんも、わたしが小学校5年生のときに、長い癌との闘病生活のすえ、すでに亡くなっていた。身体の大きく、しゃがれた声の人だった。いつもポロシャツをきちっとベージュのパンツの中にしまい、ベルトをしていた。見た目は怖かったけど、怒られた記憶は一度もない。それがおじいちゃん。おじいちゃんだと思っていた。でも、血は、つながっていなかった。
「いま住んでいるお家ね、本当は、あなたたち兄弟を引き取って暮らすために買ったのよ。それからが大変で…あなたたちは、お父さんのほうへ行ってしまったけど…」
年を重ねるにつれて、様々な事情があり、環境によって苦しめられている大人がたくさんいることを知った。お継母さんは、突然、血がつながらない子どもふたりの親になり、さぞかし不安だったに違いない。いまはそれが分かる。お継母さんもきっと家族の型にはまろうと藻掻いていたんだ。血。戸籍。家族という枠組み。おばあちゃんは戸籍上のつながりはないけど、おばあちゃんとの日々をわたしは家族だと感じる。昔は、家族が欲しかった。無条件に愛されたかった。血がつながっていれば、こんなに傷つくこともなかったと思っていた。でも、そんなのちっとも関係なかったんだ。
「なんで、おじいちゃんと血がつながっていないこと、誰も言わなかったんだろう」とは思わなかった。お母さんも、おばあちゃんも、これまでそんなこと一度も口にしなかった。それは口にする必要がないことだったからだ。血のつながりなんかなくても家族だった、家族だと思っているから。
わたしはいま、おばあちゃんと、かつておじいちゃんとおばあちゃんがわたしたち兄弟を迎え入れるために買った家に住んでいる。あの頃、大人は薄情で、暴力的で、感情的で、爆弾のような存在だった。怖かった。愛されていないことが辛かった。でも、みんな思うようにいかなくて苦しかったんだ。本当は、大事にしたいと思ってくれていた気持ちもあったんだ。
わたしはきっと、誰かをこの先好きになり、血や戸籍なんか関係なくその人の全てを愛し、家族になりたいと思うのだろう。入籍したってしなくたって、子どもを産んだって養子を迎えたってふたりきりだって、なんだっていい。わたしが家族になりたいと思った人と、関係を深めて慈しみ合えたらそれでいい。誰に許可されずとも、名付けられずとも、互いに家族だと呼び合えたらそれがいい。
決まった枠組みがあると、そこに当てはまらないととても苦しくなってしまうから、枠組なんか取っ払ってしまえ。お父さん、お母さん、おじちゃんふたり、おばあちゃんふたり。それが家族の形である必要なんかない。大事な人は自分で決めるし、それは多いほど幸せじゃないか。わたしにはおじいちゃんが4人もいた。それが今、幸せなことだと思える。
サポートしてくださったお金は日ごろわたしに優しくしてくださっている方への恩返しにつかいます。あとたまにお菓子買います。ありがとうございます!
