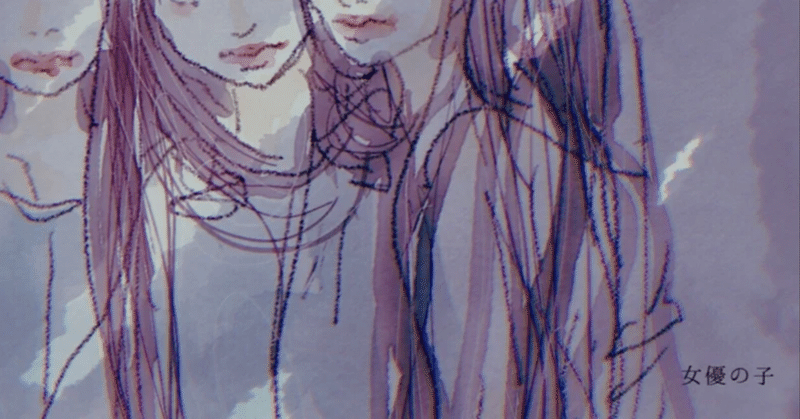
小説/女優の子 十三
水 五
この林に来てから、透明にも影ができるのだということを知った。
影ができるということは、それが完全なる透明ではないということの証明だった。だったら、この世で最も透明なものは何になるのだろうか。水にさえ影ができるのだ。
私はあともう少しでまっさらな水になれるところだった。なのに、幼女の警告を軽く見たばかりに元の苦しい椿の自我に逆戻りした。そしてそれは私ばかりの問題ではない。
揺らいでいる。
世界が揺らいでいた。
私たち司水の一族は、各世界がバランスを保って円滑に運営されるために必要な存在なのだと都さんは主張する。それが喜ばしいことか忌まわしいことかということではなく、とにかくそういうものとして存在しているのらしい。分かるような分からぬようなその説明に、最初は揶揄われているのだと思った。現にここに来て初めて得心したのであって、そうでなければ納得できなかった。
私たちは自分を過度に主張してはならない。突飛な行動も慎むべきだ。なぜなら司水の役割は、良くも悪くも「透明」なのだから。
ここは水の底なのに、上空から俯瞰してでもいるように世界の様子がよく見えた。世界がひとつではないと知ったのは驚きだった。二つや三つではない。薔薇の花びらの広がりのように複雑に幾つも円く重なりあって存在している。私は、その全貌や仕組みをまだよく解っていない。
とにかく現状の私はもはや淵の底に沈みきって、沈澱する澱みを掻き分けるようにして進んでいた。私の願いはただひとつ、百合をここから救い出すことだった。
どこか抜けたところはあるものの、からりとした性質の私たちの長姉、百合。なのに百合が閉じ込められたこの淵はどうだ。透明度がまるで失われている。この澱みの原因はきっと百合ではない。
ふと立ち止まって、底の沈殿を浚ってみる。手に取ると柔らかい小さな枯葉のようなもので、指先で摘むともろもろ崩れた。
泥──ではない。これは。
ここを濁らせていたのは膨大な言葉の山なのだと、その時私はようやく悟った。
やまとうたは、人の心を種として
よろづの言の葉とぞなれりける
言の葉。人の心から生み出された種が、出てくる時に葉となって、それがこんなにも降り積もって。
そういえば、あの林に茂っていた妖精の翅のような葉も、触れるとビリビリくるほどにエネルギーを放っていた。この腐った葉も水を介して本来そうなるはずだったのだろうか。百合はこの量を浄化しきれなかったということ?
──忘れたか。
お腹にずんと響くように、何かの意思を感じた。
*
わたくしどもは太古の昔より、水のような循環のもと存在していました。巡り濾過され、浄化され巡る。通常の生誕とは異なる方法で生まれるが故に人々より敬われ、常に神聖視される高貴な存在でした。代わりに、わたくしどもは短命でした。そうでなければ水の澱みに心が保たないのです。
覚えていますか。
年に一度の儀式のこと。
覚えていますか。
春の新月の合図のこと。
いいえ、記憶の表層では覚えてはいらっしゃらないのでしょう。いつからか風習は途絶え、よその家から娶り娶られ、当時のわたくしどもよりも今は随分と血は薄まってしまったことでしょうから。それでも、記憶の深層に刻み込まれています。あなたは司水の娘です。
言の葉は、人の心の種から生まれるのです。心に満ちているものの中から口は語る。あなたには覚えがあるはずです。他人の葉の毒素を、あなたは毎回受け取って自分のなかで処理をし無毒化していたでしょう。そのために生き苦しくなったのでしょう。
この場所をご覧なさい。ここは特にそれが多い。ご覧の通り百合には荷が重すぎました。わたくしも計算外でした。こんなにも言の葉を溜め込んでいる娘は今までいた例がありません。彼女は“葉”に執着しすぎ、愛しすぎていたのです……。
なにやら自動的に、私の思考に直接膨大な情報を流し込む者がいる。私は戸惑う。この人格は、あと少しで新になりきるはずだった私の人格とよく似ている。或いはあの幼女と。流れ込む情報が多すぎて理解も実感もない。却って恐怖心に満たされて進みにくい言葉の澱みの中をつんのめりながら進んだ。少し先にほの明るい一箇所を不意に見つけて、はっとなる。その場所めがけて澱みを掻き分け掻き分け──。
ようやっと見附けた。
浚った澱みの奥に現れたのは、青白い頬で眠っている百合の顔だった。
次話はこちら↓
前話はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
