
「フジイチエコ号と書いて走るわけにもいかないからね」 ノーナレのドキュメンタリー映画「人生をしまう時間(とき)」欄外対談
都会の片隅で「在宅死」と向き合う医師と家族を追った、ノーナレーションのドキュメンタリー映画が話題を呼んでいる。
『人生をしまう時間』は、NHKテレビで幾度も再放送されたものを大幅に再編集。東大病院の外科医から埼玉県新座市の私立病院の「訪問医」に転職した80歳の医師らを200日にわたり密着。通常はカメラや録音スタッフが加わるものだが、下村幸子監督が一人で撮影を行った。
今回、小堀鷗一郎医師と下村幸子監督にドキュメンタリーの舞台裏を「週刊朝日」(2019.10/18号掲載) で語ってもらったもののロングバージョンを掲載します。雑誌の記事は👇
https://dot.asahi.com/wa/2019101100007.html
“在宅看取りには正解がない”
小堀鷗一郎医師×下村幸子監督

カメラを向けられ「いやだょぉ」
と多弁になるおばあちゃんと看護師さん
━━映画の舞台裏を綴られた下村さんの『いのちの終いかた 「在宅看取り」一年の記録』(NHK出版)の序章で、小堀さんが下村さんに質問される場面があります。
「下村さんは事前にいろいろ情報を知りたいタイプ? それとも、あまり詰め込まないで、まずは行って見て、そこでいろいろ感じてからあとで聞くタイプ?」
出会って間もない、これから往診に向かう車の中で、後者だと下村さんは答えられていますが、小堀さんに対して「医者らしからぬ質問」をするひとだとおもわれたんすよね。
小堀 そういうことを言ったのかなぁ?(笑)。
ただ、僕はそういう興味を、ひとに対してもつんです。記憶にないというのは、ふだん無意識にしていることだからでしょうね。
下村 でも、わたしはすごくよく覚えています。というのも先生は、わたしが抱いていたお医者さまのイメージをことごとく壊してくださる。
小堀 そうですか(笑)。
私が人に対して興味をもつというのは、ある程度先天的なものだと思っている。それはテレビを見たという、20年ほど前に勤めていた病院の看護士さんから手紙をもらったんですが、こう書いてあった。「当時の先生は集中治療室に入ってきて、知らない間に姿を消していた」。つまり二年間一回も、その彼女とは口をきかなかった。ところが、テレビを見るとベラベラしゃべっている。同じ人だとは信じられなかったというんだね。
下村 へぇー。
小堀 変わったとするなら僕は40年間(外科医時代は)手術のことばかり考えていたけれど、いまは難しい手術をして治そうというのでもない。ほとんどの場合「在宅医療」でやれることは限られていますから。そういう現場が、僕の本来の性格を花開させたんでしょうね(笑)。
下村 いつもわたしは往診についていくんですが、映画に出てくるもうひとりの堀越先生は、看護士さんが運転されるクルマの助手席で、ものすごい勢いでカルテを読み込まれていく。小堀先生はというと、ご自身で運転され、車窓の向こうを見て、何とかという花が咲いたねぇと話される。患者さんに充実した時間をすごしてもらい最後のときをむかえるというゴールは同じだけど、おふたりのアプローチがちがう。それが興味深かったです。
小堀 医者が自分で運転しないといけないくらい待遇が悪いのかと憐憫の情をもって言われることもありますが、僕が運転するのは理由があるんです。あのクルマ、じつは患者さんのお金で買ったんですよ。
雑誌の「対談」にあたって、おふたりに何を話してもらうか。事前に打ち合わせはしていない。誌面では対談構成になっているが、現場ではそれぞれに構成者が質問するのをきっかけに対話へと導く。決めごとがないこともあり、さて小堀さんが何を話し出すのか、彼が「森鴎外の孫」と知り興味津々だった。
小堀 そのひとはフジイチエコさんというんですが、なぜ僕がその患者さんのことをずっと覚えているかというと、まもなく亡くなったんです。
小堀さんが埼玉県新座市の「堀ノ内病院」に勤務しはじめた頃、深夜に「息苦しい」と電話があり、往診に出向いたことがあった。半月後、その患者さんから窓口に託されたものがあった。野菜でもくるんだような紙包みから「やさしい言葉をかけてくださった小堀先生に…」というメモとともに封をされた札束が出てきた。
小堀 それだけ聞くと大変なお金持ちだと思うかもしれないですが、まったくそうではない。それが最後の貯えだった。だから、そのお金で往診車を買ったんです。病院の軽自動車はブレーキが利きにくかったりして、ひどかったのでね。しかし「フジイチエコ号」とつけて走るわけにもいかないので、せめて運転は私がすることにした。これ、ほとんど誰にも話してこなかったけど。
下村 わたしもつい最近うかがったところでした。
━━お医者さんの往診というと家族が気遣いし、もてなすものかと思うと、そうでもない。映画を観ると、しかも小堀さんの場合、患者さんと対等に雑談されているんですね。
小堀 そうですね。僕があえてそういう態度をとっているというよりも、まず相手がそういう態度と接してくるんですよ。
訪問診療では玄関に誰かが出てくるものだと思うんでしょうけれど、声をかけても誰も出てこないものだから、玄関が開いていたら勝手に入っていく。お昼だというのに病人の布団の横に奥さんが寝ていて、「あぁ先生、いらっしゃい」と挨拶される。そういうのがちっとも珍しくない世界なんです。
━━いつもキャンプ用の折りたたみ椅子を携行されていますよね。
小堀 ああ、あれはねぇ、何か書くにも部屋にスペースも机もない。患者が寝ている布団を飛び越えて、向こう側にいかないと診察ができない家というのもあって。もう慣れた先生になると、立って書いたりしているんですよ(笑)。

小堀さんが腰かけているのはキャンプ用の折り畳み椅子、
正座ができないのと患者との距離が近くなるよさがある
━━この映画が独特なのは、ナレーションがない。テレビ版にはあったそうですが、ないことで、考えながら見入ってしまいます。
下村 思い切って映画だからこそ出来ることをやろうと思ったんです。こちらが説明することで、患者さんのお部屋の中にどんなものがあるかなど映画全体が見えにくくなってしまうこともあるんですよね。
小堀 このひと(下村さん)はすごい観察力があると思ったのは、九十いくつの患者さん。終戦後すぐに航空管制官をやっていた。本棚に英語の本があったので話を聞いたら、「すっと(患者さんの)背筋が伸びた」というんです。彼の人生のプライドを満足させる話だったんでしょうね。僕は、面白いから、ただいろいろ聞いているだけなんだけど。
下村 そういう昔の話をされていると、みんな元気になっていくんですよ。
小堀 それは僕も感じます。死にそうなおばあさんが、帰るときには玄関まで歩いて送ってくれるんだから。
━━そうそう。103歳の女性が小堀さんと話しているうちに、表情が若返っていく場面がありました。
下村 先生が「あなたの脚はきれいだ」と言ったときですよね。
小堀 ああ、はにかんで、本当に若い女性の表情になりましたね。
下村 でも先生、あのおばあちゃんは、わかっていたと思いますか?
小堀 僕が聴診したあとに「こういう状態が続くでしょうか」と聞かれる場面のことね。映画には出てこないけど、その前に家族といろんなやりとりしていて、八十になろうとする息子が夜中2時間おきに起きて介護にあたる。この状態が続くと家族がまいってしまう。
下村 在宅医療は、患者さんだけの問題ではないんですよね。そこには家族との関係だとかもあったりして。お嫁さんは(デイケア施設に入るのを)「お泊り」という言葉をつかわれていたけど、おばあちゃんは戻ってはこられないとわかっていたのではないか。
小堀 あなたは、あのとき(小堀さんが患者のおばあちゃんと会話している)カメラがひいていく撮り方をしていたけれど。
下村 ズームバックですね。
小堀 突然「こんなことを言いながら死んでいくひとはいますかね」と言い出したんだよね。
下村 わたしもカメラを手にしながら震えがきてしまった。「あっ、わかっていたんだ」と思った。だからこそ迎えのバスに乗っていく場面、一度も振り返らなかった。50年近く暮らした家を出ていくというときに一度も。
━━説明みたいなテロップもナレーションもないため、観ている側が考えさせられる場面です。
下村 観る立場によって解釈が異なるかもしれない。疑問に思ったり、ひっかかったりすることがそれぞれ異なる作品にしたかったんですね。
映画を観ていだけるとわかるんですが、先生の言葉がけも、ひとによって変えていられる。意識していないのかもしれないですけど、すごく丁寧に挨拶されて中に入っていくこともあれば、長年の友人のように「おう」と入られることもある。
映画ではつかわなかったんですが、あるおばあちゃんに「きょうはいい眼をしていたね」と言ったのを、帰りしなに靴を履きながら「眼差し、といってあげたらよかったかな」とか。
小堀 あれは「目つき」と言ってしまったんだよね。
下村 ああ、そうでしたね。そういう言葉の一つひとつが絶妙で、それをナレーションでつぶしたくなかったというもあります。先生の言葉がけは診療のひとつ。どういうタイミングで、どういう言葉をいうのか。往診についていって学んだことなんですね。
━━患者さんの家族も個性的で、82歳の夫が寝たきりの85歳の妻の介護をし、二階まで食事を運んでいる。カメラに向かい妻が「わたし、いくつに見える?」と何回もはしゃいだ声で聞くんですよね。
下村 あの場面、先生もほめてくださいましたよね。よくあのシーンを入れた。美談だけでは終わらせてはいけないって。

103歳の患者さんの自室で話しこむ。
話題はほとんど病気以外のこと。
ふつうの会話が元気にさせるようだ。小堀 このことがあって医療番組を意識して見るようになったんですが、なんとなく結論が最初からあるものが多い。つまり「在宅死」は理想的な死で、「病院死」は悲惨だと。たしかにそういう一面もあるんだけれども、逆もある。
この映画は決めつけてしまうところがない。それがいちばんの特色だと思いますね。だって介護ベッドを入れ、体制を整えれば、おばあちゃんが幸せになると思ったら、暗い表情で「もう来ないで」と風呂に入れようとする介護スタッフを拒否。元気をなくしていく。
下村 そうなんですよね。
小堀 では、すべて元に戻せばいいのかというと、そうは言えない。つまり何が正解なのか、一人ひとりの状況に応じて考えていかないといけない、(マニュアル的な)正解がない世界なんです。それは、世の中にいちばん訴えたいところでもありますね。
━━ところで撮影期間に聞きたかったけど聞けなかったことはありましたか?
下村 あります。全盲の娘さんが介護しておられた、そのお父さんが亡くなったとき、先生は離れたところに立って見ていられた、あの瞬間何を思っていたんですか?
小堀 ……覚えていないんですけどね、いろんなことを考えていたとは思う。
━━たしかに映画の中で、カメラがしばらく黙って撮っている。じっと腕組みしておられましたのが印象に残りました。
小堀 いろんな人たちがやってきては、枕元で声をかえていたんだよね。
下村 臨終の場面、腕を組んで見つめているお医者さんを初めて見ました。心臓マッサージをするとか手立てをとるだろうに、何もしない。その勇気を感じたというか。
小堀 僕はあのひとの奥さんをあそこで看取っているんですよね。視覚障害の娘さんと二人で献身的に、とにかく自分たちでぜんぶやっていた。あのときは、そういう歴史を思い返していたのかもしれない。
━━もうひとつ驚いたのは、小堀さんがその前、危篤状態になったところで席をはずされることでした。
小堀 「家族が看取るんだ、医者じゃない」ということをすでに実践されていたひとがいて、そのひとは、いよいよ亡くなるというときに看護士と目を合わせ席を外すんだという。だから僕のオリジナルでもなんでもないんです。もちろん傍にいないといけない場合もあるんだけど。
下村 撮影者として同行していて、そういうヒリヒリする場面がいっぱいありました。先生はこういうふうにおっしゃるけど、患者さん大丈夫かなということとか。それは経験や患者さんとの関係の積み重ねがあってのことだと編集のラッシュを見ながら気がつくことが多かったです。
━━撮影中に疑問が生じると、下村さんはカメラを止められるんですか?
下村 迷っているときは撮っています。でも、いつカメラを下ろすべきなのか、迷いながらのことも多くて。もちろん止めてくれと言われたときには止めますが、許された状況のときには迷ったら撮れというのは先輩から教えられたことで、それは守っています。
━━映画を観ていておふたりに共通するものを感じるのは、「患者」ではなく「個人」として接しておられる。だからなんでしょうね、医療ドキュメンタリーというよりは「家族の物語」として観てしまう部分が多い。とくに、さきほどの全盲の娘さんに小堀さんが「(お父さんの)喉仏のところを触ってみなさい」と手を誘導される。最後の時間を、穏やかにすごすということの意味をさぐる場面でした。

視力障害のある娘さんが老父を自宅介護
報せを聞いて親戚のひとたちがかけつけた
小堀 あのとき、僕はヒロミさんに「ここを見たらわかるよ」と言いかけた。あぁ、見られないんだと気づき、言いなおしたんです。
下村 そのあと彼女はずっとお父さんの喉元を触っているんですよね。
小堀 そういうことでは、映画として、じつに恵まれていた。心臓の音はしなくなっているのに呼吸だけが続いているというのはめったにないことですから。しかも、「あ、先生、いま止まりました」という声が入っている。あれはもう、つくろうとしても作れない。あなたの執念ですよ。迷ったら撮り続けるといったけど、あのうどんにしてもね、ずーっと撮っているんだから。
目が見えない娘がこしらえたうどんを、起き上がる力もなくなった父親は、寝床で横になったまま箸を手に口に入れるのだが、ぽろっ、と一本が布団に落ちる。箸で必死でつかみ、口にする様子をカメラが映し続ける。
小堀 あんな場面を目にするなんて誰も想像しないですよ。
下村 もう、体調からしてそもそも食べることすら無理だったんじゃないですか。
小堀 そうだね。あれは娘のために食べたんだよね。
下村 一本たりとも残すものかというのを感じました。
200日間にわたる撮影は、病院の女子寮に泊り込みながら下村監督ひとりで行った。撮影することができたのは64家族。映画ではそのうちの9家族が登場する。なかには下村さんと同年代の女性の患者さんもいた。
小堀 同じ年齢で同じガンの末期でも、自宅に帰りたいという人もいれば、病院が安心だという人もいる。これまで僕がみてきた中で、はっきり死を意識して家に戻りたいと言ったのはひとりです。
そのひとは「終の棲家で死なせてくれ」と一度は退院したんだけど、あまりに苦しいものだから午後に入院させてくれと言われ、病院は振り回されたくない。だから、僕が「外泊」と称して家に送っていった。その翌朝亡くなったんですよね。
非常に印象に残っているのは、死にゆく人というのは、言葉は発せられなくなっても目つきででも何かを伝えようとする。これは『死にゆく人たちと共にいて』というマリー・ド・エヌゼル、パリの緩和病棟で7年間働いた心理療法士の本に書かれていたことですが。
下村 それがこの映画につながっている。
小堀 そういうことですね。だから、これは死者がつくった映画なんですね。
(聞き手・構成=朝山実)
写真は映画「人生をしまう時間」より©NHK
渋谷 シアター・イメージフォーラム
大阪 第七藝術劇場
京都 京都シネマ ほかで上映
小堀鷗一郎 こぼり・おういちろう 1938年生まれ。東京大学医学部付属病院第一外科、国立国際医療研究センターに外科医として40年間勤務。定年退職後、在宅診療に携わる。著書に『死を生きた人びと 本文診療医と355人の患者』(みすず書房)。祖父は森鷗外。
下村幸子 しもむら・さちこ 1993年、NHKエンタープライズ入社。「在宅死“死に際の医療”200日の記録」で日本医学ジャーナリスト協会賞大賞など受賞。著書に『いのちをしまう時間 「在宅看取り」一年の記録』(NHK出版)。
Bookreview
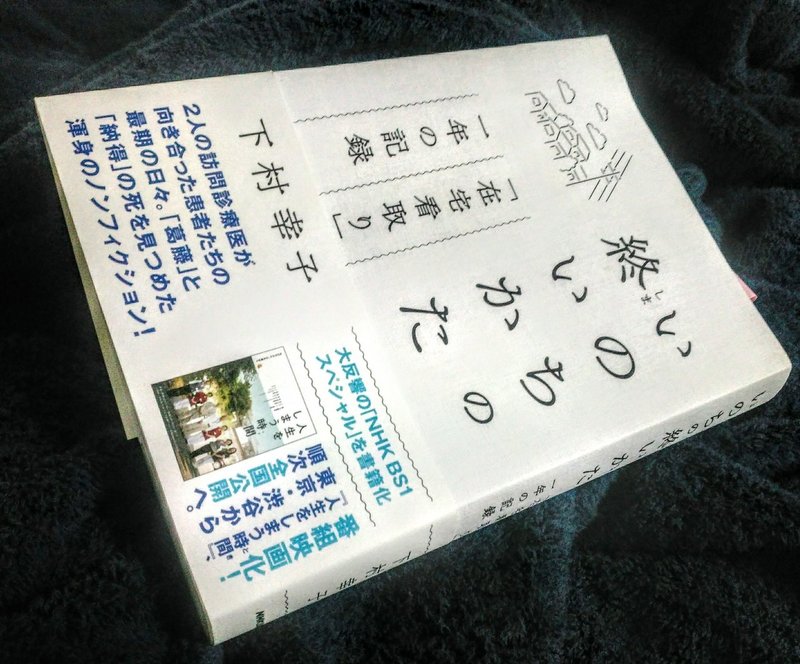
📖『いのちの終(しま)いかた』下村幸子(NHK出版)を読む
『人生をしまう時間(とき) 「在宅看取り」一年の記録』を監督した下村幸子さんが、200日にわたる撮影過程をつぶさに綴ったノンフィクション。映画を見ていなくともドキュメンタリーとして読めるし、映画を観たひとなら、ああそういうことかと理解が深まる。テレビ版とちがい、映画はナレーションなしの構成だからだろう。
とくに「対談」の最初でインタビュアーとして質問しているが、序章の「風変わりな医師」での200日にわたってカメラを向けることになる小堀医師の最初の印象を綴った部分は、取材を職業とするものとして何度も読み返したところでもある。短いやりとりだが、とても重要な要素がいくつも詰まっている。
これから往診に向かうクルマの中で、小堀医師が初対面の下村監督に尋ねている。
《「下村さんは事前にいろいろ情報を知りたいタイプ? それとも、あまり詰め込まないで、まずは行って見て、そこでいろいろ感じてからあとで聞くタイプ?」と尋ねてきた。
なんだか医師らしからぬ質問だと思いながら、私は「後者です」とだけ言った。》
その後の取材の様子を読むと、たしかに下村監督は、現場で、どういうことを目にしたのかを余さず記し、そのときに感じた疑問なども言葉にしながらも、小堀医師に質問するのは、病院に戻ってからしっかりと聞くということを繰り返している。現場で、一つひとつ知らないことを尋ねるというのは、忙しくなく動いているひとたちの手をとめることだから、しないほうがいいというのもある。それ以上に、まとまったかたちできちんと聞きたいというのは、おそらく取材者としての性分によるものだろう。
わたしなら、どうだろう?
心配性なので、事前にかなり資料を読み込んでから取材にのぞむということが多い。というのも、インタビューの仕事をはじめて間もないころに、質問するたび「はい、いいえ」とだけ短い答えしか返してくれない作家さんと出会い、取材後にそのひとの著作をぜんぶ読み返したことがあったからだ。インタビューは相性の要素もある。どんな状態になっても仕事として完成度の高いものにしたいという保身もあって、資料は可能なかぎりあたるようにしてきた。それでもうまくいかないときはうまくいかない。
ただ、いろいろ情報を頭に詰め込んでしまうと、現場で「驚く」ことが減ってしまう。とくに変わった仕事をしている人の作法は、あえて知らないでのぞんだほうがよかったりすることもある。そうすると、「そういうことも知らないんだ」と取材の相手から笑われることもある。「知らないので、教えてください」と正直に言うようにしている。知ったかぶりをしないのがこういうときには大事だ。教えてくださいと頼んで、教えないといわれたことは一度もなかった。どんなにつっけんどんなひとでも、知りたいという気持ちが伝われば、意地悪なひとはいない。
下村監督が、序章のところで、これからのドキュメンタリーの主人公となる人物を特長づけるエピソードとして、この質問のやりとりをもってきているところに、下村さんのことを面白いひとだなぁとおもった。たわいないやりとりだ。実際「対談」の場面で小堀さんに記憶にあるかどうかを尋ねたところ、覚えていないという。小堀さんは、出会ったひとにそのとき抱いた疑問などを聞くということをしてきているからだ、というのは対談の際にわかったことだ。
その場で解決するのは、「外科医」だったということも関係しているのかもしれない。とっさの判断を求められる仕事である。
じつは、この質問から当日の「対談」は始まっていくのだが、下村さんが選んだ二行の問いかけの中には、小堀医師を語る要素が的確に含まれている。
ひとつは、「下村さんは」と、会って間もない取材者に対して名前で呼びかけていることだ。「医師らしくない」のはこういう小さなところにあらわれてくる。映画の中での小堀さんは、どの場面でも「患者」として接するのではなく、ひとりの個人として対話している。「訪問医療」は治すことではなく、残された時間をいかに充実させるかに意味がある。そう考える医師だからこそ「患者」として見るのではなく、「ひと」として話し接していこうとする。その姿勢はすでにここにあらわれている。
姿勢といえば、第一章「子が親を看取る」の全盲の娘さんが、末期がんの父親を介護する家を訪問する場面。
《先生は、洋子さんの手を握って谷川さんの喉仏の位置に持っていった。
「洋子さん、ここに来て喉を触ったらわかるよ。口も動くしね。ここ触っていたらわかるでしょう。ほら、最期の、これが最期の呼吸だよ」
かすかに動く父の喉仏に手を当てながら、洋子さんはため息をついた。
「ちゃんと喉を動かして息してるのになあ。喉仏がちゃんと上下しています。息しています」
それが止まったら、最期だよ」
「一生懸命に息しているのになあ」。洋子さんは、お父さんの喉仏にずっと手を当てたままだった。》
その後、小堀医師は、人工呼吸などの「延命措置」は一切せず、娘が父の喉仏に手を当てるのを目にし、しばらくして、その場を離れたという。
そういえば、筆者の祖父が自宅で亡くなったとき、明け方に母親が気づき、時間を置いて医師に電話し、やってきた医師が臨終を告げていた。近所のお医者さんが到着したころには、すでに息はしていなかったとおもう。
40年ちかく昔のことだが、だから小堀さんがいう「最期のときは、家族だけで」と場を外すというのは、いまの医療ドラマを見慣れていると驚きではあったが、昔はそうだったとううなずきもした。
本には、一度病院に戻ってから30分後に連絡が入り、小堀医師は車を走らせ引き返している。
《そこに重たい空気はまったくなかった。皆、晴れ晴れとした表情だった。
「洋子さんが気付いたの?」小堀先生が問いかける。
「はい」
「それは谷川さん、幸せですよ。洋子さんに看取られたってことだからね。死亡時刻だって洋子さんが決めるようなもんだから」》
その後、集まった親族と娘さんとのやりとり、そのひとの輪からそっと離れていく医師の動きを、カメラを手にしながら下村さん追っている。遺された遺族に医療者がどのような「言葉がけ」をするのかは、こうした場面では医療行為以上に大事なことではないかと綴っている。
全盲の娘が、寝たきりとなった父親を看取る。
想像できない世界を映画では見せられるのだが、本では画面には映りきらない家族の事情も明かされている。
映画の中で、何度も小堀さんが口にする「庭の柿」だが、その由来、育てた父親が亡くなったあとのことも、本の中では綴っている。ささいなことだが、「百目柿」をめぐる逸話は、ノンフィクションの本ならではの読みのがしたくないところでもある。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。
