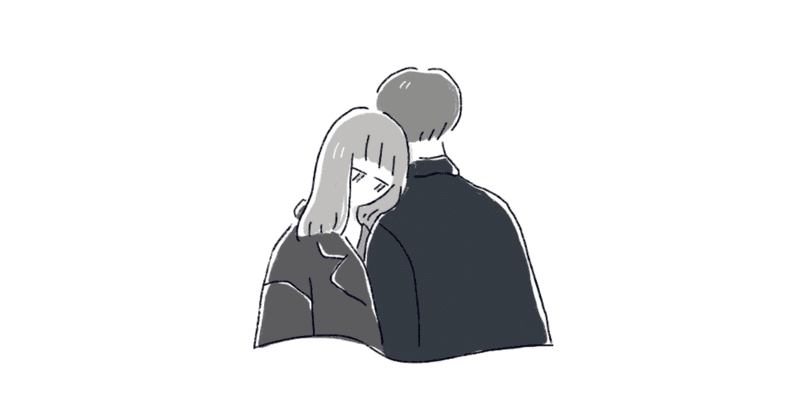
エンドロールには、まだ早い
真っ暗な部屋で、映画を観るのがいいんですよ。
キミの一言で、狭い1K の部屋は、深夜のミニシアターになった。本当に電気がいっさい消されてしまって、テレビの画面だけが発光している。キミは、ベットを背もたれにして、ただただ、画面を見つめている。私は、勝手にベットに上がって、そう、ここはキミの部屋なのに、我が物顔でベットに上がって、テレビ画面を観ているふりをして、キミの瞳を観ていた。
シーンが変わるごとに、キミの瞳にうつる、光の色が変わるのを、観ていた。
そっと、気が付かれないように観る。覗き込めないから、盗み観る。赤っぽくなったり、青っぽくなったり、白っぽくなったり。キラキラ。宝石みたい。サクマドロップみたい。あまりにもったいなくて、惜しくなって、わたしはそっと目を閉じた。口に入れられないなら、せめて大事に、記憶にしまい込みたかったから。
「あれ、寝そう?」
キミのまろやかな声がする。
ううん。とっさにわたしは、小さく喉を鳴らして返事をする。寝てない。ちょっと画面が明るくて、目がチカチカして。ほんとに真っ暗な中で観ると、映画館みたいだね。キミの瞳を、真正面から見ないように、うつむいて、早口に言う。
キミは、そうなんですよ、となんでもない風に返事をして、またテレビ画面に向き直った。わたしはホッとして、ため息をつくみたいに笑う。良かった、観てたって、バレてない。
テレビ画面じゃなくて、キミの瞳に映る、キラキラを観てました、なんて。だから、映画のストーリーなんて、ぜんぜん頭に入ってないんです、なんて。でも、映画のストーリーは、キミが観たいって言ったときに、もうとっくにGoogleで検索したから、だいたい知ってる、なんて。なんて。なんて。
「水、」
「・・・・は?」
「喉乾いてるんじゃないですか?さっきから、なんか変」
「あ、はい、うん、そうかな、そうかも」
「はーーー。黙ってたら、なにもわかりませんからね」
「ごめんなさい、でも、大丈夫」
ほしくなったら、自分でやるから、と言うと、キミの意識はあっさりとテレビ画面に戻してくれた。黙ってたら、なにもわからない。そうだ、キミは察しが悪い。だからとても、わたしは命拾いをしている。いまでさえ。
「気持ちを伝えるべきだよ」
これまで果敢に、恋と愛との格闘を重ねてきた美しい友人たちはこぞってわたしを教え諭した。好きな人と、何度も同じ部屋で過ごして、何も伝えてないなんて、嘘でしょ、あんた、ベットにまで上がって。だいたいみんな、なぜか憤る。
でも、ほんとうに伝えるべきなだろうか。
わたしは、キミになにか影響を与えたいわけではないのに。何も伝えないことは、だめなことなの?
考えたことはあったけれど、考えるほどに、思うほどに、漠然とした不安が押し寄せてくる。
気持ち悪がられたらどうしよう。迷惑がられたらどうしよう。困らせてしまったらどうしよう。優しいキミを悩ませたくない。煩わせたくない。壊したくない。離れたくない。こんなにも好きで、キミの瞳も観れない。わたしばかりが観てるだけじゃ我慢できなくなってるくせに。こんなわたし、観れたもんじゃない。
わかっている。
つまり、わたしは、キミに好きって言われたい。肯定されたい。自分じゃ観れたもんじゃない、いまのわたしを、キミに許してほしい。そのすべてが敵わないかもしれないのが、すごく怖い。簡単に、泣いてしまいそうになるぐらい。
こんななので、伝えただけで、解決すると思うなよ、と憤り返したくなってしまうのです、わたしは。
キミの瞳は、相変わらず、イロトリドリできれい。キミを好きになるって、きっと、同じようにイロトリドリで、キラキラで、ピカピカで、たのしいと思っていたんだ、ほんとうに。
たぶん、友人たちが想像している以上に、わたしはキミが好きで。
たぶん、キミが思っている以上に、わたしはキミが好きで。
好きで、好きで、好きで、大好きなので。
ゆっくりと瞼を閉じる。今日も、キミに好きって言えないまんまで。キミの瞳に映っていたキラキラが、わたしの瞼の裏に映って見えた。
最後まで読んでくださりありがとうございました。スキです。
