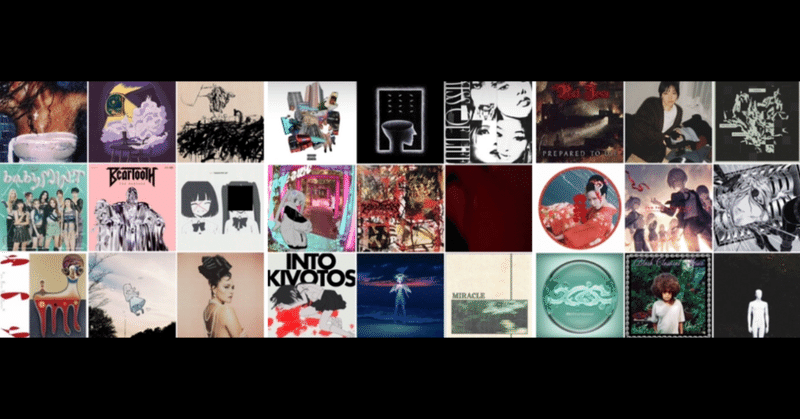
2023年 年間ベストアルバム&EP
27枚、A→Z順。
昨年は、毎月良かった新譜を月毎の記事で記録し、年末にはそれらの中から年間ベスト27枚を選んで横断的な感想を記載していたのですが、今年はその時間が取れなかったため、一作ごとの感想を本記事にまとめて書くことにしました。
Amaarae『Fountain Baby』

ニューヨーク生まれ・アトランタとガーナ育ちのシンガーソングライターによる2ndフル。アフロ・ポップとR&Bをアニメ声ともいえる独特の歌声で溶かし混ぜ合わせながら、水が床を滑るように、流動的に多領域を移動。和風の旋律と日本語が耳に飛び込む7曲目「Wasted Eyes」(Crystal Kayがゲスト参加)がアルバムにオリエンタルなテイストを加えたかと思えば、11曲目「Sex, Violence, Suicide」後半では突如初期Arctic MonkeysやDream Wifeを彷彿させるような痛快なインディー・パンクで牙を剥き出しリスナーを驚かせる。この異端者はしかし、セックス・ポジティブだがセンチメンタルで、ルーツを誇りながら違う大陸に生まれた自身の姿を夢想する、なんでもない普通の人間でもある。
Another Michael『Wishes to Fulfill』

フィラデルフィア出身インディーロックバンドの2ndフル。劇的な展開があるわけではないがウェルメイドなアルバム…と評すると凡庸なので、むしろ日常が実はずっと劇的であり続けてるということを気付かせてくれるアルバム、とか表現してみようと思う。大仰ではないがしかし神秘的なストリングスアレンジと、どこを切り取っても見惚れてしまうガラス玉みたいなメロディーが、ただ優しく流れ続ける時間。後述するRunnner『like dying stars, we're reaching out』もそうなんだけど、今年はこういうインディーフォーク + エモ的な音楽に惹かれることがままあり、その流れからJames Iha『Let It Come Down』に遡ったりもしました。
Avenged Sevenfold『Life Is But a Dream…』

カリフォルニア出身メタルバンドによる8thフル。2chまとめブログばっかり読んでたロクでもない中学生の頃、「痛いバンドの特徴挙げてけ」みたいなスレに直球で「Avenged Sevenfold」と書いてあるのを見たことがあって、彼らのことを初めて認識したのはその時だと思う。青臭くて痛々しかったA7Xも、老いて、やがては死ぬ。2chでアンチ活動するやつも老いて死ぬ。この文章を書いてる僕も老いて死ぬ。A7Xはその事実に打ちのめされ立ち上がり、ヘヴィメタルの老いと死に向き合ったこのレコードを完成させた。SOADとメタリカを融合させたかのような趣の「Game Over」から幕を開ける53分の思索の旅路は、枯れゆくM. Shadows(Vo.)がそれでもメタル・ボーカリストであり続けるための葛藤の記録だ。終着点はプログレ、シンセポップ、ジャズ、ピアノソロというマルチエンディングに至るが、それを矛盾とするか純化と捉えるかはリスナーに委ねられる。
新しいけど不可解ではない、壮大だけど複雑ではない。サラッとしたサウンドレイヤーだからこそ、作編曲の巧みさに射抜かれる一枚。30年前に聴いても30年後に聴いても傑作と思えるアルバムだし、つまりそれは老いや死を乗り越えた作品だとも言えるだろう(とはいえ、メンバーはまだ40歳前後なのでまだまだこれからいくらでも、という若さではあるが…)。
薄荷水晶 babyMINT『babyMINT Loading... FUN!』

台湾のグループ型サバイバルオーディション番組『未來少女』から生まれた9人組による1stアルバム。電波ソングとK-POPと暴カワ系Kawaii Bassを直列で繋いだらスパークしておかしくなっちゃったみたいな一曲「Hellokittybalahcurri³ hellokitty美味しい」は日本でもバズって話題を呼んだが、本作を聴けば同楽曲が「エレクトロ・トレンドをワンシーズンで網羅する」という本プロジェクトの実態の1ピースに過ぎなかったということがわかる。バイレファンキ、ドラムンベース、電波ソング、Kawaii Future Bass、Jersey Club、Drill、2step、Trap、Hyperpop、全部やってクライマックスの10曲目「2023:BBMeme ODYSSEY」で「WE LIVIN' LIKE A MEME」と歌われた瞬間、もう参りましたと言うしかない。FunnyかつInterestingな面白さは、メンバーのボーカル&ラップスキルがしっかりしてるからこそ。2023年はとにかく色んなK-POPを新参者なりに聴きまくってたけど、この一枚で描いてたマップが全部グチャグチャにされちゃいました。最高です。
Beartooth『The Surface』

オハイオ州出身メタルコアバンドによる5thフル。やんちゃなアグレッション&ヘヴィネスと挑発的なほどにキャッチーなメロディーのコントラストは、Papa RoachやHoobastankを連想させると同時に、そういったヘヴィ・ミュージックへのゲートウェイとなるバンドが現行USメタルコア/ポストハードコアシーンに不在であることへの焦りが滲む。エモ・スクリーモをリバイバルや懐古の対象としやがるメインストリームと、その扱いに満更でもない表情を浮かべるシーンに中指を立てる。同ジャンルのバンドたちの胸倉を掴んで「お前ら、嫌われるほどに売れる覚悟できてんの?」と問いただす。そのスタンスが正しいかどうかはわからないけど、ピースな表現の裏に見え隠れする熱い気持ちが楽曲のテンションに寄与してることは確か。
ex. happyender girl『happy endergirl』

蝉暮せせせ / cicada_sssと初音ミクによる音楽サークルの2nd(旧名義から数えると7th)。90~00年代のオルタナティブロックとシューゲイザーを軸に、時折虚を衝くような前衛的表現で心を揺さぶるコンセプトアルバム。個人的な印象は、「インターネットネイティブ世代のPlastic Tree」。縦書きの歌詞は、蝉暮せせせ / cicada_sssと初音ミクの関係を綴っているようでもあるし、それに仮託した、全ての喪われたもの(あるいは初めから存在しなかったもの)のためのレクイエムのようでもある。アルバムのカギとなっているのは、「 」内の歌詞は歌われないという仕掛け(2曲目「リマインドミー! [forget me]」に至っては丸々一曲それである)。カッコが閉じられていない8曲目「ghost 2 [u]」は全編通常通り歌われるのも、9曲目「その後の少女たち [afterwords]」で最後のある言葉だけが歌われるのも意味深。それは記憶の中で薄れていく誰かの声? 自発的には言葉を発さない誰かの、聞こえるはずのない声?
GEZAN with Million Wish Collective『あのち』

2020年の大傑作「狂(KLUE)」以来3年ぶりとなるGEZANの6thアルバムは、15人のコーラス隊・Million Wish Collectiveとの連名作となった。
コロナ禍寸前、混沌とした時代への予感に満ちた「狂(KLUE)」。怒りや葛藤がシームレスなビートの上でのたうち回り、11曲目の「東京」で臨界点を迎える。その制作を「いろんな背景を『東京』のために作っていくような作業だった」とバンドのフロントマンであるマヒトゥ・ザ・ピーポーは語った。
「狂(KLUE)」が「東京」を頂点とした作品ならば、「あのち」にとってのそれは7曲目の「萃点」だろう。グラデーションで異なる全ての生活を無秩序に塗り潰すリアルタイムな暴力に、それぞれの吠える声は徐々に高まり、一つの点に交わる。ただ、本作が前作のそれと決定的に異なっているのは、その頂点がゴールではなく、折り返し地点に過ぎないということだ。「狂(KLUE)」は絶頂の余韻が醒めやらぬままにインタールードを挟み、微かな希望を感じさせる「I」で幕を閉じるが、「あのち」にはまだ6曲分、語るべき言葉がある。
「BODY ODD」のパフォーマンスにおいて度々GEZANと共演している呂布カルマは、楽曲「オーライオーライ」において、こんな印象的なフレーズをラップしている。「神様が僕にだけ秘密で教えてくれた呪文 / 世界中の人が幸せになる代わりに 歌うことなくなるよう」...アーティストが抱える矛盾を暴いたこのラインを初めて聴いた時には、ハッとさせられた。ある種の真理だろうとすら思った。
「あのち」は、これに対する一つのアンサーのようなアルバムだと言えるのではないだろうか。GEZANが怒りながら同時に歓喜や愛、希望をも歌うのは、怒りの尽きた世界で芸術を為す意味を見出す行為でもあり、そしてそれは逆説的に芸術が怒ることの正しさを証明している。例えそれが軽薄に見えるぐらい芝居がかったものでも、模倣や再演に過ぎないものだとしても、だ。
2022年3月、日比谷野音にてGEZANのライブを観た。ライブ終盤、ヒートアップした観客が禁止されていたモッシュを始め、それをマヒトが制するシーンがあった。その、怒りとも説教とも違う、むしろ微かに共感を滲ませるような声色が印象的だった。
共同体として生きるということは、自身だけではどうすることもできない力に身を委ねるということでもあるだろう。その暴力がどれだけ我々を苦しめてきたか、GEZANはよく知っているはずだ。それでも彼らは大きなステージに立つことを選んだ。人と人との関わりが生む大きなうねりに、光を見出そうとした。その営みの現在地を、他でもない人間の身体から発せられる声で示した『あのち』。そしてそれを受け取った我々はどこへ向かうのか。語り部は、遠い遠い未来から、あるいはすぐ目の前に迫った明日から、じっとこちらを見つめている。
Inu『夢の翳り』

日本のプロデューサー / トラックメイカーによる1st EP。2021年のPorter Robinson『Nurture』、2022年のKAIRUI『海の名前』に続く自然派エレクトロポップの傑作。yuqueで共に活動するUztamaとも邦ロックの先の延長線上で共振。秋の夕方の帰り道のように懐かしくてあたたかくて切ない。
聴き進めながらふと、自分が熱心にライブに通い詰めていたアイドルグループ・CY8ERが、武道館で解散せずにエクスペリメンタルな方向に進化したパラレルの2023年を想像してしまった。Yunomiのサウンドに魅せられた2018年の自分に、Kawaii Future Bassの先にこんな美しい音が鳴る未来が待っていることをこっそり耳打ちしたくなる。
Jessie Ware『That! Feels Good!』

ロンドン出身シンガーソングライターによる5thフル。前作『What's Your Pleasure?』の熱狂を絶やさず受け継ぐインスタント・クラシック。真芯を1mmも外さないアンセム・アフター・アンセム。3曲目「Pearls」とか、向こう半世紀歌い継がれ&聴き継がれ&踊り継がれるべき名曲だと思う。まさにThat feels goodすぎて、快楽に感動できるアルバム。いつまでも終わらないでほしいパーティー。
Jim Legxacy『homeless n*gga pop music』

サウスロンドンを拠点に活動するラッパー / プロデューサーによる1stミックステープ。Rate Your Musicで新譜をチェックする際、「ジャンルタグが大量に付いてるアルバムは聴き逃さないようにしとけ」という個人的なポリシーがあるんだけど(独自性の高い作品に出会える可能性が高いので)、本作のそれは「Alternative R&B, Emo Rap, UK Hip Hop, Pop Rap, Afroswing, Afrobeats, UK Garage, Midwest Emo, Pop Rap, UK Hip Hop, Alt-Pop」。内容も期待を裏切らない越境性を有する仕上がりになっており、アフロなリズムやトレンディなビートに「Blonde」以降的アンビエンスを湛えることで可溶性を高め、インディーロック〜ミッドウェスト・エモなギターフレーズとの融合を実現させている。実際のホームレス経験から名付けられたタイトル&コラージュで制作されたアートワークとサウンドの親和性の高さからも、クレバーなアーティスト像が垣間見える。
JJJ『MAKTUB』

Fla$hBackSでの活動でも知られるラッパー・トラックメーカーによる3rdフル。豪華な客演陣のテイストに合わせその形を変えながらも、同じ質感でリスナーに寄り添うトラックが心地良い。夜の東京の、彩度が違えど温度は変わらない、色々な街を歩くJJJの横顔を追うカメラみたいなアルバムだ。と思っていたら、10曲目「U」で彼が目黒シネマの座席に腰を下ろした時、そこに自分の姿がフレームインして驚く。
リリシストだけが特別な言葉や情緒に選ばれているのではなく、そこら中に漂うそれを掬い取れる感性を持ち得るか否か。「MAKTUB」とはアラビア語で「それは書かれている」で、出来事はすべて意味や因果の下にあり、それを感じ取れるかはその人次第…なんてことを意味しているようだ。
KISS OF LIFE『Born to be XX』

韓国の4人組ガールズグループによる2ndミニアルバム。今年はとにかく色んなK-POP(といってもほとんどがヨジャグルだけど)を聴きまくった年で、H1-KEY「Rose Blossom」「Time to Shine」、Queenz Eye「UN-NORMAL」、XG「LEFT RIGHT」などなどなどなど、たくさんの素晴らしい楽曲に出会えた。と同時に、やっぱりとにかくリード曲のプロダクションが何よりも優先されていて、まとまった尺の高水準な作品が生まれにくいシーンであるということを認識させられもした(NewJeans『Get Up』は言うまでもなく重要作だけど、あの6曲12分という極端に短い尺自体が授賞式やフェスでのフルサイズパフォーマンスを意識した戦略の一つだろう)。その点において、本作は類い稀なるウェルメイドなプロジェクトだと思う。オールドスクールなHIPHOP〜R&Bやレゲエを軸にしたトラックで作品全体のモノトーンな空気感を制御。このモタッとしたビート感だけをじっくり楽しませてくれるK-POPアルバムというだけでありがたい。メインボーカル・ベルを筆頭とするメンバーの技量も確かで、インパクト抜群のハイトーンボイスはもちろん、しっかりと後ノリで歌いこなす(『it's Live!』のパフォーマンス映像を見ればその意識がハッキリと伝わる)楽曲理解度の高さもクオリティに貢献している。
KOTONOHOUSE『moeǝɯo』

Kawaiiミュージックシーンをリードするトラックメイカーによる2ndフル。アイドルやVTuberなど多様なボーカルアクトを巻き込みながら成長してきた「暴カワ」周辺ムーブメントの広がりを国境と次元を超えパッケージしつつ、Porter Robinson『Nurture』以降のポストEDMシーンへのシンパシーと、その先に見える地平までもプレゼンテーション。本人の歌唱も大胆にフィーチャーすることでいちアーティストとしての可能性も拡張してる点には良い意味での我の強さが表れていて、総覧的価値と作家性が両立されている一枚。
Kruelty『Untopia』

東京発・グローバルに活躍するデスメタリック・ハードコアバンドによる2ndフル。彼らのことは従前から認知していたし音源もチェックしていたのだが、それでも11月3日の『NEX_FEST 2023』で彼らのステージを体感した際の衝撃はあまりにも強烈だった。ハッキリ言って2位以下に10馬身以上を隔てての圧倒的ベストアクト。
ライブを経て解ったのは、ドロドロとしたデスメタルリフや日本語歌詞で鬼哭啾啾とした雰囲気を放ちながらも、彼らの音楽が何より「踊れること」を重視しているという点(フロントマン・Zuma氏によるnote記事「ハードコア的観点から見るデスメタルの聴き所」を読むと、よりそのスタンスへの理解が深まる)。バリエーション豊かかつツボを押さえたリズムワークとキメの多さが、灼熱地獄をさらにアジテート。奈落に引き摺り込まれた! と思ったら、鬼も亡者も案外楽しそうにやってました。みたいな。
kuragari『zzz...zzz...zzz...』

謎多きベッドルーム・シューゲイザーアクトによる3rdアルバム。Parannoulを幹とする宅録シューゲイザーシーンの極北的な一枚。かのバンドとはサウンドデザインで近似するが、本作は一切の物語に干渉されず、また一切の物語を紡がない。ファズギターが導くたった一行の歌詞。ほぼ展開しない楽曲、ささくれ立ちながらも感傷的なウォール・オブ・ノイズに包み込まれる35分間の子守唄。自分勝手に他人のことだけを想った、暗く優しい、どこにもいかない6つの祈り。
littlegirlhiace『INTO KIVOTOS』

日本の宅録ソロプロジェクトによる6枚目のフルアルバム。ART-SCHOOLやSyrup16gを彷彿とさせる00年代直系邦オルタナロックを生々しいサウンドデザインでかき鳴らしつつ、全曲テーマはスマホゲーム『ブルーアーカイブ』という、倒錯したノスタルジーと愛。スマホのボイスメモでリハスタでの練習の様子をそのまま録音したみたいな音質、その密室のどこにも行けなさがまさに作品のひねくれ方(あるいはどこまでもピュアで、ゆえに触れがたい煌めき)と合致していて心地良い。
Mirabi Frame『Mirage』

日本(Vo) x ラトビア(Composer)による国際ポスト・ハードコア〜メタルコアプロジェクトの1st EP。宇宙的に壮大なサウンドの中で、彼女の囁き声に耳を傾けるというアイロニックな体験、すなわち「セカイ系コア」です。BPM15Qがメタルを取り入れた結果「Story of Hope」やForeground Elipseみたいになっちゃった、的な親しみやすさと新しさ。Key楽曲と共鳴する場面も。3曲目「Kataomoi Riguretto」、4曲目「Mikazuki」が特に秀逸。
Miracle『Miracle』

昨年の個人的ベストニューカマーだったMemento.のメンバーも参加するフロリダ発5人組によるデビューEP。高純度な90年代ニュースクール・ハードコア〜メタルコアをプレイする……という特徴は昨今のシーンにおいて珍しいものでもなく、本作をリリースしたロンドンのThe Coming Strife Recordsからも同ベクトルのアイテムが多く放たれているのだが、その中でもMiracleのクオリティは白眉。短2度のアルペジオとオクターブ奏法&パワーコードを中心に組み立てられるリフワークとモッシュパートの応酬と、構成要素はいたってシンプル。それでもこの「リアルタイム感」の再現度が頭一つ抜けているのは、彼らが理屈抜きで先達へのリスペクトを内面化させているからにほかならない。
Rat Jesu『Prepared To Die』
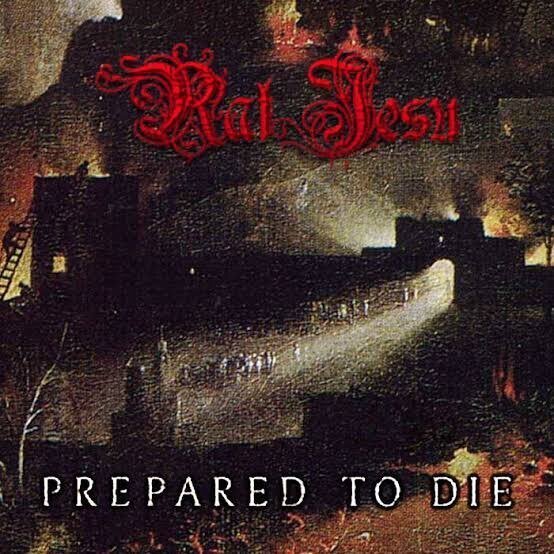
Drixxo Lordsのメンバーとしても活動するソロアーティストによる3rdフル(ミックステープを含めると4th?)。Godsmack〜Deftonesライクな直球オルタナメタル「Rat Judah」を皮切りに、HexD文脈からニューメタル/ポップパンク/ブラックメタル/サイバー・グラインド/ゴシック・メタルコアの再解釈を試みる7曲(+インタールード1曲)15分。ポップネスを保ちつつ、まるで惑星間を飛び移るかのように異ジャンルを旅する。
夢で見た荒唐無稽な景色が、目覚めてからは上手く描けない。逆に言うと、覚醒していたら辿り着けない世界も、不明瞭だからこそ形にできる。Rat JesuがHi-Fiなエレクトロミュージシャンだったら、この作品は生まれなかったのではないだろうか。メロディが砕かれ輪郭を失うHexDの磁場だからこそ混ざり合うことができる、本来は他次元にある音。3次元にしか存在できない我々は混乱させられるが、だからこそもっと理解したくなる、繰り返し聴きたくなる。
reina『You Were Wrong』

w.a.u所属シンガーによる1stアルバム。 2000年前後のR&Bがそばにある2023年の生活、という絶妙な空気感を、宇多田ヒカルのオマージュなども交え確信的かつ巧みにパッケージ。今年FLOに出会ったことをきっかけにJanet Jackson、TLC、Teedra Mosesらにハマってた自分にとっては、タイミング良くド真ん中に絶好球が放り込まれた感覚でした。7曲目「my apologiess」のすべてがとにかく素晴らしい。
Runnner『like dying sters, we‘re reaching out』

LAのシンガーソングライター・Noah Weinmanによるプロジェクトの、Run For Coverからのデビュー作。 American Football〜Owen〜Bon Iverのラインを繋ぐ、超美麗音響エモフォーク。ただ、アメフトがあの「例の家」を飛び出して天空に向かっていったのに対して、本作は星々に思いを馳せつつも地に足が付いている。カントリーな音色が感じさせる確かな手触りが心地良い。春の陽光の下で聴く日を夢想してしまう一枚。
SARI『大団円』

元NECRONOMIDOLのソロシンガーによる1stフル。作曲はTakahiro Miyoshi (QUINE GHOST)、T5UMUT5UMU、栄免建設、soejima takuma、Kei Toriki(明日の叙景)が担当、作詞は全曲SARI本人。オルタナR&B/マスポップ/UKドリル&プログレッシブトランス/フューチャーベース/ブレイクコアetc...+歌謡メロディという楽曲達は、それぞれ作家の個性が存分に発揮されている。同時に、アルバム全体で提示したい世界観がハッキリと存在していて、どの曲もそれを全く損なわないのが凄い。SARI本人の歌唱は、感情を抑えつつも様々な声色やフロウを使い分け、自在に表情を変える。
アイドル時代、"世界で一人の白塗りアイドル"として知られていた彼女。ブラックメタル・サウンドを武器としていたNECRONOMIDOLではコープス・ペイントと紐付けられたであろうそのビジュアルが、本作のジャケット写真で舞妓のおしろいに形を変えたのは、彼女が一人の表現者として確固たる信念とビジョンを持ったことを端的に示している。
She is Legend『Job for a Rockstar』

ゲームアプリ『ヘブンバーンズレッド』劇中バンドによる1stフル。正確には2022年12月リリースなのでこのリストには入れられないんだけど、サブスク配信開始されたのが2023年8月ということもあるので大目に見てください。
劇中設定では「洋楽直系スクリーモ・叙情系ハードコアサウンド」がウリとなっているのだが、実態はまあそうでもなくて、せいぜい「ラウド版Girls Dead Monster」と表現するのが関の山。でもそれこそがミソなんだと思う。麻枝准による王道コード進行を忙しなくなぞるいかにもアニソン的な詞曲を渡されて、前述の設定&ツインボーカルの編成をどこまで活かせるか、というアレンジャー・吉田穣の縛りプレイ的制作が、メタルでもなければギターロックと言うのも憚れる独特の音楽性に繋がってる。ガルデモがギタリスト・光収容のポテンシャルを爆発させたことからもわかるように、麻枝准はそういう補助線の引き方を心得てる。それにしても、なんで彼の書く歌詞って食事と睡眠のことばっかりなんだろうね。
Silica Gel『POWER ANDRE 99』

韓国の4人組ロックバンドによる2ndフル。ロックなボーカルトラックを軸にしつつ他・多ジャンルのセグメントを散りばめる本作の第一印象は、18曲1時間14分というボリュームも相まってThe 1975『A Brief Inquiry into Online Relationships』『Notes on a Conditional Form』の影と重なる。しかし、The 1975が一つのポップネスへの収斂を目的に多角的なアプローチを取ったのに対し、本作は4人の音楽家のクリエイティビティを限界を取っ払い拡散させることにこそ主眼が置かれていそうだ。スマートよりもエピックに。クリティカルよりサイケデリックに。結合子が千切れてしまいそうなほどに暴れ回る情熱を、エレキギターへの強力な愛着が繋ぎ止める。
XG『NEW DNA』

avex出身7人組ガールズグループによる1stミニアルバム。「MASCARA」や『XG TAPE』シリーズがK-POPトップアクトに劣らないスキルを、「SHOOTING STAR」「LEFT RIGHT」がグローバルな受容を予感させる普遍性を示した後で、本作は彼女たちの異形性を改めて強調。
個人的に、XGは自身をはっきりと「HIPHOP / R&Bグループ」と規定しているところにジャンルへのリスペクトがあってカッコいいなと思うんだけど、そこには同時に、「K-POPシーンを」「J-POP産業を」というコマーシャルな枠組みに囚われず、ポップ音楽史自体を更新してやろうという大胆不敵な気概を感じたりもする。たとえば、彼女たちの成長をドキュメントしながら「ラップって練習したらこんぐらい上手くなるんですよ?」とトレンドなサウンドや大物HIPHOPアーティストのビートをジャックして見せ付けてしまうのは、ラップゲーム全体の在り方に影響を与え得るんじゃないかと思う。
Yussef Dayes『Black Classical Music』

サウスロンドンのジャズシーンを牽引するドラマーによる初のソロアルバム。ラテンやアフロのエッセンスをごくごく自然に取り入れ、ブラックミュージックとしてのジャズを追求する。ジャズには明るくなくて具体性を欠いた感想にはなってしまうんだけど、とにかくRocco Palladino(Ba)のプレイの存在感が素晴らしい。彼とYussef Dayesとのコンビネーションにより生み出される高揚には、『ジャコ・パストリアスの肖像』を初めて聴いた時の衝撃を想起させられた。
ひとひら『つくる』

東京の4人組ロックバンドによる1stフル。American Football、toeをも連想させる美麗ギターフレーズに邦ロック的エモーションを衝突させることで大きなうねりを産む一作。マスロック〜トゥインクル・エモのように細かく区切られたフレーズの精度の巧拙を試されるジャンルは、実演においても構築においてもとにかく終始気を張り続けるための集中力が問われるが、その領域において12曲がひとつなぎとなった本作を完成させた彼らのポテンシャルには目を見張るものがある。同時に、前述の通りジャパナイズされた感情表現とメロディー、シューゲイザー譲りの轟音パートを取り入れることで、リスナー側にはそれほど集中力を要求せず、ワンサイドに圧倒してしまう様も鮮やかだ。タッピングを用いずアルペジオに執拗にこだわる点も彼らならではの個性に結実。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
