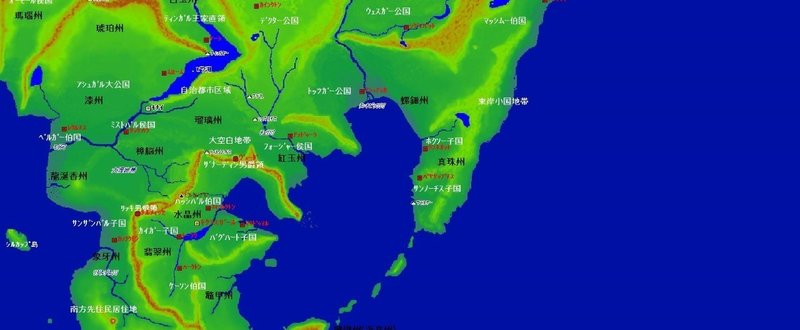
ティルドラス公は本日も多忙② 新伯爵は前途多難(33)
第七章 魔の森の喜劇(その1)
夜の暗い路地裏で、リーボックは独り、息を殺しながら周囲の様子を窺っていた。
物音を立ててはいけない。気配を悟られてはいけない。この暗がりのむこうに、自分の命を狙う者たちが潜んでいる。かすかに聞こえてくる足音や囁き声、鎧擦れの音から判断して、人数は七、八人か、もう少し多いか。うち、少なくとも一人は弓を持っている。
ユニからの迎えと名乗る五人の男が自分のもとにやって来たのは、日が落ちて間もなくのことだった。市内の治安に問題が発生しており、相談のため至急来てほしいという。
多少訝(いぶか)りながらも、言われるまま、彼らに連れられて宿営地を後にするリーボック。だが、しばらく歩くうちに様子がおかしいことに気付く。周囲の者たちから発せられる隠しきれない殺気。道も、ユニの本営ではなく街の中心から外れた人気のない場所へと向かっている。
『なるほど、そういうことか。』内心つぶやきつつ、素知らぬ顔で彼は歩き続ける。
入り組んだ裏道に差し掛かったところで、突然、剣の鞘を払う音とともに背後の足音が乱れる。彼の後ろを歩いていた者たちが抜剣して斬りかかってきたのだった。だが、同時にリーボックも素早く横に飛びすさり、襲いかかってきた者たちの剣をかいくぐると、一番近くにいた相手の胴鎧の隙間、脇の下を狙って抜き打ちざまに剣を振るう。血煙を上げて倒れる相手。そこに斬りかかってきたもう一人を二、三合斬り結んでその場に斬り伏せ、月明かりの中、近くの板塀を背に彼は残った者たちと対峙する。
これで三対一。隙を見てもう一人倒せば退路も開けるはず——。しかしその時、一筋の矢が彼の横をかすめ、背後の板塀に深々と突き刺さる。
「!」相手は五人だけではなかった。おそらく他にもいるだろう。このまま囲まれ、飛び道具を持つ相手に姿をさらし続けることになってはまずい。とっさに近くの細い路地へと飛び込んだ。狭い場所で反撃されることを怖れたのか追って来る者はない。ただ、背後で仲間を呼ぶ声と、それに応じて数人が駆け寄る足音が響く。
こちらの位置を悟られないよう足音を忍ばせて路地裏を移動し、少し奥まった人目につきにくい物陰で様子をうかがうことにした。相手の動きと人数が分からない中で下手に動くことはできない。『不覚を取ったな。』彼は内心舌打ちする。
自分を闇討ちして排除する企みがあることには気付いていた。無用の危険を避けるため、夜や人気のない場所での一人歩きは控えるようにしていた。ただ、相手がここまで露骨で乱暴な手を使ってくるとは、さすがに予想していなかった。
ユニがこの企みに関与しているのかは分からない。ただ、彼らが自分に示した符節(ふせつ。任務を証明する木片)は本物だった。ユニ自身ではなくとも、符節を発行できる立場の人間が背後にいるのは間違いない。おそらく自分がこのまま死体で発見されたとしても、盗賊かバグハート家の密偵のしわざにされて、真相は闇に葬られるのだろう。
『どうしたものかな。』
その時、あたかも周囲の闇の中から湧いたように、二つの黒装束の人影が彼の左右に立つ。「!」反射的に斬りかかろうとするリーボック。
「声を立てられますな。」彼の右手を押さえながら、右側の人影——『蜘蛛』が囁いた。「心配はご無用。ティルドラスさまより遣わされた者でございます。」
続いてもう一人——『蝉』が、闇のむこうを指さしながら何かを念じる。と、彼の指さした方角で、何者かが足音高く走り去るような音が響き、それを追って数人の者たちが叫び交わす声が聞こえる。
——あちらに走ったぞ!——
——いつの間に抜け出した?——
——追え! 逃がすな!——
——慌てるな。あの方角は行き止まりだ。焦らず囲んで袋小路に追い込め!——
——気をつけろ。思った以上に腕が立つぞ。距離を置いて槍と弓で仕留めろ。——
彼らが遠ざかるのを確認して「こちらへ。」とリーボックを促す『蜘蛛』。背後でなおも叫び交わす声を聞きながら、三人は足音を忍ばせて反対の方向へと向かう。
少し離れた場所まで逃げ延び、一息ついたところでリーボックが尋ねた。「助かった。礼を言う。ティルドラスさまお付きの忍びか?」
「少し違いますな。」『蜘蛛』が言う。「以前お会いしておりますが、お忘れですかな? 我が名は『蜘蛛』。」
「同じく『蝉』。」
「お前たちか!」目を見張るリーボック。彼自身はティルドラスが襲われた現場には居合わせなかったものの、その後二人が捕らえられネビルクトンへと護送される間に顔を合わせ、言葉も交わしている。
「仕事を受けることと引き替えに牢から出していただきました。ティルドラスさまがツクシュナップに到着するまで、あなたの身を守り、手助けをするよう申しつかっております。」『蜘蛛』は続ける。
「ティルドラスさまがおいでになるのか。」
「何かお考えがあるようでございましたな。我らも知らされてはおりませぬが。」と『蝉』。
「そうか。ともあれ、お前たちが来てくれたのは心強い。よろしく頼む。」そしてリーボックは独り言のようにつぶやく。「しかし、変われば変わるものだ。まさかお前たちに、このような形で助けられるとは思わなかった。」
「まことに。」二人の忍びはくっくっと笑う。喉の奥で押し殺したような低い笑いだったが、不思議にも陰気さはなく、むしろ可笑しさをこらえているような響きだった。「不思議な方でございますな、ティルドラスさまは。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
