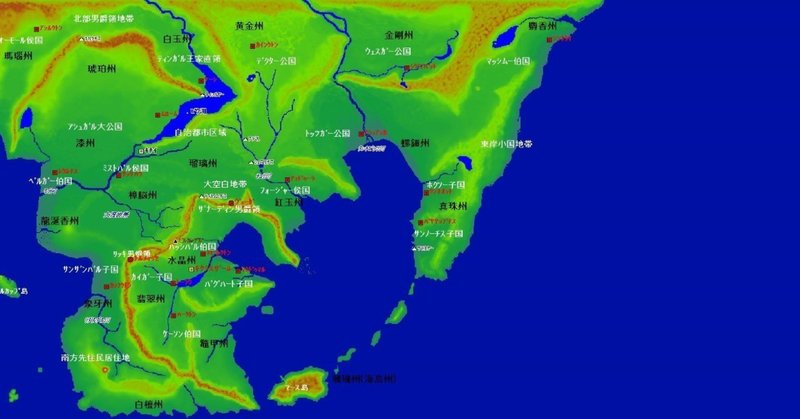
ティルドラス公は本日も多忙② 新伯爵は前途多難(44)(最終話)
終章 メイルの墓(下)
アンティルがいなくなった今、彼を諫める者は誰もいない。マクドゥマルで行われたことが、ここでも繰り返された。決戦を前に兵士の戦意を高める必要があるとの判断から、メイルも重臣たちも略奪を黙認する。ハッシバル家から子爵家を守るためには多少の犠牲はやむを得ない。子爵家あっての民ではないか――。それを受けて、これまでは自国の民から奪うことを躊躇していた者たちも略奪に加わった。地元生まれの者を中心にわずかな数の兵たちがそれを止めようとしたものの、逆に「ハッシバル家への内通者」の汚名を着せられて粛正される。
メイルは根本的に理解していなかったのだ。
乱世に生きる民たちは、国家などというものが単なる幻影に過ぎないことを知り抜いている。かつて無数の小勢力が毎日どこかでぶつかり合い、勝敗の如何(いかん)で土地の支配者がめまぐるしく交代した乱立の時代は、ここ数十年の間に、天下の諸勢力が十いくつかの国に集約されたことにより、確かに終わりを告げた。しかし、その時代の記憶と教訓は今も民の中に息づいている。もともと地上に「国」などというものは存在しない。人々が暮らす「社会」の上にいつの間にか大きな顔で居座って、「社会」よりも重要なものであるかのように振る舞っている得体の知れない存在、乱世の民にとって「国」とは、その程度のものに過ぎないのである。
民の平穏も社会の繁栄も、全ては「国」が民にありがたく与えてやるものであり、したがって民百姓は、何があろうと全てを擲(なげう)って国に尽くすべきだ、などという、支配者に都合の良いだけの理屈。それは、家畜化され、国家の存在を自明かつ絶対不変のものと信じ込まされた「近代国家」の民には通じるのかも知れない。だが、乱世の民は家畜ではなく野生動物である。隠れもすれば逃げもし、そして時には横暴な支配者に対し、牙を露わにして復讐することもあるのだ。
もともとこの地には、マクドゥマルの港で働く人足たちの束ねとして勢力を築いたマストバーグという侠客の一族が大きな勢力を持っていた。「数百の勢を率いて一帯を横行し、官吏もこれを畏(おそ)れ憚(はばか)った。」「その権は大きく、その威は重く、周囲に隠然たる力を及ぼし、あたかもこの地のもう一人の領主のごとくであった」と『ミスカムシル史大鑑』遊侠列伝は伝えている。
その分家の一つの屋敷が徴発の中で襲撃を受ける。兵士たちは屋敷を徹底的に略奪・破壊し、さらに、嫁入りを目前にしたその家の長女を初め女という女を集団で犯して去ったのである。
この行為にマストバーグ一族は憤激する。乱世の侠客は、たとえ相手が領主であろうと、黙って略奪されているほどおとなしくはない。ただちに一族の間で秘密の話し合いが持たれ、何事かが決定される。
数日後、マストバーグ本家の呼びかけで、近隣の有力者たちを集めての会合が開かれた。呼び集められたのはユックル近郊の富農や大商人、さらに、バグハート家との間に主従関係を結ぶことで自身の支配地への特権を認められている付近の小領主などもいた。
マストバーグ本家の当主は所用を理由に姿を現さず、代わって当主の名代を名乗る一族の男が座を仕切る。出席者たちが緊張した面持ちで出された料理に箸を付け、杯が一回りしたあと、名代の男は「さてご一同。ここで相談がございます。」と、立ち上がって声を張り上げる。
一斉に口をつぐみ、彼を注視する出席者たち。
「これはご本家ではなく、あくまで私個人の考えですぞ。よろしいかな?」沈黙の中、名代の男はじろりと周囲を見回しながら言う。むろん、これは表向きで、実際は本家当主の意を受けての発言なのだろう。「皆様はメイル子爵をどうお考えか。あの暗愚、あの暴虐は目に余るものがある。それに比べ、ハッシバル伯爵は温厚にして慈(いつく)しみ深く、民を愛されるという評判。ここはいっそ、メイル子爵を見限って、ハッシバル伯爵にお味方するのが良いのではと思うのだが、いかがかな。」
出席者たちは一瞬驚いた表情を見せ、そのあと考え込む。
被害に遭ったのはマストバーグ一家だけではない。マクドゥマルの豪農や大商人の多くは賄賂を使って徴発を免れたが。軍や宮廷へのつてを持たないこの地の有力者たちは、庶民同様に略奪の標的となっていた。腹に据えかねている者は少なくなかったのである。
しかも、今回の戦は長引く可能性がある。ハッシバル軍が占領地の人心を得て支配体制を固めつつある一方、メイルは敵に膝を屈して和を請う様子はなく、このままユックルの城に立て籠もってハッシバル軍に抵抗する構えを見せている。今は略奪を免れている家にしても、戦が長引けば、いつ何時襲われるか分からない。その上、両家の戦いでこの周囲が戦場となれば、自分たちも巻き添えを食うことになる。それならば――。
そう、それならば。
さらに数日後、ユックルの城門の前に、鍬や斧、大槌を手にした二百人あまりの集団が、数十台の荷車とともに現れる。何事かと兵士たちが驚く中、行列の先頭に立った男が城門の前に進み出て大声で呼ばわった。「我ら、近在の郷の者でございます。大恩あるご領主さまの難を救わんがため、ご籠城のための兵糧の献上と、普請(ふしん)の手助けに参りました!」
一行の中には名の知れた近郊の有力者も混じっていた。報せを受けたメイルは、大喜びで彼らを城に入れることを命じる。城門が開かれ、集まった者たちは荷車を囲むようにして城の中に入ってくる。
注意深く観察すれば、何かがおかしいことに気付いたかもしれない。荷車に積まれた薪の山の中には竹槍や鎌が隠され、荷台の陰、さらに兵糧や炭に見せかけた俵や叺(かます)の中には、武器を手にした男たちが潜んでいた。隠しきれない殺気も周囲に立ちこめていたはずである。
だが、それに気付く者はいなかった。
これより直ちに普請にかかるが、その前に、ご領主からのお言葉をいただければ光栄である……。そんな言葉を伝えられ、彼らの前に姿を現すメイル。「おお、大義じゃ。その方ども気持ち、嬉しく思うぞ。いずれ憎むべきハッシバル軍を国から逐(お)い、勝利した暁には、その方どもの志に篤く報いよう。そもそも我がバグハート家は、父上・ニルセイルの時代より――」
だが、メイルは最後まで言葉を続けることができなかった。その時、中の一人がさっと手を挙げ、あちこちで角笛が力一杯吹き鳴らされる。同時に周囲の者たちが、手にした得物を振りかざしながらメイルめがけて殺到する。さらに、城外に潜んでいたマストバーグ一家の手の者たちが開け放された城門から城になだれ込んできた。
城内は一瞬にして凄惨な流血の場となる。
逃げる間もなくメイルはその場に押さえつけられ、生きながら首を鎌で掻き落とされる。血を見てさらに激昂した暴徒たちは扉を打ち破って城の奥へと乱入し、そこにいたメイルの妻子眷属を皆殺しにした。令尹のアンベンバは逃れて便所の中に隠れたものの、たちまち見つかって捕らえられ、馬に縛り付けられて地面を引きずり回された後、よってたかって叩き殺される。
メイルが殺されたことを知った兵士たちは一気に戦意を失い、一部の者たちはそのまま暴徒たちに降り、残りは抵抗することもなく四方八方に逃げ散る。ジニュエだけは、虎賁の兵を率いて辛くも血路を開き、混乱に紛れて手に入れたパドローガルの銀器を抱えて、城から落ち延びていった。
その翌々日、マクドゥマルのティルドラスのもとに、ユックル近郊の村人と、ハッシバル家への投降を申し出るバグハート兵の代表からなる一団が到着する。服従の証(あかし)はメイル子爵の首級である――。
突然のことにハッシバル軍の陣営が大騒ぎとなる中、竹籠に収められた首が応対の者に引き渡され、ティルドラスの前に運ばれた。ただちに、捕虜となったバグハート家の官吏や兵士が呼び集められ、首がメイル本人のものであることが確認される。
――本当か? 本当にメイル子爵の首なのか?――
――まさか、このようなことが。――
――戦は終わったぞ。我が軍の大勝利だ。――
周囲の驚きと歓喜の声を聞きながら、ティルドラスは独りぽつねんと、目の前に置かれたメイルの首を見つめていた。
そう、民を愛さず民からも愛されなかった支配者。これがその末路なのだ。しかし、いったい何が違ったのだろう。今こうして自分の前に首となって置かれている男と、彼を見ている自分。二人の間に、果たして本質的な違いなどあったのだろうか。一つ間違えば、自分もこの男のように、どこかの誰かの前に首となって置かれていたかも知れないのだ――。
「ティルドラスさま?」チノーに声をかけられて彼は我に返る。「帰順の使者と申す者が待っております。お目通りを許されますか?」
「通してほしい。」うなずくティルドラス。
やがて、ケスラーに先導されて、もとが何色だったかも判らないネズミ色のボロ着に身を包んだ、五十代半ばとおぼしい男が彼の前に進み出る。ユックル近郊の村の木戸番だという。イック=レックと名乗ると、身なりに似合わぬ古式ゆかしい作法で丁寧な拝礼を行い、弁舌爽やかに帰順の口上を述べ始めた。
『隠者だな。』ティルドラスはぼんやり考える。乱世は、一方で知識人たちの間に遁世(とんせい)の風を招いてもいる。なまじ才能があるばかりに権力者から警戒されて罪に落とされたり、逆にほとんど脅迫同然の招聘を受けて不本意な相手に仕えた挙げ句に共倒れの目に遭ったりする――。そうした禍(わざわい)を避け、一方で世間とは完全に縁を切らずにいたい知識人にとって、田舎の村の木戸番というのは、確かに格好の隠れ場所かも知れない。
考え込むティルドラスをよそに、イック=レックは口上を続ける。そもそもこの地は本来ハッシバル家の領土であり、ニルセイル・メイル父子によって支配されていたのは決して民の本意ではない。今や伯爵がこの地に至るに及んで、民はこぞってその威徳に服し、嬰児の慈母を慕うがごとく、心から仁主のもとに帰順したいと望んでいる。宜(よろ)しく民意に従われ、新たな国主としてこの国を宰領されんことを――。
ある意味、型通りの申し出であり、対するティルドラスの答えも型通りのものだった。申し出は自分にとって身に余る名誉である。しかしながら我が徳は乏しく、我が才は拙(つたな)く、この地までを覆い包むことができない。ここは国人の中から合議により賢者を選び、国主としてはどうか。隣国の友誼(よしみ)として我が国も可能な限りの支援を行うであろう――。むろん、こうした辞退は形式的なもので、数度の辞退と重ねての懇願という手順を経て、ティルドラスは新たな国主としてバグハート領を統治することに同意する。
勝利の報にサフィアを中心とするネビルクトンの宮廷は沸き返った。この十年来、戦えば必ずと言って良いほど負けていたハッシバル家にとって待望久しい勝利、それも自国への侵攻をはね返し、さらに間髪を入れず反撃に転じて一気に敵の全領土を制圧した、文句なしの大勝利である。お祭り騒ぎの熱狂の中、人々は競い合うように、敗れたバグハート家の吏民への処置について激しい意見を叫び立てる。メイルの首はネビルクトンへと運んで梟首(さらしくび)とすべきだ。彼の父・ニルセイルの墓を暴いて死体を引きずり出せ。彼ら親子に仕えていた官吏も一人残らず捕えて処刑せよ。そもそもメイルのような悪逆無道の国主におとなしく従っていたバグハート領の民が悪い。懲らしめとして年貢を倍にし、刑罰を重くして我が国の威を思い知らせてはどうか。いや、それでは手ぬるい。土地は全て取り上げ、身分を奴婢に落とし、二度と我々に叛く気を起こさぬようになるまで徹底的に痛めつけてやれ――。
巷に満ちあふれるこうした勇ましい、そして無責任極まる声のいくつかは、上書や宮廷からの書簡という形でマクドゥマルのティルドラスの元にも届いた。しかしティルドラスはそうした声の全てを黙殺する。メイルの首は一族の遺体と共にマクドゥマル近郊の小さな丘の上に、簡素に、しかし手厚く葬られた。その後もティルドラスは時折メイルの墓を訪れては、手ずから花束を手向け、地に酒を注いで彼の菩提を弔うのだった。
かつての敵、それも自らの愚かしさによって国を失い身を亡ぼした暗君に、なぜそこまでの礼を取るのか。そんな周囲からの疑問の声に、ティルドラスはこう答えたという。――彼は我なり、我は彼なり、前代の亡びは後代の戒め。豈(あ)に訓(おしえ)とせざる可(べ)けんや――。
メイル=バグハートの墓を見よ。この言葉はその後も長い間、「自戒」や「反省」を促す故事成語として、人々の口にのぼり続けることになる。
この時代から百年ほどのち、若い頃のソン=シルバスが史料集めの旅の途中でマクドゥマルを訪れた折、諺(ことわざ)に聞くメイルの墓を訪れた時のことが『ミスカムシル史大鑑』伯爵・子爵諸家世家(せいか)の末尾に記されている。茨の生い茂る人気のない墓域の中に小さな苔むした墓標があり、そこに、誰が残したのか、真新しい小さな野菊の花束が一つ手向けられていたという……。《了》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
