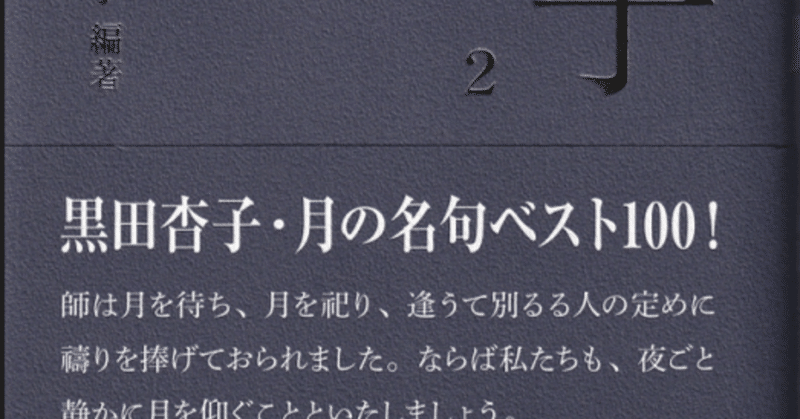
『黒田杏子 俳句コレクション 月』髙田正子編著
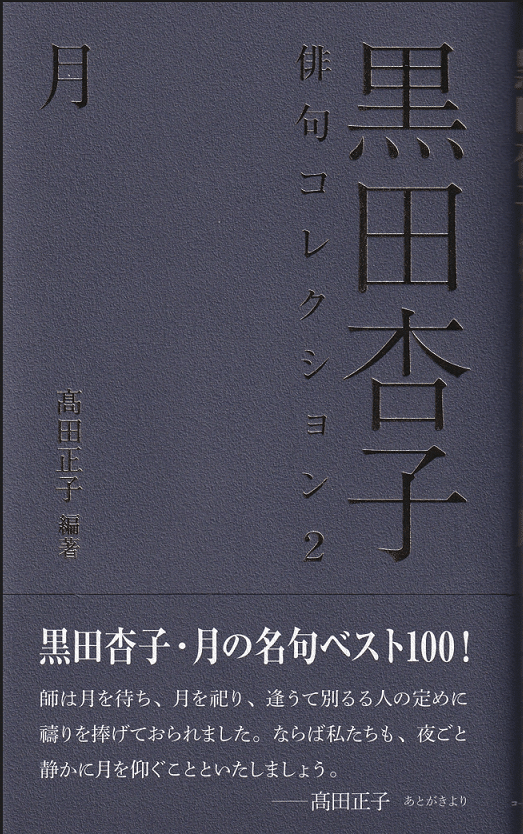
髙田正子編著による、黒田杏子の遺作集「俳句コレクション」の「月」編である。
特に印象に残った箇所を抜粋して紹介する。
※
最終句集『八月』には、
六月二十一日、信州岩波講座まつもと 兜太・杏子公開対談
一行の詩の無尽蔵梅雨の月
がある。兜太は戦争体験を語り継ぐ仕事の相方として杏子を選んだ。ひとりで語るのは難しくても、杏子が相手を務めてくれれば話しやすぐなる気がする、もちかけた兜太の判断は正しかった。インタビュアーとして、対談相手として、また書籍のプロデューサーとして杏子は兜太の伴走を見事に果たした。
戦場体験を兜太・杏子の対話形式で
「語り継ぐ」「こりや楽ぢやねえ」雲の峰 『八月』
かつて杏子は、師の青邨に「金子兜太をどう思うか」と尋ねたことがあった。「あの人はあの人の道を進まれたらよいのではないか」という青邨のことばに背を押され、兜太を「研究対象」にしようと決めたのだという。頼られ、支えながら、それだけで終わらないウィンウィンの関係を築き上げた痛快なコンビであった。
※
やはり戦争体験は大きな「物語」だと思う。
体験した内容は違っても、それがお互いの句道の背景になっているという共感がある世代だ。その後のわたしたちにはないことだ。
戦後高度成長時代、その後の経済失速停滞の時代、その中の個々は孤立していて、多様すぎて連帯のしようがない、孤愁を抱えている。
続いて、わたしが好きな句と、その髙田正子鑑賞文を抜粋して紹介する。
※
月涼し杖いつぽんで歩き出せ 『八月』
二〇一六年作。前年の初秋に脳梗塞で倒れた杏子であったが、リハビリを終えて無事「回生」した。上半身に後遺症は無かったが、杖や手押し車に助けられて
歩くようになった。これまでも杏子にとって「杖」は、遍路の杖をはじめ馴染みのモチーフであったが、文字通り歩行のための杖を使うようになった。韋駄天と呼ばれていたほどであるから、歯がゆいことも多かっただろう。だが「杖いつぽん」あれば歩ける。再びの一歩を、とはなんと力強いことばだろう。この句の「月涼し」は我とわが身へのエールにほかならない。
※
師、黒田杏子への敬意と思慕の溢れる鑑賞文である。
黒田杏子の歩みは次元を超えて、今日もたゆむことなく続いている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
