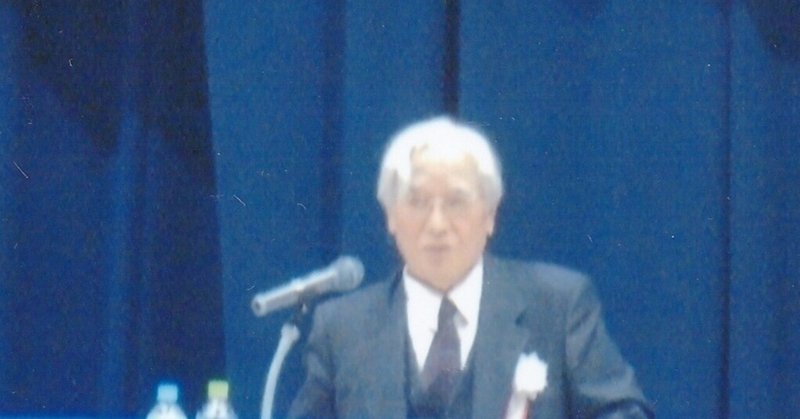
横浜俳話会俳句大会講演録 「俳句創作の「身・魂・言」レッスンのために」
2023年10月29日
俳句創作の「身・魂・言」レッスンのために
―シュタイナーの人智学(アントロポゾフィー)から
武良 竜彦
Ⅰ 第一部 創造性には身体と魂のどんな力が必要か
1 まず、身体の体操から
こんにちは。武良竜彦です。
ずっと椅子に座ったままでお疲れになり、頭がぼーっとしていませんか。これからの私の話を心身がすっきりした状態で聴いていただきたいので、そのための体ほぐしの体操をいたしましょう。照れずにいっしょにやってみましょう。
⑴ 首を上下左右に曲げて、頭をゆっくり回します。
⑵ 肩を回して凝りを解します。
⑶ 足の先を揃えて上下にさせて下半身の血流をよくします。ふくらはぎは第二の心臓といいます。
⑷ 体の余分な力を抜きます。一度全身に力を入れてから一気に開放します。
⑸ 次は呼吸を整えます。正しい吸う息・吐く息のバランスが大切。
有難うございます。みなさん素直に参加していただいて、この後の話がしやすくなって助かります。
2 次は魂の準備体操です
これから、私が子供たちに俳句を教えたときにやった魂の体操を紹介しますので、みなさんも初めて俳句を学ぶ子供になったつもりで、いっしょに体験していていただきたいと思います。今の体操のように、恥ずかしがらずまた面倒がらずに、楽しんでやってくださいね。
俳句の話に、なんで、そんなことをするのかと思われるでしょう。この準備体操をして、その後、シュタイナーの芸術教育哲学を、応用したその意義のお話をします。
魂は五感の総合力といいますので、まずその総点検からです。
五感の働きに纏わる心の動きの自覚と点検です。
五感というのは視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚ですね。
それぞれの感覚に意識を集中して、その感覚が働いているとき、どんな気持ちが沸き起こるか、ということを自覚するレッスンです。
たとえば何が見えるか。それを見ているときどんな気持ちが沸き起こるか。何が聞こえるか。その音に何を感じるか。どんな匂がしているか。その匂いでどんな思いになるか。どんな味がするか。その味にどんな思いが沸き起こるか。どんな手触りか。触ったときどんな気持ちになるか。ということを一つひとつ確かめるレッスンです。
ではやってみましょう。
―実践体験の時間。
身体的な感覚を働かせるとき、意志の力が働いていることを自覚することが大切なんですねー。たとえば聴覚ですが、今私が黙っていたとき、いろんな音が聞こえましたよね。空調の音なんかですねー。その音はこうして私が話しているときも、聞こえていた音ですけど、私が話し出すと聞こえなくなっているでしょう? つまり周りの音を聞こう、と意志を働かせて初めて聴こえるようになるわけです。五感をそのように意志を働かせて感受するという自覚をすることが大切なんですね。
シュタイナー芸術教育哲学によれば、魂の力はそういう身体感覚由来の気持の働きが、意識されて統合され、高度化したものだというのですね。俳句を含む芸術の創造は、そのことの自覚がベースになっているというわけです。
3 魂の力の実践・レッスンと、共感する喜びの体験です
俳句を詠むには基本は想像する力が必要です。
私が子供たちにした授業で最初にびっくりしたことですが、「目を閉じて、海岸を思い浮かべてみよう。一人ひとり違う景色が浮かぶはずだよね。目を開けて、今見えたものをことばにしてくれる人、手を揚げて」ということをやったとき、「え、何それ、わかんない」という子がいたんですよ。そんな子にどうすれば想像力を働かせることができるか、説明できるかちょっと考えてみてください。
どうですか。いい案が咄嗟に浮かびますか。なかなか難しいでしょう? 子供たちにどう説明すれば解ってもらえると思いますか。
想像力とは平たくいえば、眼の前にないものを、まるであるかのようにありありと思い浮かべる力のことですね。
それで私が考えたレッスンの方法を今から紹介しますので、これも子供に還ったつもりで恥ずかしがらずにやってくださいね。
最初は絵、そしてその印象、そして言葉化するという段階です。
―カード 丸 四角 十字 星 波

ESPカードと言って、超能力開発に使うカードなんですが、思い浮かべ易い象徴的な形ばかりですよね。
ではStep①です。
目の前に無いもの(カードの図)を思い浮かべる練習です。
一つひとつの図形をじっと見てから、目を閉じて同じ形のものを思い浮かべる練習です。目を閉じて手を前に伸ばしたあたりに、自分専用の白いスクリーンのようなものがあると思ってみてください。
どうですか、スクリーンが出ましたか。
では、そのスクリーンに図形を思いうかべる練習です。やって見ましょう。
―実践 丸 四角 十字 星 波
どうですか。図形が浮かびましたか。
浮かんだ人は、目の前にないものを思い浮かべたのだから、想像力を働かせることができた、ということになりますね。
これが想像力という力の初歩的なものなんですね。
大人になると言葉でばかり思考するようになって、この力が錆びついてしまいがちなんですね。言葉への依存度が低い子供時代ほど、これが得意です。古代人もそうだったんでしょうね。
ソロバンの達人はソロバンの盤面を絵で思い浮かべて、それを頭の中で弾いて、あの高速暗算ができるようになるそうですね。
画家の山下清は一度見た風景を、その場ではスケッチしないで、後で思い浮かべて、そっくりに描くことができたそうですね。
今を時めく、将棋界の藤井聡太くんは膨大な指し手の盤面を図として記憶していて、その前後の指し手の変化を秒速で頭の中でシミュレーションできるそうです。羽生さんも同じで、NHKのドキュメンタリーで、スクリーンに高速で指し手を変化させる映像を見た後、それを現実の盤上で再現してみせていました。これは映像として思い浮かべて記憶できるという意味で、想像力の発展形ですよね。
俳句会で主宰が、「景が見えて、いい俳句だね」などといいますね。何故、景が見えるのがいい俳句なんですか?
それは俳句に限らず芸術一般は、この絵画的なイメージを大切にして、このイメージを受け取ることで、芸術的な主題を受容しているからなんですね。芸術の伝達の基本的な仕組みだからですね。
俳句創作の基本はこのような実体験のリアリティをもった、映像としての景を、想像する力を働かせることが、重要だとされていますね。これでなんだか、俳句が詠めるようになる力のことが、解ったような気になりますね。ここまでは想像力を使って、俳句などを創造する、つまり、作る段階のレッスンですねー。
では、うまく俳句が作れれば、俳句の力が判ったことになるでしょうか。ならないんですね。もう一つ大事な力が必要なんです。
それは、他の人に伝わって欲しいと願う力ですね。受ける側からいえば、他人の創作物を、感受性を働かせて鑑賞する力でもありますね。
俳句は作者と読者がいて、それを受け止めてもらう人の存在が必要で、その人が自分のように想像力を働かせて、受け止め、鑑賞してくれることが前提になっていますね。
中には自分独りで楽しんで作っているだけで、他人は関係ないという人もいるでしょうが、俳句の座の文芸としての愉しさを放棄するのはもったいないですね。
俳句会を開いて、自分の俳句に共感してくれた人が多いと、嬉しいですね。それは何故ですか?
人間は独りひとり、ふだんは孤独な存在だからです。
心が通じ合ったと思った時、嬉しくなるのは、もともと孤独な存在だから、その孤独感が癒されたような気になるから嬉しいのですね。
つまり、俳句を詠むということは、そこに込めた自分の心を受け止めてくれる他者の存在を信じるということを大前提とします。句会でたくさん票が入ったときうれしいのは、他の人と心を共有できたという歓びゆえなのですね。その体験をゲーム的に疑似体験してもらうゲームを今からやりたいと思います。
Step②の願う力と分かち合う歓びの体験です。
私が、今からこのカードの中から一枚ずつ引いて、思い浮かべて、みなさんに念で送りますから、自分の心のスクリーンに、どの形が浮かぶか、体験してみてください。浮かばなくてもいいですよ。
誤解の無いように先にお断りしておきますが、これは「当てる」ことが目的ではなく、当った時に沸き起こる「嬉しい、楽しい」という心の動きの確認の方に主眼があるゲームです。だから、当らなくてもいいんです。相手に届けと願う気持ちと、届いたとき嬉しいと思う気持ちを、確認する体験のゲームです。
―実践。(※講師が想念で送ったカードをみんなで当てるゲームと、みんなが思い描いたカードを講師が当てるゲームの実践。この日はその双方が見事に当てられるという奇跡のようなことが起きました)
先にも言いましたが、これは当てることが目的のゲームではなく、当れ、と願う体験と、当ったときの喜び、他人と共有できたという歓びの疑似体験が目的です。今日はみんな当りましたね。奇跡のようですねー。子供たちとこれをやると、不思議なことに、かなりの確度で当るんですよ。当てることが目的のゲームではないんですけど。
これが芸術的な交歓の心的な仕組なんですねー。俳句会でみなさんが行っているのは、つまりこういう心の働きを使っているというわけですねー。俳句という座の文芸の愉しさの秘密はここにあるんですねー。
Step③は①と②を言葉の力に置き換えるレッスンです。
子供たちには、すきな海と山とか、好きな風景を思い浮かべて、何が見えて、それを見ていて、どんな気持ちになったか、言葉にしていくレッスンです。
こうして、最初は「わかんないよ」と言っていた子供たちも、自分が好きな風景を心に思い浮かべることができるようになるわけです。
ここまでくれば、心身の力を使って俳句を詠むことができるところまで来たことになりますよね。
レジメには書きませんでしたが、もう一つ仕上げのステップがあって、最後の課題として、物語性のある場面のヒントを揚げて、どう思うか尋ねて、それに応えてもらう練習をしました。
―実践 場面性、物語性の言葉化の体験
今から私のナレーションを目を閉じて聴いて、その場面を思い描いてください。いいですか。「街なかに小さな公園があります。片隅に古びたベンチが見えます。おや、何か置いてあります。なんでしょう。ああ、小さな可愛いお人形さんですね。どうしたんでしょうね。『どうしたの。どうしてここに一人ぼっちでいるの』とお人形さんに話しかけてください。はい、目を開けてください。さあ、お人形さんは何と答えましたか。どなたか、思い浮かべられた方、発表していただけますか。
(会場で挙手があり、人形の気持になって応えてくださった方がいました)
拍手。すばらしいですね。そんな感じでやって欲しいのですね。
子供たちの答えで一番多かったのが、わすれられた、捨てられたでしたが、その中でとてもユニークで、びっくりさせられた例を紹介します。
例⑴「気が付きましたか。私は地球の様子を見に、天国から伝わされた天使なのです。他の人には内緒ですよ」
例⑵「私を余り大切にしてくれない家だったので、いやになって逃げだしてきたの。でもこんな夕方になって、寂しくて寂しくて、困っていたの」
例⑶「フフフフ。私は地球人を滅ぼしにきた宇宙人なのだ、アッハハハ」
いかがですか。想像力のこの豊かさ。びっくりしますねー。
ここまで来たら、もうどんな俳句も詠めそうな気がしませんか。物語だって書けますよねー。
文学的なモチーフの形成というのは、こういうことではないですかね。誰かに伝えたいという願いと、伝えたい思いが自己の中に在ることが第一歩です。創作に必要なモチーフのことですね。このように、伝えたいことが自分の中にないと、何も始まらないわけです。
今日の演題は〈俳句創作の「身・魂・言」レッスンのために―シュタイナーの人智学(アントロポゾフィー)から野木桃花メソッドへ〉ということで、何やら難しそうな演題で、レジメには第一部と第二部の資料を準備しましたが、たぶん時間的に第二部の1まではなんとかお話できたらいいなと思っています。残りは、ご自分で読んでください。またはこの二部の方の話も詳しく聞きたいというご希望や機会がありましたら、またいつか、お話できたらいいなと思います。
第一部は「創造性には身体と魂のどんな力が必要か」という観点からの話で、実際に私が小中学生に行った俳句、短歌、詩、随筆、物語の、表現創作講座というもの中の、俳句の授業の最初の部分を今、体験していただきました。
私が子供たちに俳句や短歌や詩や随筆、物語のことを教えるようになった切っ掛けは、昔、都内のマンションに住んでいたとき、同じマンションに住んでいたお母さんが、「この学研の『小学五年生』という学習誌に童話を書いている方ですか」と尋ねて来られたのが最初の切っ掛けです。童話の作者名と同じ名前が郵便受けにあるのを娘さんが見つけたんですね。そのとき掲載されていた「キララと十八匹のこどもたち」という、私が書いた童話が気に入って、それを書いた人なら、いろんなことを聞きたいから、おかあさん、聞いてきてって頼まれたようなんですね。
その娘さんは学校でいじめにあって不登校になっていて、それで娘が自分から進んでそんな頼み事をすることが嬉しくて、ご迷惑でなければ娘の願いを聞いていただけないか、ということなんですねー。それで、それは私も嬉しいですねーと、お招きしてお付き合いを始めたのが、私が子供たちに授業することになる切っ掛けなんですね。その女の子は「どうしてあんな話を思いつくの」と目を輝かせて私を質問責めにしたんですねー。それから私の本棚から、その子が気に入った本を選んでいっしょに読んで、いろんな話をしました。楽しかったですねー。自分で詩と短いお話を創るようになりました。
それがしばらく続いた後、お母さんが見つけたフリースクールには行けるようになったそうなんです。その子が通い始めたフリースクールの運営者の方が訪ねて見えて、文学的なセンスの豊な子たちがいるから、何か文学的な授業をしてもらえないかと相談されて、それを引き受けたわけです。ボランティアで
そこの子供たちはいろんな形で心に傷を負わされた子たちですけど、本当に感性が豊かで、私が選んで持っていた文学作品の全ジャンルの朗読をしてあげて、感想を自由に述べ合って、自分でもこんな作品を書いてみない? と勧めただけで、次の授業の日には、びっくりするよう作品を書き上げて、「読んで、読んで」と私の感想を聞きにくるんですよ。これも楽しい体験でしたねー。
この子たちには「文学とは何か」なんて、改めて教える必要はなかったので、みんなそんなものだと思っていたんですよ。
でも、そうばかりではない、という体験をこの後にすることになったんですね。それは進学塾の方が塾で特別授業をしてくれと頼み来られたのが始まりです。その塾で使っている教材開発会社のプリントに、私の『メルヘン中学物語』という童話の一部を、記述式問題にしたものがあるので、その作者に授業をしてもらいたいというのですね。童話を書いたのは私ですけど、国語問題を作ったのは、私じゃないですから、そんな授業はお受けしかねます、と断ったんですね。
でも諦めずに何度も訪ねて見えて…。というのは、最近、国語の入試問題に記述式問題というのが増えて、進学塾に来ている生徒たちは、論理的な文章の読解と記述式問題は解けるのに、文学的文章が課題のとき、さっぱりできない、という話なんですね。
先生たちもどう指導すればいいか困惑したそうですが、結論として、作家は書いた方の人だから、記述式の読解と答えの書き方のヒントをもらえるのではないか、という相談で、できれば模範の授業をしてもらって、先生たちも勉強して、先生たちが習熟するまで模範の授業をして欲しいという依頼なんですね。
何度も訪ねて来られる熱意にほだされて、つい引き受けてしまったのですねー。ところが、いざ行ってみたら、本当に困りましたねー。
フリースクールの子どもたちは、教えなくても感想文や作品を書けるのに、進学塾の生徒は、私が出来て当たり前と思っていたことが、さっぱりできないんですよ。
これはどうしたことなんだろう、この子たちに文学というものを、どう教えればいいのだろう、と迷いに迷って最初の半年は過ぎてしまいました。そしてだんだん解ってきたのです。
進学塾の生徒たち知識の分野では優秀な子供たちですが、なんでも知識として受け止めて、その知識をそのまま正確に表明する論文の読解には優れていても、文学的文章の読解と記述式問題は苦手なんですね。そこに問題のすべてがあったのです。
一言で結論を言いますと、文学という心の領域のことを受け止める心が育っていないことが問題だったようですねー。
精神的な傷を負うほど魂の深い、フリースクールの子どもたちにような文学的なセンスのある心を育てることから先ず始めないと、俳句だの短歌だの詩だの随筆だの物語だのといったって、チンプンカンプンなわけなんですねー。
そのことは解りましたけど、じゃあ文学的な表現を鑑賞できる心をどうやって育てるのか、ということになったわけです。
そこで、いろいろ教育学の本を読んで勉強しました。
ルソーの『エミール』や、ペスタロッチの『ゲルトルート教育法』や、フレーベルの『人間の教育』などの教育理論の本を読みました。
子供を子供として大切にしようとか、発達段階に合った指導が大切だとか、世の中の悪から子供の心を守ることが大切だとかは書いてありますけど、その心をどうやって育てるのかは書いてないんですよ。せっかく読んだのに全部役に立たないわけです。
諦めかけて最後に読んだのがシュタイナーの本だったのです。
シュタイナーの人智学(アントロポゾフィー)における芸術教育哲学で説いている、心というものについての視座が、とても参考になったのですねー。見事に心の原理が解き明かされていて感動しました。
シュタイナーによれば、心というものは先ず、身体的な五感によって体験したものが、心の機能となったもの、というわけです。
その理論を実践化したものを、たった今、みなさんに体験していだだいたわけです。これでさっきのゲームの意味が解ってもらえましたか。その体験の意味のまとめをしておきますと、魂の力というのは、
感性、知性、意志、悟性及び霊性の総合力だということですね。
⑴ 感性……かんじる力。(共感力と想像力が働き、魂が豊になる)
餌に対する生物学的快感が発達したもの。自分を生かす喜びです。
⑵ 知性……かんがえる力。(集中力と理論力がつく)
自分が他の生き物の餌となる危機から逃れようとする生物学的な危機感が発達したもの。だから知性ばかり働かせる状況は緊張を強いられ魂は疲弊しがちだというんですね。
⑶ 意志……ねがう力。(身体的欲求から精神的欲求へと発達したものです。自分を生かしている力を悟性の働きで自覚する神秘的な力です。
この総合力の悟性・霊性が魂の力というわけです。
もっとも大切なのは「意志」の力で「感性」と「知性」を統合する創造性が人間の魂の力の基本だということですねー。
この「シュタイナーの人智学(アントロポゾフィー)」を略図にすると次のようになるでしょうか。

以上が私の俳句指導の考え方と実践なのですが、神奈川県に引っ越してきて、野木桃花先生と知り合って、「あすか」という結社の俳句会に招かれて勉強会を開かせていただいているんですが、そこで実践さている「野木桃花メソッド」というのがありまして、それが、私が実践したシュタイナー哲学の考え方と同じで、びっくりしたんですね。それをここで紹介します。
4 野木メソッドのドッキリ・ハッキリ・スッキリ
◎ 高次な抒情の中にドッキリ・ハッキリ・スッキリと自己を表現したい。
○ ドッキリ 自分らしい発見感動のことで、日々の生活の中で四季
折々に出会う自然や人事など、すべてのものに敏感に
反応する素直な心。
○ ハッキリ 余分な言葉を省いた具象的な表現で、共感を誘う自己表現をすること。
○ スッキリ 季語や切字の働きを最大限に生かした定型の句で、表現は簡素に、心情内容は深い俳句。
このように提唱されているのですね。
ドッキリが、シュタイナーのいう感性の力。
ハッキリが、シュタイナーのいう知性の力。
スッキリが、シュタイナーのいう意志と悟性の力。
シュタイナー哲学と同じ考えですよねー。
これらのことを踏まえて総括的に俳句表現で言えることは、次のことではないでしょうか。
① 知性だけで俳句を詠まないこと。「理屈俳句」は人を理屈で説得しようとし魂を痛める。
② 先ず感性(感じる力)を大切にして、物・景・ものごとの場面と心の在り様を想像する。
③ ここで初めて知性を働かせ、言葉の力でそれを鮮やかに造形表現する。
④ 自分の俳句表現を自分以外の人に共感してもらうには、その思いが届くよう「願う力」を働かせることが大切。自分が俳句で表現したことが、他の人にも気づきと共感を促し、かつ、自分を生かしているこの宇宙・自然の有り様にとっても「真」と呼べる表現であるか、悟性の自覚する力で検証する。
⑤ 感性と知性の往復だけ詠んだ俳句は 、狭い自分だけの「主観」から脱皮できない。
⑥ 自分のだけの独善的な感慨の表明に終わらないように、自分以外の人にとっても共感できる普遍性のある表現をするには、悟性の力が必要になる。
⑦ 悟性の力とは、自分を生かしている力を悟性の働きで自覚する神秘的な力であり、その視点を他の人と分かち合える表現になっているかと、思いを深めること。
⑧ 個人的な感慨表現から命と魂の普遍性に向かう表現へ。
というようなことではないでしょうか。
私が野木先生の句で代表作だと思っているのは、次の句です。
火に仕へ水に仕へて昭和の日 野木桃花
人間は自然のものを人間の好きなよう使っていいとして酷使して、公害問題など、いろいろなことを引き起こしてきましたよね。野木先生のこの句は、人間の方が自然の力に「仕えて」生きると言う謙虚な生き方の表現で、個人的な感慨を超えた普遍性がありますよね。
第二部 言葉のどんな力を働かせるか(文学的創造性とは)
ということで、いよいよ俳句論らしい、言葉の問題に入ります。
Ⅰ 言語表現の種類―説明的表現と文学的表現
文章表現は大きく二種類に分けられますよね。
説明的表現と文学的表現で、吉本隆明は『言語にとって美とは何か』という本の中で、それを指示表出と自己表出というように呼んでいます。つまり文学的文章は自己表出という表現なのですね。理屈だけの言葉で生きる社会では人間は息苦しくて、自分を生かす自己表出の表現が必要で、それが文学の役目だというんですね。
この説明的表現と文学的表現を、子供たちが詠んだ俳句と、その後の推敲指導の結果の違いで説明してみます。
最初、子供たちは自分の気持丸出しの次のよう句を作るんですね。
梅雨の時期じめじめしてて嫌いだな
雨ふれば服がびしょびしょ気持ちわるい
お祭りで食べてばっかりいもうとは
これを学校の俳句の課題で出したら、「いい俳句ができたねー」って、先生に褒められたっていうんですね。困ったもんですねー。学校の先生は文学の専門家ではないから、これが俳句ではなく、五七五で書いただけの説明文だ、という指導ができないみたいなんですね。
この句で伝わるのは、そのように言っている小学生がいる、ということだけで、こう表現されても、読んだ者は同じ気持ちにはならないですよね。説明文というのは、その状況を詳しく説明することはできますが、それを読んだ人が同じ気持になるとか、心が動かされるような伝わり方はしない文章なんですね。
つまり「気持ち言葉は気持ちを伝えられない」のです。説明するだけで、心底共感することはないですね。頭で解るだけです。
そう思っている、その人の気持の説明だけでは、心は伝わらず共感作用は起きない。ではどうすれば文学的表現になって共感してもらえるか、ということになりますが、もうそれは簡単なことで、そう思って場面を思い出して、つまり「景を詠む」という俳句の方法を工夫するだけのことですね。どんなとき、そう思ったの? という具合に問いかけて思い出させて、それを言葉にしてゆくわけです。それでいい場面を思い出して言葉にできたら、「あ、今のいいね、それだよ、それを書こうよ」という具合に表現のゴールに辿りつくわけです。
最初の二人の子は次のように作り直すことができました。
しまってたケーキは黒いカビだらけ
梅雨にぬれ下着が肌にまといつく
どうですか。これなら読んだ私たちも、いやだなーという気持ちになって共感できますよね。これが文学的表現なんだねー。これは俳句になったねー、と言うと、ああ、そうかーと解ってくれます。
三番目の「お祭りで食べてばっかりいもうとは」の句を作った女の子には、これだと君は妹が大食いなので呆れてるか、厭だなと思ってることになってしまうけど、そんな妹が嫌いなの、と尋ねると、可愛くて大好きなんだというんですね。夏祭のどんなときにそんなことを感じたわけ? と聞くと、「自分の頭くらいの綿あめに必死に齧りついて、どっちが綿あめかわかんないようになって、おかしいでしょう」というんですね。「それ。いいね、それじゃない。それを書こうよ」というと、必死に推敲して、持ってきたのが次の句です。
綿あめになった妹夏祭
すごいでしょう、この句。可愛いと言わなくても、妹の可愛さが見えますし、お姉ちゃんが妹のことを可愛いと思ってる気持ちまで伝わって、心が揺さぶられて共感しますよね。すごいねー、これぞ俳句だねー、文学だねーと言うと、「ああ、こんなふうにいえばいいだー」と解ってくれるわけです。
つまり、俳句は「言わないで言う」こと、「気持ちは言わないでも、場面を語るだけで伝わり、共感してもらえる表現なんだ」ということですね。それを実感してもらうことが、俳句指導というものではないでしょうかねー。こういう指導をすると、進学塾の子供たちも文学的文章の記述式問題が書けるようになっていくんですね。
そして最後に大切なことは、世界は自分の外ではなく、内側にある、ということです。想像力で自分の中に取り込まれたことが、映像的な表現として、外に自己表出する形で表現されるということですね。そのことを略図にすると次のようになるでしょうか。
A図が科学的な認識ですね。
B図が、すべてが自分の中にあるという、芸術的、文学的認識ですね。こうやって自己の中に取り込まれた世界が俳句の素材です。
A図 科学的認識 すべてが自分の外にあるという認識

B図 芸術的認識 すべてが自分の中にあると言う認識

もう講演の残り時間が少なくなりましたので、レジメの残りは概略の説明だけにさせていただきます。
機会がありましたら、この後半のお話は改めてじっくりと、お話させていただきたい思います。
Ⅱ 俳句表現とは何か
1 方法論の違いは、対立ではなく多様性
表現方法の話になると、すぐ伝統俳句とか、前衛俳句または花鳥諷詠俳句、社会性俳句などという違いなどの話になって、その方法論の違いで無意味な対立をしてきた歴史があるようですね。最近は論争が下火で、それがなんか表現力の衰えのようにいう方がいらっしゃるようですが、それはただの多様性という問題に過ぎないのではないでしょうか。いろんな表現があってもいいわけで、互いに認め合って、表現を豊にしてゆけばいいだけの話ですよね。
アメリカの作家で評論家のス―ザン・ソンタグは「多様性を認めない文明は滅ぶ」と言っていますね。九・一一でアメリカがテロを受けたとき、アメリカは偉大だ、今こそ一つになって、敵に立ち向かおうと、社会全体がそんな意見一辺倒になったのを痛烈に批判したんですね。それで家を襲撃されたらしいですけど。彼女に言わせれば、アメリカがなんでそんな目に遭ったのか、立ち止まって考える人がいないのが、とても危ない、というわけです。
堀田季何さんは「俳句は認識の詩」だと言っていますね。多様な認識がある詩の世界だという考えなら、違いは対立ではないですね。
堀田さんの、認識別の俳句表現の例は、レジュメで紹介していますので、それをご覧ください。
私なりに、この堀田式で有名な句を分類すると、次のような感じになるのではないでしょうか。
遠山に日の当りたる枯野かな 虚子 「存問俳句」
人体冷えて東北白い花盛り 兜太 「象徴造形俳句」
頭の中で白い夏野となつている 窓秋 「観念造形俳句」
野菊まで行くに四五人斃れけり 枇杷男 「実存造形俳句」
こうして、多様で豊かな表現が産み出されてきているんですね。
2 「俳句は比喩を創り出すこと」
こういったのは金子兜太ですね。詩も俳句も韻文は多様な比喩表現を使って、表現を豊にしてきた歴史がありますね。何も俳句に始まったことではなくて、万葉の時代からそうだったわけです。レジュメにその参考例を揚げておきましたので、もう時間がないので、後で読んでいただければ幸いです。
3 高野ムツオが佐藤鬼房から継承した「小熊座」の理念
最後に私が所属している「小熊座」の俳句理念を紹介します。その同人ですから、私もこの理念に従っているわけです。佐藤鬼房の俳句理念は「人間風土」を詠むということです。つまり、そこで生きている人間の存在感の詩が俳句だという理念ですね。
時間がありませんので、そのレジュメも各自、読んでいただければ幸いです。
◎ 結びに
子供たちの例の話のくだりで、フリースクールと進学塾の子供達の違いを話しましたが、それは私が一例ずつ体験しただけのことですから、特殊な例かもしれません。一般論として語ると語弊があります。一例としてお話ししただけです。でも、進学塾の子供達が、文学が「解らない」と正直に言ってくれたので、文学ってなんだろう、それを教えるとはどういうことだろう、そもそも文学に必要な心の力ってなんだろう、と、私が根源的に考える切っ掛けを与えてくれたわけですね。その意味でその子供達に感謝しています。
今日は、俳句に精通した方たちの前で、俳句に取り組む前の段階のお話をさせていただきました。見当違いの話だったかもしれませんが何かの参考になりましたら幸いです。ご清聴、有難うございました。
参考文献
『シュタイナー教育入門─現代日本の教育への提言』高橋巖 (著) 若松英輔(監修 解説) 亜紀書房(叡知の書棚) 二〇二二年刊 ※角川選書で再刊
『人智学・心智学・霊智学』シュタイナー・高橋巖訳 ちくま学芸文庫二〇〇七年刊
「現代俳句界の表現多様化の見取り図―明日も春を待つー俳句の十年後の問題」堀田季何「季論21」二〇二〇年夏号
『同じ時のなかで』スーザン・ソンタグ 木幡和枝訳 NTT出版 二〇〇九年刊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
