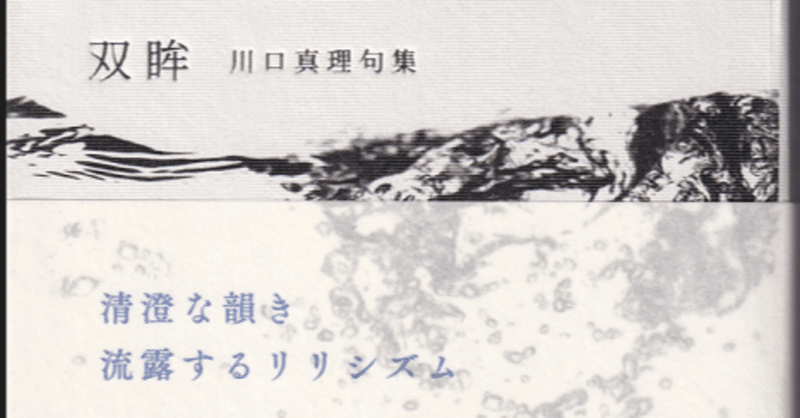
川口真理句集『双眸』を巡って


川口真理の句集は、第二句集を先に読み、その為人と作風に触れているので、第一句集である『双眸』は、刊行の逆順に鑑賞することになる。
第二句集『海を醒ます』については、本ブログにて紹介しているので、そちらも是非、読んでいただきたい。
川口真理句集『海を醒ます』 |武良竜彦(むらたつひこ) (note.com)
https://note.com/muratatu/n/nd498c3f1393e
『海を醒ます』の鑑賞で、わたしは次のように述べた。
※
「海を醒ます」という作者の詩句の指し示す謎は、認識の詩であるわたしたちの俳句世界の、そのことへの覚醒ということでもあろうか。
わたしたち俳人の認識の海面を覚醒させようと、句集『海を醒ます』という、認識の一行詩集は、その謎の只中にそっと置かれているかのようだ。
※
このように、どこか哲学的思念を感じさせる作風を感じたのだが、そんな作者はいったい、俳句の扉をどのように開き、この地点へと至ったのだろうか。
前置きは以上にして、早速、その航路を辿る旅を始めよう。
句集『双眸』には二人の俳人による序と跋が収録されている。
先ず、故人となった大牧広の序文から紹介しよう。
タイトルは「すずやかな詩性」。
※
双眸の黒々として夜の秋
川口真理さんの初期の頃の作品である。自画像と思われる作品であると思う。「双眸」という言葉は、単に二つの眸、ということではなく、聡明な黒目勝ちの眸を思わせるのである。その点が日本語の深さを思わせるのだ。
ふと何気なしに鏡を覗く、すると黒々とした眸の自分の顔が現れる。この二つの黒い眸、それは今まで自分が気のつかなかった以上に鮮明に心に残ったのである。暑い夏も一段落して秋を感じさせる夜、その心に残った黒い眸が自愛に似た気持を誘い、心を豊かにさせたのである。
(略)
やがて著者は田中裕明の「ゆう」門を主にして作品を発表して、「ゆう」時代に「俳壇賞」を受けたことを知った。田中裕明という夭逝した天才が澄明な作品、すぐれた作品を残したが、師の薫陶を受けた著者の作品も鋭く澄んでいて、筆者のようなすこし世の塵にまみれた作風をなす人のところへ拠られたことに忸怩とした思いを抱いたことが記憶にある。
(略)
こうして抄出してみると、川口真理俳句は時空を越えたすずやかで知的な俳句であることがわかる。
現実からは知的操作をもって離れてすずやかな「詩」を発見している。そして、その「詩」は体温を感じさせるのである。このような「俳句」を納めた『双眸』を、自信をもって推す倖せを味わっている。
※
続いて中島鬼谷氏の「跋」を紹介しよう。
※
(略)川口真理の作品に出会ったとき、あたりの空気が透明度を増し、少しひんやりしてきたような思いにとらわれた。
(略)うつし世から膜一枚へだてた向こうにある世界を垣間見たような、不思議な雰囲気を湛えた作品群である。私はこの作者にただならぬ詩才を感じたのであった。
(略)川口真理が初学の頃、田中裕明に学んだことは幸せだった。裕明の句の中に時折現象する不可思議な世界を体得した人こそ川口真理だからである。だが、真理の句は裕明句のなぞり書きではない。川口真理は透明なかなしみを詠う俳人として自立してきた。(以下略)
※
大牧広と中島鬼谷氏の証言のように、川口真理は最初から川口真理として自己の世界を持つ完成した姿で俳句界に登場したようだ。
では秀句揃いの句集の中から、特に強く印象に残った作品を抜粋して紹介しよう。
「自画像」の章から
双眸の黒々として夜の秋
夏草や今宵生れし児の匂ひ
自画像の強きまなざし濃紫陽花
ヴァイオリンになる樹と思ふ十二月
美しくほどけぬ紐や春寒し
炎天のゆれたる紐をつかみをり
焚火消え乾ききつたる翼かな
一瞬の君一瞬の冬の薔薇
野分雲みしみしものを食べるなり
※
炎天のゆれたる紐をつかみをり
焚火消え乾ききつたる翼かな
読者も一読して気付かれると思うが、表現のステージが尋常のものとは一線を画している。ただの写生描写などではなく、また、ただの心象造形表現とも言い難い。哀調を帯びた、流れるような不思議な韻律性をともない、虚とも実とも、景と想ともいえない、独特の表現世界が創造的に展開されている。
作者の訴えようとしている主題の在処だけが、静かな韻律の彼方に見え隠れしているのを感じるが、「作者はこんな気持ちを表現したいに違いない」と、訳知り顔に解説したとたん、この淡い世界からわたしたちは遠く隔てられてしまうだろう。
わたしを含めて、俳句界は未だ川口真理俳句を評すに適した視点や言葉を持っていない、ということだ。
敢えて言うならば、想いが想いとして言葉化され造形される前の、無意識より意識に近いが、ことばになることが拒否されているような、繊細な心の手触り、というところか。
生きて在ることの孤愁のような旋律。
そう書きながら、こんなことなど書かず、ただその心の旋律に酔っていれば良かったと、評者に後悔させる独創的な表現世界である。
「海の砂」の章から
十六夜や胸にこぼるる海の砂
立冬や海にもつもと近き指
日の深きところに立ちぬ蓮枯るる
冬の霧身を閉ざすとき濃かりけり
悼田中裕明先生
逝く年の空に解く紐ありにけり
ゆつくりとこの世にまぎれ春の間
亡きひとのうしろに昼の雪解水
野遊びのさびしき紐をほどきけり
笹ちまき身の透けるまで歩きけり
新しき傷に日の射す桜貝
虹のあとあはき交はりのこりけり
白靴や波間は瞳ゆたかにす
湖底よりつめたき小鳥来てゐたり
朝霧や同じ言の葉深く持ち
※
逝く年の空に解く紐ありにけり
野遊びのさびしき紐をほどきけり
川口真理俳句のキーワードの一つの「紐」が使われた二つの句。最初の句はかつての師、田中裕明への悼句である。
前の章にも、次の二句があった。
美しくほどけぬ紐や春寒し
炎天のゆれたる紐をつかみをり
通常の連想として紐という言葉からは、細長く切れやすい危うさ、紐解く(繙く)ということばから、何かを学ぶ、その世界に繋がろうとするような意思のようなもの、「帯解き」と同意とする辞書的な意味からは、着物の付けひもをとって、初めて普通の帯を締める祝い、中世末ごろから男女とも五歳、のちに女児七歳の十一月吉日に行い、江戸中期ごろから十一月十五日の七五三に移行したとされる、子どもの成長の通過儀礼などを想起する。
要約すると、繋がろうとする意思、その関係の危うさ・儚さ、成長、つまり別の世界への旅立の意思のような語感を、この句の「紐」は背景に含ませつつ、作者独得のものが付与されている表現語になっている。
どの意味にも回収されない、想念以上、言葉未満の思いの所在だけを指し示す表現語であり、世によくある一対一的な比喩でもなく、暗示的な暗喩でもない。西洋詩の歴史を引き摺るサンボリスムでもない。
川口真理詩語としか呼びようのない表現語である。
「紐」とは何かという問いすら無効になる詩語であり、まさに詩世界にだけある何かなのである。読者はそれを意味的な解釈なしで、想いの塊のようなものとして感受するほかはない。
そう「解読」すれば、ここに揚げた句すべてに通底する表現の秘密に少しは近づき得たと言えるだろうか。
言葉で言葉以前の思いの根源、発生の瞬間を指し示す俳句。
こんな俳句が今まであっただろうか。
川口真理以前にはもちろんなく、川口真理以後もないだろう。
俳句界は未だ、この独創性の真価を理解できるステージにはないことだけは確かだろう。
世には意味が溢れている。
世には合理的に説明のつく言葉が溢れている。
そんな言葉たちで出来ている社会はわたしたちの魂を窒息させる。
詩はそのことに対する批評性を孕み込み、自己表出という唯一無二の存在性の表現を目指すものではなかったか。
川口真理俳句は、その最先端の地平を切り開こうとしているのではないだろうか。
「はらから」の章から
夫
骨肉の透きてゆきたる十二月
露草や乳房に力生れはじむ
満月を押しくる狩の匂ひかな
夫の忌日
地につかぬ花びら十二月十四日
遺品みな雪の樹間のごとくかな
我が顔にさくらのいろのうつらざる
面上げて柱現はる厄日かな
※
前半は自らの身体感覚から立ち上ることばたち。
そして、後半はどこにも至り着くことのない「喪」の想いのゆらぎ。
そして何か対してのかすかな違和感。
面上げて柱現はる厄日かな
「柱」は川口真理俳句のふしぎなキーワードの一つである。
次の章には、
枯野道柱しづかに降りてゆく
という句もある。
何か確たる意義をもって現前しようとしているものの気配か。
日本の伝統的語彙では「柱」は神の依り代であり、また多数のために身を犠牲にする個としての命の暗喩であった。
その「意味」性をやわらかく拒否しつつ、しかし、言葉の「概念」という空洞化へ誘う作用に対する違和感のようなものとして、句集の中に置き直されている。
明示的ではないが人の心に確かにあるリアリティ。
こんな俳句は川口真理にしか詠めないだろう。
「元町」の章から
大震災から一年
日射し死すそこに小さき春日傘
棒立ちの空の真中のこほろぎよ
みちのく五句 ※注 そのうちの三句
白鳥や真新しきは死者のこゑ
枯野道柱しづかに降りてゆく
黙々と電柱傾ぐ白鳥来
道草の昼の閑や開戦日
元町の本の匂ひや阪神大震災忌
憲法記念日あけがたの雨甘かりき
夏つばめ父の歩幅の匂ひかな
父の日のしづかな身体風押しぬ
星を待つ鎖骨に雨や青芒
広島忌夜のハンカチの熱匂ふ
木の根よりつめたき紙に強く書き
しぐるるや身の芯にある鳥の性
百千鳥引き返すには急な坂
※
白鳥や真新しきは死者のこゑ
道草の昼の閑や開戦日
元町の本の匂ひや阪神大震災忌
憲法記念日あけがたの雨甘かりき
大震災のみちのく、開戦日、阪神淡路大震災、憲法記念日、広島忌などの「時事的」「社会的」な事柄を詠んでも、川口真理俳句のまなざしは独創的である。
紋切り型の悼句とは無縁の独特のまなざし。
震災の犠牲者に想いを馳せて、風化を拒むひりひりとした悼みを「死者の声」として蘇生させ続ける意思を表明し、開戦日を詠むに、批評性より「道草」の「閑」を添え、「憲法」を詠むに、薄明の雨の甘やかさを添え、広島忌を詠むに、涙や汗拭くハンカチが吸い取った体温を添える。
「社会性俳句」の、意味に満ちたスローガン性とも無縁で、ことばが、とてもしなやかで瑞々しい。
ことばが概念化を拒否し、今ここに生きて在る川口真理という俳人の存在感に満ちた、実体のあることばたちによって、「今」という現実世界が立ち上る。
この句集の独創性は、俳句界における表現史的に言えば、時代を画する一つの「事件」というべき偉業ではないか。
木の根よりつめたき紙に強く書き
しぐるるや身の芯にある鳥の性
百千鳥引き返すには急な坂
俳句をパソコンでは書かない人だろう。「木の根よりつめたい紙」に筆圧強く、一句一句を刻むように書く人だろう。
ことばを「身の芯」という実体的存在性から立ち上げて、鳥のように羽搏こうとしている。百千鳥のような多様な表現が溢れる俳句界に踏み込んでしまった「わたくし」という個性は、もう立ち止れない。
こうして川口真理はその詩世界をより深めて、第二句集『海を醒ます』という、ことばの新しい「覚醒」の世界を切り拓く旅に出たようだ。
― 了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
