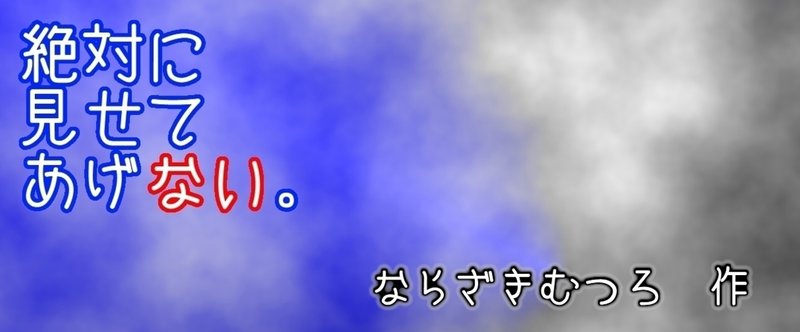
『絶対に見せてあげない。』
この作品は有料作品ですが、投げ銭方式をとってますので最後まで読むことができます。
投げ銭にしたのは理由があって、いちおう購入してくださった方には理由が読めるようにはしておきますが……
……ま、大した理由でもないので、気にせず最後まで読んで楽しんでもらえれば幸いです(^-^)
コメントやスキは投げ銭関係なしにお待ちしておりますですよ~♪
では、まいりましょうか。
『絶対に見せてあげない。』
作 ならざきむつろ
罫線提供 短腿さん
「ちょっと祥子、ご飯まで時間有るから、ロンの散歩行ってくれない?」
ゴールデンウィークのまっただ中の夕方、居間でぐったりしながらテレビを観ていた私に、台所から母の声が聴こえてきた。
「えー、っと、やだ」
「やだじゃないわよ。そんなゴロゴロしてるくらいなら、少しは運動して気を紛らわせなさいよ」
はっきり否定することで勝ったつもりでいた私に、しかし母の容赦ない声が返ってくる。
「まったく、フラれたからってお腹は空くんだし、ロンは散歩に行きたがるんだからね」
私に聞こえないように言ったつもりの母の声が、しかしくっきりはっきりと私の耳に届いてくる。
「ちょ、フラれたんじゃなくて、私は――」
「あ、ロープは勝手口に有るから」
反論すらさせてくれない母に口を尖らせながら、私はよっこらせ、と身体を起こしてテレビのスイッチを切る。
まあ、いいか。
どうせ、大したものは観てなかったし。

我が家の犬――柴犬でロン、って言うんだけど――は散歩が好きだ。
それがこの近辺で巻き起こっている熾烈な縄張り争いのためか、自らの体調管理のためか、我が家の険悪な雰囲気からくる閉塞感から逃れたいためかは解らないけど、とにかく散歩が好きだ。
嘘だと思うなら、一度我が家に来て、今の私と同じように勝手口に立ち、
「ロン、散歩に行くよー!」
と、叫んでみてほしい。
たとえ縁側で母親がわりの猫とじゃれてようと、トイレで用をたしてようと、好きなご飯を食べてようと、フロアの板に爪を立てるチャカチャカ音とともに勝手口まで猛ダッシュで飛び込んでくるから。
ロンは首輪が嫌いだけど、散歩に行くときだけは自分から頭を下げて着けさせてくれる。
首輪を着け、散歩用の紐を付けたあと、ロンは眼を嬉しそうに見開いて、ハッハッと口から舌を出してこちらを見る。
そのいかにもワクワクとした顔を見ると、それまではめんどくさく感じていた私もさすがに仕方ないか、と笑みがこぼれてくる。
「よし、行きますか!」
私が立ち上がって空元気混じりにそう言うと、ロンは嬉しそうにワン!と一声吠えてまっしぐらに勝手口へと駆け出し、閉まっているドアの前で急停止する。
「だから慌てないの。また激突するんだからね」
私は苦笑いしながらロンに言い、それでも急かすように見つめる我が相棒に少し呆れつつドアを開ける。
開けた途端に入り込んできた春の暖かなそよ風が、サンダルを履く私とロンの鼻先を誘うように撫でる。
風にのって微かに香ってくる花の香り。その香りが昨日の出来事を思い出させ、私の上がり始めたテンションを一気に下げていく。
「――ねえお母さん、やっぱりめんど――」
サンダルを履いた私が母親に声をかけようと立ち上がりかけた、その瞬間だった。
まるで私が何を言おうか分かったかのように、ロンがワン、と一声鳴いて外に飛び出して行く。
もちろん、立ち上がろうとした私も巻き込まれるように外に引っ張り出されたのは言うまでもない。
「わ、ちょっ、わかったから……って早いはやい!」
私は前へつんのめるようになりながら、ロンに引っ張られるように歩を進めていく。ロンは脇目も振らずに私をぐいぐいと引っ張りながら、歩き慣れた道をまっしぐらに駆け抜けていく。
「ちょっ……ロン、いつもの電柱は?」
いつもおしっこをかける電柱を勢いよく過ぎ去るロンに思わず声をかけるが、ロンはお構いなしにぐいぐいと引っ張り続ける。
「なんなのよ……こら、ロンったら!」
思わず出た私の叱責にも構わず、ロンはひたすらまっすぐに駆け抜ける。
そう、まっすぐに――あの家にむかって。
「……ちょっ、待てロン!」
ロンの意図が解った私は、慌てて引き止めようとするが、勢いにのったロンはすぐには止まらない。
「ダメだって、あそこは――」
真っ正面に見える平屋建てのおうち。
あそこには、ロンの大好きな人がいる。
そして、私の大好きな――『だった』人も。
タケシ兄ちゃん。
小さい頃からずっと好きだった、2つ年上のお兄ちゃん。
私は兄ちゃんとずっと一緒に居たくて、がんばってがんばって受験勉強して、どうにかこうにか同じ高校に飛び込むことが出来たんだけど。
「ロン……ああもう、止まれっての!」
私はようやく姿勢を立て直し、アスファルトに突き刺さるくらいに足を踏ん張る。ロープが引きちぎれそうなくらいに張り詰め、ロンがそれでも負けじと身体を伏せながら前にじりじりと進んでいく。
「ダメなんだって!兄ちゃんは彼女と一緒なんだから!邪魔しちゃダメ!」
私の叫びに似た声が、でもロンには届かない。
ロンだって、昨日の事を知ったら、とても兄ちゃんに会いたいとは思えないはずなのに。

昨日の事だ。
入学後のドタバタも一段落して、ようやく兄ちゃんのクラスに顔を出せた私は、そこで兄ちゃんと仲良く話している早川先輩を見かけた。
早川先輩はタケシ兄ちゃんの同級生で、中学の頃からタケシ兄ちゃんと一緒に居た女性で、おまけに美人で性格も良くて友達も多いはずなのになぜかタケシ兄ちゃんの傍にいつも居る女性だった。
私は二人の様子を見て、それこそ気を失いそうになった。
まさか高校まで同じだったとは思ってなかった。
タケシ兄ちゃんも何も言ってなかったし。
少なくとも二年間は、私の知らない所で二人がああやって仲良くしていたんだ。
もしかしたら、二人は付き合ってるのかもしれない。
なんだか恋人同士みたいな空気にも見えるし。
……などという考えが一気に頭のなかを駆けまわり、私はもうどうして良いか分からなくなって、そのまま兄ちゃんに声もかけずに家に帰ってきてしまい、そのままゴールデンウィークに突入して今、って感じなのだ。

そりゃあ、会いたくもないってもんでしょ?
それをロンにも解ってほしい……っていうのにこのバカ犬はそんな事も知らずにとうとう兄ちゃんの家の前まで来てワン!と軽快な声で鳴いてしまったのだ。
「こ、こらロン!しーっ――」
私が慌てて止めようとするが、吠え始めた犬の口は閉じることが出来るわけもなく、ただオロオロするばかりで。
「ああもう、なんだろうこのカッコ悪さ。どうすればいい――」
私がそうつぶやいていた、その時だった。
兄ちゃん家の玄関がガラリ、と開き、そこからなんと兄ちゃんが顔をのぞかせたではないか。
「はあい……あ、ロンと祥子だ」
「うわ、なんで兄ちゃん居るの?!」
思わず飛び退った私に構わず、ロンは嬉しそうに兄ちゃんに飛びつく。
兄ちゃんはロンを撫でながら呆れたような表情で私を見ると、
「そりゃいるだろ、俺んちなんだし」
と、ばっさり。
「いやまあそりゃそうだけど、折角の休みなのに、デートとかじゃないの?」
「デートぉ?なんで俺が」
私の問いに素っ頓狂な声を返し、兄ちゃんはロンにそうだよなぁ?と続ける。
「いやだってほら、早川先輩とか――」
「はやかわぁ?なんであいつの名前が出んだよ」
ロンの首根っこをカキカキしながら逆に聞かれ、私は思わずうろたえる。
「へ?だって兄ちゃん――」
「そもそもあいつ、カレシいるし」
その瞬間、私の思考回路はストップした。
多分兄ちゃんとロンの目にはとんでもない表情の私が見えているんだろうけど、今の私にはほんとどうでもいいことだった。
「――は?か、カレシって、」
「そう、カレシ。ほら、山根だよ」
兄ちゃんの口から発せられた山根、という名前が、頭のなかでぼんやりと人の形を作っていく。
「……ああ、あのヘタレメガネ」
「俺の親友をヘタレメガネ呼ばわりすんな」
私のつぶやきにすかさずツッコミを入れる兄ちゃんに口を尖らせて見せる。
「ふーんだ。ほら、ロン、帰るよ!」
できるだけ普通な感じで紐を引っ張るけど、案の定というかなんというか、ロンは兄ちゃんの足元から離れようとしない。
――おまけに、何だか妙な眼で私を見つめてくる。
「なあにが言いたいのかな、このバカ犬は」
少し叱るように、でもほんのちょっとだけ楽しくなって私が言うと、
「ロンが何か言いたいんじゃなくて、お前に何か言わせたいんだな、きっと」
と、兄ちゃんが屈みこんでロンの喉の辺りを撫でる。
「何か、って、何を――」
……まさか。
私はその可能性に気づいて、思わずロンを見る。
兄ちゃんに撫でられて気持ちよさそうにしながら、それでもロンはこちらを見ていた。
――なぜか、ドヤ顔で。
「ああもう、ロンめ、覚えてなさいよ」
もういい。
言ってやる。
私は突然バクバクし始めた心臓の音を聴きながら、思い切って兄ちゃんを見つめる。
短パンにTシャツ、ボサボサ頭のイケてない兄ちゃんは、きょとん、とした顔でこちらを見ていた。
「に、兄ちゃん、」
くっそ、声が震える。
簡単なセリフなのに、なぜか口にするのが恐い。
兄ちゃんが好きだった、って。
兄ちゃんと一緒にいたいから同じ高校を受けたんだ、って。
それだけを言いたいだけなのに、喉の辺りで詰まったまま出てこない。
「なんだよ、妙に改まっちゃって。おかしいよなあ、ロン?」
何だか妙に余裕かましてる兄ちゃんと、何だか楽しそうにしているロン。
生まれた時からずっと遊んでくれた兄ちゃんが、ロンはほんとに大好きなんだ。
そしてたぶん、きっと、私のことも。
――よし。
私は大きく深呼吸をすると、兄ちゃんと同じように屈みこんで、わざと兄ちゃんの目の前に顔を近づける。
当然、ロンの白い公家さん眉毛も目の前にあるが、それは気にしない方向で。
これでもう、後戻りは出来ないぞ、私。
「兄ちゃん。私、私ね――」

それから先は、敢えて書かない。
書いてやらない。
書くもんか。
隣であんたたちが覗いてる間は、絶対に書かないからね。
わかったらさっさと離れなさい。
兄ちゃんも、ロンも。
(了)
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
