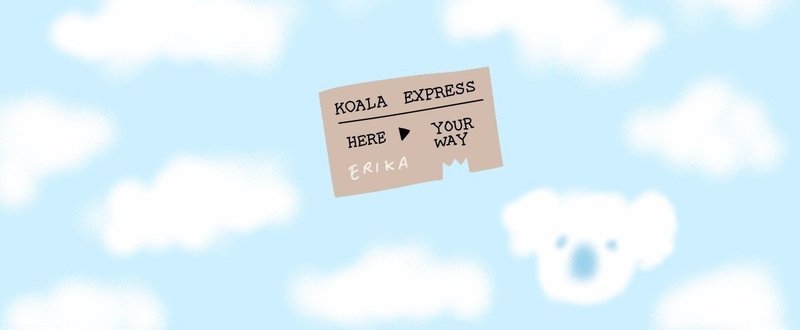
コアラのマーチ ~Erika~
うららかな音楽とともにアナウンスが流れる。
「Ladies and gentlemen. Welcome to the Shinkansen…」
最近、英語の聞き取りが難しくなった。エリカは耳を澄ませたが、辺りの騒々しさがすべてをかき消した。待合室では、十名以上の女子学生が、おしゃべりに花を咲かせている。
9月も始まったばかりというこの時期に、どうしてリクルートスーツの学生たちを街に見かけるのか、エリカには皆目わからなかった。ふだん東京で色鮮やかなものばかり見ているせいだろうか、なつかしいはずの方言で昨日のテレビを語る女の子たちが、とても野暮ったく思えた。
きっかり15時、新幹線がホームにすべりこんだ。逃げるように乗り込んで席に座ると、ふう、と思わずため息が漏れる。
すぐにSNSの画面を開いて、「いま新幹線!早く東京に帰りたいよー」などと打ち込んだ。瞬く間に数十もの「いいね」が返ってきたが、エリカの顔は一瞬曇った。フォロワーがまた減っていることに気づいたのだ。
エリカは携帯をシートに投げ出し、景色が前から後ろに流れるのをぼんやり見つめた。故郷の風景は、あっという間に後ろへ過ぎ去っていた。
「出版の件ですが、今回は上の判断で、見送りとなりました。力不足で申し訳ありません」
編集者からメールが届いて以来、気持ちが大きく揺らいでいた。ふわふわと生きてきたこの五年間が、シビアに結論付けられたような気がした。
NY留学生活を綴ったブログは、かつてメディアに頻繁に取り上げられた。同世代が共感する22歳のブロガー、好きなことで生きていく。謳い文句のまんなかで脚光を浴びているのは、年齢だった。22歳、23歳、24歳… キラキラとした光は、泡のように儚かった。
――今はもう、求められてない、ってことなのかな…。
「それとなく就職口をあたってみるから、よく考えてみんさい」と、両親には言われた。
「おまえは運が良かっただけだ」銀行員の兄は、ばっさりとそう斬った。
久しぶりの帰省は、最悪だった。
「おまえがあの出版社の採用、断ったんだからな。自分の意志で」
別れ際、ぽつりと兄は言った。
五年前に受け取った「内定通知」。真ん中を途中までやぶいた、一枚の紙。それはエリカの心の隙間、過去と今のあいだに引っ掛かり、バタバタともがくように風に煽られていた。
――「上の判断」って、何だよそれ。
エリカは心の中でつぶやいた。行き場のない憤りをぶつける先はそこじゃない。分かってる。でも、他にどうすればよいのか分からなかった。
つらつらとそんなことを考えていると、いつの間にかまどろんでいたようだ――
***
「おーい、お客さん」
誰かがゆさゆさとエリカの腕を揺さぶっていた。眠りから覚める途中、ぼんやりとした視界から、輪郭がおぼろげに浮かび上がってくる。
パリッとした紺色の制服、ちいさな金ぴかのネームプレート。そして背の低い、小太りで、毛むくじゃらの――
エリカの眠気は吹っ飛んだ。
驚くべきことに、目の前に立っていたのは、
「こ、こ、こ、こ…」
コアラ。
そう言いたいのに、自分でも呆れるくらい言葉が出てこない。
「あんた、何を言うとるん。自らコアラ号に乗ってきたくせに」
しかも、喋った…!?
…幻覚だ。
本の企画がボツになったショックで、情緒不安定になってるんだ。いや、さすがに、ここまで妙なものを見てしまうっていうのは、やばいんじゃないか。だったら、夢だ。『不思議の国のアリス』だって、結局あれは夢だったんだし…。
「ほかのところ、満席じゃけん、こちらのお嬢さんと相席願います。同い年くらいじゃろ、ええ話し相手になるわ。ほら。どうぞ」
喋るコアラは、エリカの意見など、完全に無視だった。
一人の女性がエリカの向かいに腰をおろした。
クリーム色のさらさらとしたブラウスにしわひとつないグレーのスカート、ひざの上にA4の革のバッグをちょこんとのせ、それを押さえる手には品の良いダイヤの指輪がなじんでいる。
柔らかい印象の中に、聡明なオーラが滲んでいた。コアラの言った通り、立派なお嬢さんだとエリカは思った。――いや、そもそも、「コアラの言う通り」なんて、おかしな話だけれど。
急に、自分の服や靴が、ひどく安っぽい、子どもじみたものに思えた。あのドラマの主人公、NYの街を闊歩する、独立した大人の女性を気取っておしゃれしていたのに。
「最近、あんたらみたいな若い人は皆、自分で勝手にがんじがらめになっとるな。まあ、話してみたらいいが」
コアラの車掌は、ずんずんと歩き去った。
その人は、賢そうな瞳で、ふふっと笑った。
「コアラって初めて見ましたけど、意外と、おっさんみたいですね。それに、方言きつい…」
どうやら彼女の方は、状況を受け入れているらしい。
「そ、そうですね」
エリカは呆気にとられた。夢にしては、全てが鮮やかに目に映る。そして…
この女性には、見覚えがあった。
待合室で彼女は、エリカの正面に座っていた。ひっきりなしにかかってくる電話を、冷静にひとつひとつ対応しているのが印象的だった。お客さんへ丁寧な口調で説明したかと思えば、次の瞬間には「リンギ」などエリカの知らない言葉で部下に指示を出す。実に見事な電話さばきで、ひそかに観察せずにはいられないほどだった。
出張中だろうか。首にかけられたネームホルダーには「SATSUKI, K.」とあり、それは働く女性の誇りとしてしっかりと刻み込まれていた。エリカの心にちいさな棘がチクッと刺さった。
「…あ、あの。失礼かもしれないですが、ブロガーのエリカさんじゃないでしょうか」
「え」
サツキの顔がぱっと明るくなった。
「やっぱり!待合室でずっと、『何でこんなところに!? でもきっとそうだ!』って思ってたんです。私、エリカさんとは同い年なんです。ブログ、NY留学の時から読んでます。エリカさんの行動力に憧れて、ずっと応援してます」
まだ戸惑っているエリカとはうらはらに、サツキは興奮していた。
「本、出版されるんですよね? 絶対買いますね。…あ、ちょっと失礼」
サツキはかかってきた電話に対応するため、席を外した。「はい…ええ、すみません、申し訳ございませんが…」といった言葉が断片的に聞き取れた。
私のことを、知っていた。
落ち目の自分を有名人と言ってもらえるのはありがたいけれど、正直、居心地が悪かった。サツキの口調が本の出版を期待する明るさに満ちていたから。それは今、エリカが最も触れられたくない話題だった。
エリカは別の話題を必死で考えた。
そのときふと、サツキが席に残していった封筒の「ユーカリ出版」という文字が、目に飛び込んできた。
ユーカリ出版。
こんな偶然があるものだ。
五年前の記憶が、あざやかに蘇った。
「厳正なる選考の結果、貴殿を採用致すことを内定しましたのでご連絡します。――株式会社ユーカリ出版 人事部」
なぜ、内定を断ったのか? と、人に聞かれるたびに、うまく答えられなかった。
銀行員になった兄は仕事の話しかしなくなった。そしていつも胃を痛めていた。満員電車の大人たちは皆、疲れ切った表情でスマホを見つめている。日曜の夜はタイムラインがため息だらけになり、月曜の朝は灰色になってあふれだす。
自分の行き着く先もそこなのだろうかと想像する時、なぜか体の芯から言いようのない寂しさが湧き出してくるのを感じた。暮れなずむ時間帯に、いてもたってもいられなくなるような寂しさ、なんのために生まれてきたのだろうと、わけもなく自問するような寂しさ。
だからこそ、その寂しさから逃げるように、スマホの画面の向こう側の、ワクワクする世界の住人になるのだと自分に言い聞かせていたような気がする。周囲の反対を押し切ってNYへ飛び立った時、うっとりと自由に酔いしれた。あのドラマの、主人公の世界に来た…。
でも、今となっては、自分がいかに狭い視野で大人や社会を見ていたのか、よく分かる。「着実なキャリア」という道がそこにはある。それはもはや、エリカには一生捉えることのできない大きな魚だった。
「ごめんなさい、お話の途中に」
サツキは少し疲れた様子で戻って来た。後輩のミスで、取引先の大学を怒らせてしまい、謝罪に向かっていたが、たった今それをキャンセルされたのだと、ため息まじりに説明した。
「もう、大激怒。確かにこっちが悪かったとはいえ、言い方がきつくて」
「こっち」という言葉には、特別な響きがあった。社会という大人の世界に、確固たる居場所が彼女にはある。そんなことを見せつけられたような気がした。
――何よ、「頑張ってる私アピール」?
エリカはふと、「私だって、今あるものを捨てたら、それくらいなれる」と思った。
疑うことなく新卒入社した会社に、ずっと居続けているだけ。誰かの代わりに謝りに行って、キャンセルが出たらのんびりと引き返す。そんな仕事、難しいことなんて何ひとつない。
寝る間も惜しんで企画も取材も記事もひとりでやって、出版社に持ち込んでは断られて。キラキラの「自由」を演じて、あることないことネットでたたかれても、会社が守ってくれるわけじゃない。
そんなことを考えてしまったからか、エリカの口から、つい嫉妬がこぼれ落ちた。
「へえ、会社員って、無駄に使えるほど時間があるのね、サツキさん」
二人はいま、のどかな田園風景の中を通り過ぎていた。風景は二人に等しく同じものを見せていたが、二人が見つめているものは、全く違っていた。
サツキは何にも乱されなかった。バッグの中からお菓子を取り出し、エリカに差し出した。
「…エリカさんみたいな人はきっと、自分は何も悪くないのに謝るとか、無意味な時間を押し付けられることなんて、ないんでしょうね。どうぞ。お菓子、一緒にいただきませんか」
それから一息おいて、サツキは続けた。
「まあ、ときどき考えますけどね。これ、何の為の仕事なんだろ、とか」
まるで、うしろから思いきり前の人の足を蹴ってしまった時のような、驚きと、申し訳なさの入り混じった気持ちが、エリカに覆い被さった。
――今回は「上の判断」で、見送りとなりました。力不足で申し訳ありません。
ああ、あの担当者も、きっとこんな気持ちで…。
「あの」
ごめんなさい、そんなつもりは…、とエリカが言いかけたその時だった。
「やれやれ、席交換の時間じゃ」
いつからそこに居たのか、二人の会話に割って入ったのは、さきほどの車掌コアラだった。
「ちょっと、切符を拝見しますよ」
「あっ」
エリカは、体ごと宙にふわっと持ち上げられ、今度は力任せに投げ下ろされたような錯覚を覚えた。
気がつけば、二人は依然としてそこに居るのだが、何といえばよいのだろう、二人の「中身」は、入れ替わっていた。
エリカは、窓の外の景色がものすごい早さで背中にぶつかって弾けるのを感じながら、目の前にいる「自分」であるはずの、エリカを見ていた。サツキにも同じことが起こっているらしく、二人してお互いを、きょとんと見つめ合っていた。
すると、エリカの心に、サツキの気持ちが流れ込んできた。
私だって自分が悪いわけでもないのに誰かの代わりに怒られるなんて、イヤだよ。でも、こんなの、どうってことない。だって、これが私の歩んできた道だから。いま目の前にあることを頑張って、少しずつ出来ることを増やしていく。みんなに認められて頼られることが、どれほど人を成長させてくれるか、私は知っている。
私は会社に「雇ってもらってる」なんて思ってない。誰のものでもない私の人生を、ちゃんと生きてるって言える。遠い将来が見えなくて、つらくて、やるせなくなる時だってもちろんあるけど、そんなときは、心を落ち着けて、お菓子でも食べながら、ほっと一息いれるんだ。
エリカは感じ入っていた。自分の顔が、考え方が、行為が、とんでもなく子どもっぽく思えた。
――大人だな、サツキさん。
――そうだ、私も、五年前そう思ってたんだ。
「誰のものでもない、私の人生を生きる」って。
自分の原点のようなものを見いだした時、兄の言葉がリフレインした。「おまえがあの出版社の採用、断ったんだからな。自分の意志で」
ただの嫌味だと思った。でもそれが今はサツキの影響で、全く違った意味にとれる。
――だったらお前、その選択を貫き通せよ。
ふと気づくと、どこかの駅に停車していた。入れ替わっているような違和感が無くなっており、サツキの姿はなかった。おそらくこの駅で降りたのだろうと、人影のまばらなホームを窓越しに見ながら、エリカは直感でそう思った。
「ブログ、これからも見ますね」
「私もユーカリ出版の雑誌、今後もチェックする」
そんな会話を最後にしたような気がした。これからも、お互いを称え合う約束のように。
サツキの置いて行ったお菓子を一つ、口に放り込んだ。子どもの頃好きだった「コアラのマーチ」。兄と一緒に食べた、なつかしい味。まゆ毛のあるコアラを見つけたら、きっと良いことがあるよと、一つの箱の中身を広げて競い合うようにそれを探した。結局、見つけたのは、兄だったのか、私だったのか。
今日は、サツキさんでありますように。
「あんたは東京行き、ってことで変更はないね?」
と、どこからかあの声がした。私は辺りを見回し、コアラの顔を探した。
【コアラのマーチ/エリカ編】おわり♩
----------
あの noter さんによる【サツキ編】はこちらです。ぜひ、あわせて読んでみてください!
サポート、メッセージ、本当にありがとうございます。いただいたメッセージは、永久保存。
