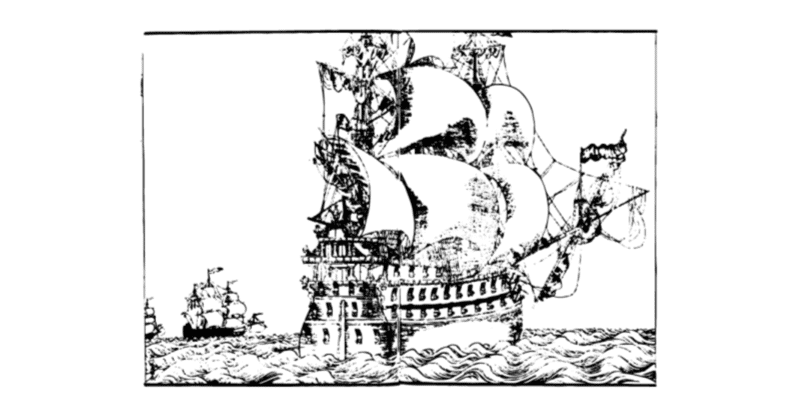
九天九地2:度胸千両も神頼み
供出米の代金支払いの件で、皆が考えあぐね、重い沈黙が続いたあとである。
「それでは、この米が入手できない場合、ご領内に多くの餓死者が出たとしましょう。それが、この好機を見逃したせいと発覚すれば、お殿様はどれだけお怒りになりましょうか」
「うむ…そうなったら、われら三人、腹をかっさばく以外の道はあるまいな…」
「なるほど、確かにそれが、武士の道というものでありましょう。しかし人間、ほんとうに命がけで至誠をもって事に当たれば、たいていのことは成就するものでございます。ましてや、今回の鍋島藩側の条件は、情もあり、完全に理にかなったものでございます。とにかく今は、先方の条件はお呑みになり、早く交渉をおまとめになった上で、次のご思案をなさるのが賢明、というものでございます。お手元不如意のことは、今はおくびにも出されぬがよいでしょう」
三人としては、嘉兵衛の言葉に反論もできず、鍋島藩と何度か会談を持ったうえで、やっと合意に達した。
その間にも、大阪の米相場は、天井知らずと言われたほどの高騰を続けていた。それにもかかわらず、鍋島家のほうでは、約束当時の7月24日の相場に、一文の上乗せもしなかった。
江戸での交渉はこれでまとまったものの、まだ空証文の段階である。そして次の難題は、米の現物を輸送する、という大問題である。
厳しいが、当然の条件?
ここで読者諸氏は、鍋島藩側の条件に、「米を積んだ船の出航と同時に、総代金を頂きたい」という条項があったことを、思い出されるのではないだろうか。
そうなのである。海上輸送には危険がつきまとう。現代においても、輸送船の火事は皆無ではない上に、天保四年(1833年)のことである。
当時としては、九州から奥州南部までの三万石の米、現代に換算すると、約4,500トンの重量である。
何十艘の船が必要だろうし、難破や海賊の危険もある。鍋島藩としては、船の出航と同時に代金の支払いを要求したのも、当然であろう。
そして、この現物引き取りと運搬の実務にあたる責任者に、誰を任命するか、という大問題が待ち構えていた。
代金支払いの目途さえ立っていない、危険極まりない大量の海上輸送の任務に、就きたい者がいるだろうか。その思いは、誰しも同じであろう。
留守居役から、運搬責任者の選定が難航していることを聞いた嘉兵衛は、大きくうなずいた。
「なるほど、この任務は、船の扱いや船頭舟子たちへの対応など、かなりの荒業でございます。お侍様には荷が重うございましょう。乗りかかった舟、手前がお引き受けいたしましょう」
嘉兵衛は役目が終わるまでの間、一時的に南部藩江戸詰勘定奉行という肩書を貰い、輸送の任に当たることとなった。
当時としては、一ヵ月余りの旅である。しかも、物見遊山や単なる商売目的ではなく、何が起こるか分からない、危険な海上輸送である。気の休まる暇もないであろう。
旅の途上の霊夢
嘉兵衛は、南部藩江戸詰の侍たちと、自分の店の手代たちの中から、選りすぐった供を連れ、江戸を出立した。途中、京都で北野天満宮に参詣して、使命の完遂を祈願した。
嘉兵衛が短冊に記して、北野天満宮に捧げた和歌がある。
「八百万(やおよろず)、神の恵みの宝船、
救いたまえや 大洋(わだつみ)の原」
この歌には、大きな不安と切実な祈念がこめられている。陸路を九州鍋島藩まで行って、船積みまで無事完了したとしても、その米が無事に奥州盛岡まで届くかどうか、誰にも保証はできない。
旅を続けて、一行は九州大宰府まで来た。嘉兵衛はここでも天満宮に参詣し、使命の完遂を切実に祈願した。
大宰府で一泊した夜、嘉兵衛は不思議な夢を見た。
子供の頃から馴染み深かった、鹿島神宮を思わせるような深遠な森、その中を歩き回っているうちに視界が開け、一棟の祠が目にとまった。祭神はわからない。
正面の狐格子には、何種類かの絵馬が奉納され、中に一枚の短冊が混じっていた。
それを手に取った嘉兵衛は、唖然となった。
「八百万、神の恵みの宝船、救いたまふぞ 大洋の原」
少しだけ、嘉兵衛の和歌とは表現が違っている。いわば、神からの返信である。これが霊夢なのか、ただの雑夢なのかは、この後、判明する。
嘉兵衛はすぐに目覚め、身を清めて衣服を改め、東雲の天満宮に参詣し、霊夢のお礼を言上した上で、旅を続けた。
肥前鍋島、現在の佐賀県佐賀市である。
江戸表からの早飛脚で、嘉兵衛の出立を告げられていた藩は、嘉兵衛を丁重に出迎えた。
当時の廻船は、最大のものでも千五百石積みである。
つまり、三万石の米を運ぶには、数十艘が必要になる。それを手配するには、廻船問屋との交渉など、様々な急務が発生する。それらの問題を、嘉兵衛はあざやかな手腕でさばいていった。
たいした御仁だ
それらの仕事ぶりを見た鍋島藩の重職お歴々は、いたく感服してしまった。中でも、密かに嘉兵衛を観察して、いちばん舌を巻いていたのが、城代家老である井上三郎兵衛である。
着々と輸送の準備は整い、最後の一艘である竜神丸千二百石は、伊万里で荷積みを完了し、玄界灘へと向かった。この時には、さすがの嘉兵衛もどっと疲れが出て、二日間、床を離れることが出来なかった。
「自分は人力の限りを尽くした。後は神命にお任せするのみだ」
嘉兵衛は、江戸から伴ってきた南部範士の一人に、こう語ったという。ただしまだ、最大の難問が控えていた。十一万両という代金の支払いである。
係りの家臣から催促を受けた嘉兵衛は、平然と答えた。
「はて、その代金のお支払いは江戸表にて、ということでございました。ご当家江戸お屋敷からのご書状には、そう書いてはありませんでしたか?」
とぼけた大博打と言えばそれまでの話だが、これは、係の役人だけで解決できる問題ではない。何度か協議が繰り返されたが、拉致があかないので、事は鍋島城内での重役会議に持ち込まれた。
なにしろ、江戸まで事情を問い合わせるにしろ、ひと月以上はかかる。
この時、場を仕切っていたのは、かの城代家老、嘉兵衛の隠れファンになってしまった、井上三郎兵衛である。
井上はこの時、並居る重臣たちを押え、こう述べた。
「書面の書き間違いは、絶対に無いとは言い切れない。人間はまず、人間を信じてかかるべきではないか。わしは嘉兵衛殿に会ったとき、信じるに足るべきお方とお見受けした。このお話は、そのまま飲むがよかろう。後日、殿よりお咎めがあった時には、わしが一切の責めを負おうぞ」
数日後、嘉兵衛たちは鍋島城下を離れ、陸路を江戸へと向かった。
しかしまだ、これで一件落着というわけにはいかないのである。
九天九地3へ
この章の音声ファイルは以下からダウンロードできます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
