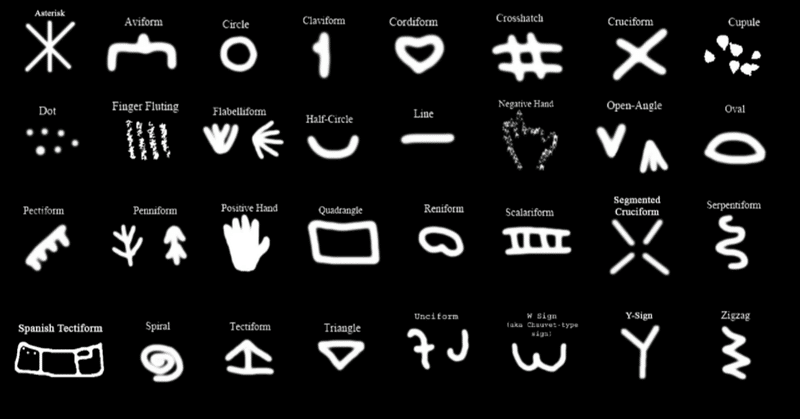
文字的世界【27】
【27】声と文字の捩れ、文字現象学─白川文字学3
白川静は、良くも悪くも、詩人であった。──三浦雅士氏は「白川静問題──グラマトロジーの射程・ノート1」の最後のパラグラフを、そのような言葉で書き始めています。あたかも古代人であるかのように、縦横無尽かつ断定的に漢字の起源を語った白川静、その学説の芯を形成したのが、卜片のトレースから筆耕、油印という身体的修練によって獲得した「飛躍すなわち詩的直観とでもいうべきもの」(50頁)であったことを踏まえての評言です。
このことは、白川文字学の孤立性や自己完結性に、つまり貝塚茂樹や吉川幸次郎が抱いた「違和感」(50-51頁)、あるいは「白川静に触れてはならないという禁則があるのではないかと疑われても仕方がない」(38頁)学会の沈黙につながります。(白川文字学のこの孤立を、三浦雅士は「白川問題」と呼んでいる。)
前回につづき、『人生という作品』に収録された三浦氏の論考から、デリダのグラマトロジーに言及された箇所を三つ、まるごと抜き書きし、白川文字学というプリズムを通じて見えてくる文字的世界の拡がりを見定めておきたいと思います。(論じようと目論んでいた、それと同じ事柄をより濃く深く鋭く描いた文業に接したなら、潔くその麾下に入るに如くはない。)
◎声と文字の捩れ─忘却の淵に沈んだ起源
《古代ギリシア哲学は文字の一般への普及によって生まれたとはエリック・ハヴロック『プラトン序説』(一九六二年)の説くところだが、これもまたパリーの衝撃[ミルマン・パリーの博士論文「ホメロスにおける伝統的な形容辞(The Traditional Epithet in Homer)」(1928)──「『イーリアス』にせよ『オデュッセイア』にせよ、もとは楽人たちによって朗誦されていたものであることを、枕詞あるいは序詞ともいうべき修飾句の使い方に法則があることを突き止めることによって立証してみせた」(53頁)もの──が後のホメロス研究に与えた影響]の三十年後の残響である。プラトンがその国家から詩人を追放したのは、詩人とは当時、朗誦者すなわち日本で言えばさしずめ琵琶法師のような存在だったからだというのだ。プラトンは暗誦によって人生に対応してゆくものたちを嫌った。柳田国男風に言えば諺で物を考える人間、集団的思考に身を委ねる人間を嫌ったのである。そして、物を書く人間たち、すなわち思考する個人に未来を託した。
デリダによって人口に膾炙することになる音声中心主義は、逆説的にも、文字の一般への普及によってもたらされたことになる。孔子もソクラテスも文字によって声が定着されたのである。個人的思考の登場ははじめからこの声と文字の捩れとともにあったのだと言わなければならない。文字の一般への普及こそが口承文芸すなわち叙事詩を変容させ、哲学や歴史や抒情詩を生み出したとするハヴロックの着想は、この捩れの仕組みを解明する企てにほかならなかった。》(『人生という作品』54頁)
三浦氏によると、内藤湖南は、春秋から戦国時代にかけて文字が一般のものになったその衝撃が諸子百家を生み、五経を生んだと考えることで、パリー、ハヴロックに近接している。「文字は、誰もが用いるようになってその意味を変えてしまったのだ。原義は忘却の淵に沈んだのである。」(55頁)
ここで言われる「原義」は、「文字の起源は占卜に、詩歌[山川草木、鳥獣虫魚への挨拶を根源とする詩歌、枕詞や序詞を(古代的)発想法とする詩歌]の起源は呪術にある。漢字の起源は詩歌の起源と時をへだてはしても重なり合うのである。」(43頁)とされる、その「起源」にかかわる。「白川静がその詩的直観によって解明したのはこの忘却以前の世界の、見ようによっては美しい、また見ようによっては恐ろしい姿なのだ。」(53頁)
◎文字現象学─表意文字から音声文字への移行・巨大な転倒
《占卜の文字は必ずしも声に出して読まれる必要はない。文字として機能していたとしても、刺青が声に出して読まれる必要がないのと同じことだ。だが、それが一般の読み書きにまで下ってきたときには必ず声に出されなければならなかった。形声の必然もそこにあった。それはほとんど表意文字から表音文字への移行に匹敵する事態である。漢文から漢字仮名混じり文への移行に等しい。(略)
表意文字と表音文字の差は同じ次元における差ではない。文字はそれを用いるものによって表意にもなれば表音にもなる。それこそデリダがその初期の著作『ド・ラ・グラマトロジー』すなわち『文字学について』で力説しているところである…。物にはすべて記号の要素があるとはパースの説くところだが、意味──たとえば食べられるものと食べられないもの──を付与するのが生命である以上、それは当然のことだ。
記号作用とは概念作用のことであり生命現象のことである。記号作用が言語現象へ、言語現象が文字現象へと飛躍する過程は、その過程そのものを忘却する過程にほかならなかった。図と地という語を用いるならば、図は地が変容するつどその意味を大きく変えなければならなかった。それは生命現象から離れる過程、生命現象を転倒させる過程であったというほかない。
むろん、生命現象そのものがひとつの巨大な転倒であると言えばそれまでだが、いずれにせよ、現象学は文字にこそ適用されなければならないのであり、デリダがはじめに意図したものもまさにそれであった。声すなわち表音に執着する言語学は、逆説的にも、文字によって切断されたまさにその文字の側を右往左往しているだけである。》(『人生という作品』55-56頁)
「占卜の文字は必ずしも声に出して読まれる必要はない。」という指摘は、文字は独立して(音声とは無関係に)言語体系をかたちづくるという、かの第一仮説を裏書する有力な“論拠”になる。
また、「漢字仮名混じり文」の成立が、表意文字から表音文字へという異次元の移行に匹敵する事態であるとの指摘は、前節で論じたこと、すなわち「“上方”から降下してくる文字と、“下方”から湧出する声という、本来は相交わることのない二つの別のものが、一つのフィールドに繰り込まれ」る事態に通じている。
◎デリダは白川静を必要としていた
《白川静は何度かデリダの名に言及している。だが、その所説に言及しているわけではない。当然のことだ。白川静を必要としていたのはデリダのほうであって、逆ではない。マルセル・グラネはデュルケームの弟子である。周口店の発掘に参加したのはテイヤール・ド・シャルダンである。モースやグラネに学んだルロワ=グーランもまた同じような流れのなかにある。フランスのシノロジーの伝統は考古学の伝統と交差して長く豊かだが、白川静を生むにはいたらなかった。呪術に遡る文字の起源を精密に分析するにはいたらなかったのである。年代的に不可能であっても、理論的には『ド・ラ・グラマトロジー』は白川静を参照しなければならなかったのである。》(『人生という作品』58頁)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
