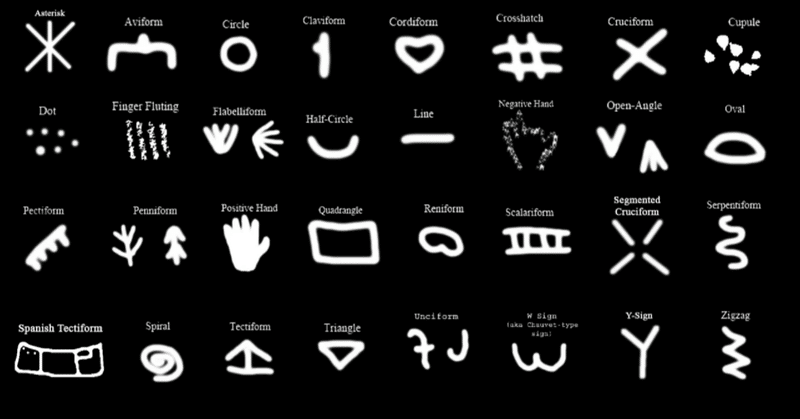
文字的世界【30】
【30】言文一致と音声中心主義──柄谷文字論1
“柄谷文字論”は、複数の論文にわたって展開されています。ここでは、『〈戦前〉の思考』(1993年)所収の「文字論」を基本テキストとして、「言文一致」と「漢字かな交じり文」(柄谷の表記では「漢字仮名交用」)をめぐる議論の概略を抽出し、適宜、他の論考によって補うことにます。
(言文一致については、「仮面的世界」の第14・15節で『定本 日本近代文学の起源』における議論を一瞥したことがある。そこでは、柄谷文字論についていずれ「文字的世界」のなかで言及すると予告していた。また、続く第16節では「文字論」の議論を(先走って)引用している。)
1.言文一致の問題──音声中心主義
◎近代日本における「言文一致」という出来事がもたらした“転倒”あるいはその問題点。──第一、話し言葉を書き写したものが言文一致体である(「言→文」または「言>文」)という“錯覚” (音声中心主義の問題)。第二、それが文語をもとに作られた新たな「文」であり、話すように強いられた「国語」(規範化された標準語)であったこと(「言←文」または「言<文」)の“隠蔽”(ナショナリズムの問題)。そして「古代」に起きた出来事へのそれらの“投射”。
【近代の言文一致】
◎明治20年代、小説家を中心に進められた「言文一致」は、「言」すなわち話し言葉を「文」すなわち書き言葉に書き写したものではない。言文一致とは、実際のところ、それまでの文語体(ある程度日本全域に共通していた書き言葉)の語尾を江戸弁で口語化すること、つまり新たな「文」をつくりだし、それを標準語として「話す」よう日本全域に強制することだった。
◎明治から大正にかけて。日露戦争後、西洋に対する緊張がなくなり、「日本的」なるものが出てきた。その典型は、文学では私小説である。それはプロット(筋)もない、構成もないような小説で、もともと西洋近代小説の影響からはじまったのだが、私小説家たちは徐々に独自の意味づけを与えはじめた。芥川龍之介がそうだったように、こうした小説の非構築化は西洋に比べても尖端的なものだといっている。
◎このような「日本化」はもともと「西洋化」があってこそ生じたのである。しかし、明治時代の「西洋化」は別の面から見れば「中国化」でもあった。それは西洋の概念が漢語に訳されたということにもとづいている。したがって、文字の問題は重要な鍵を握っている。
【古代の言文一致】
◎古代の日本における「中国化」は、明治時代の「西洋化=近代化」と類似している。また、明治から大正にかけて起きたのと同じことが奈良から平安時代にかけて起きている(私小説の先端化≒仮名文字による歌や物語の繁栄)。
◎『万葉集』は、歌われたもの(話し言葉)を万葉仮名(書き言葉、表音文字)を使って表記したものではない。『万葉集』の歌人は文字を前提にしている。日本語のエクリチュールは漢文を「読む」ことからはじまっている。読まない人は書かない。
◎奈良から平安時代にかけて。中国における帝国の衰退があり、日本との関係が希薄になった。形の上では律令制を保っていたが、実質的にはそれと異質な政治経済システム(摂関政治、荘園制)が出てきた。文学でいえば、仮名文字による歌や物語が栄えた。
◎『源氏物語』は仮名で書かれているからといって、同時代の口語(大和言葉)すなわち話し言葉を書き言葉に書き写したものではない。すでに存在し全国で通用していた文語すなわち漢文、あるいは漢文を読むことによってつくりだされた日本語のエクリチュール(書き言葉)に依拠し、それをあたかも「言文一致」のように書いたものだった。参勤交代で江戸に集まった各地の武士が、互いの話し(方言)が通じないので、謡曲や漢文にもとづく侍言葉を作りだしたように。だからこそ『源氏物語』は広範囲に読まれ、規範的な古典になっていった。
【国学者の音声中心主義】
◎本居宣長をはじめ賀茂真淵以後の国学者たちは、『万葉集』『古事記』『源氏物語』は仮名で書かれているから本体の音声をとどめていると考え、そこに漢字によって浸食され汚染される以前の日本人の思考のあり方、すなわち「古の道」を見ようとした。しかし、「古代」とはせいぜい十八世紀後半に見いだされた想像物にすぎない。もともと音声があってそれが仮名で表記されたというわけではない。それらの書物はその当時あった音声を表記したものではなく、漢字を前提にしたエクリチュールによって可能になっていた。
◎音声志向は国学より先に儒者の荻生徂徠からはじまった。国学者は『古文辞学』の影響を全面的に受けている。徂徠は漢語であれ日本語であれ言語は音声なのだという視点を提出し、音声から中国語に入らなければならない、つまり奇妙な読み下し文(漢字仮名交じり文──註に掲げた鼎談における柄谷の発言)ではなく口語で意訳すべきだといった。徂徠が言語を音声としてみようとしたということは、いわば、身体、感情というものを重視するということであった。これはヨーロッパと並行している近代的な考えである[*]。
[*]子安宣邦・酒井直樹・柄谷行人による鼎談「音声と文字/日本のグラマトロジー 十八世紀日本の言説空間」(『シンポジウムⅠ』(1994年)所収)は、徂徠、仁斎、宣長の江戸思想史とスピノザ、カント、ヘーゲルの西洋哲学史との並行関係を背景に、国学における漢字と仮名、翻訳と文法、等々の論点をめぐる刺激的な討論の記録で、汲み取るべき示唆に富んでいる。
通りすがりに一瞥して済ますことなど本来できないのだが、ここでは、音声文字と表意文字の対立は、話し言葉と書き言葉の対立とは別のものであるという(酒井直樹の)指摘にかかわる柄谷の発言を引いておきたい。
《話すことと書くことは、根本的に違いますね。(略)ところが、「音声文字」のごときものができあがると、あたかも文字は音声を写すものであるかのような観念が生じる。また、話すことと書くこととの差異が、音声文字と表意文字の差異にすり替えられてしまう。これもどこでも生じることです。(略)
日本の場合が特異なのは、やはり漢字仮名交用ということを歴史的に続けてきたからだと思うんです。つまり、概念は漢字で、テニヲハは仮名で書くという歴史的な慣習があった。そうすると、本来はどこでも共通する事柄なのですが、日本では、それが、文字の差異という問題に、また、宣長が「玉の緒」と言ったように、漢字で書ける部分と仮名でしか書けない部分の差異という問題に転化されている。そして、それが漢心と大和心の差異にまで転化される。》(『シンポジウムⅠ』270-271頁)
漢字仮名交じり文に関する「文字論」の議論は後に取りあげる。テニヲハ、玉の緒、あるいは辞の、漢字や玉や詞に対する優位的な位置づけが、国学における音声中心主義(ただし、それは東西を問わずどこでも生じることであった)のあらわれであることは見やすい。
ここで気になるのは、前節で引いた藤井貞和氏の議論との“整合性”である。藤井氏はそこで、「深層の機能語(辞)/表層の意味語(詞)」という垂直的な構図を呈示している。このことと、柄谷氏による「表音文字・仮名(大和心)/表意文字・漢字(漢心)」の構図との関係をどう考えればよいのか。先走った議論になるが、たとえば次のような図式で両者を“和解”させることができるのだろうか。
書き言葉
表層の意味語(詞)
┃
┃
┃
┃
表意文字━━━━━━╋━━━━━━表音文字
漢字(漢心) ┃ 仮名(大和心)
┃
┃
┃
深層の機能語(辞)
話し言葉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
