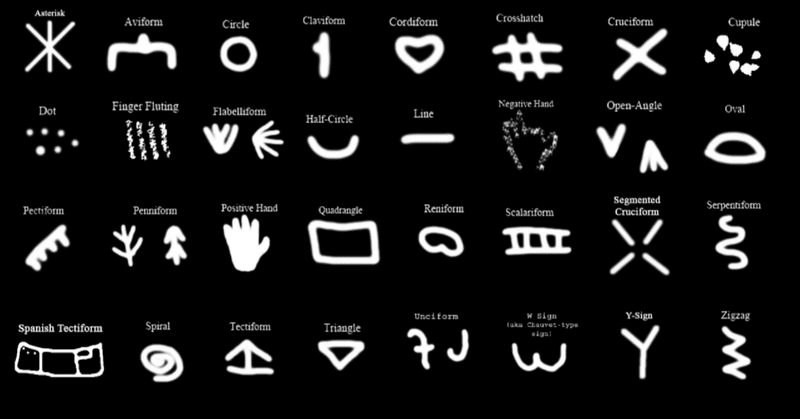
文字的世界【29】
【29】表層の意味語が深層の機能語によって下支えされる関係
第26節から前節まで、ほとんど三浦雅士氏の議論の祖述、というより、ほぼ丸写しのかたちで叙述してきました。なにも付け加えるべき知見も見解も持ち合わせていなかったからです。
ここでいったん、これまでのことを“総括”しておきたいと思います。便宜上、文字の誕生(垂直的体系の成立)、象形の体系から形声の体系への移行を経て、表意文字の表音文字への転化(水平的体系の成立)へと至る過程を三段階に区分し、それぞれに三浦氏の言葉を割り当てます。期せずして、このプロセスは、かの三つの仮説に対応しています。
1.文字誕生─呪術に遡る起源
〇文字の起源は占卜に、詩歌の起源は呪術にある。漢字の起源は詩歌の起源と時をへだてはしても重なり合うのである。
〇声は超越にかかわるが、文字は超越論的次元にかかわる。声は現象を、生を意味するが、文字は永遠を、死を意味する。
2.象形と形声のあいだ─起源の忘却
〇記号作用とは概念作用のことであり生命現象のことである。記号作用が言語現象へ、言語現象が文字現象へと飛躍する過程は、その過程そのものを忘却する過程にほかならなかった。
〇形声の体系は水平に無限に広がってゆく。だが、象形の体系は、血みどろの犠牲を撒き散らして神に縋ろうとする垂直な体系である。とすれば、起源の忘却は象形と形声のあいだにあるということになる。
〇白川静は、孔子がソクラテスやイエスと同じように、みずから書く人ではなかったことに繰り返し注意を促している。「聞くことと話すこと」と「書くことと読むこと」との違いに注意を促しているのである。「耳と口」の対は、「目と手」の対と違っている。たとえば巫女は「耳と口」の伝統に属し、占卜は「目と手」の伝統に属す。この二つの伝統の交叉するところに孔子は位置していたと、白川静は考えている。
3.表意文字の表音文字への転化─個人の誕生
〇書に臨むとき人が思い浮かべているのは声ではなく形である。聞くこと話すことと、読むこと書くこととはまったく違うことだ。だが、表意文字が表音文字に転化するということは、それが合致したということである。この合致こそが、個人の思想を生み、思想としての個人を生んだのだ。
〇文字が声として振る舞いはじめたとき、すなわち象形文字が義である以上に声として振る舞いはじめたときに生じた捩れを、たとえば「私はなぜいまここにこのようにしてあるのか」という問いのかたちで考えることができる。
三浦氏は、象形から形声への飛躍を、表意文字から表音文字への移行に匹敵する事態であるとし、また漢文から漢字仮名混じり文への移行に等しい、と書いていました。文字誕生にはじまる三段階のプロセスの最後のステージにおける、声と文字の拮抗・相剋の問題が、漢字とかな、意味語(自立語)と機能語、あるいは詞と辞の関係性のうちに集約的にあらわれているということでしょう。
藤井貞和氏は、『日本近代詩語』に収録された論考「漢字かな交じり文、神経心理学、近代詩」において、「『万葉集』以来、日本語の表記は一三〇〇年、漢字かな交じり文であり続ける。」(63頁)と書いています。「中世には和漢混淆文など、漢字かな交じり文で書かれる。近、現代では物語文学(例えば『源氏物語』)が、教科書を始めとして漢字かな交じり文として書き直されるようになっており、そのことをだれも疑わず、ほぼ困りもしない。」
藤井氏は、この「漢字かな交じり文問題」をめぐって、岩田誠著『脳とことば──言語の神経機構』に準拠して、意味語と機能語とでは脳内で取り扱う場所を異にすることに触れた上で(72-73頁)、「人類史上の音声言語から表記言語へという流れのなかに位置づけられるのでなければ、依然として日本語特殊説(比類ない言語だとか、よい加減な言語だとか言われる毀誉褒貶)に終わることになりかねない」(74頁)と論じています。
《意味語と機能語と、言語が意味と機能という別個の回路を有することは、…日本語以外でも言えることではないか。とともに、漢字かな交じり文以前の話しことばにおいてそれらが成長したということも、世界の諸言語において言えることになる。真には表層の意味語が深層の機能語によって下支えされる関係であり、たまたま日本語が意味語と機能語との居場所を別にすることによって見ることのできた区別に過ぎない。〈表層と深層〉という差異に意味語と機能語とは対応しそうに思える。
それらを西洋語にあてはめるならば、まず〈冠詞、助動詞、前置詞〉が〈かな〉に相当し、その他の意味語が〈漢字〉になる、ということではなかろうか。》(『日本近代詩語』81-82頁)
《…人類約五万年と見て、巨大な高次連合野の〈第一の飛躍〉によって、内部メモリーを拡張させ、話しことばを獲得したヒトは、情報量を増大させる。ついで、五五〇〇年ほど前か、〈第二の飛躍〉によって、時間と空間の壁を越える自由なコミュニケーションの能力を獲得する。
私の推察すべきこととしては、意味語と機能語という差異を、文字以前のかなた、約五万年かもしれない第一の話しことばのなかに用意してきたということだ。第二の、文字の使用に至って、それらの二種が分化するするようになり、書記言語を成立させてきたおおもとに、音を言語とする話しことばのうちなる文法的成熟が、たまたま日本語にあって漢字かな交じり文として現前したということである。》(『日本近代詩語』84頁)
藤井氏の問題意識は、萩原朔太郎が『詩の原理』の「結論」を「島国日本か? 世界日本か?」で終えたことを踏まえています(25頁)。すなわち、日本語で書かれる詩が世界文学の一部となるためには、数や性といった文法上の問題についてルーズであってはいけない──「古池や」の蛙は何匹かという問題を避けて通ってはいけない──ということです。
とても大事な視点だと思います。たとえば、明治の言文一致、これもまた漢字かな交じり文の問題と同様、声(パロール、言)と文字(エクリチュール、文)の拮抗・相剋の問題に通じています。それは、「第三の飛躍」と呼んでもいい巨大な転換であり、かつ日本特有の問題ではありません。
いまひとつ付言します。橋本治は「「和漢混交文」という概念は、言文一致体が出来た後になって登場するか一般化するようなものだ」と書いています(『失われた近代を求めて(上)』第一章五節「大僧正慈円の独白」)。だとすると、「漢字かな交じり文」という概念自体が、言文一致体の成立後に遡及的に一般化したもの、いわゆる遠近法的倒錯にもとづくものだということになるのでしょうか。
以上の二点、つまり日本語における出来事の普遍性とその転倒性(の普遍性)、そして藤井氏の議論に登場した「深層/表層」の構図、これらのことが第三のステージにおける論点になります。“柄谷文字論”の出番が到来しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
