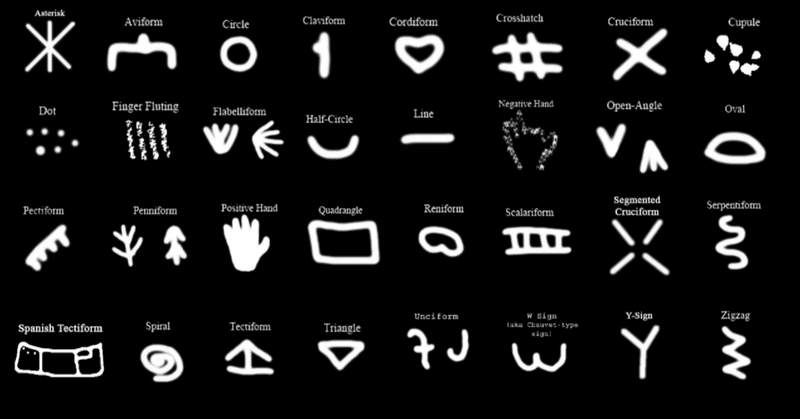
文字的世界【32】
【32】意識をつくる言語、意識がつくる言語─余録として
エクリチュールと声、漢字と仮名の関係をめぐって、個人的な関心事にそくした一文を余録として挿入する。個人的関心事とは、紀貫之の歌論(古今集仮名序「やまとうたはひとのこころをたねとしてよろづのことのはとぞなりにける」)の解読、貫之歌の世界をどうとらえるかというもの。
以下に自己引用するのは、神田龍身氏(『紀貫之──あるかなきかの世にこそありけれ』)と山田哲平氏(「日本、そのもう一つの──貫之の象徴的オリエンテイション」(『語りのポリティクス──言語/越境/同一性をめぐる8つの試論』所収))の議論を“素材”として(勝手に)編集した“偽装”の論争をもとにした文章(出典は「哥とクオリア/ペルソナと哥」第16章)。
■二つの世界と二つの言語
……屏風歌や鏡像歌の詠歌体験を通じて、まこととまことならざるもの、リアルなものとフィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)なものとの水平的な交換関係を発見した貫之は、この二項関係が、実はもう一段下位のフィクションの上に成り立つものであることを自覚していた。そして、その根源的なフィクション(何もないこと)を「地」として、「ある」と「ない」との水平的な交換関係が「図」として立ちあがるのか、あるいは逆に、「ある」と「ない」の交換を「地」として、「何もない」が「図」として透かし彫りにされていくのかはともかく、そのように二重化された交換関係こそが、森羅万象の世界を造形し稼動させる原理であり、かつ、言語というものがもつ根本的な構造にほかならないとの認識に達した。
貫之が、あくまで歌を詠む、あるいは編むという体験を通じて見出していった、この、世界と言語の構造的な相同性は、さらに高次元の交換関係を切り結んでいく。すなわち、言語の構造は世界の実相を反映する写像なのか(世界内存在としての言語)、あるいは逆に、世界のあり方の方が言語をなぞっているのか(世界の造形・稼動原理としての言語)、端的にいえば、「世界が先か言語が先か」をめぐる二つの立場が、対等の権利をもって成り立つことになる。この二者択一を前にして、貫之自身は、万象は言語の産物であり、「歌の心」(クオリア)や「人の心」(ペルソナ)もまた、言語がかたちづくるコンテクストのうちに立ちあがってくるとする言語一元論の立場を採った。精確には、そのような「世界を創造する言語」へとつながる言語観を“偽装”し、かつ、自らが“偽装”した領域内において「歌が歌を生みだす(アナグラム的な)プロセス」を探究した。
いや、問題は「言語が先か世界が先か」ではない。「ヴァーチュアル/アクチュアル」の垂直的な二者並立関係において、「言語/世界」なのか「世界/言語」なのかということこそが、問われなければならない。(「言語/世界」や「世界/言語」がいかなる事態を表現しているかは、この際、措く。肝心なのは、いずれの描像にあっても、両者の「垂直的な」並立関係が表現されていることである。)
しかるに、「言語が先で、世界は言語によって産出される」と主張するとき、言語の側がアクチュアルかつリアルである(言語の方が現実存在で、世界はその言語によって仮構される)とするか、逆に、世界がアクチュアルかつリアルである(世界の方が現実存在なのだが、それは、言語によってそのようなものとして制作される)とするか、そのいずれの場合にあっても、一方の側のヴァーチュアル性は否定され、リアルなものに対するフィクショナルなものの側へと繰りこまれてしまう。つまり、言語と世界の関係が、「ヴァーチュアル/アクチュアル」の垂直的な並立関係から「フィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)/リアル」の水平的な交換関係におきかえられ、その結果、両者は同じ平面上で図地反転の関係を切り結ぶことになる。それは、「世界が先で、言語は世界の内部にあって世界を映しだす鏡像である」と主張したところで同断である。
それでは、そもそも貫之において言語はどのようなものとして認識されるのか。
貫之歌(「二つ来ぬ春と思へど影見れば水底にさへ花ぞ散りける」)にあらわれた鏡像(水面に映じた桜)は、現実世界のたんなる写像ではなく、そこから現実世界と並行して存在するもう一つの自立世界が開いている。つまり、貫之の鏡像歌において、世界は二つあった。一つは、「中国」「仏教」という普遍的文明や世界宗教によってかたちづくられた(アクチュアルかつリアルな)「現実世界」であり、いま一つは、その現実世界に投げこまれ、そこにおいてたゆたうもう一つのローカルな世界、そして、「現実世界」からの自立や離反をめざす(ヴァーチュアルかつリアルな)「自立世界」である。
この二つの世界に対応して、言語もまた二つある。貫之の場合、現実世界に対応するのが漢字・漢文であり、もう一つの自立世界に対応するのが仮名文字・仮名文だった。そうだとすると、先の、言語と世界の関係をめぐる問いへの回答は、それが貫之における言語の位置づけをめぐるものであるかぎり、「言語/世界」でも「世界/言語」でもなくて、「ローカルな世界(=日本)/ユニヴァーサルな世界(=中国)」という垂直的な並列関係と、「ローカルな言語(=仮名文字・仮名文)/ユニヴァーサルな言語(=漢字・漢文)」というもう一つの垂直的な並行関係とが、それこそ並行的に成り立たなければならないというものになる。ローカルな世界がユニヴァーサルな世界からの自立をはたすためには、ユニヴァーサルな言語に拮抗しうるローカルな言語を確立しなければならないということだ。……
■意識をつくる言語、意識がつくる言語
……意識は、言語によってかたちづくられる。そうした力をもつ言語(意識をつくる言語)を「ユニヴァーサルな言語」と呼ぶならば、この言語が造形する意識によっては掬いとることができない残余の意識(たとえば、神仏由来の光が達しない、あやなき闇にうごめく「あるかなきか」の音や匂いや気配)、もしくは、そのような言語がかたちづくるコンテクストのうちにはすまいすることができない体験(たとえば、クオリアとしての「歌の心」やペルソナとしての「人の心」)が、ユニヴァーサルな言語に拮抗するものとしてつくりだす言語(意識がつくる言語)のことを「ローカルな言語」と名づけることができる。
一つの言語には一つの世界が対応する。ユニヴァーサルな言語には「ユニヴァーサルな世界」が、ローカルな言語には「ローカルな世界」がそれぞれ対応する。ところで、ユニヴァーサルな世界の住人にとっては、言語と世界(と意識)の関係はあまりに身近で自明なものであり、「世界が先か言語が先か」(あるいは、「意識が先か世界が先か」「言語が先か意識が先か」)といった問いは意味をなさない。そのような問いを意味あるものとして受けとめる(受けとめざるを得ない)のは、ローカルな世界の住人である。(「ユニヴァーサルな言語」や「ユニヴァーサルな世界」は、ここでの文脈でいえば、それぞれ「漢字・漢文」であり「中国」である。しかし、これを一般化して、それぞれ「母語としての○○語」、「○○語が母語として使用される世界」におきかえて考えてもよい。)
ローカルな世界の住人の立場から、言語と世界(と意識)の関係を、「アクチュアル/ヴァーチュアル」の垂直的な並立関係にそくして構成すると、まず最初に成立するのが、「ユニヴァーサルな言語/ユニヴァーサルな世界(意識)」である。この図式は、二つのことを同時に表現している。ローカルな世界の住人にとって、ユニヴァーサルな世界(とそこに住む人間の意識)の実質は(ともに)ヴァーチュアルでうかがいしれないものであり、ただその言語(文字や音声)だけがアクチュアルで知覚可能なものであるということと、ユニヴァーサルな言語を永年にわたって使用しつづけることで、やがて、そのような言語生活者のヴァーチュアルな心の次元に、ユニヴァーサルな世界の住人のそれと同等の意識が造形されていくということである。
意識は、言語によってかたちづくられる。このことを、ユニヴァーサルな世界の住人は自覚できないが、ローカルな世界の住人は痛切に自覚する(自覚せざるを得ない)。なぜなら、そこには残余の意識と、ユニヴァーサルな言語をもってしては表現できない体験がうごめいているからである。いや、そのような残余の意識や体験が、(たとえば、「からごころ」に対する「やまとごころ」のように)、ヴァーチュアルかつフィクショナル(イマジナリー、ポッシブル)なものとして仮構(制作)される、というのが精確かもしれない。しかし、たとえそうだとしても、残余の意識・体験は、いずれ、ヴァーチュアルな次元におけるリアルなものとフィクショナルなものとの図地反転を通じて、ヴァーチュアルかつリアルなものとしての地位を獲得し、やがて、あくまでヴァーチュアルな次元においてではあれ、ユニヴァーサルな言語に拮抗するローカルな言語をつくりだす。こうして、第二の図式、「ユニヴァーサルな言語/ローカルな言語(意識)」が成り立つ。
(ちなみに、ここで、ヴァーチュアルかつフィクショナルな「やまとごころ」が、ヴァーチュアルな次元での「リアル/フィクショナル」の水平的交換関係を介することなく、したがってユニヴァーサルな言語との拮抗関係を経ずして、直接的に「やまとうた」のうちに自らの表現を見出すのだ、といった議論を展開することも可能である。たとえば、「はじまりの歌(=やまとうた)/人の心(=やまとごころ)」という描像を「偽装」することで。
ところが、その場合、「やまとうた」は「やまとごころ」から受け継いだフィクショナルなものという身分を保持したままアクチュアルな次元に位置づけられることになり、すると今度は、アクチュアルな次元における「リアル/フィクショナル」の図地転換を通じて、アクチュアルかつリアルなものとしての地位を獲得するに至る。その結果、「ローカルな言語/ローカルな世界(意識)」という図式が得られることになる。
しかし、これは、かの第一の図式「ユニヴァーサルな言語/ユニヴァーサルな世界(意識)」と同型であって、その意味するところは、ローカルな意識(ユニヴァーサルな言語が造形した意識によっては掬いとられない残余の意識)が、自らに表現を与えるローカルな言語をつくりだし、そして、その言語こそがユニヴァーサルな言語(意識をつくる言語)であると主張しているに等しい。もちろん、そのような主張をするのは勝手だが、少なくともこれは貫之の歌論とは似て非なるものである。)
ローカルな言語は、「ローカルな世界(意識)」を造形する。すなわち、「ローカルな世界(意識)/ローカルな言語」。(この議論の最初からでてくる「ローカルな世界の住人」は、実はこの段階にいたってはじめて登場するものだった。)しかし、この図式は、たちまちのうちに、「ユニヴァーサルな世界(意識)/ローカルな世界(意識)」という第三の図式におきかえられてしまう。なぜなら、ユニヴァーサルな言語(意識をつくる言語)の方がローカルな言語(意識がつくる言語)よりも強力だからであり、したがって、ユニヴァーサルな世界とローカルな世界は、あたかも帝国と植民地の関係のように、一つの政治権力が統治する平面上で対等の関係をむすぶことはできないからである。
かくして、「ユニヴァーサルな世界/ローカルな世界」と「ユニヴァーサルな言語/ローカルな言語」が並行的に成り立つ貫之の言語観が確立された。……
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
