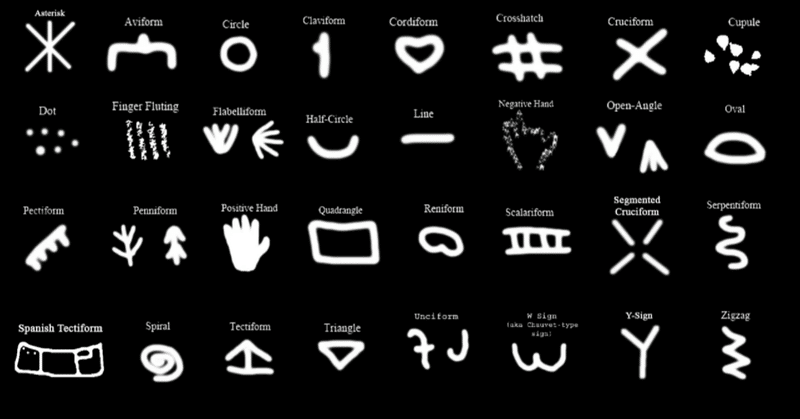
文字的世界【21】
【21】メカニカル=メトリカル・ライン、錯綜体=透過的身体
前々節と前節で、その場の思いつきのようなかたちで導入した、人間の言語の「メカニカル」な帯域の意義をめぐって、自分自身のための覚え書きを残しておきます。
この概念、というより語彙を選んだ背景には、吉本隆明「固有時との対話」の「メカニカルに組成されたわたしの感覚」云々の詩句に触発されたこと、そして古代ギリシャ劇の「機械仕掛けの神(デウス・エクス・マキナ)」や、歌舞伎舞踊における「人形振り」という語がもたらすイメージに刺激を受けたことがありますが、より直接的には、「仮面的世界」の第17節で和辻哲郎の『歌舞伎と操り浄瑠璃』を取りあげた際、坂部恵著『和辻哲郎』の議論を踏まえて述べた(自己引用した)事柄が念頭にあります(「哥くクオリア/ペルソナと哥」第81章第4節「能楽と操り浄瑠璃と歌舞伎─やまとことばのメカニカルな展開」参照)。
すなわち、浄瑠璃劇の舞台上に作り出される「現実よりも強い存在を持ったもの」(和辻哲郎)とは、「はじまりの言語」の記憶をフィギュールとして保持する“やまとことば”のメカニカルな展開がもたらす憑依=表意(意味の受肉)の体験そのものなのではないか。あるいは、これを言い換えると、舞台上の“人形(=仮面)”のメカニカルな動きは、「脱我的な憑依体験」をかたどるフィギュール(文字)なのであって、すべては舞台上の外面的な関係性の中のメカニカルな“おもて”の出来事であり、そこには“うら”(心)はない。
(念のために注記しておくと、ここで言う“やまとことば”や“人形(=仮面)”は、固有の歴史性を帯びた実在の物・現象であると同時に、より普遍的なもの、つまり「はじまりの言語」の記憶や「脱我的な憑依体験」のかたちを保持する“フィギュール”として捉えられている。)
言葉遊びのようですが、私は、今述べた意味での「メカニカル」な動きが展開される帯域のことを、かつて「韻律的世界」の第15節の註で導入し、第18節から第21節において複線化していった「メトリカル・ライン」──「生命界」を横断し、知覚(今ある現実)と想起・想像(様々な可能性)をつなぐ「身体のライン」にして「リアリティ」の水平軸、「日常言語(‘うつつ’の言語)」の可動域──と重なりあうものと考えています。
メカニカル=メトリカルなラインは、歌謡、舞踊、演劇、芸能、祭祀、儀礼の帯域でもあります[*1]。
ここで引用しておきたいのが、養老孟司氏が「まさに古今東西にわたって、歌謡、芸術の起原を探求し、現在に至るまでを描く驚くべき書物」と推薦の言葉を綴った、武田梵声著『野生の声音──人はなぜ歌い、踊るのか』の議論です。帯に記されたこの賛辞と、カバーのそでに印刷された「旧石器時代、人類はみな、野生の芸能者であった。自在に歌い、語り、舞い、踊り、演じる力を持っていた──。」というコピーが、この書物の“本質”のようなものを語っています。が、すべてではない。細部に宿る息遣いを聴き取ってこそ、この書物の“精髄”に迫れるというものです。
採取しておきたい多くの言葉のうち、第4章「原初の歌唱芸能の姿を探る」から、次の一節を引いておきます。
《「文字」の発生が人の声や芸能に、多大な影響を与えたことは間違いない。しかし、ここではさらに過去にさかのぼり、分節言語の発生が原初の歌や芸能に与えた影響を考えてみたい。(略)
…この分節言語発生以前には何があったか。それは「歌」である。…少なくとも分節言語と文字の発明の中で、徐々に「歌の喪失」が起きたことは間違いないだろう。「言葉」を得ることにとよって、それまで人類が当たり前のように享受していた「歌」の力=神の声の喪失が始まったということだ。
発声の技法という点でも、分節言語は我々の「喉」が持つ可能性の、ほんの一部しか使わないことは明確となっている。その後、さらに文字言語が発生することによって、それまで当たり前のように行われていた口承伝承も減少し、脳における声の原初的なネットワークの発達が抑圧されていったと考えられる。(略)
誤解のないように補足しておくと、ここでいう「神の声」というのは、あくまでも脳内に鳴り響くいわゆる内部音であり、いわゆる狭義の歌、狭義の原初の歌とは別のものである。しかし、内部音や神の声は原初の歌と感応しあうものと考えられる。
シャーマンが内的体験により精霊から習うとされるパワーソングなどの例から考えても、この内部音と原初の歌唱の能力との関係は極めて密接なものと考えられる。この内部音、もしくは内部音的なもののイメージが人類の歌唱能力を高め、倍音をたっぷりと含んだ声の語りや歌唱がまた内的音響を増強するという感応しあう相互関係であったのだ。これがある段階まで、ほとんどの人類が当たり前に体験し、それがある段階で失われたのだとしたら、ここでの仮象能力の喪失も極めて大きいものであったはずである。
分節言語の獲得と後の文字の発明によって、人類から原初的な歌の力は消え、「神の声」もまた沈黙したのである。》(『野生の音声』102-105頁)
これだけだと、ここではなく「韻律的世界」で論じられるべき問題圏域にとどまるので、いまひとつ、身体性もしくは形象性により強くかかわる話題を引きます。
第9章「アルトーと未来的祝祭演劇」において、武田氏はポール・ヴァレリーの「錯綜体(implexe)」の概念──「まず、自分が実感している第一身体。他者から見た私の身体である第二身体。客観的、解剖学的、生理学的な身体である第三身体。そして、それら以外のあらゆる身体感覚のレベルを内在した第四身体[=錯綜体]」(245頁)──を取りあげ、これを、たとえば折口信夫の「透過的身体性」[*2]、さらには武術的な身体観に関係づけています。
《実は、こうした錯綜体の概念と通ずる捉え方は、古今東西の身体論にも、見出すことができる。禅竹の六輪一露論やアルトーの精神のアスリート論などがそうだ。近代では、和辻哲郎が、古代日本人の身体感覚は心=身体=自然が不可分な一体性を持っていたと指摘している。和辻は上代歌謡の分析からそのような身体感覚を導き出したわけだが、これは旧石器時代の思考法であり、身体感覚であると言われる浸透概念や流動概念とも重なるものだ。あるいは、中国における体内神の実感やその瞑想技法である存思[そんし]とも重なる。
折口信夫もまた、内外の境界が、生理的な皮膚ではなく、身体感覚的に拡張されたり縮小されたりするような身体感覚、すなわち透過的身体性を持っていたと言われている。こうした身体感覚はこれまでにも空手家であり武道研究者であった南郷継正や、ゾーン・フロー理論で研究されてきたものに通じている。(略)
錯綜体、あるいは透過的身体性というのは、武術の分野において特に重視され、研究されてきた概念だ。植芝盛平が到達した、敵と自分との境界線がなくなり、あるいは溶け合っていく黄金体、すなわち武産合気[たけむすあいき]の境地も、こうした身体観に連なるものであろう。古柔術である竹内三統流を基礎に持つ木村正彦の「透明な肉体」の境地も、またこれに類似するものである。
身体性という観点に立つと、武術と民俗芸能の間に共通点が多い。それも当然で、折口信夫が言うように、もともと武術と芸能は一つのものなのだ。》(『野生の音声』246-248頁)
折口信夫の身体感覚は「まれびと」のそれに通じているはずです。そして、透過的身体は、“フィギュール”が持つ透明な(精霊的・幽霊的な?)肉体に連なるものにほかならないでしょう。
[*1]メカニカル=メトリカルなラインは、「仮面的世界」の第34節で、ケネス・バークの「五つの鍵語」をもとに作図した劇的表現の「ペンタッド」における水平線に対応している。
【舞】━━━━【面】━━━━【聲】
「聲(agent)=哥」の形が 「舞(act)=文字」である。あるいは哥の姿が可視化され、文字すなわち「動きつつある形」(大石昌史)となったのが舞である。また聲が舞に成るためには、聲はなんらかの「面[オモテ](agency)=身」を装着しなければならない。
[*2]津城寛文氏の論考「折口信夫の鎮魂論──研究史的位相と歌人の身体感覚」によると、「透過的身体境界」とは「霊魂の容器である人体・物体がそうした「魂」の出入を防げ得ない状態」をさしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
