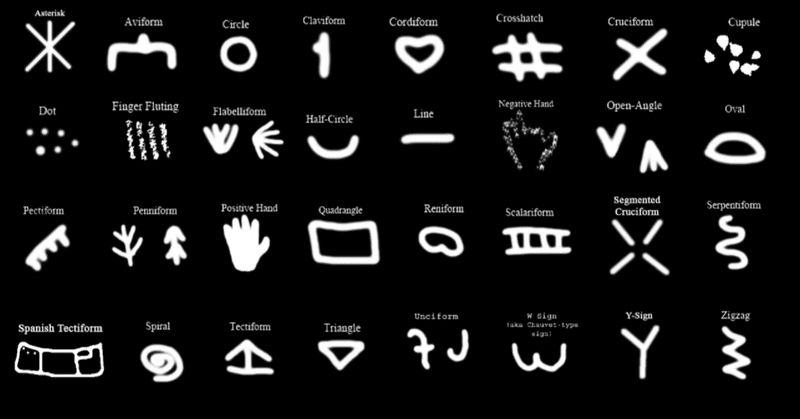
文字的世界【25】
【25】独在性と文字─永井均の議論に即して
本稿の第2節で、次のように書きました。「この安田説に加えて、私は、クオリアや共感覚やアウラやヌミノーゼといった“非言語的”ないし“超言語的”な体験も、そして、もしかすると永井(均)哲学における〈私〉や〈今〉といった「独在的存在」もまた、文字発明というシンギュラリティの産物なのかもしれないと考え始めています。」
「安田説」とは前節で引いた議論、つまり文字の発明が心を生み、その心からリニア―な時間や論理が生まれたというアイデアのことを指しています。クオリアや共感覚[*]、アウラ、ヌミノーゼなどについてはさておき、ここでは、永井哲学における「独在性」の概念と文字の関係について、少し立ち入って考えてみたいと思います。
その際のキーワードは、前々節で引いた白川静の言葉、すなわち「形象化」です。それは、これまで何度か引用した永井均氏の次の文章──自己同一性(〈私〉の持続)が成り立つ複合的プロセスに説き及んだもの──に出てくる「文字化」と同義であることは言うまでもないでしょう。
《〈私〉が同一性を保って持続するには、《私》化と「私」化の媒介を経なければならず、そこには《今》化と「今」化が介在している…。「そこに書かれている〈私〉をあたかもいま読んでいる自分自身であるかのように理解している」とき、そういう問題を考えている人物としての記憶とともに、独在性の形式的・概念的理解もまた介在し、経由されている。と同時にまた、〈いま〉にかんするそれと同種の読み換えも介在し、経由されている。この例では、文字化によってそのことがあからさまになっているが、この構造自体は通常の〈私〉の持続においても避けることができない。そもそも記憶という現象自体がこの仕組みの介在によってはじめて可能になるからだ。ちなみに、ジャック・デリダが自己同一性の成立に不可避的に介入するこの外在化の仕組みを、フランス人らしく隠喩的に「文字(エクリチュール)」と呼んだことは印象深いことであった。しかし私見ではむしろ、カントの「観念論論駁」におけるデカルト批判のほうが、機先を制して隠喩的でない精確な問題提起をおこなっていたと思う。》(永井均・森岡正博『〈私〉をめぐる対決──独在性を哲学する』277-278頁)
言葉の確認をします。『〈私〉をめぐる対決』第一章の「語句解説」(森岡氏執筆)を借用すると、まず「独在性」とは「私は、この世界のなかに、他人とはまったく異なったあり方で存在している」と考えられる、そのようなあり方やその性質を指す。(ただし、「この世界に存在するのは私だけである」という「独我性」とは異なる。)
次に、独在的に存在するもののうち、「即座に特定の対象を指示する」もの──もしくは「現在の世界にはなぜか存在している、一人だけ他の人間とはまったく違うあり方をしている人」(永井『世界の独在論的存在構造』23頁)──が〈私〉、「独在性という形式を表現する」ものが《私》であって、「無数のそのような主体(諸《私》たち)のうちから、唯一の現実の〈私〉はどのように識別されうるのだろうか、という問題が生じる」(永井前掲書82頁)。
(若干補っておくと、永井氏が考えている独在的存在としては、〈私〉以外に〈今〉や〈現実〉がある。また、上記引用文で「私」や「今」の表記が指し示しているのは、日常的な言葉遣いのもとでのそれ(概念)である。)
さて、以上の“道具立て”のもとで、永井氏が語っている事柄の前段部分を、試みに図式化してみると、次のようなものになります。
かつての〈私〉
│ │
<文字化=外在化> │持│
独在性の形式的 │ │ 人物の記憶
・概念的理解 │続│
↓ ↓
いまの〈私〉
これまでに製作した図(たとえば第19・20節)と関連づけるならば、「かつての〈私〉」と「いまの〈私〉」の間に拡がる圏域(事象内容もしくは「リアリティ」の圏域)のうち、「人物の記憶」にかかわる右方は「声、パロール」の、左方は(文字通り)「文字、エクリチュール」の領域に該当します。
(付言すると、「かつての〈私〉」と「いまの〈私〉」もしくは「かつての〈今〉」と「いまの〈今〉」が属するのは「アクチュアリティ」の圏域である。さらに蛇足を加えると、《私》や《今》は形式的・概念的に理解された独在的存在として「リアリティ」の圏域に属している。「かつての《私》」と「いまの《私》」が持続するとして、それはどの〈私〉なのかが問題となる。なお、「私」や「今」は「リアリティ」の圏域の中核もしくは基軸(水平軸)をなす日常的・公共的・客観的言語そのものに属している。)
永井氏の議論の後段部分について、ごく簡単に言及しておきます(というのも、詳細に論じる準備が出来ていないので)。
まず、デリダのエクリチュールをめぐって。──高橋哲哉氏が『デリダ 脱構築と正義』第二章で、「プラトンのパルマケイアー」(『散種』)におけるデリダの議論を次のように括っています。「パロールはある意味ではまさにエクリチュールの一種であり、だからこそ、パロールの記述にエクリチュールの「隠喩」が必要とされるのである。このパロールのなかにあるエクリチュール性を、デリダは、のちに見るように、「根源的」エクリチュールという意味で「原[アルシ]エクリチュール」と名づけている。」
デリダ入門篇ともいうべき基本的な記述ですが、ここで言われる「パロールのなかにあるエクリチュール」(もしくは、魂のうちに“書きこまれた”パロール)が、〈私〉の持続をもたらす文字化=外在化のメカニズムを「隠喩」的に表現しているわけです。
次に、カントのデカルト批判をめぐって。──『〈仏教3・0〉を哲学する バージョンⅡ』で永井氏が「カントの議論のなかなか精妙なところ」として語った事柄。「何が問題かというと、デカルトは「我思う、ゆえに我あり」と言った。つまり、客観的世界の存在を疑って、自分の存在は確かだ、と言った。それに対してカントは、それに反対したわけではなく、しかし、もしその自分というものが時間的に持続していると考えるなら、そのとき、客観的世界も持続的に存在していることを前提していることになるのだ、と言ったのです。そうでなければ、自己の持続は不可能なのだ、というのがカントの主張です。」(204頁)
上図に即して言い換えると、「かつての〈私〉」と「いまの〈私〉」の持続が成立していると考えるなら、そのとき、客観的世界すなわち「リアリティ」の圏域の持続的存在が前提(証明)されているのだ、となります。
[*]三浦雅士氏は『孤独の発明 または言語の政治学』で、共感覚とは言語現象であって、言語によって表現されなければたんなる生命現象にすぎない、と語っている。
《私には共感覚とは言語現象であるとしか思えない。
共感覚の問題は、言語の獲得とともに人間が直面しなければならなくなったさまざまな問題、すなわち社会的・政治的・宗教的問題の基層に潜んでいる。共感覚すなわち感覚の転位にこそ、人間の基層を解く鍵が潜んでいる、と私には思える。
むろん、言語以前にすでにこの種の感覚の交響あるいは照応があったと想像することもできるわけだが、かりにそれがあったとしても現実には意味を持たない。なぜなら、感覚の転位も交響も照応も、表現においてしか意味を持たないからである。(略)
要するに、感覚を比べるということ自体が言語以前にはありえない。コウモリであるとはどのようなことかと問うこと自体が言語以前にはありえないのと同じである。人はコウモリを演じることはできるが、蝙蝠は人を演じることができない。演劇は言語でなされるからなどということではない。さらに深く、演技という表現そのものが──つまり無言劇でさえも──言語という構造のもとにしか発生しないということである。感覚の交響があるにせよないにせよ、表現されなければそれはたんなる生命現象であって、それだけのことにすぎない。》(『孤独の発明』447-448頁)
本文で使った永井氏の記法に関連させると、ここで言われる生物現象や感覚の交響は「生物現象」「感覚の交響」と、共感覚は《共感覚》と表記することができる。山括弧(二重否定)の記号を使って表記すべき事柄についての言及はない。強いて言えば〈コウモリである〉ことが該当するかもしれないが、それは「《コウモリである》とはどのようなことか」という問いの中で既に転落している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
