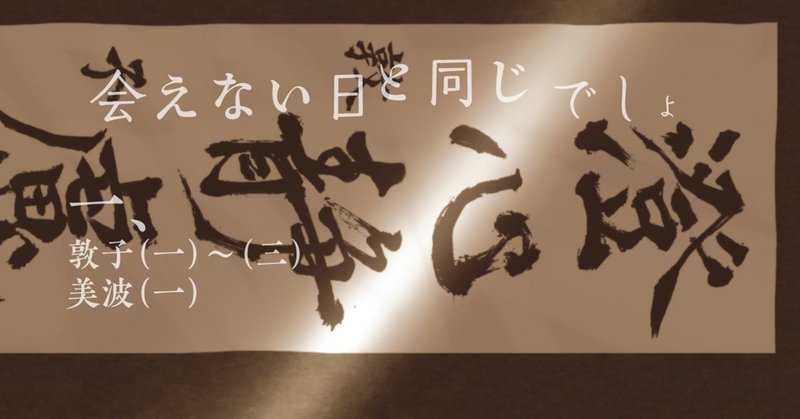
「会えない日と同じでしょ」(1)
■あらすじ
いまはもう居ない 少女との年月を思い出しながら。
私の切実な本当の時間が誰にも触れられないように、少しの嘘を混ぜながら。
あの子たちの選んだ言葉や生き方が嘘にならないように、真実だけで固めた芯を通しながら。
覚えていることを忘れないように綴っておくノート。
敦子、初めて会った日に宿題を押し付けた元気な先輩のこと。
美波、ポテトチップスを箸で食べていた死にたい友達のこと。
■ 更 新 履 歴
・敦子(一)/約 7,000字…2015/1/19
・敦子(二)/約23,000字…2015/2/10
・敦子(三)/約21,000字…2015/3/12
・美波(一)/約 3,000字…2015/1/19
■収録ナビ
一度単行本化したのですがデータの不備が見つかったため、出版をキャンセルしました。改訂版の再編集と併せ、最終回までを収録した完結巻を校了次第、ご購入者様を対象に改訂版の無償配信をいたします。続報をお待ちください。
2018年6月現在、購読可能な媒体はnoteのみとなります。
収録マガジン:こちら
■登場人物のプライバシー
人物特定を避けるため、登場人物設定や何か起きた時期などは、「ストーリー(登場人物の反応・感情・信条・人生選択など)が変わってしまわない範囲で」事実から一部を改変しています。それに伴い回想シーンに登場する小物や景色も、時代性や地域性の印象を大幅に変えない範囲で、時期や正確な年齢、正確な居住地、正確な勤務先等を特定できない形で描写しています。予めご了承ください。)
■かんたんなご案内
*この記事は【4話分/更新確約3回中】で公開を満了しました。
*続章は次の記事をご購読ください。
*更新ルールやお値段の仕組みなどは「総合案内」をご参照ください。
*テキストではなくマンガをお探しの方はこちらに。
「会えない日と同じでしょ」
敦子 (一)
とにかく悲劇的な脚色を背負った日付だったけれども、“敦子は誕生日に亡くなった”のだったか、“敦子は誕生日を明日に控えて亡くなった”のだったか、どちらだったのかを、私はいつの間にか忘れてしまった。
誕生日に亡くなったのだとして、悲劇である。敦子に料理を食べさせることが大好きな敦子の母は、十代最後の一年を迎えた娘の帰りを待っていたに違いなかったし、台所で敦子の好きな物ばかりを、切るなり焼くなり揚げるなりしながら、あの子も来年ハタチなのね、なんて、きっと感慨で胸をあたためていたに違いなかった。三百六十五分の一の確率で、生を受けた日に死を受け止めることの悲劇“らしさ”は、他の追随を許さないものである。
或いは、誕生日の前日に亡くなったのだとして。生を受けた日から一年また一年と歳を重ねた果ての、或る一歳の末日に、折り目正しく生を終えるというのは、遺された者のみで迎える翌日の誕生日が手伝って、やはり仕上がり過ぎて悲劇的な末日であると思う。
いつ亡くしたところで敦子を亡くした重みなど変わらないというのに、悲劇的な脚色が施された最期に気を取られた私は、幼い頃に読んだきりの『白雪姫』と『眠り姫』の所々を混同させるみたいに、敦子の身に起きた悲劇の日が、誕生日であったか、その前日であったか、すっかり定かでなくなってしまった。
記憶の混濁に気付いた時、私は己の誠意を心から疑った。よもや、まさか、いくらなんだって、大好きな敦子の命日を忘れるわけなどないと思っていた。否、思ってなどいない。わざわざ思うことすらしないほど、敦子の命日に“忘れる”などという末路は有り得ない筈だった。
焦った私は先ず、平静を装った。心の底から、体の芯から、瞳の動きから、呼気のリズムに至るまで平静を装った。悟られまいとした。既に実体のない存在となった敦子に。
人智を超えた方法で私の心を覗いて不誠実を暴けるかも知れない敦子に。よりによって命日を忘れたことを、全身全霊で悟られまいとした。私の体が司る細胞の隅々まで、微弱な脳波の一瞬まで、疚しい手汗の分泌を身勝手に決定しているらしい詳しくない器官に至るまで、平静を装うように厳しく命じた。汗をかくな。呼吸を乱すな。普通に、普通にしていろ。バレるな。平常心だ。心拍数を一定に保て。落ち着け。
静かに部屋を見回す。顔を、首を、動かしてはならない。顔はこれまで通り正面を向けたまま、眼球を、眼球だけ、眼球だけだ。眼球、右…左…あまりキョロキョロするとおかしいから、虚空を見つめてから…少し間を置く。そして、意識的に正視。はい、落ち着いて…。はい、やめ。
部屋の空気が動いていないことを、目視と、急拵えの霊感で確かめた。振り返ることはしなかった。誰も居ないはずの部屋で振り返るなんて、まるでワケアリに見えるからだ。敦子に怪しまれてしまう。背後に気配がないことは、やはり、取り急ぎ湧かした霊感により静かに確認した。
居ない。
部屋には、居ないな。一応、分かってはいたけれど、敦子の霊らしきものは、私の部屋では、私を見張っていないようだった。
それはそうだ。敦子の霊に関して言えば、わざわざテレビのない私の部屋を好き好んで彷徨くわけがない。なぜなら、結局のところは別の原因で死んだ生前の敦子曰く、敦子は「テレビがないと死ぬ」のだ。だから敦子の霊は、テレビのない私の部屋を好まない。
ところで私は、「死んだ人は、いつまでも心の中で生きている」などという使い古されたフレーズを、長らく嫌ってきた。
だって、そんなわけないだろう。死んだら居なくなるのだ!と私は思う。こんな軽い気休めの言葉で深い深い喪失の穴が埋まってなるものか!私が喪ったものはもっと大きいのだ!と思う。
そう、もう、このフレーズの頭文字を掴んで、ふた文字目から一字ずつ、ゆっくり力一杯、音がするほど強くひっぱたいて、右へ、左へ、弾き飛ばして、フレーズをバラバラに、意味のない一文字ずつになるまで分解したい。そして最後に私が掴んでいる頭文字の"死"というやつを、 思い切り地面にぶつけて、叩き割ってやりたい。そして粉々になったそれに怒鳴りつけてやる。
—死んじゃうっていうのは、 このぐらいのメチャクチャなことだろう!!—
とにもかくにも気に食わないのだ。どんなに会いたくとも会えない人を、それなのに、「いつまでも生きている」だなんて、くれぐれも適当を言わないで欲しいのだ。
聞くところでは人の感情や意識というのは、脳がどうにか操縦しているらしいので、つまりは故人の脳を火葬してしまったら、もうどうしようもないのだ。魂なんて残らない。体を焼かれて尚、脳を焼かれて尚、魂が生き延びられるほど勝手のいいものならば、脳死した人の魂などは一体どこで何をボンヤリしているのだ、もう少し頑張って、せっかく残っている肉体に戻って生き延びてくれ。
脳と肉体を焼失したところを境に、人は消失されるのだ。だから、敦子だってもう、居ないのだ。死んだだろう、敦子は。居ないだろう。とっくに焼いただろう。脳も、体も。意識を作る仕組みも、心を保つ仕組みも、敦子はとっくに焼失した筈だ。
ところが気に食わないフレーズを、理屈と、苛立ちでもって、突っぱねてはみるものの。思い描けば心の中の敦子は微笑む。声を聞こうと思えば喧騒に紛れようと私の中にハッキリと聞こえる。
これは、「まだ生きている」と言うには心許ないけれど、「どこにも居ない」と切り捨てるには存在しすぎている。この実感を断つ術を持たない私はやむなく、“心の中に生きている説”の糾弾をやめている。
死亡と火葬によって敦子の焼失と消失が世界から完了したことは確かなのだが、私の中からも居なくなったとは言い切れないのだ。
敦子。
だって、呼べば返事をする。私には聞こえているのだ。
ということは、だ。
つまり恐ろしいことである。敦子の命日を忘れてしまった私を、敦子がどこから監視しているかといえば、天国でもない、空でもない、あの虹の向こうでもない、部屋の隅でもない、霊道か何かでもない。よりによって、最も欺きにくい、私の中からなのである。であるからして私は、私の中の敦子をどうにか欺くために、呼吸を乱すわけにいかないし、眼を泳がせるわけにもいかない、慌てて命日を確認するための手帳を開くわけにもいかなかった。少しでも普段と異なる挙動を起こそうものなら、すぐさま私を通して私を見ている敦子に、不誠実がバレてしまう気がしたのだ。
なんとかして敦子の命日を調べねばならない。
さりげなく部屋の本棚に目をやり、左から順番に背表紙をなぞる。『月下の一群』…堀口大學、『羆嵐』…吉村昭、あれは、SHIBUYA109でもらった何かの冊子…、『憂国』…三島由紀夫、『真夏の死』…三島由紀夫、梶井基次郎全集、東京超詳細地図…23区全域、『その名にちなんで』…ジュンパ・ラヒリ、『転がるマルモ』…篠﨑絵里子、『大奥』…よしながふみ、『誠のくに』…——————『誠のくに』。さてこの、『誠のくに』は会津の侍の登場する漫画で、名作である。
それはそうと小学生時代、福島県は幕末の会津藩白虎隊に執心した私は、たびたび会津若松市の鶴ヶ城を目当ての中心として、会津、郡山、喜多方、猪苗代と、福島を旅したものだった。初めて会津に行ったのは小四の夏だ。
一旦、敦子とは何の関係もない、会津若松旅行を思い出す。
確かこの旅行の三日目だった。土方歳三の請願で会津藩主松平容保公によって建立されたという近藤勇の墓…天寧寺近くの駐車場だ。あの駐車場で突然発進した車に運悪くぶつかられた私の元には、お詫びの品として毎年夏になると、運転していた高齢の男性から福島産の桃が一箱届いていた。
ところがある年、それがパタリと止んだのだ。亡くなったのかも知れないし、なんとなく時効を感じたのかも知れないし、どちらでもないのかも知れない。いずれにせよ、桃が償う夏は前触れもなく途絶え、それきりになった。
本棚にささった会津にまつわる漫画本を経由して、敦子の思い出からグッと離れることに成功。
私は現在、福島旅行の思い出の先にある福島県産の桃と、桃の送り主について考えているのである。そうして、桃から少しずつ、平常心を装って、じりじりと、敦子の命日まで意識を向かわせるのだ。敦子とは全く関係のない思い出を経由して、じりじりと。遠回りをしながら、偶然を装って。
数々の余計な回想を経た私の思考の最初の目的地は、『敦子と出会った日』だ。出会った日まで辿り着けたなら命日の頃を思い出すのは自然なことであるから、そうしたタイミングで素知らぬ顔をして、当時のプリクラ帳やアルバム、敦子の命日が書かれている古い手帳を開けば、波風のない成り行きである。
敦子の命日を失念してしまった私は、私の中から私を見ている敦子に、これを暴かれるわけにはいかないのである。なんとしても、「敦子の命日を忘れたから手帳を開いた」のではなく、「敦子の思い出を辿っているうちに懐かしくなって当時の手帳も開いた」、という”テイ”で行きたいのだ。
——————先に断っておこう。
全ては気のせいだ。
敦子に私の不誠実が見透かされるというのも、敦子の声が聞こえるというのも、”敦子の意思で動いているかのように”敦子が心の中で生きているということも、全て気のせいだ。
私はおかしくなってしまったのではない。全ては虚構で、茶番だ。わかってやっているので、そっとしておいて欲しい。
私の中の敦子は、結局のところ私が操っているのだ。声だって笑顔だって、私が見ているものは思い出なのだ。記憶にアクセスすることが「心の中に生きている」と呼ばれているのだ。知っている。
会えた気がすることが只管嬉しく、”気のせい”だった筈の感覚が一層真実味を帯びるよう、不誠実を隠してみたり、すぐさま命日の書かれた手帳を開かず思い出を遠回りしてみたり、”居る”みたいに扱ってみる。そう扱えば扱うほど、居る気がする。誰も居ない部屋でイタコごっこに興じているだけではあるが、本当は居なくなっている人が、まだ居る瞬間を、嘘でいいから、どうにかこうにか編み出しているのだ。
ゆっくりと、落ち着いて、たくさんの、敦子と関係のないことを思い返す。会津旅行、毎年夏に届いていた福島の桃、私の暮らした街、校舎、派手な色のジャージ、校歌、部活動、県大会の成績…———。
————そして、私の少女時代の思い出を一回りして、やっと辿り着く、敦子と私が出会った日。
それから、敦子が亡くなった五月。
あの年の五月十六日は、敦子と出会って以来初めて迎える主役の居ない誕生日で、私は「敦子が居ないのに誕生日は来た…」と、窓の下の大通りを通過する車の音を聴きながら思った。
その時点で敦子が居なかったということは、やはり前日の、五月十五日には亡くなっていたのか。それとも五月十六日の誕生日当日に訃報を聞いたその場だったのか。どうしてもそこだけが思い出せない。両方だった気さえしてしまう。
大通りを走り抜ける車の音を聴きながら感傷に浸った記憶は確かだ。敦子の最後の経験は、交通事故だった。交差点へ勢いよく進入してきた車の側面に、敦子はスクーターごと真っ直ぐ突っ込んだ。即死する寸前の敦子が最期に自分の意思で見たものは、おそらく正面の青信号。その直後、意思と反して見た景色を最後に、敦子は即死んだ。
敦子の事故死を境に車の音を真面目に聴くようになった私が、初めて意識的に耳を傾けたのは、敦子の誕生日に思いを巡らせた窓辺の下の大通りだ。ゴー…ゴー…と、そのほとんどが無感情に通り過ぎていく。たまに主張の強いエンジンをふかす音も聞こえてくるが、大抵の車は同じような音で走り去っていく。罪のない車の音も仇の音も私にとっては変わりなかった。
敦子と何の縁もないくせに、タイヤや車体が、敦子の血の一滴でも持って行ってしまったのかも知れないことが恨めしかった。ただのアスファルトのくせに、敦子の最期の傍にいられた道路が羨ましかった。車と道路の擦れる音を聞きながら、私は臨終の現場を幾度も想像した。ただ「敦子が可哀想」としか言い表せない光景が浮かんでは消えた。
仮通夜や通夜に関する案内はなく、葬儀でも告別式でもない「お別れ会」と称された集まりの日時を敦子の母親から告げられたのは、それから一週間か十日ほど経ってのことだった。火葬と葬儀は両親のみで済ませたらしい。
聞く限り、敦子の遺体を見た友人は一人も居なかった。敦子の両親の口から敦子の死に顔についてを語られることもなかったし、私も尋ねることはしなかった。きっと、敦子は損傷が激しかったのだろう。少し想像して、少しでやめた。
* * * *
敦子は、私の、中学校の同級生の、お姉ちゃん、の、友達、だった。
駅前の商店街に流れる曲が、オルゴールに編曲し直された一昔前のJ-POPから、陽気なジングルベルに変わる頃。寒さに耐えかねて立ち寄ったハンバーガーショップで、私は同級生の本田という女子に鉢合わせた。私は書道教室の帰り道。本田も英語だったか何か、塾の帰りだった。
間もなく仕事が終わる親の車を待ちながら、高校に通う姉と、いつもこの店で合流するのだと言う。どれくらい経っただろう、本田が片想いをしている剣道部の高橋だとか何とかいう男子の外見及び内面的に優れた点などを聞かされているうちに、店のドアが開いて、その瞬間、甲高い声がワッと入ってきた。
暗めの緑がかったブレザーに、灰色のチェックスカート。高校生らしき五人組だ。一人がこちらに気づくと、その後ろに四人が続いた。先頭の学生が本田の姉だろう。
本田は姉たちの集団に向かって軽く手を振ると、向き直って、教室では聞いたこともないほど得意げな口振りになった。高校生がついていると調子に乗るタイプだという意外な一面を知った。
私たちと同じ席についた高校生たちは凡そ揃いのデザインの制服を着ているが、襟元だけ、紺のネクタイを締めた生徒と、赤地に黄色い線の走ったリボンをつけた生徒とが居た。ネクタイが音楽科、リボンが普通科だそうだ。
ネクタイを締めているのは本田の姉ともう一人だけで、残りの三人は普通科のリボンだった。そう言えば本田も吹奏楽部だ。姉もきっと何か専門的な楽器をやるのだろう。
本田は慣れているようで高校生全員と話していたが、見知らぬ五人に囲まれた私は、特に共通した話題もなく、居心地の悪さを感じていた。高校生たちはこの週末、本田の家に泊まって期末試験の勉強をするらしい。全員よく喋るので、どうせ捗らないくせに、と思った。
面倒になってきた私は立ち上がって、「そろそろ帰ります」と、誰の目を見るでもなく、いい加減に微笑みながら言った。マフラーを巻き直して、カバンを肩にかけ、足元に置いていた書道バッグを抱えた時、本田の姉ではないほうの、ネクタイを結んだ、もう一人が私の顔を見て口を開いた。
「習字やってる!?」
プラスチックで出来た名札には"錦織"と刻まれていた。名札をつけないという選択は、私たち世代なりの教師や校則へのささやかな反抗であったし、出来る範囲で出来たお洒落だった筈で、他の誰一人名札をつけていない中、胸に真っ直ぐ名札をつけた、この、錦織先輩という人はきっととても真面目な人なのだろう。そう思った。
「習字やってるの?うまい!?」
返事にまごついていると錦織先輩は再び私に尋ねた。
「うまくはない…ですが、下手…でもないです…」
「そうなんだ。うますぎない人がいいんだけど、あのさ、冬休みの書き初め、代わりにやってもらえないかな!?今度なんかおごるからさ!」
何故私は、名札ごときでこの人を真面目だと思ってしまったのだろうか。人は名札によらないものであり、錦織先輩はどちらかと言うと不真面目寄りの生徒だった。こんな人だ、お泊まり会をしながらの試験勉強など、一切捗らないに違いない。
私の意向などお構いなしに、書いてあげなよ!と、本田が煽る。
店の外に出ると、師走の風が益々冷たくなっていた。少しぐらい寒くとも油を売らずにさっさと帰れば、こんなに凍みた時間にもならなかったし、書き初めの代筆など押し付けられなかったのだ。
振り返ると、店のガラス窓越しに錦織先輩と目が合った。私に気づくと、掌と掌を合わせてペコペコと会釈をし始めた。私が軽く会釈を返すと、微笑んで小さく手を振った。一瞬、手を振り返そうかと思ったが、相手は高校生だったので謹んで、一度、少し深めにお辞儀をしてから、家路に就いた。
街灯の下を歩きながら渡されたメモを広げてみる。ハンバーガーショップの紙ナプキンに書かれているのは、書き初めの代筆を依頼してきた高校生の携帯アドレスと、名前。
錦織先輩の下の名前は、城郭(ジョウカク)の郭(カク)に、子供の子、と書いて、"郭子"。カクコだった。
城の子かあ…。カクコ先輩。錦織郭子。へえ、これはまた、随分と貫禄のある字面の人だなあ。———————————————と、すっかり思い込んだ私は、歩きながら携帯電話のアドレス帳に情報を打ち込んだ。
ニ、シ、キ、オ、リ。カ、ク、コ。
打ち込んだついでに、挨拶がてらメールを一通送った。名前と簡単な自己紹介、それから、書き初めのお手本が学校から配られたらまた連絡をください、ということ。
一分もしないうちに返信が来た。
《ありがとう!これからもよろしく!》
****
敦子 (二)
週が明けた月曜の五時間目、音楽の授業を受けながら、週末に会った高校生たちのことを思い出していた。
音楽科の高校というのは、一体どうした組織なのだろう。一人一人に専門の楽器でもあるのだろうか。それとも、徹底して譜面の読み書きや採譜のコツでも仕込まれるのだろうか。歌を歌うのだろうか、それとも、歌わない生徒もいるのだろうか。
音楽科に通う姉を持つ本田に尋ねれば済むのだが、ハンバーガーショップでの態度を見るからに、この女はとにかく、年上の学生を絡めると偉そうなのだ。一時間聞こうものなら、内の五分は音楽科の説明だろうが、残りの五十五分は高校生との親しい関係についての演説になろう。聞く前から予め辟易した私は、二度と本田の前で高校生たちの話はすまい、と誓った。
音楽室の壁には歴代の吹奏楽部員の集合写真が掛けられている。一番新しい写真に目をやると、後列向かって右手に、本田が撥(ばち)を構えて、真剣な面持ちで写っていた。譜面台でもなければ客席でもなく、指揮者を一途に見つめている。この本田は、かっこいい。高校生の前で調子づく姿とは別人のようで、人というのは、つくづく、状況を変えれば、佇まいも変わるのだ、と思った。
ということは、だ。
私に書き初めの代筆を依頼した、あの錦織先輩という図々しい人も、きっと、ピアノなのか、クラリネットなのか、バイオリンなのか知らないが、得意な楽器を構えた時は、きっと別人のような、精悍な佇まいをするに違いない。涼しい顔をして複雑な楽譜にちらりと目をやっては、五線譜に記された作曲家の指示と意志を丁寧に汲み取り、芳醇な音色を奏でるのだ。
ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、という七種類のカタカナ—————それだけでは済まない、シャープやフラットの係る音には丸印を、いちいち、譜面に住まうオタマジャクシ一匹ずつに書き込まねばピアノの前で両手を動かせない私にしてみれば、錦織先輩は、ある側面において、きっと、素晴らしい人なのだ。
宿題の代行は約束してしまったのだし、この際、音楽に関しては尊敬できる、という点にだけ注目してやり過ごすことにしよう。図太い人には変わりないが、ある側面ではきっと、おそろしく繊細なのだ。
このところ、私たちの受ける音楽の授業は、ほぼ一年間歌い慣れた合唱曲を繰り返すばかりの、少々退屈なものだった。
文化祭の会期中に開催される夏の合唱コンクールで歌った各クラスの課題曲を、年度末に在校記念のCDに収録するのだ。そのため、春先の曲目決定から夏の合唱コンクールにかけて歌い込んだ合唱曲を、二学期の終盤から再び、今度はレコーディングのために練習せねばならなかった。
合間合間に、器楽や音楽史の授業もあるにはあったが、夏の合唱コンクールと年度末のレコーディングに挟まれているせいで、課題曲が私たちの手や耳を離れることはなく、通年、合唱曲に偏った授業を受けている印象があった。
在校記念のCDは学年ごとに製作され、一枚あたり三千円ほどで希望者に販売される。通常、生徒や保護者は自分や我が子が在籍している学年のCDを一枚だけ購入するのだが、片思いの相手が他学年にいる生徒に限っては、"好きな人のグッズ"と して、身内のない学年のCDも注文する傾向にあって、こんなところから毎年、誰が誰を好きらしいという噂が流出するのだった。
全校で歌う『校歌』と『大地讃頌』だけは、どの学年のCDにも収録されるので、この二曲さえあれば、好きな人の声と自分の声とが混じった素晴らしいボーナストラックの役割を果たすではないかとも思うのだが、どうもこれでは物足りないらしく、少なくない数の女子と、幾人かの男子は、余計なCDを注文していた。親に、どうして他の学年のCDを買うのかを問い詰められて不貞腐れているクラスメイトもいた。
私はといえば合唱曲が大好きだという、色恋と無縁の理由で全学年分を一枚ずつ購入するのが常だったので、他の学年に想い人のある目敏い学友たちから、MDやカセットテープやCD-Rにダビングさせて欲しいという申し出を受けていた。
頼まれる都度、何年何組の曲をダビングすればいいのかを尋ねる。彼女たちは、うっかり特定のクラスを答える。
バレたくなければ、単純に、学年分、全クラスをダビングしてくれ、と言えばいいのだ。
そうして私は、誰にリークするでもないが、どの生徒がどの生徒に想いを寄せているのか目星をつけては、人知れず情報通の気分を味わい、ダビング依頼を愉しんでいた。
ハンバーガーショップで散々聞かされた、剣道部の何とかいう一学年下の男子に片思いしている本田も、余計なCDを買うか、私にダビングを頼むか、どちらかするのだろう。
* * * *
今年、春からずっと、三部合唱の『親知らず子知らず』を歌い続けている私のクラスは、この日も音楽室のある北側校舎に痛切な歌詞を響かせていた。
給食を詰め込んだ午後の眠気に抗いながら、今日何度目かの、寂しげなピアノの前奏を耳で追う。伴奏は本田だった。
吹奏楽でもピアノでも、コンクールや演奏会に臨み続けてきた本田にしてみれば、専門性も低ければ意欲も低い中学生のクラス合唱は退屈なのかもしれない。しっかりと暗譜しているらしく、譜面に目を遣ることは全くなかったが、だからと言って、吹奏楽部の写真に収まった本田のように、指揮者を一途に見つめるわけでもなかった。譜面にも、指揮者にも、手許にさえも、一瞥もやらず、気怠そうな顔で虚空に視線を留まらせたきり、手癖でピアノを弾く姿は、同じクラスにいる男子バスケットボール部のエースが体育の授業で行われた試合中に見せる、露骨な手加減とよく似ていた。
どれほど手を抜こうが、クラス中の誰よりも洗練されているところまで。
口を大きく開き、歌声を合唱に溶かす行為によって、私は授業に集中しているふりをしながら、本田の顔を眺めた。
ずっと、面倒臭そうな、飽きたような表情をしている。その姿は、本命の演奏会ではないから格好つけているだけのようにも思えたし、最悪の場合は手だけ動けば片手間に奏で切れるのだという徹底した反復練習の証明にも思えた。
小さな顔の輪郭に沿って横に流した長めの前髪が、本田の視界を遮っているような気がしたが、たとえ、今突然に失明したとしても、最後まで弾き切れるのだろう。本田に対する敬意が、癪に触りながらも、私の頭に、意識に広がっていく。
なんにしたって、本田の弾くピアノの音色は、よかった。
混声三部のうち、ソプラノ・パートとアルト・パートの、ちょうど境目の最前列に、私は置かれた。最前列に置かれた理由は歌の良し悪しではなく、単に身長の問題である。パートの境目に置かれた理由は、音感の問題で、独唱テストでほかの音につられなかった生徒たちが、各パートで隣り合うことになっていた。
地の声は、女か男かほとんど区別がつかないほど重く低く、所属の演劇部では小学生時代から五年間、男役以外ついたことがない。バレンタインになれば、男子生徒のような扱いで他校からもチョコレートが届いたし、女の子から、彼氏になってくださいと告白されるようなことも、たびたびあった。
そんな私が、いかにも女、といった声の要る音域に宛てがわれている事実をふと客観すると、我ながら小恥ずかしさがあるのだが、とにかく、どういうわけか、合唱に向く歌い方をした時だけは、私の声は、容易く、高く伸び、いつもソプラノ・パートに割り振られた。
この配置が決まった日、私の歌声を初めて真横で聞いた並びの女子が、私に“オペラ”というあだ名をつけたほどだ。
尤も、雑談に気づいた音楽教師による、
「オペラはこの程度の歌声と知識では務まらないの!」
という、業界ベースの手厳しい批評によって、新しいあだ名と一介の中学生である私の歌声はコテンパンに評され、“オペラと呼ばれた私”の存命時間は、僅か二分ほどであったが。
今年の春先、私たちのクラスの課題曲となった『親知らず子知らず』の譜面を配りながら、この教師が展開した歌詞の解説は、親不知子不知(おやしらずこしらず)の海岸で命を落とした旅人が聞けば卒倒して、改めて死に直すほどの代物だった。
「昔はね、道路がないじゃない。断崖のところをね、旅人は歩いて通るのよ。みんな日本海に海水浴行ったことあるでしょう?新潟行ったことある人?あ、居るわね。あんまり居ないか。思ったほど居ないわね。日本海は海が荒れるのよザブーンザブーンって。すごいのよ、先生も見たことあるけど、すごいのよ。それで、ワッと、波が来て、旅の途中のお母さんと子供を連れてっちゃうのよね。その悲しみ、親子の絆と悲しみを歌った歌なの。わかる?歌詞よーく読んで、気持ち込めてね。わかった?」
———————わからない。
音楽も、合唱も、好きだ。でも、頼んでもいないオペラへの適性審査と、驚くべき雑な楽曲解説を機に、私はこの音楽教師に対する信を失い、授業が些か億劫になってしまった。もっと興味を持ちたくなるような教え方があったって、いいではないか。
母を呼ぶ子と、子を呼ぶ母。二人の叫びや啜り泣きが聞こえぬか————という、『親知らず子知らず』の歌詞は、おそらく日本でもっとも親不知子不知で起きた悲劇の歴史を多くの人に伝えたことだろう。それをどうして、もう少しでも事の重み通りに伝えようと努めないのか。歌詞の読解も、音楽ではないのか。 私はこの授業内容がどうしても不服だった。意味も知らずに歌う歌に、なんの力があろうか。
舞台となった天下の剣“親不知子不知”というのは、今でこそ鉄道も北陸自動車道も開通して、インターチェンジまで備える拓けた陸路だが、それ自体は飛騨山脈の北端が日本海の放つ荒波によって侵食されて形成された断崖絶壁であるそうだ。
明治十六年に崖の上が掘削されて国道八号が開通するのだが、それまでの親不知子不知は、通行する旅人の命を奪う北陸道の最大難所として君臨していた。
絶壁と聞けば、崖下に落ちる危険性を想像してしまったのだが、ここは、どうもそういうことではないらしい。かつての旅人が通った北陸道は、親不知子不知の崖の上を通っているのではなく、崖の足元、を通っていた。併せて分かったことは、北陸道が通っていたと言っても、道らしき道が開通していたわけではないということだ。
道なきところを通った人がいた。通れた人の居た場所を道と呼んだ。それだけだ。
親不知子不知に限って言えば、“道なき道”が譬え話ではなく、ひたすら字の如く、土地の説明なのである。
潮が引けば旅路になるが、満ちてしまえば陸地であることさえ辞めてしまう。ひとたび荒れれば海岸を越える高波が絶壁に打ち付けてくるし、波に越されているその間、海岸は実質の海底となる。建前では“陸路”として知られながらも、その実は、殆ど気まぐれな日本海の一部であった。
狭い陸地に立った旅人は片手を海に、片手を崖に挟まれて北陸道を進む。泳ぎきれない水と登り切れない山に挟まれているため、波が打ち付ければ逃げ場などほとんどなかった。
絶壁のところどころに天然の岩の窪みがあり、これらは西から順に、“小穴” “大穴” “小懐” “大懐” と呼ばれ、一応は旅人の避難所になっていたそうだが、そうは言っても全長にして十五キロほどの道程である。スニーカーを履いて舗装道路を踏破したとして四時間や五時間の距離を、しかも、長旅の途中で迎える、冬の大シケの波打ち際を。手ぶらではないし、当然、悪路から受ける衝撃の吸収に長けた履きものもない。登山靴を履いてさえ苦になる足許の岩や石くれを越え、負っている荷はリュックサックやカート付きのスーツケースではない。満足な防寒着もないのだから、疲弊も甚だしいことだ。大昔の装備では、一定した速度で駆け抜けられるわけがないし、高波に合わせて都合よく岩の窪みに逃げ込める自由など、旅人には許されていないのだ。
避難場所として機能した“大懐”から“大穴”までの道程は凡そ五キロほどだが、避難場所があるからといって比較的安全な場所ではないらしい。 頑固な岩肌にどうしたら窪みなどできようか、と、考えてみる。避難できるほど大きく岩に窪みができる区間というのは、要するに岩肌を穿つほどに、波が当たる場所なのではないか。いずれにせよ避難場所の点在する区間は、足下千丈の道中でも、特に、わざわざ、“長走り”と呼び直されて括られる難所であり、字のごとく、長く走ってでも突破せねばならない危険な区間らしかった。
天嶮・親不知子不知の波打ち際を通る親は、子を省みることができず、子は親を追うことができず、懐に抱いた子を波に攫われる母もあったという。
クラスの課題曲となった『親知らず子知らず』の歌詞には二つの命が親不知子不知によって奪われたことが明記されているが、ここに登場する母子もまた、道なき道を突き進み、日本海の藻屑と消えた犠牲者であった。病に倒れた夫の元へ急ぐ旅路の途中で怒涛に襲われた母子は、二人とも帰らぬ人となってしまう。
絶望しながら生身を波に弄ばれたことだろう。おとなしく沈ませてもらえるのではない。意図せず顔面にシャワーがかかったくらいでも、それなりに呼吸や視界が不自由になる人間の体で、大波に攫われて、押されたり引かれたり、上も下も右も左も後ろも前も区別がつかなくなり、ついと水面の方角を見失い、もがけばもがくほど波間に深入りしてしまう。息もできず、髪は顔にまとわりつき、衣服は重く張り付くか、剥がされるか。湿った荷物が泳ぎを邪魔したかもしれない。
意識を失うまでの時間、恐怖に苛まれながら、共に波に攫われた赤子に詫び、病に倒れた夫を案じ、この道に踏み込んだことを強烈に後悔しながら、やがて。
十分前は陸にいたのに。三十分前は生きていたのに。二時間前は親不知子不知の海岸に入っていなかったのに。すべてを水だけに取り囲まれて、口も、鼻腔も、耳腔も、喉も、肺も、塩辛い海水に浸されて、二度と生きて乾くことはないのだ。
海よ、なんたる悲痛の根源だろうと思ったが、そもそも古来より魚介や海獣によって、絶命にも、生命にも、慣れてしまった海は、こうした、海にとっての細かな絶命や生命を、一々気にしないのかも知れない。死別ごと呑み込んで返さない海を思っては、地球の仕組みの底のなさに脅される。
人生などはきっと、人間の思い通りにはコントロールできないのだ。
私は、親不知子不知どころか、この海岸が位置する糸魚川市を訪れたこともなかったが、柏崎、鯨波、直江津、谷浜、過去に辿った新潟の日本海沿岸を思い出せば、日本海を覆う灰色の空と、哀しみの茫々が胸中に満ちるようだった…。
————————ちなみに私と日本海の関係だが、小学生時代、晴天の予報が出た日を狙って、新潟に縁のある級友や従姉たちに連れられて炎天下の海水浴に行ったのみであり、日本海の荒天などただの一度も見たことがないし、そもそも真夏しか訪ねたことがないため、冬の大シケとも無縁だ。哀しみの色をした空も、北冥の怒涛も、なんと、『親知らず子知らず』の譜面を手にして以降の妄想である!
新潟の思い出といえば、小さなバケツにヤドカリを捕獲したり、浜茶屋で、半切りのハムと味付け海苔、ブワブワにふやけたナルトと、客が使い終えた割り箸でも煮込んだのかと思うほど硬派なメンマがチャッチャと散らされたノビたラーメン、あれは八百円ほどしたと思う。それから、シロップの少ないかき氷を食べたり、スクール水着の、足の付け根の間にある布の折り返しに目一杯溜まってしまう浜辺の砂に苦心したりしていただけの、微笑ましい真夏の海水浴紀行のみである。冬場の日本海沿岸と言えば、寒そうだし、雪も降るだろうから。寒がりで、乗り物酔いが酷くて、寿司も刺身も愛せない私にしてみれば、わざわざ出向く魅力のない土地だった。
それでも軽やかな思い出の景色より、歌から想起した暗いイメージを、好んで、優先的に思い浮かべるようになったのは、きっと、そちらのほうが深くて重くて、人生のなんたるかを知っていそうに見えるからだと思う。大人だと思われたかったし、子供扱いをされたくなかった。遊ぶことよりも思慮を好んでいるように思われたかった。
新潟県内各地に点在した海水浴の記憶は私の自意識によって片隅に追いやられ、この歌と出会って以降、私が思い浮かべる日本海のイメージは、見たこともない親不知子不知の冬になった。白い泡と波を蓄えた、鉛か鼠のような色をした重量のある海。一波、一波が、しつこく、重たく、巌壁に衝突する。灰色の空。雪なのか雨なのかで霞む沖、その先に有る虚無と、水面下に眠る命の気配。苔生した波除観音が岩肌から、黙って、幾多の絶命を、押し黙って見つめている。
重く、暗く、深い歴史に思いをうずめることこそ、大人の嗜みに思えたし、荒れた日本海を想うことは、私の背伸びそのものだった。
天嶮の断崖を舞台とした譜面には、病床の夫の元へ急ぐ悲しき母子を怒涛が攫った運命の理不尽を問い詰める歌詞が、叙事とも叙情ともつかぬ形で綴られている。
悲しみに直面した人に更なる悲しみで追い打ちをかけるのが人生か。——————————と。
クラスを見回しても、目の届く限りでは、心底からこの歌詞を読解した様子のある同級生はなかったし、私もまた、怒濤とか悲劇とか運命の神とか、劇的な言葉を咀嚼した気になって、消化不良に気づかぬまま消費するだけだった。それでも、悲しみの追い打ちを人生と呼ぶのか。というフレーズを、中学生にして使いこなせた気になれるのは、この歌の良さだった。
実際のところ、私たちの身の丈どおりの合唱関連の話題といえば、寒ブリの名産地である富山県の氷見では海中でブリが押し合いへし合い泳いでおり、また、真冬の氷見は大変しぐれて降雪し、暗い空には雷も轟くということをリズミカルに歌い上げる『寒ブリのうた』が、自分たちのクラスに回って来なかったことと、野生の馬が走ると筋肉の躍動がすごい!という現象を足速に歌う『野生の馬』という曲が、やはり自分たちのクラスに回って来なかった幸運について。それから、所縁のない土地に住まう野生の馬や寒ブリの生態について歌った声が、在校記念のCDに収録されてしまう両隣のクラスを、憐れみの言葉で笑うというのが、殆ど全てだった。
* * * *
三学期も終わりに近付いた年末の音楽室は、朝から放課後まで暖房が入って暖かい。暖房を入れるほどでもないがそれなりに肌寒い秋口よりも、よほど居心地が良く、追い打ち多き悲しき人生の歌を歌う傍から、給食の満腹感と暖房の温もりに追い打ちをかけられて、睡眠欲が、本当によく刺激される。
間も無く授業も終わろうという頃、プリーツスカートのポケットに入れた携帯電話が少し震えたのが分かったが、歌の途中だったので、気になりつつも放っておくことにした。
錦織先輩だろうか。
特に楽しみな相手でもないどころか、よく知らない人だというのに、連絡が来たかもしれないと思うと、なんとなく気になってしまう。
本当はプリーツの隙間を探って手を突っ込まなければ確認できないスカートのポケットよりも、制服の上にいつも羽織っているカーディガンのポケットへ携帯電話を入れられたらよかったのだけれども私のものは、折り畳み型が流行する前に買った細長い機種だったので、カーディガンの浅いポケットに入れるとはみ出してしまう。先生に見つかるとうるさいので、しぶしぶ、深さのあるスカートのポケットに忍ばせていた。
プリーツスカートのポケットは、ちょうど左の骨盤の脇あたりに入り口があり、スカートの内側では太腿に当たる位置にメッシュ生地のポケットが垂れ下がっていた。ひんやりとした硬い携帯電話と、それより少しだけ温もりのある生地が、左足に触れっぱなしになる。左側だけ、ほんの、ほんの少し重いスカートというのが、登校日の体感だった。
得意げにつけているストラップは、中学生や高校生が憧れたブランドのもので、どこで買ったの?と、聞かれるたびに、少し照れ臭かったので、原宿に直営店があるよ、と答えていたのだが、本当は同級生からのプレゼントだった。ある日の放課後、資格試験の勉強をしていたら、机に寄ってきて、合格祈願に、と、つけてくれた。それまでは、その子の携帯電話についていたものだ。
私がもらってしまったせいで、その子の携帯電話につけるストラップがなくなってしまったから、お礼に、休みの日に一緒に買いに行こうと誘った。あんなにいいストラップをもらってしまったのだから、私も何だってプレゼントしようと思い財布を満たして出掛けたのだが、その子が選んだのは、二千円するかしないかの、小ぢんまりしたストラップだった。本当にこれでいいのか何度も尋ねたが、これがいい、と言って譲らなかった。
ずっとつけてくれているところも、慎ましさも、可愛い人だな、もてるだろうな、と思った。こういうところから始まって、きっと、将来はとてもいい人のお嫁さんになるのだろう。
そう、慎ましいというのは、延いては、可愛いのだ。
わかりますか、先輩!書き初めの代筆を押し付けた錦織先輩の顔が浮かぶ。私がしている想像の中でも悪びれない顔をしており、どこまで図々しいのだ、と思った。私の前で可愛くある必要はないのだが、よく知らない間柄なのだから、もっと慎ましくあったっていい。
携帯に届いたメールが、誰からの何の用件であるのか、気になって仕方なかった私は、チャイムが鳴るのを待ち侘びながら、窓の外に目をやった。南校舎の建て替え工事をしている作業員の姿が見えたが、暖かい音楽室からの窓越しには、彼らの寒さを鮮明に察することはできない。
よく澄んだ真っ青な空の手前に、中庭に枯れ葉を落とし切った焦げ茶 色の木が枝を伸ばしている。
歌い終えたあとに先生が何か喋っていたが、ろくに聞かなかった。どうせ、聞いても聞かなくても大差ないことだろう。信頼していない大人の言葉というのは、試験の情報など明確な利害でもない限り、どっちみち、聞いても、聞かなくても、大差ないのだ。私に取り合う気がないのだから。
チャイムが鳴った。
起立はするが、深々とした礼はしない。首を軽く曲げるだけだ。気に食わない教師への反抗を遂行する。私の進路には錦織先輩や本田の姉のように音楽科はないから、音楽の成績ぐらい部分的にどうなろうと構わなかった。評点が下がるとしたらせいぜい “音楽に取り組む姿勢”とかいった、曖昧な箇所だろう。私の態度の改善を望むなら、先生こそ、親不知子不知に関する雑な説明をやり直すなどして、授業態度を改めるがいい。なあにが、
「ワッと波が来て連れてっちゃうのよね!」
だ。
* * * *
授業が明けて、音楽室の引き戸を開ける。鮨詰めになったきり、ビクともしない廊下満タンの冷気と、渡り廊下から吹き込んでいるらしき寒気によって、やっとさっき窓越しに見た作業員たちの寒さが、我が身のことになった。
我が身のことにはなったのだが、我が身のことになった途端、作業員のことなど忘れて、私の身に降りかかる寒さの心配で心が一杯になる。慮る器などない。窓越しの寒さは他人事であったし、我が身の寒さは、誰にも負けない世界一の寒さであった。 今、日本で最も温まるべきは私であり、私より厳しい寒さを感じている人の存在など、察知したくないのだ。
だって私が寒いのだから。
親不知子不知の海岸で波に攫われた母子の悲痛を丁寧に思い遣る日など、私には来ないのかも知れない。
寒さに気を取られた私の頭から抜け落ちてしまったのは、なにも、建て替え工事の作業員のことや、親不知で命を落とした旅人のことだけではない。音楽の授業が終わる間際に携帯電話が震えたことも、私はすっかり忘れてしまっていた。
携帯に何かしら来ていたことを思い出したのは、帰りの通学路の中腹だった。呼び水は、スーパーの前に設置された公衆電話が目に飛び込んできたことで、そうだ、と思って慌てて受信箱を開いた。
途端、携帯のバッテリーが落ちた。
思い出した、昨日の晩御飯を食べた時、充電器をダイニングのコンセントに差し込んだまま、だらしなく置いてきてしまったのだった。真冬の親不知子不知の海岸を大昔の衣類で通る人と比べたら寒さのうちに入らないのだろうが、然りとて、現代でも真冬は真冬である。嫌なのだ、寒いのは。自室のベッドで携帯をいじりながら充電がなくなりつつあることに気づきつつも、どうしても布団から出るのが億劫で、充電の残量をぼんやりと気にしつつも、そのまま眠ってしまった。
あの時、えい!と布団から飛び出て、早足でダイニングまで行って戻れば、こんなことにはならなかったのだ。その程度の手間がなんだというのだ。
ああ、いやだ。
自らの不注意によって引き起こされた不都合というのは、どうしてこうも遠慮なく、自分に対して頭にくるのだろう。自分のことだから遠慮なしに怒れるのだろうが、そうは言っても、ほかならぬ自分のことだ。自分が可愛いのであれば、もう少し、自分に対して苛立たないで欲しい。自分をもっと大切にすべきだ。甘やかして欲しい。だけれども、イライラする。
「お前さえ昨日の晩、布団から出ていれば、私は今、こんなに慌てずに済んだのだ!」
と、昨日の自分に語りかける。
それを聞いた昨日の自分が、今の私に返事を返す。
「お前が明日なんとかすればいいだろう。おやすみなさい。」
歩道のタイルに当たり散らすような靴音を立てながら、家までの残り七百メーターほどを、雑な小走りで戻った。
帰宅してすぐ、携帯電話の尻に充電器を繋ぐ。
バッテリーを落としてしまったので、すぐには点かない。三十秒…一分、二分ほど待ったろうか。やっと電源ボタンと液晶画面が反応を示し、受信箱にたどり着く。受信箱の一番上に表示されたのは、ニシキオリカクコという名前だった。やっぱり、錦織先輩だ。
《栄第一で合ってるよね?帰りに寄ってもいいかな?近くに用事があるから放課後行ってみよっかなー!?》
私の学校まで、来るとも来ないともつかないメールを受信したのは、五時間目の終わりだ。もう、優に一時間半は経っている。
私は益々、バッテリーを切らした自分を呪った。それ以前に、授業が明けてすぐに携帯を確認しなかったことも。あの段階だったら今より少し充電があったのだから、メールを一瞬読んで、充電が切れそうなことと、学校で待つ旨を伝えられたかもしれないのに。
返事をしていないのだから来ていないかもしれないし、近くに用事があると言うくらいだから、一応学校に寄ってみるのかもしれない。これから寄るところかもしれないし、もう居るのかもしれない。
錦織先輩の通う高校から私の通う中学までは、電車で五駅か六駅だ。途中一回の乗り換えを挟む。まだ十六時半を回っていないから、もしかするとこれから向かってくるところかもしれない。
私は慌てて、玄関に脱ぎ捨てたローファーに足を捻じ込んだ。さっきまで履いていたので、まだ生暖かい。玄関を飛び出して、千鳥掛けの飛び石を一つ飛ばしで駆ける。真っ直ぐ敷けばいいものを、一体なぜこんなにジグザグと敷くのか。大昔の日本人のカリスマ庭デザイナーが編み出した風情か、侘び寂びか。知ったことか、不便だ。敷地全面にコンクリートを打って欲しい。
財布を部屋に置き忘れたことに気が付いたのは、ちょうど木戸に手を掛けたところだった。通り抜けるのに時間が掛かるからと、石の並べ方に文句までつけておいて、忘れ物をしたなどと、なんとなくバツが悪いので復路は飛び石を踏まずに、花のない花壇を強めに踏み荒らしつつ斜めに突っ切った。私は草花が嫌いだ。そして草花よりもっと嫌いなのは、草花を嫌う自由を与えてくれない人々だ。芝生を挟んだ先にある玉柘植の生垣も勢い良く飛び越えた。邪魔な草だ。チェーンソーかビーバーか何かで刈り取ってしまいたいが、植物は嫌いだから触りたくはないのだ。どうしたものか。刈り取ろうとして揺すろうものなら、こいつらは断末魔のように、青々と、みどりの匂いを香らせるのだ。
どこに引っ越そうとも自然豊かな庭を整えてしまう家人たちが、私はどうにも疎ましかった。家人たちも、私の両親も、みな、植物は人に嫌われないものだと思い込んでいるのだ。
その偏見の証として、私の戸籍謄本には“桜子”の名が記されている。私の、社会生活上ではなく、法律上の名だ。
春先に咲き、そこらじゅうに飛散しては私を苛む、散らかった花の名である。短期的な視点で見れば多くの人を喜ばせている花であろうが、見頃は短く、すぐに散る。通年需要があるわけでもなければ、花弁の命が長いわけでもなかった。
我が名は、一瞬の見頃と、小まめな絶命が、定期的なサイクルで訪れる花の子、であるぞ。
たまったものではない。幾度も散らされる名を負わされて、一体どんな苦労を重ねて生きてゆけというのだ。何度も、何度も、何年も、十何年も、何十年も、風の吹きたいまま、雨粒が落ちたいまま、追い打ちのように散らされた挙句、次の季節までには、見栄えがするほどまでに再起せねばならぬ花の名だ。咲かぬ間も、見向きもされぬ幹を守って、一体何度の厳冬を越さねばならぬのか。
忘れ物を取りに屋内に戻ると、テーブルの上には、財布どころか、肝心の携帯電話まで転がっていた。錦織先輩との唯一の連絡手段まで置いて出たようだ。私は、もしかすると、相当な馬鹿なのかも知れなかった。
問題はそれだけではない。まず原点に立ち返るべきなのだ。バッテリーが落ちたばかりの携帯電話を持って出かけたとして、私はどうするつもりだったのだ。また志半ばで切らして、戻ってくるつもりか。まずはバッテリーに電気を蓄えないことには、錦織先輩と合流できないのだ。
最低限のメールを送信して、三十分充電することにした。三十分以内にメールの返信があれば、電池の残量に合わせて綿密に待ち合わせ場所を伝えればいいし、来なければ、念のため、その段階で家を出ればいい。
《すみません!しばらくメールに気がつきませんでした。栄一中で合ってます!何時頃にこのあたりに来るとか、もしわかれば教えていただきたいです!》
三十分しても返信はなかったが、電車に乗っているとか、何かのはずみで気づかないとか、もしかすると向こうも充電が切れているとか、何があるかもわからないから、結局、学校まで行ってみることにした。既に学校に居て、もしかしたら、顔見知りの本田と合流して、喋りながら私を待っている可能性だってある。
ローファーでは取り戻せないと踏んで、体育祭でもない限り見向きもしない無骨なスニーカーに履き替える。制服に革靴以外は似合わないのだから、とても嫌だったが、背に腹は変えられないし、ローファーは運動靴ではない。
家から曲がり角を一つ過ぎたところに、駅に続く少し大きめの交差点がある。その交差点を過ぎた先には、三叉路がある。そのまた少し先にある小さな橋の袂には、横断歩道があって、橋を渡った先にもまた一つ、横断歩道がある。学校まで信号はこの四箇所だ。どこかしかで赤信号に引っかかるに違いないから、信号に引っかかるたびにメールを送れば、立ち止まる時間を最小限に留めながらも適度な休憩を取れ、なおかつ、学校まで走り続けることができるだろう。
* * * *
瑣末な不自由ではあるのだが、私は完全に健康というわけではない。頑丈ではあるが病弱で、死にはしないが元気もない。入院も多いし、細かな不調は日常茶飯事だった。命に別条はないが日常に支障があった。
人一倍走るのが遅いところへもってきて、少しばかり不良を持った体は、こうした時、やたらと不便に思える。余計なオプション機能をつけてくれたものである。或いは、電源は入るが真面目に動かそうとすれば動作が鈍くなる、動作確認済みですがジャンク品であることをご了承ください、と但し書きされた訳ありパソコンのような、少々、分の悪い身体を掴まされたものである。
一応はきちんと動くので文句は言いにくいのだが、急に走ると、さっきまでトク、トク、トク、と、丁寧に一定におとなしくしていた脈がヤケを起こしたように雑になり、ドッ、ドトトッ、…トク、…トクトクッ、……バクッ、と、投げやりな勤務態度に変わる。ハードワークに対する意欲のない循環器だ。
呼吸器は、上半身の芯がキュッと詰まったようになって、痛く締め付けられる。初めて発作が起きた時は、トイレットペーパーを両手で力強く握りしめて、芯の空洞が潰れて、どんどん小さくなっていくような、それとも、どんどん細くなっていくシュノーケルを咥えて、SOSを伝える声も出ないまま水中にとどまるような、イメージだった。
長めの距離を走る時は、様子を見ながら小走りから始めるか、どうしても疾走するのであれば、幼稚園児の運動会のかけっこのような、ほんの短距離にするしかなかった。
小走りで最初の交差点に差し掛かると、ちょうど赤信号になったところだった。 立ち止まったついでに、もう一通メールを送る。
《度々すみません、今どちらですか?もう学校ですか?》
送信完了を確認して、信号が青に変わるのと同時に小走りを始め、少しずつ速度を上げていく。
そういえば、錦織先輩はどうして私の学校を知っているのだろう。伝えた覚えはなかったが、週末、上着の間からセーラー服の襟元でも見えたのだろうか。リボンを差し込む穴に校章が入っている。或いは、通学カバンに縫い付けられた校章を見て気づいたのかもしれない。もしくは、本田から、同級生だと聞いたのだろうか。
駆け足の振動で受信や着信の挙動を逃がしてしまわないように、携帯電話を握りしめたまま走った。間も無く三叉路が見えてくる。二つ目の信号に差し掛かろうとしているが、今のところ携帯電話に動きはない。
二つ目の信号も赤信号だったが、返信はまだこないので、息を整えながら青になるのを待った。
再び小走りで駆け出して、少しずつペースを上げる。三つ目の信号と横断歩道が遠目に見える。あの横断歩道を渡ると、住宅街と住宅街の合間を流れる川に架かる橋だ。
歩行者用の青信号が点滅している。幾人かの人が小走りで渡り切ったところで赤に変わった。間も無く車道の信号も、黄色、赤、と、完全に横断を拒絶した。
一歩一歩近づくごとに信号機は大きくなる。できれば休みたいので、このまま赤信号であってほしかったが、私が横断歩道に辿り着いた瞬間、狙ったように青に変わった。正当性のある休憩のタイミングを逃してしまったような気持ちになる。
あーあ、と思った。
いいや、休もう。
携帯電話がうんともすんとも言わないのをいいことに、走ることを放棄した足が、タタタ、タタ、タ、タ、…タ、…タ、…タ、…タン、…タン、と、ばらついた靴音を立てながら、横断歩道の中程で速度を落とす。いよいよ小走りが歩行に変わる境の一歩をタン!と踏んだあたりで、私の所在も、横断歩道から橋の上に変わった。
目立たなくなった靴音のかわりに、ヒュー、シャー…、ヒュー、シャー…、という乾いた呼吸音が耳に届く。こういうときは、大きな深呼吸をするように長く深く強く、胸やお腹を膨らませるようにして息を吸うと、平常時に浅めの呼吸をしたぐらいの量を吸うことができる。
息を吸う途中で、喉の奥が、キュウッ、と音を立てる。冬のツンと冷たい空気が細い芯をくぐって肺に辿り着く。息が申し訳程度に白くなったが、呼気が足りていないのか、すぐ、外の空気に掻き消されてしまった。
それでも、息はしている。息を、している。
発作を起こしたとき、発作を抑える吸入器を咥えるとき、痛む胸元や喉元を抑えながら思うのだ。狭く詰まったような気道に意識を向けながら思うのだ。 ああ、私は今、とても、息をしているのだ、と。
死なないために、息を、吸ったり吐いたりしているのだ、ちゃんと。生きる仕組みが作動している。生命体としてすべきことを全うしている。息を吸って、息を吐いて、呼吸を成立させている。
私は、明日も生きたいほど、今日を愛おしむほど、昨日を懐かしむほど、希望を人生に抱いたことは一度としてない。きっと、これからもそうだろう。誰が何を楽しみに生きているかも知らないし、長く生きたところで何の喜びがあるかも想像できない。
中学を無事に卒業できたって、高校に行ったって、大学に行ったって、大学院に行ったって、就職したって、憂さの晴れた人生がどこかから急に始まるとは思えない。結婚はしない。家庭もいらない。じゃあ一体私は何のために大人に向かっているのか、まったく見えてこなかった。
だからと言って、死の恐怖と絶命の苦しみを受け止めてまで、すぐさま死にたいほど、私は恐怖も苦しみも歓迎できなかった。毎日をただ生きていることを重荷に感じる脆弱な心を持った私ごときが、自ら死ぬなどという更なる苦痛を乗り越えられるわけがないだろう。眠ったように息を引き取れるのであれば都合よく死んでしまいたいものであるが、人体はそれほど都合よく絶命できるようにも思えないので、踏ん切りがつくまでは、淡々と日々を嗜んでゆくのだ。
早く、成人は自らの意思により健康状態に拘らず安楽死が可能、といった法律が制定されるといい。そうしたら大人になるまで頑張る目標ができるのに。
橋の欄干に背中を預けて、息を整えながら、街を見回す。川の流れる音と車の流れる音が、雑多な街の生活音として、混じったまま耳に入る。
私の暮らす街の音だ。
左手に広がる住宅地の屋根が小さくなった向こうに、マンション群が見えた。ベッドタウンとして開発が進んだ街には、駅を囲むように幾つかの団地ができた。この地域にしては高層のマンションが、何本も、何本も、林のように建っている。
一棟に五十戸以上の入居があるマンションが数棟まとまっているのだから、その中に暮らす児童生徒の数はなかなかのもので、多くの友人たちは住まいを説明するために住所や近所の目印を利用せず、マンション群の略称と棟の区分、それから階層を口述すれば済んでいた。
低層階の住居にしか暮らしたことのない私は、高層から街を眺望できる上、同じ棟内、同じ敷地内に学友が集う暮らしに憧れていた。
年賀状はエントランスまで降りて直接郵便受けに入れておくのが普通なのだそうだ。元旦まで開けないでね、と書いた封筒に年賀状を入れて年末のうちに投函しておいたりするらしい。
それだけではない、年賀状を郵便受けに投函しに行こうと乗ったエレベーターで同じ目的の友人と鉢合わせ、エレベーター内で大晦日の夕方のうちに年賀状交換を済ませてしまったとか、巨大団地ならではの偶発イベントもあるらしい。
もう年の瀬だ。あのマンション群の中で、間も無くそんなことが起きるのだろう。まるで郵便配達員のように、巨大団地のエントランスで郵便受けに年賀状を投函する友人たちの姿を思い浮かべる。
体の向きを変えて、右半身で欄干に凭れる。だんだんと整ってきた呼吸が気持ちよい。酸素がある。呼吸の大きさと、入ってくる空気の量が、少しずつ噛み合うようになってくる。
“体を思う心”は、いつでも死ぬことを嫌がっている。
“人生を思う心”は、いつでも生きる上での苦痛を拒んでいる。
人生への不服と、体の不調は、根元が違うのだ。
日々に嬉しさなどなくとも、呼吸と脈拍が整うことは、人生と同じ重さをした、尊い安心であった。もちろん、日々に体の安心を見つけたからといって、嬉しい人生が起きるわけでもない。どちらか欠けたら、苦しいのだ。
日の入りを迎えた暗い空と交代に、街は煌めく時間帯を迎えた。逢魔が時の表情を見せているのは橋の陰になっている水面の一部分ぐらいのもので、橋梁のライトアップを受けた都市河川も、あのマンション群も、駅も、道路沿いのコンビニも、街灯を備えた歩道も、電話ボックスも、ガソリンスタンドも、通り過ぎる車も、遠目には影だけになりながらも、ここに確かに人が暮らしておるのです、という事実を、煌々と世の中に示し始めていた。
携帯電話が震えたのは、再び歩き出した私の息がすっかり整って、通学路最後の信号機を迎えた時だった。
《おーい、どこだー?》
さっき私が送った居所の確認には返事もくれず、私の居所の確認ときた。文面から察するに、錦織先輩は、もう学校に居るのかもしれない。
曲がり角を小走りで曲がると、目の前に校門と校舎が現れる。
校門に続く路地を駆けていくと、門のすぐ先に、私の学生カバンとは違うデザインの、革カバンを脇に挟んだ学生の姿があった。肩甲骨あたりまで伸ばした髪を左右に結わえた後ろ姿。コートの裾からは、先週ハンバーガーショップで見た灰色のチェックスカートが覗いている。
コートのポケットに手を突っ込んだままの錦織先輩は、花壇の縁石の角にローファーの裏を宛てて、足の真ん中、ちょうど土踏まずのあたりを支点にしたシーソーのような動きをしていた。
縁石の上につま先を乗せて、カカトが縁石から宙にはみ出る形で直立したかと思えば、カクッと、カカトを縁石の外に広がるアスファルトにつけ、つま先を立てたような姿勢になったりする。単調なシーソー運動は、待ち人への不服と、退屈の明示に思えた。
校門と昇降口に挟まれた、この花壇には、校歌が刻まれた大きな石がディスプレイされている。石碑の真ん前で花壇に向かっている錦織先輩は、おそらく、石に刻まれた校歌を読んでいるのだろうが、街に所縁ある著名な政治家の、位の高いミミズのような揮毫である。いくら熱心に見つめたところで、書き初めの宿題を見知らぬ中学生に押し付けるような人が、読解できるはずもない。
「錦織先輩」
あ、という形に口を開けて振り返った。足許のシーソー運動は続けたままで、ローファーの、足の甲あたりの、決まった位置が伸びたり歪んだりしている。
ある角度に至った瞬間だけ、革の表面が、昇降口の街灯の反射で、てらっ、と、白く艶めいてみせた。影に溶けた黒い革靴に反して、白いハイソックスが夕闇に、ぼうっと、浮かぶ。先週と同じ紺のネクタイは今日も、赤いマフラーと濃紺のダッフルコートの奥で白いカッターシャツの襟元を締めていた。
「中から出てくるのかと思って昇降口で待っちゃった!」
革のカバンとは別に肩に掛けたトートバッグから丸めた大判の紙が顔を覗かせている。書き初めの一式だろう。
「すみません、帰っちゃって。」
手短に謝ると、元々まん丸な目を更に大きく見開いて、今度は、え、という形の口を開けた。
「うそー、ごめん!部活でもやってんのかなーって思っちゃってたんだー。家から戻ってきたの?遠い?大丈夫?帰宅部?」
家から引き返した私への配慮と、所属部に関する関心が混同した雑な語り口と、だいじょうブ、きたくブ、と韻を踏まれたことが少しおかしくて、私は半分笑いながら質問に答えた。
「すぐそこです、歩いて十五分もしないですよ。」
それから、私が演劇部に所属していることと、それでいて今日は早く帰宅できた理由を説明した。
「生徒会だったから、部活なかったんですけど、この時期何も行事ないじゃないですか。文化祭も終わってるし、選挙も引継ぎも済んでるし、今学期の生徒総会もこの前終わっちゃったから、ヒマなんですよ。話し合うこと何もないし、出欠とって、沈黙して、苦笑いして、何もないね、帰ろっか!って。一瞬で解散です。」
私の話をケラケラと笑いながら聞き終えてから、最近は何をやっているの、と尋ねた。大雑把な質問の答えをどうしたものか迷ったが、錦織先輩が音楽専攻の学生だったことを思い出し、
「ずっと同じ歌、歌ってます。合唱。暗いやつ。」
と、今日の音楽の授業を思い出しながら答えた。
「木琴?!蝶の谷だ!!」
錦織先輩の挙げた『木琴』は、戦争が妹も妹が大事にしていた木琴も焼き払ってしまった、という兄の目線から歌われた悲痛な詩を元に作られた合唱曲だ。もう一曲の『蝶の谷』というのは、誰の目線だろうか、神様のような、一生と転生を司るような存在の目線かもしれない。または、既に絶命した先代までの蝶たちの心の目線かもしれない。
蝶よ、やがて亡びるさだめであるけれども、永遠に空を舞い続けたいならば、姿を捨てて、心になれ。亡びゆくさだめをそんなにも悲しむことはない、大空を知らぬまま土へ還る命もあるのだ、という歌詞だった。
いずれも合唱コンクール定番の子供の背伸びナンバーである。
先に挙がった『木琴』を歌ったことはなかったが、『蝶の谷』は小学生の頃から幾度か歌っている。蝶を筆頭に虫という虫の徹底的な絶滅を願っている私でさえも、やがて亡びる“生命の容器としての姿”の在り方と、それを失った後の、生き方、————死後に及んで“生き方”というのは矛盾があるかもしれないが、死してなお、亡びずに生き続けるというのはどういったことか、歌詞に登場する蝶の生死を通じて、しみじみと考えたものだった。
蝶そのものに関しては、蛾や蚊と同じ虫でありながら待遇が異なり、殺虫剤で追い払おうものなら正しき人々から咎められそうであり、また、蝶を愛することは人間として心が美しい証拠であるとして処理される場合も大変に多く、その逆もまた然りである、という特権も相まって、相変わらず大嫌いである。蝶の谷から人里に出てくることなく永遠に生き続けるか、とにかく今世代限りで滅びるか、どちらかにして欲しいものだ。
錦織先輩は、まだ、縁石で足のシーソーを繰り返している。
昇降口から出てくる生徒たちは見慣れない高校生に気づくと、校門に直進せず、私たちから距離を置くように弧を描いて校門を出て行った。
私は、蝶そのものに対する感情と、蝶を題材とした合唱曲に対する感情を努めて分断しながら、
「いいですよね、蝶の谷!歌いました?間奏のところが好きで、何度も弾きましたよ。今年は一年生のどこかが歌ってます。」
と、感想と、思い出と、校内の選曲情報を述べた。
「わー、同じ!私も伴奏だったよ!六年生の頃歌った。間奏いいよねー。なんだっけ、どんなだっけ、えーっと。」
そう言いながら『蝶の谷』の間奏の主旋律を口ずさんだ錦織先輩の鼻歌は、傍に立っている私以外の誰にも聞こえないほど小声であるのに、掠れることもなく、ぶれることもなく、息継ぎが目立つこともなく、細くて密度の高い声と、几帳面な方法によって、大変綺麗なものだった。
いまだかつてないほど高音質の鼻歌の完結を待ってから、私は、特に伴奏担当というわけではなかったことを話した。
あんな曲が弾けたらいいなと思って練習したこと。カタカナでドレミを書き込んだ無様な楽譜なしでは演奏できないこと。そもそも、音楽を専攻する人にとって演奏と呼べるものではないだろうこと。当然、正しい運指も知らないし、ペダルの使い方がわからないので気分がノッたら適当に踏んでいること。こんな不真面目な向き合い方の私だけれども、音楽には関心があって、合唱曲が大好きだということ。
錦織先輩は、黙って頷きながら聞いてくれたあと、一言、
「なんでもいいじゃん。」
と微笑んだ。それから、ピアノに備えられたペダルの役割を三本分それぞれと、グランドピアノとアップライトピアノでは殆どの場合、真ん中のペダルの機能が違う、ということを丁寧に教えてくれた。
ペダルの名前も細かく説明してもらったのだが、一つを除いて、あとは覚えることができなかった。一つは、マフラーというペダルだそうだ。バイクや車だけでなく、ピアノにもマフラーというパーツがあるのか!という覚え方で、たった一つ覚えることができた。マフラーといえば、原動機に繋ぐ排気消音器であるが、ピアノのマフラーペダルも消音に使われるらしかった。
冬の放課後というのはあっという間で、立ち話をしているうちに、辺りはすっかり夜という空気になってしまった。通用口から出てきた教師に、早く帰るように促される。私はとっくに一度帰っているし、かたや高校生であるし、北校舎からは、部活動がない日でも練習を欠かさない大人数が成す管楽器の音が、体育館からは、熱心な部員のものか部活動の生徒がいないのをいいことに遊んでいる生徒がいるのかバスケットボールの跳ねる音がまだまだ聞こえてくるのだから、そんなことを言われる筋合いはそれほどないぞ、と思ったが、体も冷えてきたので、とりあえず学校から離れて、駅の方角に歩くことにした。
校門の間で立ち止まった錦織先輩は振り返って、我が校の校歌が刻まれた碑を指差して、言った。
「あれさあ、書いた人、自分の字読めてんのかな?!」
* * * *
歩き出してすぐ、『木琴』でも『蝶の谷』でもなく、どの暗い歌を歌っているのかと尋ねられた。錦織先輩が、 『親知らず子知らず』か!と正答したのは、私が、 断崖絶ぺ…————まで、のみ、口にした瞬間だった。
一人で走って来た通学路を、よく知らない高校生と歩いて戻るのは、不思議な気分だった。この人は、どんな、誰なのだろう。どんな生活をしていて、学校ではどんな生徒で、家ではどんな様子で、どんな話をするのが好きなのだろう。
「週末のお泊まりはいかがでしたか?本田の家。試験勉強。捗りましたか?」
共通の話題がほとんどなかったので、どうせ捗らなかったろう、と思いつつも、一応、週末のことを尋ねてみる。
「それがさあ、喋ってばっかで、全っ然!最後のほう、誰もテストあること覚えてなかったね。」
少し黙ってから錦織先輩は続けた。
「っていうか、分かって聞いてるんだよね?今の!お見通しみたいな冷めた顔してるのわかるよ!顔に出てるよ!」
私がお見通しなら、先輩だってお見通しじゃないか、と思った。
「やめてください。思ってませんよ、そんな偉そうなこと。」
「うっそだー。」
嘘だとも。
歩道を並んで歩く背中を、何台もの車が照らしていく。横を走り去るヘッドライトが逆光で私たちの姿を炙る数秒間だけ、車道側を歩く錦織先輩の真っ黒な髪が、亜麻色に揺らめいた。
すれ違う人々や車の運転手たちが私たちに気づけば、なんだと思うだろうか。学校の友達、それとも部活の先輩と後輩、或いは幼馴染か、私は錦織先輩ほど愛らしい顔立ちではないので、似てない!と一蹴されるのかもしれないが、それでもギリギリ姉妹だと思う人もいるかもしれない。
残念!みなさん不正解!私たちは書き初め代筆の発注者と受注者なのです!——————————————誰がそんなことに気づくだろう。
街角に対して秘密になっている私たちの真相が滑稽でたまらなかった私は、些か不謹慎な気もしたが、どうしても、このくだらなさと不躾で成り立った関係の面白さを分かち合いたくて、
「たとえば今、ここにトラックが突っ込んできてどっちかケガしたら、付き添いの友達として救急車に乗せられるんですよ。書き初め頼まれただけの知らない人同士だなんて、誰も気付かなくて!すごいですよね、私たちお互い誰だか知らないんですよ。」
と、話を振った。
「知らない人じゃないよ!知ってるし!もう友達!」
躊躇いなく人懐っこい言葉に、たじろいだ私は、
「友達は宿題なんか押し付けてきませんよ。」
と、突っぱねてみせるしかできなかった。
肩掛けのバッグからはみ出ている大きな紙の束は私に渡すべきものではないのかと尋ねてみれば、家から慌てて出てきた手ぶらの私の荷物になるだろうから、と、私の家の前まで送り届けたかったらしい。だからと言って急に家の前まで押しかけるのもおかしいかもしれないし、一体いつ、家の前まで行っても構わないかという相談をしたものか、ずっと悩んでいたそうだ。
代筆を押し付けた図々しさにばかり気を取られていたことを、私は、少し申し訳なく思い始めていた。この人が、ああまでして代筆を頼むからには、何か理由があるのかもしれない、と思った。
私の家の前まで行くのか、行かないのか。逡巡を口にした流れに乗って、錦織先輩はもう一つ、切実な悩みを口に出した。本当はずっと、これを、私に伝えたかったのだろう。ずっと、この人は、私が学校に着くより前からずっと、トイレを我慢していたと言うのだ。
縁石に足を引っ掛けてシーソーのような動作をしていたのは、退屈の明示ではなく、寒中、尿意との格闘をする仕草であったのか。
今の今まで平然と喋り、歩き、先ほどに至っては鼻歌まで歌っていたというのに、ずっと、ずっと、ずっと、トイレに行きたかったなんて。気の毒に輪をかけて体にも毒なことを強いてしまった。
気づいてあげられなかったことを詫びると、
「気づかれたら、その時はもう超ヤバい状況じゃなくない!?なく、んんっ?!ヤバい状況じゃない!?ヤバいからね!」
と早口で言い切ってから、コンビニに駆け込んで行った。最後のほうは何を言っているのかよくわからなかった。
コンビニの外に並んでいるゴミ箱の前で、預かったトートバッグを抱きながら待つ。少し遅い気がしたのでガラス越しに中を覗くと、用を足しただけではお店に悪いと思ったのか、何か買っているようだった。
レジに並びながらこちらを気にしていた錦織先輩は、ガラス越しに私と目が合うと、初めて会った日と同じように掌と掌を合わせてペコペコと会釈をした。手で、いえいえ、という動作を返すと、微笑んで小さく手を挙げた。私は、バッグを胸に抱えたまま会釈を返した。
コンビニから出てきた先輩が手にしていたものは、暖かいお茶が二缶と、肉まん、あんまん、ピザまん、カレーまん、それぞれ一つずつだった。
「多くないですか?」
と聞くと、
「どれが好きかわからなかったから。」
と、饅頭がゴロゴロ投げ込まれた袋を私に差し出した。
多いような気がしたが、すべてを半分ずつ、あっという間に二人で四つ食べてしまった。厳密には、錦織先輩が肉まんを割り損じて具の大半を道に落としてしまったため、私たちが食べたのは、半かけの中華まんを三つと、ごく少量の豚肉の破片が付着した饅頭の皮を二分の一ずつであったが。
先輩は道に落とした具をコンビニのビニール袋で包んで拾うと、小走りでコンビニまで引き返して、ゴミ箱に捨ててから、私のところに戻って来た。そうして、眉間と鼻にしわを寄せ、唇を噛み締めてから、
「全部丸ごとあげれば、こんなことにならなかったのに、私も食べたいなーって思っちゃったんだよねー。」
と言って、仰々しく舌打ちしてみせる。
あの中で一番好きなのは肉まんだった、と胸の内を明かす顔を面白がって見上げながら、この人をよく知る友人になるための道を、自ら選んで進もうとする私を感じた。
さっき、学校に戻る途中で凭れた橋に差し掛かったところで、錦織先輩は、マンション群を眺めながら、すごいなあ、と呟いた。
「先輩は、どちらですか?おうちは。」
私のほうに向き直ると、
「ええと、中央の…ハブ駅寄りのほうなんだけど。」
と、少し言いにくいそうに答えた。それなりに裕福な人が多い土地柄だったので、人に言う時には遠慮しているのかもしれない。
「ああ、あっちは、大型の団地はないですね。」
錦織先輩の口にしたエリアは、商業地として開発されており、住居を備えた大型のビルはあっても低層階が会社や飲食店で埋められていて、オフィスビルやショッピングビルを上回る規模の、いかにも住宅といった建築物は、ほとんど見当たらなかった。
「そうなんだよねー。こんなでっかい団地ー!って感じの団地ないからさ、ベッドタウン、いいなあ。大きい団地って友達いっぱい住んでて面白そうじゃない?いつでも友達が同じ屋根の下にいるってすごいよ。私一人っ子だから、つまんなくて。」
橋を渡りきる寸前まで、二人ともマンション群のほうを眺めたままでいたが、ふと正面に目をやると、橋の境目から延びている横断歩道の青信号が点滅を始めていた。短い横断歩道なので、渡ろうと思えば、今から走れば赤信号になる前に渡れる。もとより、車通りの少ない場所なので、赤かろうが青かろうが、多くの人は渡ってしまうところだ。
私は、何よりもまず、急ぎたくない!のんびりしたい!という理由から、信号を焦って渡ることも、無視することも、満員電車に突撃することも、階段を駆け上がることも、自転車で急ぐことも、何もかも、交通に関する慌ただしさのすべてを猛烈に嫌っていたので、青信号の点滅の前では立ち止まりたかった。もっと言えば、点滅に備えて青信号のうちから止まっていたいくらいだったけれど、多くの学友たちは信号など気にせず、赤でも、この道を渡ってしまうのが常だった。
どうしたものか。ここはひとつ錦織先輩の出方に任せることにした。この人は公共の場で、どんな出方をするのだろう。私の好きな出方だろうか、苦手な出方だろうか。
錦織先輩は、消えかかって、“マレ”だけになった、“トマレ”の白線の手前に描かれている、人間の足跡マークに靴を合わせて、ピタッと止まった。
えらい、と思った。
そうしてから、こちらを向いて私の足許を指差して言った。
「おっ、ちゃんと止まった!えらい!」
赤信号で立ち止まっている間、私は、まだ誰にも話したことがなかった、自分だけの秘密の話を、世界でたった一人、錦織先輩だけに打ち明けることにした。
「私、この街がベッドタウンとして開発されるっていう話を聞いた時に、ラブホ街のことだと思っちゃったんですよ。ほら、ベッドシーンとか言うじゃないですか。だから、ベッドタウンとしての開発!?ベッドシーンを、タウン規模で!?って。それで、うわあ、これは、とんでもない街になるぞ、大変だ!ベッドタウンだぞ!って。」
先輩は手を叩いて大笑いしていた。
敦子 (三)
駅に向かう道と私の自宅に向かう道とが分かれる交差点で解散したとき、コンビニで買ってもらったお茶の空き缶を錦織先輩が引き取った。缶をペコペコと音を立てて潰しながら駅にゴミ箱があると言うので、駅で買ったわけじゃないものを駅に捨てたらよくないと咎めると、じゃあ家で捨てるからと少し面倒臭そうな笑顔を湛えて、潰れかけた缶を二缶とも右手の指に挟んだ。どうせ面倒に思われたのだから念を押すことにした私が、絶対ですよ、と言うと、錦織先輩は二度三度頷いた後に、眉と口角を上げた。
「うん。うちに来た時に見せて、駅で捨てなかったんだってこと信じてもらえるように、証拠に取っとくから。」
書き初め道具の受け渡しだけを目的に門前まで寄ってもらうことは気が引けて、私は交差点でトートバッグに収まった一式を預かった。委細は改めてメールをくれるという。これだけ一緒にいたのだから説明を受けるべきだったのだが、頭の片隅に本命の用事を置きつつも雑談の引き際を誤った私たちは結局、何も果たさぬまま帰宅しなければならない時間を迎えてしまった。
それにしても、他人の持ってきた布というのは、どうしてこうも私の手に馴染まないのだろう。初めてのトートバッグを肩からぶらさげて、いつもの路地を、歩く。名前こそ知らないものの、これはトートバッグによく使われている類いの生地で、これまで幾度となく出会ってきた種類なのだが、どうしても私の人生と関係のない感触がする。それは同級生に借りた体育ジャージを羽織った時にも感じた布からの疎外感だった。まったく同じ材質でできた同じ型番の衣類であるのに、とにかく私のものとは着心地が違うのだ。他人の布というのはいつもそうだ。錦織先輩のバッグの持ち手を握れば握るほど、これは預かり物なのだ、という事実が掌に伝わる。
ふと、お正月休みが明けた廊下に思いを馳せた。整然と並ぶ同じ大きさの台紙、同じ大きさの用紙、そして同じ文言と、同じ文言なのに、色んな字。
美しい文字なのに控えめな筆致のもの。堂々と書き上げられた毛虫のような筆致のもの。サイズの配分を誤ったために後半に行くほど小さな文字になっているものや、字がどんどん大きくなっていく序盤の土地配分を誤ったことが明白な類いのもの。市販の墨汁の出す、力んだ黒。擦り足りない墨で書かれた、弔事のように薄い黒。凍みた空気が充満する真冬の廊下には、奥の突き当たりまで、どこを見渡しても、全員分の個性を滲ませた規則正しい長方形の紙が、整然と並ぶに違いなかった。
学業の成績は全国的に見て“下の特上”、運動神経は“日常の穏やかな動作用以外に機能しているのか不明”、部活での佇まいは“頭数の問題で居ないよりは居た方がいいが気難しいので居ないほうがいい可能性も否めない”、絵は学年に横並びで十人は居るタイプの“結構うまい人”止まり。挙句、“トップを逃したことがない科目はよりにもよって保健体育のみ”という不名誉を収め続けた私が唯一、全国区に参戦できる最低限の技量を満たしているのが、書道だった。尤も、最低限出展に漕ぎ付けている、というだけであって、上位入賞の常連組ではなかったし、専攻する学生たちに言わせれば悪筆の部類には違いない。それでも一般の学生集団に紛れている分には見劣りがないので、ハンバーガーショップで錦織先輩に答えた“上手くはないが下手でもない”というのが、私の嘘偽りない自己評価でもあったし、客観的評価でもあった。見知らぬ高校生の宿題を押し付けられることを歓迎するか否かは別問題だが、そうは言っても、まったくの不得手ではないと自覚できる物事を活用できる季節が年に一度巡ってくることを歓迎するのが、この季節の私の姿勢であった。
待ち遠しい気持ちが湧いた私は街灯の下、バッグの中を覗いてみた。そこには、お手本と、同じサイズに切り揃えられた書き初め用紙の束が入っているはずで、それから、もしかすると錦織先輩が使っている書き初め用の下敷きや筆と墨池も入っているかも知れなかった。
少し覗いた限りで、お手本は目に入らなかった。どこかに折り畳まれて挟まっているのかも知れない。私はどんな文字を書くのだろう。弾む心を抑えながら少しバッグの中を漁ってみると、入っていたのは、大きな書き初め用紙と、小さな書き初め用紙。つまり、サイズの疎らな書き初め用紙たちだった。新品の半紙三枚判と、使いかけの東京判。大きめの書き初め用紙だ。この大きな書き初め用紙の他に、二回り以上小ぶりな、八ツ切判の書き初め用紙の新品パックも二パックほど入っていた。これらは当然、書き初め用紙には違いないのだが、おかしい。
何かが、おかしい。
この感じは、おかしいのだ。これはおかしいと言い切れる証拠が揃っているわけではないが、これで正しいと安心できる根拠も一切なかった。普通、書き初めと言われて渡される道具の揃い方ではないのだ。なにしろ書き初めというのは、冬休み明けの廊下に整然と展示されるものであって、紙のサイズはよくよく測ればそれぞれ親指の先か小指の先程の差はあるかもしれないが、それでも遠巻きには必ず、同じサイズなのだ。同じサイズの用紙に、同じ文言を、指定された書体で書く。これが書き初めの宿題なのだ。かくして、それらは、整然と並ぶのだ。
筆も硯も文鎮も墨も持っているから、それらが入っていないことは不問として、サイズが揃わない書き初め用紙と藁半紙に刷られた教科プリントらしきもの以外、何も入っていない。厳密に言えば、『稲中卓球部』という漫画本と『彼氏彼女の事情』という漫画本も一冊ずつ入っていたのだが、これは書き初めに関係なく、私への贈り物でもなく、出し忘れだろう。きっと借りたか貸したのだ。いずれも途中の巻だった。将来的にこれらの漫画を読む機会が無いとは言い切れないため、中を見てしまわないよう留意した。
それはそうと、お手本はどこだ。まさかお手本だけ錦織先輩の持ち帰った学生カバンのほうに入っているのだろうか?今ならまだ電車に乗っていないかも知れない。もう一度バッグの中をよく見て、それでもなければ電話をかけて引きとめて、お手本を今日のうちに受け取ろう。後日改めて会ったら、私はきっと再び、錦織先輩の時間を意味のない雑談で潰してしまう。
書き初め用紙のパックを一つ一つ指でどかしながら、トートバッグの中を覗き込んだ私の目に飛び込んできたのは、教科プリントに刷られた喫驚の書き初めルールであった。
《♪冬季休業 音楽科×総合芸術分野選択書道・共同課題♪ がんばりましょう!》
《♪課題(1) 漢字に限る四字。手本、とくになし。あなたが良いと思う書体を追求。オリジナルの書体もよい。書道家を参考にする場合は影響を受けた書道家を提出票裏に明記。最もイメージに近く書けた作品を一点発表。サイズは半紙三枚判を使用のこと。東京判も可。》
《♪課題(2) 上記(1)の四字の書体を決定するまでの紆余曲折の記録。書体の完成にいたるまでの試作習作をすべて残すこと。サイズは半紙三枚判または八ツ切。東京判、東京小判も可。》
《♪書道作品提出後 翌週の希望別講習にて書体のイメージの原点となった楽曲を演奏することをもって冬季休業課題の修了。希望別講習にて声楽補講者は専攻を問わず希望の楽器とする。》
《☆この課題の目的 イマジネーションを高める心と頭の体操をして有意義なお正月を過ごします。がんばりましょう!》
————————————————————————————… 一体。
一体、これは、なんなのだ。
冒頭と結びで二度も念押しされる、“がんばりましょう!”といい、これだけの重量と奥行きを備えた課題を“体操”呼ばわりしている教師も、こんなものを私に回してきた錦織郭子も、錦織郭子の通う音楽科というのも、一体なんなのだ。音楽科というのは、音楽漬けであるから、つまりこんな大変な課題の文頭にまでいちいち《♪(音符)》を散りばめてくるものなのか。全国的な教育法なのか、この課題の担当教師が変わっているのか、校風なのか。一体、これは、なんなのだ。
それとも教科プリントを私に預けたことは誤りで、こっちは錦織先輩がこなす音楽的書道、私に本来代筆させる予定だった書道的書道のお手本は別にあるのだろうか。錦織先輩が間違えて持っているのだろうか。そうであってくれ。さもなくば、一体なんなのだ、これは。概要は理解できるが、どうしてこれを私に投げたのか理解できないではないか。
さりげなく書かれている「書体のイメージの原点となった楽曲の演奏」というのも、何よりも、これが、一体、なんなのだ。裏を返せば、私がその楽曲を知らねば書体を確定できないということではないのか。それとも、休み明けの何とか講習の授業では適当な曲を演奏して乗り切るつもりだろうか。これでは、音楽科と総合芸術分野選択授業とやらの共同課題ではなく、私と錦織郭子の共同課題になってしまうのではないか。いずれにせよ不誠実であり、無茶だ。
錦織、錦織!錦織!!錦織!!!
どういうつもりなのだ。なんの説明もなく帰って行った!どういうつもりなのだ。戻って来い!
先週、錦織先輩が言った、うますぎない人がいい、というのは、要するに、本当の用件は、“書写”がうまいとか、へたとか、そういうことではないのか。きっと、書道に慣れていて、手本のない課題に取り組む根気が訓練されていて、それでいて、型を破れる、或いは、破るほどの型すら持っていない未完の人。但し、最低限書ける。——————ああ、察しがついた。
さっき学校で石碑に刻まれた揮毫を熱心に眺めていたのも、そういうことか。きっとどんな書体があるのかを探求していたのだ。だったら自分でやれ!
教科プリントをしみじみと手に取ってみる。
《手本、とくになし。オリジナルの書体もよい。》
「手本、とくになし。オリジナルの書体もよい。」
思わず道端で音読して、笑ってしまった。手本、とくになし。書き初めとして、本質的ではあるが、書道の授業としては教育的でない。自由な書道という行為と、手本のある書写という課題は、好物を飲み食いすることと頼まれ仕事の調理くらいに、同じ世界で同じものを使った、まったく違う現象だ。
あまりのことに、家路を中断して、悴む手でメールを送る。
《概要を読みました!なんですかこれ!》
文末には、目をバツ印にして口を丸く開けた絵文字を三つ連続で添える。寒さを紛らわすための足踏みをしながら路上に留まった。五分ほどして届いた返信は
《でしょ!?やばくないそれ!?》
だった。
私の綴った“なんですかこれ!”の真意は、“この宿題やばいっすね!”ではなく、“錦織先輩、あなたはどうしてこのような厄介なものを私に預けたのですか?”だったのだが、明るい錦織先輩には一切通じず、やばい宿題である、という共感として処理された。
悪い気がしなかったのは、きっと、さっき、錦織先輩に、友達!と呼ばれたからだろう。
それでも今きちんと気に食わない素振りをしてみせなければ、あの明るさに軽々と押し流された気がして悔しかったので、私は、私にだけ聞こえるように小さく舌打ちをしてから、改めて家路の続きに就いた。さっきの錦織先輩がコンビニで、落とした肉まんに対してやってみせた仰々しい舌打ちの真似だ。
ポケットに投げ込んだ家の鍵を探す。キーホルダーのリングに指を引っ掛け、片方の爪先が我が家の敷地に触れるか触れないかという時、再び、携帯が震えた。錦織先輩だった。
てっきり書き初めの要件かと思えば、単なる愚痴で、なんでも錦織先輩の通う高校では、普通科の生徒に関しては芸術分野の選択授業が『選択音楽』『選択美術』『選択書道』の三択なのだが、音楽科の生徒に関しては『選択音楽』の授業内容が音楽科独自の授業と重複してしまう。それどころか、選択授業の内容が劣っているため、音楽科に在籍する生徒に限り、芸術分野の選択授業で『選択音楽』を選ぶことはできず、『選択美術』か『選択書道』の二択になってしまうとのことだった。
本人曰く絵は三歳児以下のため、消去法で書道一択になってしまったものの書道も苦手で毎週芸術授業の日が辛くてたまらないらしい。また、美術を選択した生徒も音楽を選択した生徒も宿題などないのに、書道を選択した生徒だけ担当教師らの意向で特別に宿題を出されてしまったことが、
《どうしても納得いかない!》
のだそうだ。無事、私に押し付ける形で成約したのだから、一体あなたに何の文句があるのだ、とも思ったが、私の返事も待たずして立て続けに、納得いかない!というメールを送ってくる些細な直情が小気味よかったので、
《不公平ですね。笑 とにかく頑張ります!》
と返した。書き初めの委細には触れられなかったので、とにかく宿題の存在が気に食わないことを伝えたかったのだろう。
* * * *
玄関を開けると、リビングから重厚なピアノの音色が聞こえる。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。ピアノソナタ、第八番の『悲愴』と第十四番の『月光』以外をまったく弾かなくなった私の祖父は、他に知らないわけでも、運指の穏やかな曲しか弾けない趣味のピアニストでもなかった。ただ、認知症が進むにつれて譜面を扱えなくなり、記憶と言動が曖昧になった時期を境に、他には何も弾けなくなってしまったのだ。
ねえ、おじいちゃん、何を弾いているの、と尋ねてみても、ある時は答えられなかったり、ある時は食べたい野菜を申告したり、お小遣いをあげましょう、と何も入っていない胸ポケットに手を差し入れたまま訳が分からなくなって硬直したのちに、タバコが切れたと嘆くこともあった。真っ当なやりとりは何一つ成立しない。道も分からなくなったし、病院に連れていく時も、本人は何も分かっていないようだった。ピアノを弾いている最中に話し掛けて、返事があるほうが珍しかった。
この世のほとんどすべてを上手に認識できなくなり、記憶を次々と手放していく祖父の人生の手には、幼い日々に弾いていた『悲愴』と『月光』だけがこびりついたまま残り、認知症の老人が時に、思い出のどこかを頑なな目的地として徘徊に出てしまうように、止めても、止めても、祖父の指は鍵盤の徘徊に出ては、幼い祖父が幾度も奏でた曲を執拗に辿るのだった。
楽譜などない。ただ、ピアノの前に腰掛け、目を閉じて、酒臭い口を半分ばかり開き、鍵盤の上を節くれだった細い指がいつまでも徘徊する。黄色くなった爪にはでこぼこと白い線が入り、爪の奥に隠れた指の肉は、内出血したような色をしている。皮膚は固かった。
数年内に亡くなる祖父の手が死ぬ間際まで放さなかったものは、酒と、煙草と、女の腰と、月光と、悲愴。あとのすべては認知できなくなり、生前に置いていく。懐かしむほどの思い出も、確かな記憶も、かつて落ちたかもしれない恋のことも、誰かに対して抱いたかもしれない愛のことも、大切にした数々の音楽のことも。祖父の死後、祖父の部屋に残っていたものは、吸いかけのセブンスターと、移動式の酸素吸入器、小型冷蔵庫に入っていた飲みかけの日本酒と牛乳、それから、押入れ一杯の楽譜。
祖父の定期演奏会が始まるようになってから、夜間、近所に音色が漏れてしまわぬよう防音工事を施すと、この家に暮らす人間は全員、毎晩の『悲愴』と『月光』を受け容れた。受け容れたというよりも、諦めたのだ。誰もが、五月蝿がるという反応の選択を封じ、聴いている自覚を封じた。そうしているうちに、まるで祖父がピアノを弾いている間こそが無音であるかのように、家中が振る舞うようになった。
ピアノの音色を黙殺するようになったとき、“祖父の生命”とは別に、“祖父の存在”を、みんなで殺したのだ。
誰が発案するでもなく、誰と示し合わせるでもなく、なんとなくそうして纏まった祖父を除く我が家の構成員たちは、ピアノが鳴る間も、必要があればお構いなしに会話をした。ピアノの存在を全否定するかのような、小声で。まるでそれは、無音の空間で喋るときの声量で。テレビを点けることもあった。もちろんそれは、ピアノなど鳴っていない部屋に居るときのような、通常の音量で。少し距離が空くと、だいたいよく聞こえなかった。全員、狂ったように冷静だった。
「ただいま。」
私の小さな声はピアノに遮られて誰にも届いていないようだ。億劫だったので自室の冷蔵庫から出したパンを麦茶で流し込み、入浴を済ませ、さっさと布団に入る。今日はよく走ったから疲れてしまった。
パジャマに着替えて布団に潜っていると、携帯が鳴った。錦織先輩だった。大した用事ではない。
《ひま?》
と来たので、
《ひまですよ》
と返したら、即、
《そっかー!メールしようよ!》
と返ってきた。暇が深刻なのだろう。
何通か交わした後に届いたメールには、名字で呼ばれるのは堅苦しくて嫌だということと、私が採用している“先輩”という敬称について同じ組織の先輩ではないのだから先輩と呼ぶのはおかしいのではないかという異論、ただの友人同士なのだから名前も呼び捨てでいいし、敬語も必要ないということが書かれていた。
同級生の本田が高校生を連れて歩いて得意げになってしまう気持ちを、少しだけ理解した。見上げてきた相手に、対等を許されるというのは、それまでの礼節が実を結んだようにも思えて、悪いものではなかった。
私は思い切って、錦織先輩の下の名を呼び捨てただけのメールを送った。
《郭子!》
読み違えて覚えた名前のまま、敦子(アツコ)!ではなく、郭子(カクコ)!と。トイレに行き忘れたことを思い出した私が用を足している間に届いていた返信は、
《書き初めのことまた連絡する!ねむーいzzzおやすみー!》
だった。返信を返すと起こしてしまうかも知れないから、おやすみなさいと、今日から友人となった人に胸中で呟く。祖父は、まだ今晩何周目かの『悲愴』を弾いていた。私はベッドで仰向けになりながら、目を閉じて、普段は意識して聴かないピアノの音を、珍しく丁寧に聴き取った。郭子には、一つ屋根の下で音楽を無視したことなどあるのだろうか。拒絶したい音楽を、持っているだろうか。
翌朝、昨晩返信をしなかった非礼を詫びつつ、朝の挨拶を送ると、ダルさの欠片もない返信がすぐに届けられた。
《今日もダルいけどがんばろー!しゃー!》
* * * *
私は一体何度、敦子(アツコ)宛てのメールに、“郭子(カクコ)”と打ち込んだのだろう。あーあ、カクコじゃなくてアツコなら一発変換できるのになあ…などと、ヒドく失礼な思考を繰り返しながら、私は、“カクコ”呼ばわりされたままの“アツコ“と毎日のようにメールを送り合うメル友になった。
内容は無い。ただ、部活が終わった、とか。バイトが終わった、とか。おはよう、とか。寒いね、とか。眠いよー、とか。テレビ観てる、とか。何観てるの、とか。テレビ終わった、とか。何観てたの、とか。
毎日続くことばかりをダラダラと送り合う。ついつい雑談ばかりしてしまい、書き初めの委細については未だ触れていない。冬休み明けに間に合えば問題ないわけで、お互いに焦っていなかった。
私たちは毎日のようにメールを交わしたが、おやすみなさい、だけは、ほとんど交わさなかった。布団に入ってメールをしているうち、どちらが先に寝てしまったのか、いつの間にか二人とも眠ってしまって、おやすみ、を告げてから眠るなどという高等で丁寧な生活は、なかなか果たされなかった。翌朝になって初めて自身の入眠に気づく。最初の四、五回は簡単に謝り合ったような記憶があるが、それ以降は、おはよう、とか、朝だー、という短い言葉に明るい顔文字や絵文字を添えて済ませるだけになった。
慣れて適当になったのかもしれないし、それを仲良くなったと呼ぶ場合もあるかもしれない。悩みを相談することもなければ、好きな人の話をすることもなく、ただ、ひたすらダラダラと、日常を交わし合うだけだったので、距離が縮まったような気もするし、暇を潰しあっているだけのような感覚もあった。
私が敦子の名前について、まったく城郭の子ではなく、敦厚の子であったことに気付いたのは、間も無く迎えた元旦のことだった。自発的に気付けたのではない。遂に正されたのだ。
届いた年賀状の差出人の欄には、フリガナ付きで《錦織郭子(ニシキオリカクコ?) 》と黒字で書かれた上から、赤い大きなバツ印が被せられ、その脇に赤字で、勿論フリガナを添え、《敦 (アツ)》と書かれている。 特に、敦(アツ)を、郭(カク)ではなく敦(アツ)たらしめる“攵”の部分に関しては、太字になるまでペンで幾重にもなぞられていた。
赤入れされた《錦織郭子 ×敦》の末尾には、青インクのペンで《(笑)》が付き添っており、私の読解力と敦子に対する理解が定かであれば、これは、怒ってはいないよ(笑)、という意思表示だろう。
マメなメル友とは言え、込み入った話をしたことなどない。親しいとは言い切り難い知り合ったばかりの先輩の名を間違えてしまった手前はバツが悪くて堪らなかった反面、敦子が採用した訂正手段の意外なまでの気立ての良さが、気に入って、気に入って、いたく気に入って仕方がなくなった私は、この年の元日から、信じられる友達は誰?という自問自答に即答できるくらい、敦子のことが大好きになった。
既に“カクコ”に宛てて年賀ハガキを送ってあった私は、上はパジャマのまま、ズボンだけ履き替えて、財布と携帯をポケットに捻じ込んだコートを羽織った。慌てて黒と赤のペンとハサミ、それから余りの年賀はがき一枚をバッグに放り込んで、近所のコンビニまで、走り初めをする。
喉や鼻腔に飛び込んでくる真冬の空気が硬くて冷たい。息が上がる前にコンビニまで辿りつくことができたのは、度々赤信号に引っ掛かったおかげだった。
漢字練習ノートと両面テープを買う。のりではダメなのだ。私はのりつけが得意ではないので、貼り付けた箇所がフニャフニャのボコボコになってしまう。既に名前を間違えるという失敗をやらかしているのだから、ハガキの見た目が無様では恥ずかしい。
コンビニの表のゴミ箱の上に、大急ぎで丁寧に破り取った漢字練習ノートを一枚置いて、四辺に両面テープをピッタリと備えたハガキを、漢字を書き込むためのマス目の角度と真っ直ぐ揃うよう、慎重に押し付ける。ハガキの周りに余ってはみ出たノートは、ハサミで切り落とし、風で舞ってしまわないよう、急いで丸めてゴミ箱に捨てる。
こうして片一面が漢字練習ノートと化したハガキに、びっしり《敦(アツ)》 の字を書いた。先頭の一文字目だけ《郭(カク)》にして、その上から赤でバツ印を被せた以外は。余ったスペースに、本当にすみませんでした!と書いて、住所と宛名を書き込んだ。
宛名を書き違える気などなかったのだが、まさか、さすが私は私であって、ちゃんと、大切な宛名を、勢い余って《郭(カク)子様》と、書き間違えた。仕方なくこれにも赤いバツ印を被せて、隣に、《敦(アツ)子様》と書いた。 さも、元々ここも誤字と訂正を演出する予定でした、と言わんばかりに、上からレタリングなど施して。
道ゆく人がゴミ箱を机にしている私を見ていやしないかと気が気ではなかったが、どうしてもすぐに投函して早く敦子に見せたい。逸る気持ちは、思春期の屈強な自意識に容易く勝るほどだった。郵便局に行って、無事に投函を済ませて、やっと私の元日は落ち着いた。
敦子から携帯に着信があったのは三が日が明けた一月四日の夕方だった。あれほど毎日メールをしていた敦子から音沙汰がないのだから、きっと私の送った年賀ハガキに落ち度があったにちがいないと連日胃が痛かったのだが、単に親御さんの実家に帰っていただけで、郵便受けを見たのは今しがただったそうだ。
叱られるのかと思って電話を受けたので、電話口から突然聞こえてくる笑い声に拍子抜けしてしまった。挨拶もせずに笑い声から始まった敦子の電話はきっと、ハガキを手に取った流れのまま、もう片方の手に取り出した携帯電話から即座に掛けられたものだった。
「超ウケたんだけど!これ何?印刷?あーっ、漢字ノート貼り付けたのか!」
「そう…。」
「買って?小学校の時の余りか!」
「や、買って…。」
「あはははは!ウケるわ!書いたんだこれ!よく思いつくねこんなこと!」
敦子は小一時間私の送った二通目の年賀状を褒めてくれた上で、とにかく名前を間違えたことは気にしないように、と繰り返した。
初めて私が敦子を下の名前で呼んだ日、あの、郭子(カクコ)!と呼ばれたメールで、敦子はすぐ間違いに気づいたそうだが、即座にメールで伝えると気を悪くしたとか、怒っていると思われるかも知れないから、と、本当は次に直接会って話すまで黙っているつもりだったらしい。ところが年賀状を書くにあたって、さすがに差出人名を自ら間違えるわけにいかなくなってしまい、年賀ハガキでの指摘に至ったそうだった。
ふいに電話の向こうから生活音がしたかと思うと、遠くのほうから
「あっちゃん、ごはんー!…あ、電話!」
という声が聞こえた。電話機を口元に持ったまま、少し距離の離れた人に返事をした敦子の声が急に大きくなる。
「すぐ行くー!」
というわけだから、と電話を切ろうとする敦子に、あっ、と思い、私たちにとって今のところ最も大切な用件を伝える。
「書き初め!どうする気?イメージの元になった曲とか。」
あーそっかそっかそっかそっか、と少し早口になった敦子は矢継ぎ早に尋ねる。
「明日ひま?」
予期せず、敦子の家に行くことになった。明日の昼十一時に、敦子の家の最寄駅。
* * * *
指定された駅の、指定された改札口に着くと、制服姿の敦子が立っていた。今日は部活か何かがあるのかと制服の理由を尋ねたら、私服で会ったことがないから、制服を着ていかないと見つけてもらえないのではないかと心配したらしい。私が敦子の顔を忘れてしまった可能性と、忘れてしまった非礼を言い出せずに更に困るという可能性を懸念して、制服で出てきたという。
いつもカッターシャツの襟元を締めているはずの、あの、紺のネクタイの姿はどこにもなく、その代わり、二つ目まで空いたボタンの奥には鎖骨の影を纏った、首の皮とも胸板の肌ともつかない、敦子の表面が覗いていた。
「お昼まだ済んでない?済んじゃった?お母さんが今私たちの分のお昼作って待ってるんだけど!」
済んでいようが済んでいまいが、もう作って待っているのであれば、いただく以外どんな選択ができるというのだろう、と思って、私は少し笑ってしまった。
家に着くと開口一番、敦子の母は、
「あらー、あなたが面白い年賀状の子!」
と甲高い声で話しながら私の肩をポンと叩いて微笑んだ。地声は低めの敦子と比べると、母親の高い声は似ても似つかなかったが、目元と口元は敦子にとてもよく似ており、敦子も将来こういうおばさんになるのだと思った。
「ごちそうさまでした。」
昼食を食べ終えて、お皿を片付けようとすると、
「いいのよ。」
と、敦子の母に静止された。
「あんたたちせっかく冬休みなんだから、人の家まで来てお手伝いなんかしないで遊びなさい。大人になったらそうもいかなくなるんだから。」
招かれた敦子の自室には、ベッドと机、譜面らしきものがびっしり詰まったストイックな本棚、漫画や教科書が差された雑多な本棚が一つずつ、それから、グランドピアノと、どういうわけかテレビが二台置かれている。どうしてテレビが二台あるのか尋ねたら、テレビがないと死ぬからだそうだ。だからって、命が二つあるわけでなしに、一台でいいじゃないか、と思った。
他にも、楽器メーカーのロゴらしきものが刻まれたケースがいくつか並べられていたが、ケースの外から楽器を特定できるほど音楽に明るくない私に読解できたメーカーロゴは、見慣れたYAMAHAのみであった。
「敦子、お母さんとそっくりだね目元と口元!」
「やっぱそう?血は繋がってないんだけどよく言われる!」
沈黙してしまった。
一瞬、沈黙してしまった。けれど、一瞬の沈黙だと思っているのは私だけで、もしかすれば、五秒くらい沈黙してしまったかもしれない。なんとか取り繕わなければと思った私は、
「あっ、うわっ、ごめん、嫌なこと聞いちゃって。」
と、慌てて謝った。
「なんで?」
キョトンとして、敦子は言った。
本当に、キョトンとした顔というのはこういう顔のことを言うのかと、辞書の“キョトン”のページに図説として掲載してくださいと出版社に写真を送りたいほどに、キョトンといった顔で、こう続けた。
「みんなそう言うの。なんでだろうね。私お母さんと超仲いいし、気にしてないけど。」
——————————————————————“なんで?”
なんで、だろう。私は、なんで謝ったのだろう。なんで私は、聞いてはいけないことだと思ったのか。なんで、それが嫌なことだなんて決めてしまったのか。なんで、敦子を不幸な子として、確認も取らぬまま扱ったのだろう。
「なんかねー、言うと、問題のある家庭だと思われちゃうんだよねー。ただ私は、友達だからさ、うちはこうだよって説明しただけ。弟がいるよ、とか、何歳離れているよ、とか言うじゃんみんな。その感じなの。お母さんいるよ、血は繋がってないよ、って普通に言ってるだけなのに変な空気になっちゃって。お父さんも血が繋がってないんだよ。私が赤ちゃんの頃に本当のお父さんもお母さんも事故で死んじゃったんだって。」
どう返事をしていいのか、まったく見当がつかなかった。敦子は私の返答を待たずに、話を続ける。
「会ったことないから、いや、あるんだと思うし赤ちゃんの頃は一緒に住んでたはずなんだけど、全然覚えてないから、悪いけど、そっかーって思うだけなんだ。そんなに若いのに死んじゃうなんて、かわいそうなんだけどね。子供生まれたばっかりで死んじゃうなんて、きっと辛かったと思うよー。でも、フクザツ。かわいそうだけど、本当のお父さんとお母さん生きてたら、私、お母さん、あっ、今のね、育ててるほうのお父さんとお母さんの子になってないんだって思うと、正直そっちのほうが寂しくて。今本当のお父さんとお母さんが生きてたとして、帰っておいでって言われても絶対やだし。だから私これでいいじゃんって思ってるよ。」
黙って曖昧に頷く私を一瞥した敦子と目が合った。母譲りではない、母似の目元は、いつも通り、穏やかな様子だった。
「でも、そんなこと言ったら死んじゃったほうのお父さんとお母さんに悪いから、フクザツだね!今のお父さんとお母さんに育ててもらえたのは、死んじゃったほうの親に産んでもらったおかげだしさー。」
敦子は片方の頬に空気を含ませて、困った顔をしていた。私は気の利いた言葉の在庫を切らして、引き続き黙っていた。
「まあとにかく、よくお母さんに似てるって言われるよ!あとねー、お父さんは血が繋がってないこと感謝するほどゴツいからね、全然似てない!」
テレビドラマだったのか、漫画や小説で読んだのか、具体的にどんなタイトルの、何の、どの場面というのは覚えていなかった。ただ、両親と血縁がない、とか、両親が事故で死んでしまった、とか、そういうのは“秘密”として描かれるのが普通だったと思うし、そんな事実を打ち明けるシーンというのは、決まって重要なシーンであったはずだ。何より私の一族に関して言えば、血縁にしろ、戸籍にしろ、続柄にしろ、何にしろ、ストレートコースから外れた関係性は、恥じたり、社会に対する不便を感じたり、若しくは当人たちの気持ちを案じて、隠してきた。親族の間で触れることもなければ、ましてや友人に口外することもない。そのため私は、健在で面識のある親族以外に一体どんな身内が居るのかを知らされていなかったし、これまでどんな血族が亡くなっているのかも知らなかった。本当は誰と誰が血が繋がっていて、本当は誰と誰が血が繋がっていないということも、偶発的に知ってしまうことはあっても、それを受け止めて生きるための準備などは為されなかったし、わざわざ明るみにしようという者も居なかった。
とにかくこうしたことは私にとって、秘密か、非日常か、何か人生の演出が強くかかりすぎた現象であって、ノンフィクションであろうと、フィクションであろうと、ドラマチックの根幹になり得る要素なのだ。敦子のように、さっき食べた昼食のメニューを述べるみたいに血縁を語る人物を、生身の時も、創作の中でも、私は一度も見たことがなかった。
学校で待ち合わせたあの夕方、尿意と激闘していた事実と、どうしてもトイレに寄りたいことを遂に打ち明けた敦子のほうが、よほど重荷を抱えた人のように思える。
結局、この日も私と敦子の雑談は満開に咲き、書き初めの話は何一つ進まないまま時計の針は今日二度目の七を指した。
「泊まってけば?冬休みだし、いいじゃん。」
ここから先は
¥ 639
