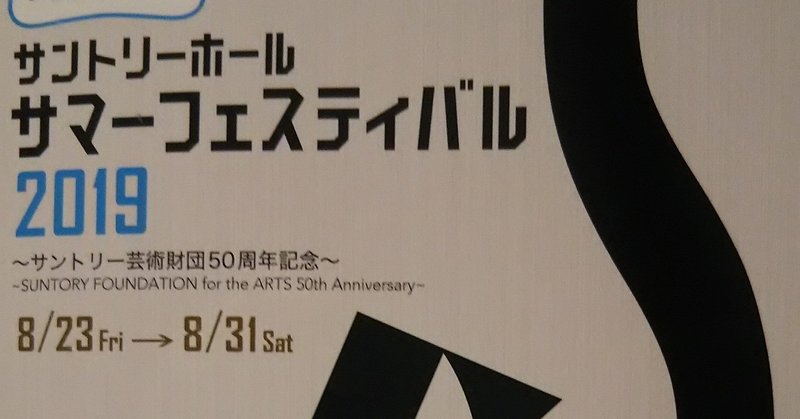
【Opera】ジョージ・ベンジャミン作曲『リトゥン・オン・スキン』(日本初演)
サントリーホール・サマーフェスティバル、今年の「ザ・プロデューサー・シリーズ」は指揮者・大野和士によるもの。大ホールで2日間に渡って上演されたジョージ・ベンジャミン作曲のオペラ『リトゥン・オン・スキン』は、大野としても力の入った企画だったと思われる。2012年にエクサン・プロヴァンス音楽祭で初演されたこの作品は、その後欧米各地で上演されており、21世紀、つまり「現代オペラ」の中では最高傑作との呼び声も高い。日本にいてはなかなか接する機会のない最先端のオペラを体験できたことを、まずは素直に喜びたい。
物語は、13世紀からの伝承である「心臓を食べた話」をモティーフにしている。まず冒頭で3人の天使が登場し、時代を800年ほど巻き戻す。登場人物は、横暴で支配欲にまみれた領主(プロテクター)、従順で学のない妻アニエス、そして天使の1人が、プロテクターが自分の本を作るために雇い入れた写本彩飾師の少年に変身する。3人を巡る三角関係は、ドビュッシーの『ペレアストメリザンド』を思わせる(ベンジャミンはドビュッシーを敬愛していたメシアンの弟子であり、彼自身『ペレアス』の指揮も手がけている)。また、残る2人の天使も、物語の途中でアニエスの姉マリアとその夫ヨハネを演じる。
オーケストラはステージ上に配置。今回、歌手は衣裳をつけメイクも施した上で演技も行うもので、一種の「セミ・ステージ形式」での上演といっていいだろう。歌手が演じる場所は、舞台前方、指揮者の両サイドのスペースと、オーケストラの後方に設けられた白いデッキ。登場人物のうち天使たちはデッキ上におり、プロテクターとその妻アニエス、少年は舞台前方にいるので、デッキが天界、舞台上が現世という捉え方もできる。少年に変身する第1の天使を演じたのはカウンターテナーの藤木大地。ある種「性を超越した」声はこの役にぴったり。アニエスと関係を持ったためにプロテクターに殺されてしまう少年の複雑な内面を、藤木は繊細な表現力で見事に表現していた。藤木だけでなく、出演した歌手陣のパフォーマンスは、総じてクオリティが高かったと思う。特に、本番の1週間前に第3の天使/ヨハネに代役として抜擢された村上公太の熱演には拍手を送りたい。
大野指揮の都響の演奏も含め、音楽の説得力が強かったのに対して、ではこのプロダクションが「オペラ」としてどうだったのか、と問われるとそこにはクエスチョンマークをつけざるを得ない。デッキ上には巨大なモニタが設置され、実際のプロヴァンスの森や古城などに鮮明に映し出す。さらにそこにプロテクター、アニエス、少年に当たる3人の人物が、歌手と同じ衣裳を身につけ顔には白いマスクをつけた姿で登場して、ストーリーに沿ったパントマイムを繰り広げる。針生康による映像自体はたいへんにクオリティの高いものだったと思うが、映像の雄弁さが舞台上で「声によって繰り広げられているドラマ」と有機的に繋がっていたとは思えない。よくできたPVか、ある種の短編フィルムのようだった(実際私が映像を見ながら思い出したのは、あるヴィジュアル系バンドによる、オール・フランス・ロケのミュージック・ヴィデオだった)。あれだけ映像に語らせるのであれば、歌手はむしろ衣裳をつけたり演技をせずに、オーケストラとともに演奏に徹したほうがよかったのではないだろうか。
オペラに映像を用いるのは今やありふれた手法だが、それはあくまでも「オペラ」を形作る要素でなければならないはずだ。「音楽」や「演技」や「美術」や「映像」といった個々の要素があるいは融合し、あるいは反発しながら有機的に結合して初めてそれは「オペラ」となる。たいへん残念なことながら、今回のプロダクションでは、映像と音楽とがそのように結びついていたとは思えなかった(ちなみに、随所でモニタの前で2人のダンサーが踊っていたが、これこそまったく音楽とも映像ともかみ合わず不要だった)。音楽は言うに及ばず、映像単体で見ても非常に高レベルであったにもかかわらず、なぜ「オペラ」として成立していなかったのかというと、おそらく総合的な演出が不在だったことに原因があるのではないだろうか(プログラムのどこを見ても「演出」というクレジットはなかった)。やはり「舞台上演」をするならば、しっかりとした方向性を持ってディレクトする存在が必要なのだろうし、もしそれができないのであれば、中途半端な演技などをつけず、いっそ普通の演奏会形式の方がよい。何しろ、音楽は存分に美しく、またドラマを喚起する力を持っていたのだから。
2019年8月29日、サントリーホール 大ホール。
皆様から頂戴したサポートは執筆のための取材費や資料費等にあてさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします!
