
私が愛したライター
臨場感と物語性
私が彼女(Nさん)を見つけたのは、「別冊宝島」というムック本でした。「別冊宝島」は、1990年代に出版されていたジャーナリズム系のシリーズ本です。
Nさんが綴る文章は、まるで当時全盛だった小室哲哉のポップスのようでした。流れるような滑らかな疾走感、小気味良いリズム感、踊りだしたくなる躍動感、平易な言葉なのに、示唆に富んだ物語性…。
私がNさんに連絡をとって、寄稿を依頼したのは「ワイアード」というIT系雑誌の編集をしていたときでした。
私はNさんなら、きっと私が思い描いていたストーリーを書いてくれると考えました。
私が記事を作るのに最も重視していたのは、その場にいるかのような「臨場感」と心を動かされる「物語性」です。
テーマは、「ITと危機管理」。震災やテロなどに直面したとき、現代のテクノロジーが果たす役割について考察したものでした。
取材先は危機管理会社、都庁、大手建設会社、そして実際にハイジャックテロに遭遇したパイロット。
ノンフィクションノベルの実現
私が「臨場感」と「物語性」を重視するようになったきっかけは、学生時代に触れたノンフィクションノベルでした。ノンフィクションノベルとは、フィクションではない、事実や事件をそのままに「小説」という形でまとめたジャンルを指します。米国の作家、トルーマン・カポーティが『冷血』で打ち出した手法として知られます。

その後、このスタイルは文学界の新しいジャンルとして浸透し、ゲイ・タリーズの『汝の父を敬え』や、トム・ウルフの『ザ・ライトスタッフ』、ジョン・ベレントの『真夜中のサバナ』などの名作が次々と生まれました。
日本では佐木隆三の『復讐するは我にあり』や、沢木耕太郎の『テロルの決算』、村上春樹の『アンダーグラウンド』などが有名です。
感動ドラマを生む群像劇
そして当時、私は「群像劇」にとても惹かれていました。映画『パルプ・フィクション』のような一見関係のない物語がバラバラに展開しながら、最後にすべてが一点に収束するという手法です。「グランドホテル方式」「アンサンブルプレイ」とも呼ばれます。
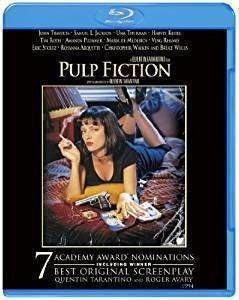
『パルプ・フィクション』は、アカデミー賞の7部門でノミネートされ、脚本賞を受賞。後にアカデミー賞3部門でノミネートされた『マグノリア』や、アカデミー賞作品賞を受賞した『クラッシュ』など、名作にはこの「群像劇」を用いた作品が多くあります。あの人気ドラマ『24』もこの手法を使っています。
「ITと危機管理」の記事では、導入でテロに遭遇したパイロットの様子を描き、そこから、危機管理会社(安全ボケしている日本)→都庁(災害時の対応策は万全か)→大手建設会社(公にできない危機)→パイロット(携帯電話の活躍)へつないでいきました。
Nさんが他のライターと特に違った点は2つありました。
ひとつは他のライターさんにはあまり勧められませんが、彼女は録音テープを一切使わなかったことです。私は何度も録音するように言ったのですが、「へへっ」と笑いながらも頑として使いませんでした。私は編集者の立場として心配なので、彼女の代わりにいつも録音していたのですが、結局録音データを聞き返すことはほとんどありませんでした。
なぜ録音しなかったのでしょうか? Nさんは臨場感と物語性を重視していたので、記録より記憶を信頼していたのだと理解していました。心に残った言葉だけを刻み込み、余分な情報をすべて削ぎ落とす作業を行っていたのです。
私はいまもライターさんには録音をしてもらうようにしてますし、私自身も保険的に必ず録音をしています。ただ、私自身、書き手になるときは、まずメモを頼りに骨子を作ります。
そして、完全なインタビュー形式のときはそこから録音データを聞きながら肉付けをしていきます。そうでないときは、なるべく録音に頼らずストーリーを組み立てるようにしています。そのほうが、より伝えたいメッセージの輪郭がはっきりするからです。
Nさんのもうひとつの特長は、取材後に書き始めると、毎日のように連絡をしてきたことです。どこでドラマを起こして、どこで驚かせて、どこで笑わせて、とこで泣かせて、と常に語り合い、展開を一緒に考えながら書いていくスタイルだったのです。
Nさんは締め切りに遅れることも多かったのですが、毎日のように連絡してくるので、掴まらないということはありませんでした。ライターが締め切り日に遅れる場合は、連絡がとれなくなることがほとんどです。しかし、Nさんは締め切り日になっても連絡してきて、相談してくるため、気づいたら私も締め切りに遅れる共犯にさせられていたのです(笑)。
「もう原稿はできてるけど、これじゃあ納得できないですよね(笑)?」とでも言いたげに。
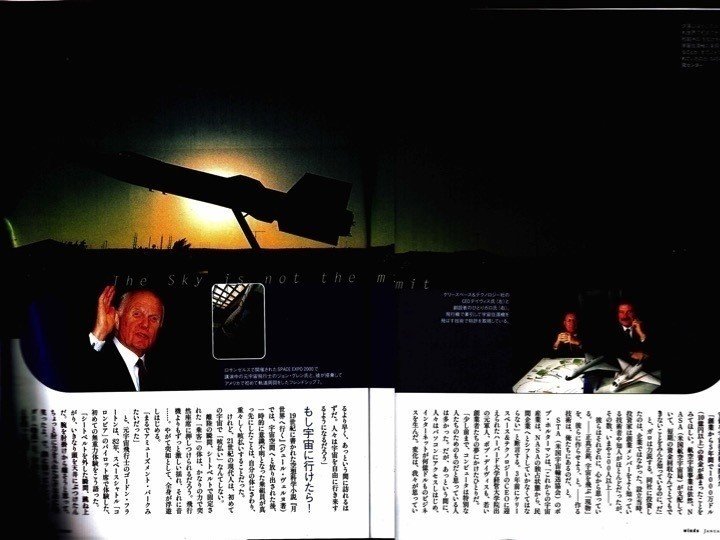
彼女は米国でMBAを修得後、ニューヨークのウォール街で働き、その体験を本にしてライターに転身した変わり種です。ライターという枠に収まらないタイプだったのか、Nさんは後にフランスに留学したり、歌舞伎の支援をしたり、映画監督をやったり…といまやライターに留まらない活躍をされています。
企画力と突破力
私が編集者として携わった「ワイアード」や、日本航空の機内誌「winds」は、米国での取材が結構多くありました。そんなときニューヨーク在住のライターのMさんは、ニューヨークでの私の目となり耳となり、足となってくれました。
直接ニューヨークへ行って彼女と一緒に取材することもありましたが、ほとんどはお任せで現地取材をしてもらっていました。
ニューヨークには他にも多くのライターがいましたが、私がMさんを最も頼りにしていたのは、どんな難題にも応えてくれる企画力と突破力があったからです。
たとえば、かつてブラッド・ピット主演の『セブン』という衝撃的な映画がありました。デビッド・フィンチャー監督の名を一躍有名にした作品です。私はこの映画の導入部分のタイトルシークエンスにとても衝撃を受け、調べてみました。そして、映画にはタイトルシークエンス専門のクリエイターがいて、『セブン』でこれを担当したのが、カイル・クーパーというモーション・グラフィック・デザイナーだと知ったのです。そこで私はMさんにカイル・クーパーを掴まえてほしい、と依頼しました。するとどういうルートを辿ったのかわかりませんが、あっさりインタビューにこぎつけてくれ、驚いたのを覚えています。

これに気をよくした私は、日本から依頼するのは難しそうな米国の著名作家、映画監督、スポーツ選手など、まるで魔法の杖を持っているかのように、私が希望する人たちを掴まえて取材してくれました。ベストセラー作家のジェイムズ・エルロイ、トム・クランシー、CNNキャスターのラリー・キング、映画監督のデヴィッド・リンチなど、錚々たる面々に取材できた(それもプロモーション扱いですべてノーギャラ!)ことは、本当に編集者冥利に尽きました。
もちろんニューヨークをテーマにした企画でもいつも頼りにしていました。

日本航空にとってニューヨーク線はドル箱ラインなので、機内誌では毎年2回ニューヨーク特集を組んでいました。その中で私が特にお気に入りだった企画は「ニューヨークの贈り物」。映画『三十四丁目の奇蹟』や『素晴らしき哉、人生』、あるいはO・ヘンリーの『賢者の贈り物』のようなほろりとくる物語を紹介してみたいと考えました。そこでニューヨークで活躍するセレブたちに生涯忘れない贈り物について語ってもらう企画を立てました。ニューヨークの名物ニュースキャスター、一流レストランの有名シェフ、ブロードウェイのプロデューサーなど、現地では知る人ぞ知るセレブたちに、ほろりとくるクリスマスギフトのエピソードを語ってもらったのです。そして、そこにクリスマスに関するアメリカの有名な詩や小説の一節を紹介しながら、アメリカ人にとってクリスマスが持つ意味について探ったのです。
Mさんは、いまはニューヨークで舞台劇の劇作家として活躍しておられます。
リアリティとユーモア
海外取材でよく組んでいたライターのひとりにイギリス人のKさんがいました。私は彼のイギリス人特有のユーモアセンスがとても好きで、彼のキャラクターを生かして何かできないかと考えました。
そこで彼に「舞台裏体験シリーズ」と題し、ちょっ突撃体験レポートを書いてもらうことにしました。これも私が探求していたノンフィクションノベルのひとつの形です。
ふだん旅行では馴染みがなさそうなテーマを通して、クスっと笑ってもらって、その土地の文化を奥深く知ってもらいたいという思いからです。
たとえばロンドンのボディガード養成学校。ロンドンと言えば近衛兵が有名ですが、近衛兵の発展形でもあるボディガードが、イギリス人にとってどんな存在なのか。私たちがふだん接することのないボディガードですが、ボディガード養成学校で痛い目に遭いながら、厳しい訓練を体験してもらいました。そして、ボディガードという仕事の社会的ポジションや、イギリス人の安全に対する考え方を伝えました。

あるいはモスクワのサーカス学校に1日体験入学。モスクワは、サーカスのメッカです。サーカスを観るだけでなく、サーカス学校で平均台から何度も落ち痛い目に遭いながら、その訓練の厳しさを体験してもらいました。またプロのサーカス団員たちにインタビューをして、彼らがどうやってあのようなアクロバットな技を身につけてきたのか、またサーカスという仕事への誇りを語ってもらうことで、サーカスの魅力に迫りました。
そして、トンガ相撲。トンガという南太平洋に浮かぶ小さな島国で、なぜ相撲が根づいているのか。日本での活躍を夢見て日々練習に励む若き力士たちの稽古に参加し、巨漢の力士に投げ飛ばされ痛い目に遭いながら彼らと交流し、トンガという国がいかに日本と文化的に深く交流がある国であるかを伝えました。

Kさんはオックスフォード大学で文学を学び、「シェイクスピアが嫌い!」と言いながらシェイクスピアの有名な一節を丸暗記していたのがとても印象的でした。いまは母国イギリスに帰国して、雑誌の編集者として活躍しているそうです。
体験に新しい価値を与える
私は取材の醍醐味は、その土地や人びとと触れ合い、彼らの文化や思想を知ることだと思っています。それをコンテンツを通じて、読者に一生の思い出に残る追体験をしてもらいたいと考えていました。そして、追体験を楽しむことで、その価値を生んだコンテンツと、発信者に信頼を寄せてくれることを期待していたのです。
*********
臨場感の演出と物語性の構築に長けたNさん。打ち出の小槌のように意外性に満ちた企画力と突破力でいつも助けてくれたMさん。そしてユーモアを織り交ぜながら、カラダを張ってリアリティ溢れるストーリーを生み出してくれたKさん。
私が愛したライターさんたちは、それぞれ個性もスタイルも違います。彼らに共通するには、読者の心を動かすコンテンツを作りたい!という熱い思いです。そして、最初の読者である私を、いつも熱く興奮させてくれたのです。
ということで熱いライターさん、絶賛募集中です!
ご連絡はこちらへ
↓
narita.yukihisa@gmail.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
