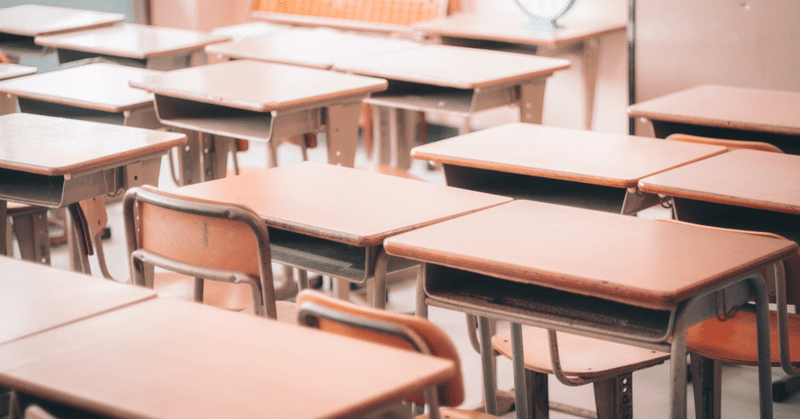
校長室通信HAPPINESS「体罰の大罪」
「体罰」は教師の暴徒です。絶対にあってはならない行為なのに、教師による体罰は後を絶ちません。今回はそんな体罰についての考え方をまとめてみます(ここで言う「体罰」には、暴言、脅し、恫喝など、教師によるすべての「威圧的指導」を含めます)。
体罰がなくならない理由は、実ははっきりしてるんです。この国にある、「子どもは時々ゴツンとやるほうがしっかり育つもんだよ」という「体罰肯定論」が、子育ての考え方の根っこにあるからです。特に部活動やスポーツの世界は深刻で、この考え方が武勇伝として語り継がれています。「あの時の先生のげんこつがあるから、今の自分がある」「あの先生の体罰が自分の心を強くしてくれた」と、自分の体罰体験を胸を張って語る人が結構います(中高年に多い)。これは「生存者バイアス」です。実は体罰が心を強くしたんじゃなくて、もともと体罰に耐えられるだけの環境があっただけなんです。それなのにこの「体罰肯定論」を真に受けて、「これは愛のムチだ」と堂々と体罰を繰り返す教師がいる。勘違いしてはいけません。「体罰」は感情的な行為です。一見、理性的な行為と思われる「愛のムチ」は、暴力の免罪符として後から付け加えられているだけ。それを大上段に振りかざして、明らかに自分より力が劣っている幼い子どもに、「お前のためだ」と言って暴力をふるう…こんなことをしておきながら、教師は「いじめはダメです」と声高に叫ぶのです。子どもたちはたまったもんじゃありません。
体罰は「百害あって一利なし」です。体罰が与える悪影響は数えきれないほどありますが、その中で、あえて2つだけ挙げておきます。
ひとつは、「差別の容認」です。人間社会は、「自分以外の他者が、豊かで自由に生きていくことを最大限に尊重する」という、一人一人の「他者に向けた敬意の心」から成り立っています。これが「リスペクト・アザース」です。「リスペクト・アザース」の精神が軽んじられたら、世界のいたるところで差別が起きます。そしてそれは、その先にある「戦争・殺し合い」にまで繋がっていきます。だから教師は、どんなことを差し置いても「リスペクト・アザース」の精神を子どもたちに染み込ませ、世の中の平和を維持しなければなりません。しかし体罰での支配は、それとは真逆です。体罰を目撃した子どもは、「世の中には敬意を払う必要のない人間もいるんだ」という差別意識を知らず知らずに植え付けられてしまいます。
もうひとつは、「心理的な悪影響」です。こんな実験があります。2匹のネズミに電気ショックを与えます。Aのケージは暴れているネズミが偶然でもレバーに触れると電気ショックがおさまるしくみです。Bのゲージはどんなに暴れても、ひたすら電気が流れ続けます。Aのネズミは、暴れているうちに偶然レバーに触れて電気ショックが止まるという経験を何回かするので、電気ショックがあってもあきらめずに激しく暴れます。しかしBのネズミは、どんなに暴れても電気ショックが止まらないので、そのうち動かなくなってしまいます。人も含めた生命体は、避けることができない痛みを伴う刺激を繰り返し受けると、やがて避けるのをあきらめて、ただただ耐えようとする傾向があります。このときの心理状態を、アメリカの心理学者セリグマンは「学習性無力感」と呼びました。教師の体罰を繰り返し受けている子どもは「学習性無力感」の状態になり、「とにかくじっとしていよう」という精神状態になります。恐ろしいのは、その無力感により、やがて「死」を選択してしまう可能性があることです。
「子どもたちを威圧せずに教育する」ことを「理想論だ」と否定する人もいます。でも我々教師は、子どもたちの未来を守るために、理想を語り続けなければなりません。「子どもたちが間違えても、暴力ではなく、心に落とし込めるような話で正していこう」…教師にはそんな決意が必要なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
