
鳥は空に、魚は海に、人は社会に
『津久井やまゆり園事件』。
2016年7月26日、入所者19人が殺害され、27人が重軽傷を負ったこの事件で被告は、意思疎通を図ることのできない障害者を「心失(しんしつ)者」とし、「障害者は不幸を作ることしかできない」「意思疎通を取れない人間を安楽死させるべき」と主張した。
命の価値が大きく揺さぶられる事件だった。
命の重さは、あらゆる人において平等なのか。
折に触れて、このことについて考える。
『津久井やまゆり園事件』の後、わたしが命の価値について深く考えることとなったのは、その約1年後だった。
訪問介護ヘルパーとしてメンバー登録していたACTでの『コーディネーター養成講座 障害を持つ人への理解と地域支援のあり方』を聴講した時のこと。講師は、自立生活センターHANDS世田谷 理事長の横山 晃久さんだった。
横山さんは、脳性麻痺で四肢に不自由があり車イスを利用している身体障害者である。
世田谷区という地域は、光明養護学校という日本で最初の養護学校があるところ。昔は、重い障害者は通学することが困難ということもあり、「就学猶予」といった形で、義務教育の対象から外されていた。(これも権利を剥奪された、障害者差別だ、と横山さんははっきりと意見を述べた。)
それでも、せめて教育だけでも人並みに受けさせてやりたいと情熱を持った親たちが、学校に通わせるために家族ごと引っ越してきて集まったために、他の地域と比べて障害を持つ方々が多く住んでいる地域になったという。
そして、横山さんも同じ思いで世田谷に引っ越してきたひとりだ。
障害を抱えて生きるということ。
これまで重度身体障害者がどのように扱われてきたか。
入所していた施設での、人間としての尊厳を損なわれた経験。
そして、自立生活を望み、実現に向けて苦労を重ねてきたこと。
時に、怒りの涙をにじませながら語った横山さんの姿が今でも目に焼き付く。
お話の中で特に印象的だったのは、家に引きこもっている身体障害者を訪ねては、自立生活を薦めて回ったこと、「自立なんて無理だ」と最初から諦めている施設入所者を鼓舞する言葉を掛けつづけたこと。そういうエピソードだ。
1990年に 自立生活センターHANDS世田谷は設立された。
重度の障害があるからといって、自立生活を望んではいけないなんておかしいのではないか。自立生活を望み、選択できる仕組みをつくっていくことが必要なのではないか。
そんな「あたりまえ」がかつてはなかった。
人の命の重さについて、はっきりと優劣が付けられていた時代が確かにあった。尊重されるべき人権に格差があったという事実が胸に重くのしかかる。
命の重さは、あらゆる人において平等なのか。
決して忘れてはならない問いとして、このことについて深く考えるきっかけは、やってくる。
そして、今現在においてもその「あたりまえ」は完全ではない。
自立生活センターHANDS世田谷と同じく、全国自立生活センター協議会(JIL)に加盟している、NPO自立生活センター グッドライフとNPO自立生活企画が登場するドキュメンタリー映画がある。
『道草 みちくさ』
2018年/監督・撮影・編集 宍戸 大裕
今年の3月にはじめて鑑賞し、不思議な衝撃を受けた。
こんなふうに自立生活を営む重度知的障害者がいること、そしてその生活を支える介護者の姿とその支援に。
そして先日、縁あって二度目の鑑賞となった。
場所は、映画の舞台である練馬区。
映画の主人公である知的障害を持つ彼らが暮らすこの練馬区で、どうしても『道草』の自主上映を行ないたいという人々の願いと努力で、それは実現した。

わたしは、友人の紹介でこの自主上映会を主催する生命倫理カフェねりまの代表、森本 陽子さんと出会い、上映会当日のボランティアをさせてもらえることになった。
「ぜひ、物語の主人公である彼らが暮らす練馬で上映を」という同じ想いを持った「ちぃねり」(地域をつくる上映会 in 練馬)の共催のもと、上映会は満員御礼の大成功。観客の中には、保護者の付き添いを得て訪れた自閉症児や知的障害を持つ当事者の姿も多く見られた。
スクリーンに映し出される知的障害を持つ彼らと介護者のユーモラスなやりとり。そんな場面で、当事者の彼らも手をたたいたり、声を出したり、笑ったりと豊かなリアクションがあって、会場には終始あたたかい空気が流れていたように思う。
映画上映後のシンポジウムでは、映画に登場したヒロムくんのお母様、桑田 貴江子さんがパネリストとして登壇された。
「自立生活、それから、これから」。
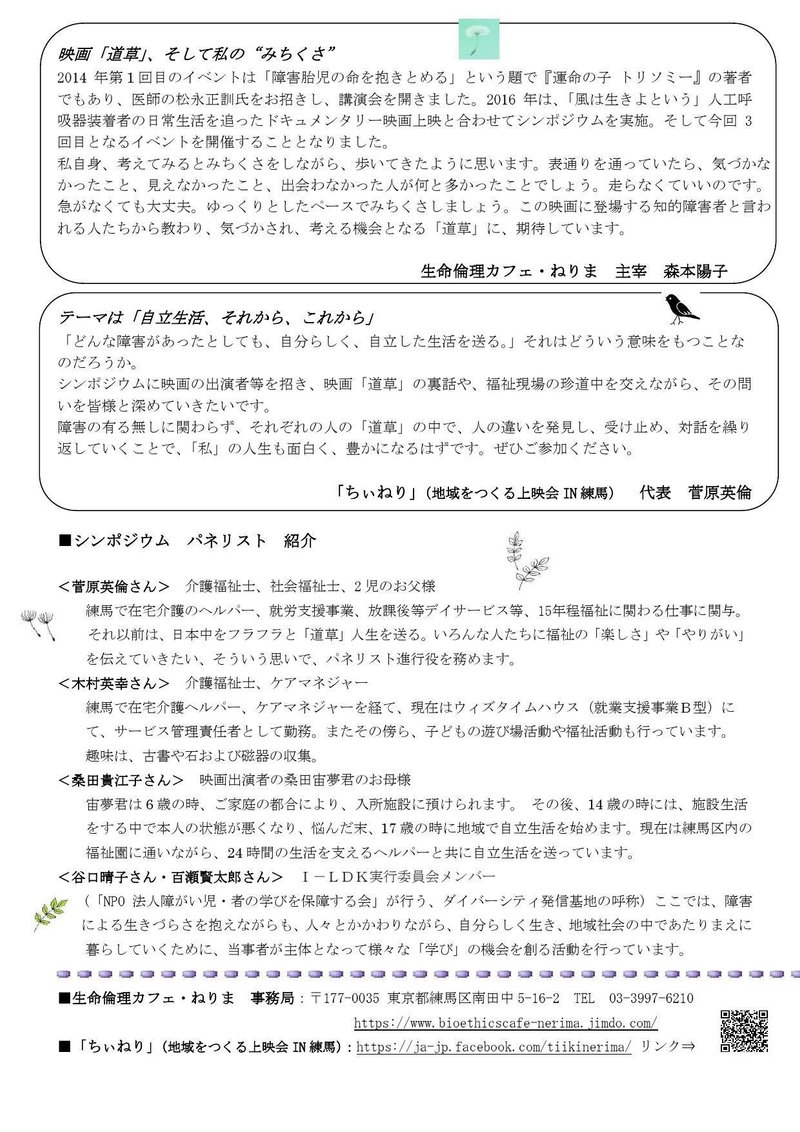
わたしは、この上映会の前に『道草』のパンフレットをもう一度読み返してみた。そこで、はっとした言葉がある。
それは、宍戸監督のプロダクションノートに綴られている社会なんてないという言葉。知的障害を持つ人の保護者が発した言葉だ。
「“社会が助ける”っていうのやめませんか?社会なんてないですよそんなの。」
『津久井やまゆり園事件』から1年後の追悼集会での、岡部 耕典さんの発言。岡部さんは『道草』に出演するリョースケの父親だ。
同じく映画に出演するオノ カズヤさんの父、尾野 剛志さんは、その追悼集会で施設批判派の参加者の発言に対し、その反発を一身に背負い、施設を擁護する立場をつらぬいた。
(オノ カズヤさんは事件に巻き込まれ、当初心肺停止状態だったが、一命をとりとめた。その後、自立生活に向けて歩みだす姿が映画に収められている。)
そこに居合わせた宍戸監督が、そんな尾野さんの姿に「親の苦労に対する無理解」「苦労を背負わせた世間ではなく親に向けられる批判」それらへの憤りと、子を施設に預けたという後ろめたさ、それがないまぜになった痛々しさを感じていた時に、手を挙げて発言したのが岡部さんだった。
「尾野さんは“誰も助けてくれる人がいない”って言ってる訳ですよ。“自分はリアリティ感じられない”って言ってる訳ですよ。もっと自分が引き受ける、自分が一緒に生きていこうってなんで言わないのか、そういう言い方じゃないと僕は全然南風にならないと思うんですよね、言ってることが。」
岡部さんのこの発言を聞き、宍戸監督が思い出していたのは、14年の夏から1年半、撮影をした知的障害者入所施設、さやま園でのことだった。
「施設やグループホームを一生懸命作るのは親のエゴなんじゃないですか?そんな場を作らなくったって社会が助けてくれるじゃないですか」と問いかけた宍戸監督に対して、保護者のひとりが憤然として返した言葉。
「………“社会が助けてくれる”なんて………、そんな社会なんてどこにあるんだよ!親は今なんだよ。助けてくれる“社会”なんてものがあるなら今ここに連れてこいよ!」
“助けてくれる社会”なんてものはない。
今、目の前で困っている人に手を差し伸べることのできるのは、“社会”なんてものではなく、間違いなくわたしたち一人ひとりだ。
目の前の状況に気付いている一人ひとりの人間だ。
大きな“社会”を批判すること、理想の“社会”を語ることは容易い。
ただ、目の前の自分が“社会”を構成するひとりだという自覚、“自分が引き受ける”という覚悟のない批判や意見は、今まさに救いを求めている人にとってまったくの無味乾燥だ。
リアリティがない。
そう、“社会”なんてものはなく、ただ一人ひとりのわたしたちがいるだけだ。ただ、ひとりのわたしがどうするか、そういう問題なのだ。
社会なんてない
パンフレットの中のこんな言葉と、今回の上映会シンポジウムでの議論にリンクするところがあった。
それは、ヒロムくんの母、桑田さんのこんな発言だ。
「入所施設から自立生活への協力はまったく得られませんでした。施設にいてもそんな情報はなかったです。それで、施設勤務も辞めました。」
「とにかく、周囲の無理解が辛かったです。区の担当職員さんは、障害者と接したことがまったくないというような人ばかりで………」
何とか自立生活を支援してくれる事業所と出会え、それからはすんなりと新しい生活をスタートすることができたのだそう。
そして、「相性の合わないヘルパーさんもいたのでは?」という参加者からの質問に「代表の方がとっても目利きなようで(笑)息子にぴったりなヘルパーさんを派遣して下さり、今までに相性が合わなかったという方はひとりもいません。」と回答された。
ここにもやはり、社会なんてないということが感じられる。
ただ目の前の人間が、手を差し伸べたかどうか。
“社会”が、“制度”が救ってくれるのではなく、実際は一人ひとりの人間の想いと行動、関わり合いが人を救っていくのだと思う。
結局は、人と人、人間同士の関わり合い。
それゆえに、支援のあり方に定型はない。『道草』に登場する彼らと介護者、ふたりの関係からそれがじんわりとにじみ出てくるのが感じられる。
この、支援のあり方について、シンポジウム進行役を務める菅原 英倫さん、そしてパネリストの木村 英幸さんの意見を聞くことができた。
お二人とも介護福祉士であり、長年にわたり介護職に携わってきた方々である。
木村さんの勤務するウイズタイム(就業支援事業B型)では、「一緒に困って一緒にやる」というスタイルなのだそうだ。解消しようとか治療していくとかではなく、「付き合いつづける」という気持ちで関わりを持つ。
一方、菅原さんのお話で気になったのは、シュークリームをつぶしてしまう子のエピソードだ。
いつも寄るコンビニで、大好きなシュークリームを見つけるとつぶしてしまう。5個置いてあれば、5個全部つぶす。
そして、つぶした当の本人もつぶれたシュークリームは食べたくないようで、残念そうにしている。
そんなことがつづき、いつものコンビニでも顔を覚えられた。そして、店頭のシュークリームはひとつだけになった。店員さんの苦肉の策である。
そうこうしているうちに、そのひとつのシュークリームをつぶすことなく大事に食べるようになったのだという。
地域に暮らすことは、こんなふうに当事者と介護者という関係性の範囲で収まるものではなく、地域の人々との関係も大きいというお話だった。
わたしはお話を聞きながら、少しだけ違うことを考えていた。
適応ということについて。
支援のあり方に定型はない。
もちろん、倫理的に問題のあることや当事者を危険にさらすことはあってはならないとして。
支援は、人と人との関わり合いである以上、両者の個性があり、ニーズがあり、その時々の状況もある。
では、“いい支援”とは何だろうか。
そんなことを考えていた。自分なりに出した答えは、
基準を「当事者のしあわせ」に置くことだ。
シュークリームの子は、シュークリームが食べたいのにつぶしてしまって、食べられなくしてしまっていたのかもしれない。
シュークリームがつぶれることは「ふしあわせ」だ。
それならば、「つぶさずに食べられるように」修正できた、その支援は“いい支援”ということになる。(「食べ物を粗末にしない」という道徳的観念からも成功だ。)
そして、きっとこれはシュークリームに限らず、ずっとついてまわることなのだ。当事者が「しあわせ」と思うところにたどり着けること。
そのニーズをくみ取り、一枚一枚障壁をはがしていくことができたなら。
適応していくことが、本人の「しあわせ」につながっているか、それを注意深く見ていて伴走していくのが介護者だ。
人間同士、ぶつかることもある。
間違うことだってある。
だけど、せめぎ合いながらもお互いを深く見ている。
並んで歩く。
『道草』するふたりを見ていて、何か胸にあたたかいものがこみ上げてくるのは、不器用でも分かり合おうとするふたりの気持ちが伝わってくるからなのかもしれない。
あぁ、これは、自立生活を目指す自閉症や重度知的障害者のためだけの物語ではないな、そう思った。
「生きづらさ」という言葉をあちこちで見かけるようになり、すっかり浸透している現状を複雑な想いで受け止める。
それだけ「生きづらさ」を抱える人が多いのだろう、と思うと。
『道草』するふたりの映像は、「生きづらさ」を抱えるすべての人の胸に、“「生きづらさ」とともに生きる姿”として何かを刻むのではないだろうか。
「生きづらさ」を解消していくことの始まりは、権利の主張ではない気がする。
『道草』するふたりのように、不器用に距離を測りながら、ぶつかりながらお互いを知って、自分が求める「しあわせ」を知っていくこと。
きっと、そんなことから始まるのではないのか。
社会に適応していくのか、適応できる場をつくるのか。
そんな二者択一ではなく、実はその双方が歩み寄っていくことが大事なんじゃないかと思う。
適応ということについて考えていた時、また別の形で障害者の自立生活を描いたドキュメンタリー映画のことを思い出した。
『アラヤシキの住人たち』
2015年/監督 本橋 成一/プロデューサー 大槻貴宏
撮影 一之瀬正史/編集 石川翔平
二年前にこの映画を観た感想を綴っている。
ワーカーズの先輩のお勧めで
『アラヤシキの住人たち』の上映会にきました。
『アラヤシキ』といっても
「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の
『阿頼耶識システム』
とは関係ないようです( ´,_ゝ`)w
しかし、大乗仏教の用語である
『阿頼耶識』の〝ものごとの根源〟
というような意味は
この映画に垣間見える〝人間の根源的な生きる力〟に重なる部分もあります。
監督の本橋成一さんも後からこれに気付き、
「なんだか、すごいタイトルになったなぁ」と語っています。
これは、長野県小谷村にある真木共働学舎での
春からまたその次の春までの〝何の変哲もない〟一年を追っただけのドキュメントです。
ですが、真木での生活やそこで暮らす人々は
私たちの思う〝ふつう〟とは掛け離れ過ぎていて
〝何の変哲もない〟ことは全くなく、
全てがまるで時代を遡ったかのように原始的で
登場人物たちも個性的な役者が自然体の演技を見せているようかのようにドラマティックなのです。
山羊や鶏、犬に猫、茅葺きのひとつ屋根の下に暮らすいわゆる〝変な〟おじさんやコミュ障の若者、現代社会において肉体的・精神的な生きづらさを抱える人々。
無駄なものを極限まで削ぎ落とした、
『生きる』ことを浮き彫りにさせる生活は
自分のやるべきことと、
それぞれのできることをシンプルに洗い出します。
社会や環境に適応するため、
自身を変えることを学んできた私たちには
思い及ばなかった世界がそこには広がっていました。(2017.8.26)
社会に適応していくのか、適応できる場をつくるのか。
はっきりとした二択ではなく、そこにはグラデーションがある。
どちらが正解かといった答えはなく、あるとしたら「当事者のしあわせ」に基づいているか、そこに向かうために選べた道か。
『道草』に見る地域での自立生活も、『アラヤシキの住人たち』に見るいわゆる一般社会から一歩引いた自立生活も、大きくは真逆のようで、実は当事者にとってみれば、向き合っているものに違いはないのかもしれない。
それぞれの「しあわせの基準」は、社会にあるのではない。
それは自分の中にしか見つけられない。
ただ、そのしあわせに向かう選択肢が社会にないのだったら、それは社会の責任だ。
わたしたちは、誰でもしあわせになっていいし、その道を選んでいいはずなのだから。
タイトルの「鳥は空に、魚は海に、人は社会に」。
これは、1970年代初めに東京都府中療育センターで暮らす重度障害を持つ人たちが、施設から出たいと訴えて都庁前で座り込みをした時のスローガンだ。フリージャーナリストの佐藤 幹夫さんが、映画パンフレットに寄せた記事に引用したものである。
人が、息を吸える場所。それは、やはり社会なのだ。
社会とは、目の前のわたしとあなたのつながりであり、助け合う関係性だと思う。人は、決して分断・孤立されるものではなく、人の中で生きていく存在だ。
「人間は社会的動物である」とは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉として有名だ。
アリストテレスの著書『政治学』において、正確には「人間は、Zoon politikon(ポリス的動物)である」と述べられている。アリストテレスは、2300年も前に「人間は、自己の自然本性の完成をめざして努力しつつ、ポリス的共同体(善く生きることを目指す人同士の共同体)をつくることで完成に至る」と説いたのである。
社会制度や社会構造は時代とともに変化しても、原始時代から現在にいたるまで、人間は一人では生きていけない存在だ。
その基本的なあり方は変わらない。
社会がどんな存在も分断・孤立させないものだとしたら、そこは多様な存在が相互に複雑な関係性をつくる場となる。
だからこそ、相互に理解し合うことが求められるし、秩序を保つためのルールがうまれる。
適応していくことは、社会においてポリス的共同体をつくる上での必要条件を満たしていくことなのかもしれない。
そして、社会形成の大前提が「善く生きることを目指す」ものならば、「個」一人ひとりを起点として、その適応には幅があってもいいのかもしれない。社会システムに合わせて人がつくられるのではなく、本来は人があり、その人が「善く生きる」ために社会システムがつくられたのでなかったか。
NPO 障がい児・者の学びを保証する会がつくるダイバーシティ発信基地 i-LDKは、まさに安心できる居場所と社会の中間なのかもしれない。
パネリストのロージーちゃん、ケンタロウさんが素直な言葉で語ったi-LDKの魅力はきっと本物だ。
一人ひとり違う、ということを事実として前向きに捉え、それぞれの「生きづらさ」を軽くしていける場所は、少しずつ増えている。
自分らしさを大切にできて、社会と人と関わり合いながらゆっくりと学べる場所。居心地を確かめながら、時に我慢したり慣れたりも必要。
その都度、本当に望むものを知っていく。
人との関わり合いの中で、自分らしさもあなたらしさも大切にできるようになる。それが、「善く生きる」ために必要な適応だ。
葛藤もあるけれど、乗り越えたその先に居心地の良い関係性を手に入れる瞬間があるのかもしれない。
大きなストレスを乗り越えた達成感は、困難の先に待っているもののために自ら壁に向かっていかなければ得られない。
「ユウイチローさん、100点?」
その表情が、すべてを伝えてくれる。(1:09)
介護者の藤原さんが口にした疑問。
「なぜ、こういう人たちはこの世界に必ずいるんだろうっていうのはいつも思っていて。僕は何か意味があるんじゃないかって思うんですよね。どうですかね?」(0:26)
このシーンを観た時には、本当にびっくりした。
わたしもずっとそんなことを考えていたし、その答えを見つけたいと思っている。
この世界に生まれたからには、
その存在を否定されるものなどない。
社会を構成する一人ひとりが、
その一人ひとりの持つ「しあわせの基準」においてしあわせであること。
そこに向かう道を選択できること。
そんな社会こそ、“こうだったらいい”社会だと思う。
どんな存在も、生まれた瞬間に価値を携えている。
生きているだけで、その役割において価値がある存在だ。
そう言いたい。
論理的根拠はまだない。
見つからない可能性だってあるけど、
これが今のわたしの精一杯の答えだ。
社会が何かをしてくれるのではない。
社会を構成する一人ひとりの想いが社会となって、そのひとりが手を差しだす。
その手を掴む人がいて、わたしたちはつながっていく。
そう、とりあえず、「わかる人」からつながっていくしかない。
そして、それをどう広げていくかという話なのだ。
究極的にシンプルにしてしまえば、「気付くか、気付かないか」。
そして、「やるか、やらないか」なんじゃないかと思う。
「人間は、自己の自然本性の完成をめざして努力しつつ、ポリス的共同体(善く生きることを目指す人同士の共同体)をつくることで完成に至る」
自己の自然本性の完成、それはつまり「しあわせ」を求めるということではないか。
経済学における合理的選択理論、「個人利益の最大化」の行動原理をとってみても、つまりは「しあわせ」が人間の最大の目的であるとは言えないだろうか。
それならば、ただ“利”を求めればいい。
他人に“不利”を押し付けない方法で、みんなが“利”を求めればいい。
人と人は、助け合いこそすれ、足を引っ張り合ったり、他人を貶めることで自分の価値をあげたりするものではない。
それこそ生産性の欠片もない。
咲き誇る花のように、揺れる草木のように、ただそこに生きて時に安らぎを与えてくれる重度障害者を思う時、生産性の所在はどちらに多くあるか。
生産性や比較など持ちだしたくはないけれど、そこに「気付き」があるのなら、考えてみる意義はあるのかもしれない。
わたしだって、このままならただ“社会”という大きなものに「こうだったらいいな」という理想を描いただけになってしまう。
そこにリアリティはない。
ただ、わたしは気付いているひとりだ。
手を伸ばそう。
目の前の手を掴むことから
“こうだったらいい”社会は、はじまっていく。
そうか、わたしのやりたいことははじめからこれだった。
みなさまからのサポートは、クリエイター支援のために使わせていただきます。

