
これからの開発教育の展開を考える 金谷敏郎(1983年)
DEAR設立時のメンバーのおひとりの金谷敏郎さん(国立教育研究所
アジア地域教育協力室室長・当時)が、去る4月に逝去されました。「Development Education」という英語を「開発教育」と翻訳された経緯や思い、立ち上がったばかりの「開発教育協議会(DEAR前身)」に寄せる期待などが、機関誌『開発教育』創刊号(1983年5月)に寄稿されています。
36年前の当時、金谷さんが示してくださった「実践事例の収集と分析」「調査研究」「教材開発」「人材育成」は今もDEARの主要な事業として実施、継続されています。
金谷さんの切り拓いてくださったこと、そして、開発教育への貢献に感謝し、本稿を掲載いたします。
開発教育協議会が発行する機関誌の創刊号に執筆の機会が与えられたので、開発教育の今後の展開について考えるところをいくつか提示し、ご批判を仰ぎたい。これからの展開を考える前提として開発教育そのものについて考えることから始める。
1.開発教育そのものについて
<用語>
開発教育を一つの教育活動として理解したい、と私は考えている。教育として理解するところから、「開発」という用語に対するこだわりが生まれる。開発ということばは、国土開発、経済開発、開発援助、開発協力、などという使い方をされることが多く、つまり、これらの場合、開発ということばが経済活動の文脈の中で理解されているからである。
1980年の国連総会では「開発の過程は、人間の尊厳を高めるものでなければならない。開発の最終目的は、すべての人々が開発に十全に参加し、そのことによって、すべての人々を、常に、より幸せにしていくことにある」と規定し、開発は経済だけではなく、社会や文化を含む人間の価値観そのものまで含むのであることを示している。
また、1982年7月の第2回世界文化政策会議における「文化政策に関するメキシコ宣言」でも「文化は、国の独立、主権及び独自性を確立するのに貢献する開発・発展プロセスの基本的な部分を構成する。(中略)開発・発展に人間性を与えることが不可欠であり、その究極の目標とするところは人間存在の個人としての尊厳と社会的責任でなければならない」としている。
にもかかわらず、それでもやはり日本語の慣用としての「開発」という語感に私はこだわりを覚える。だから、別のいいまわし、たとえば開発問題学習とか、国際理解教育の今日的課題とか、あるいはグローバル・エデュケーション、国際教育、などといういいかたをしてみたりもする。これが「開発」のほうに力点をおいて、開発教育をとらえると、少し感じかたが異なるかもしれないというふうにも考える。
そういうふうに開発教育という語感になじみ切れないものがあっても、国際的にはDevelopment Educationという表現が、ある程度の市民権を得てきているので、その直訳である開発教育を用いたほうがいいのかもしれない。また1974年以降、国内においても折にふれて開発教育ということばが使われ、特にこの一両年には、開発教育ということばを共通理解する人びとの輪が少し広がってきているという感じをもつので、このまま「開発教育」といい続けてみようという気持ちになっている。
英語の表現との関連でいうと、Development Educationと、Developmental StudiesあるいはEducation for Development といういくつかのことばと、その意味するところの違いの問題が一方にはある。Development Educationを開発教育とおきかえる場合には、Developmental Studiesは「開発教育」とか「開発に関する研究」とおきかえたいし、その次のEducation for Development は「開発のための教育」とでも訳しておきたい。ところが、これらの用語がすべて開発教育とされている。あるいは開発教育と同じであると考えられていることに気づかされることがある。
したがって、開発教育といっても、工業国における教育活動であり、発展途上国における教育活動ではなく、さらに開発そのものについての教育研究ではない、というふうに限定しておきたい。
<目標>
これを教育と考えることから、開発教育の狙いが明らかになってこよう。いうまでもなく、教育は、その営みの主体と客体、それぞれの生きかたに関わってくる。したがって、開発教育は人間の生きかたに関わる教育活動である、と考えておきたい。
人間の生きかたをとらえるには、さまざまな視点がある。身体的健康という視点で生きかたをとらえることもあるし、社会性という視点で生きかたを考えることもある。開発教育は、開発問題という視点から人間の生きかたに関わる教育活動と考えたい。
1974年のユネスコ総会では「国際理解、国際協力、国際平和のための教育並びに人種及び基本的自由についての教育に関する勧告」の中で、人類主要問題の研究としていくつかの課題領域をあげて、それらを教育にとりあげることを求めたが、たとえばそのひとつ、
d.) 経済成長、社会開発及びこの両者の社会正義に対する関係。植民地主義と非植民地化。開発途上にある国への援助の方法と手段。文盲根絶の戦い。病気と餓死の防止運動。生活の質の改善及び健康の水準を可能な限り高めるための戦い。人口増加及びこれに関連する諸問題
という視点で教育を考えてみたいのである。
一言つけ加えておくと、開発問題はここに引用した領域だけに限られているわけではない。文化、宗教、生活はもちろん、資源、汚染、国際機構や国際政治などまでも含む、幅広いものである。その開発問題を、高度に工業化された豊かな国と農業中心の開発度の低い貧しい国々、という対極構造を軸としてとらえ、対極構造の原因とその改革を考えさせ、改革のために参加する態度を養う、それが開発教育であるとしておこう。国連合同情報委員会は1975年に開発教育を、
開発教育の目標は、人々を自分が属する社会、国家そして世界全体の開発に参加できるようにすることである。この参加のためには、社会的、経済的、政治的諸問題の理解に基づく、地域的、国家的、国際的な状況についての厳しい自覚が必要である。開発教育は開発国、開発途上国それぞれにおける人権、人間の尊厳、自立、社会的正義の問題と結びついている。低開発の原因や開発の意味するものへの理解の促進、そして新しい国際経済秩序の確立の方法とも関連している
と規定している。「参加できるようにする」という具体性が少しひっかかるが、大筋としての開発教育の目標は、ここに記されているようなことだという合意は得られるだろう。
開発教育の目標はそのほかの期間や政府、個人によって、いくつも試みられている。それらに共通するのは、国連合同情報委員会の定義による「参加できるようになる」ほどの具体性はなくとも、いずれにおいても個人の態度の変容、行動様式の変化、生活様式の変化を求めている点である。生きかたに関わる教育活動であるせいだろう。
これらの目標を実践面に即して、わが国の現状を考えながら分析すれば、次のようになろう。すなわち、開発教育は、発展途上国の総合学習を導入部として、これらの国々が直面している諸問題、いわゆる低開発の諸様相と特にその原因を理解させ、そのうえに立って低開発の諸様相を克服し、人類社会の均質な発展をめざす態度を養う、ということになる。
<場>
開発教育の目標を一応、以上のように考えるとして、次は、それがどこで実践されるかということになる。当初から繰り返して述べているとおり、開発教育を教育活動としてとらえると、それは教育活動であるかぎり、意図的な営みであり、組織的、体系的に営まれるということが前提となる。したがって、キャンペーンや動員、行事などへの参加そのものを開発教育活動とみなすわけにはいかない。さまざまな狙いをもって組織されるキャンペーンや動員、あるいは行事は、それ自体として価値あるいは意味のあることではあるが、それらへの参加が即開発教育の実践とは考えたくない。体系的な開発教育活動展開の一環として、関連するキャンペーンや行事への参加が位置付けられなければならないと考える。
このようにとらえてみると、開発教育の場はおのずと明らかになるであろう。意図的、体系的に教育活動を営みうる学校教育及び学校外で行われる社会教育が、開発教育の場である。
学校教育の場合、幼稚園から高等学校さらには大学や専修学校など、すべての教育段階で開発教育の展開は可能であるし、なんらかの形での展開をはかってほしいと思う。だが、開発教育をひとつの、独立した学習領域として設定するのは、いくつかの理由によって非現実的な発想といわざるをえない。
ふつう、初等、中等教育段階だと、社会科教育あるいはクラブ活動、学校行事さらには学校裁量の時間(いわゆる、ゆとり時間)の活用が開発教育実践の場として連想されてくるだろう。しかし開発教育は、国際理解のための教育がそうであるように、特定の教科学習や活動のなかだけでとりあげるのではなく、学校内のすべての教育活動を通じて展開されなければならない、と考えたい。社会科学習あるいは学校裁量の時間における活動が核になることはあるにしても、他の教科学習における展開がこれを相互に補完しあい、児童生徒の開発問題に対する関心を刺激し、考えさせ、生きかたを変えさせていくことが必要だろう。
すべての教科学習が、音楽、美術、家庭科、あるいは算数や理科、英語や国語の学習活動においても、開発教育の実践に関わることができるし、それら他教科学習におけるかかわりを統合し、開発問題を体系的のとらえさせ、自己の生きかたを考えさせるのが社会科や学校裁量の時間における開発教育の機能だというようにとらえることができよう。
社会教育の場においても基本的には同じことが考えられる。しかし社会教育活動には、学校教育のような教育内容や方法の広がり(多くの教科学習やその他の教育活動という)がないし、かつ、常時的(週に5日も6日も継続してというような)に実践されているものではないので、開発教育のための社会教育活動という目的的な展開が多くなるだろう。
たとえば公民館などで開かれる開発教育関係講座などがそうである。しかしここでもまた、主催者が、たとえば青少年団体であったり、あるいは地域のさまざまな学習、余暇、趣味、市民活動などのグループだったりする場合には、その団体やグループのさまざまな活動や事業を総合的に開発教育にかかわらせて展開するという体系性が必要である。ある一時期に、ある場所でだけ開発教育活動を展開し、そのほかの時期にはまったく開発教育と無縁であるというのは望ましくないと考える。
社会教育において開発教育を展開するにあたっては、その展開形態が、講義、討議、調査、作業参加、実施体験など、どんな形態であれ、そこに展開される内容にも体系性が必要である。一日だけで終了するプログラムは、往々にしてキャンペーンと同じような効果はあげられるかもしれないが、参加する人びとの生きかたにまで迫りにくいものである。体系的・継続的な展開が求められてくる。
社会教育における開発教育活動への参加者は、その学習意欲において教室や集団のすべての構成員を対象とする学校教育の場合と異なって、一段と積極的であるといえよう。その積極的な意欲を、さまざまな動機や諸経験、既得知識などを持つ集団として学習のなかでどのように生かして学習活動をすすめるかという課題が、社会教育の場における開発教育の展開にはある。

2. 開発教育の展開 ― 広げていくこと
以上のような開発教育そのものについての考えかたに立ち、その今後の展開を考えるとき、先ず第一に必要なのは開発教育実践の輪を広げていくことだろう。
開発教育という用語を使用するかどうかは別にして、そしてそれがどこまで教育活動であるのか(いいかえれば、研究活動だったり、実践活動であったりするのかどうか)ということは別にして、さまざまな団体やグループが開発問題を学習したり、発展途上国について調べあげたりしている。また学校でも、全校をあげて発展途上国の学習に取り組むところもあるし、クラブ活動でこれらの国々の学習を取りあげるところもある。また社会科などで、開発問題や南北問題をきちんと教えようとしている教師もいる。
しかし、全体としてみると、他国理解や異文化理解というと、ヨーロッパや北アメリカを取りあげるのが圧倒的であろうし、また、開発問題や発展途上国の学習を授業時間やクラブ活動などできちんと取りあげているといっても、それは多数派でないことだけは確かである。
学校では開発問題や発展途上国の学習をきちんと取りあげてないのではないかという思いがするのは、教科書のせいでもある。昭和56年度の中学校社会科地理的分野の、ある社の教科書をみてみると、東南アジアの国々については7ページほどがさかれている。これに対して、いわゆる西欧地域は20ページ、アメリカ合衆国は一国だけで10ページもさかれている。発展途上国学習についての比重の置きかたがここから想像されようというものである。アフリカ全体が10ページでおさえられているところからみると、まだ東南アジアのほうがましな扱いともいえる。同じ社の歴史的分野の教科書をみると、東南アジア地域はヨーロッパの侵略との関連でしか登場してこない。
教科書だけで学習活動を想定してはいけないが、この教科書は一例にすぎない。ここには、先のユネスコ総会の勧告にある、文盲、病気、飢餓、保健衛生など、発展途上国が直面している、したがって人類が直面する主要問題にはふれられていないのである。
開発問題や発展途上国について若い世代の認識がうすいというのは、調査報告からもうかがえる。
フィリピンの人々の主食はなにかと質問されて正確に答える中学生は10人に1人にしかいないのに、嫌いな国はどこかとたずねると半数近くがアジアの国の名前をあげている。その同じ中学生の3分の2近くが、好きな国としてヨーロッパか北アメリカの国名をあげるのである。学校できちんと教わっていないから、と学校教育を批判するのは簡単だが、批判すれば変化していくようなことではない。
また、ある特定の国に対して好悪の感情を持ったり、偏見を抱くようになるのは学校教育だけのせいでは決してない。外国に関する情報源は大多数の人がテレビ、そして新聞をあげるし、中学生においても学校の勉強を外国に関する情報源としてあげるのは3分の1にとどまり(複数選択による)、それは「親・兄弟・友人」を情報源にあげた中学生の割合と同じなのである。(以上のデータは、国立教育研究所内・開発教育カリキュラム研究会が、1981年5月に実施した「外国に関する興味・関心についての調査」による)。
筑波大学付属中学校が昭和45年と52年に、中学2年生を対象に、同じ質問項目による東南アジア(ビルマ、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムの5か国)の人びとに対する生徒の意識を調査している。
その中の親近意識の調査によると、「その国の人の血を輸血されても何とも思わない」という意識を支持する者が、昭和45年にはどの国をとってもほぼ半ば近くいたのに、昭和52年には10%内外にまで支持率が落ちている。「その国から人間の生き方で学ぶべきものがある」という考え方を支持する者は、やはり昭和45年にはどの国についても50%内外あったのに対して、昭和52年には3分の1から4分の1まで落ちている。
調査結果の分析の中で、担当者は「今日の学校教育において、東南アジア諸国・諸民族に関する学習を進めようとする場合、この厳しい現実を直視したうえで計画を立てなければならないということを示唆していると思われる」としているが(日本ユネスコ国内委員会編, 国際理解教育の手引き, p.93, 昭和57年)、マスコミその他によるアジアに関する情報の相対的増加、関心の増大が表面的にはみられるにもかかわらず、偏見と蔑視が一方では広がりつつあるように思える。子どもたちがそういう認識をもつようになっているというのは、家庭や社会での認識を無意識のうちに注入されているからにほかならないだろう。
南北問題あるいは現在の地球的規模における開発問題が、21世紀の人類社会を左右するというのは、一般には、現実性をもって考えられにくいところである。
核兵器を含む世界の軍事力のゆくえが21世紀の地球を左右するというのは、比較的に現実性をもって理解されやすい。しかし「貧しい国々と豊かな国々」という対極構造のゆくえは、豊かな国々のひとつであるわが国の、たとえば身につける衣服の原材料のどれほどはどこからきて、街のそば屋の天ぷらそばの原材料の輸入国はどこであるというふうに、常時表示でもされないかぎり、現実性を持って想定しにくい。地球上における貧しい国々や、飢餓と貧困を克服できないでいる8億の人々の存在を、地球そのもの、そして人類社会の危機と結びつけて理解して、はじめて南北問題が21世紀の社会を左右するという考えかたに立ちうるであろう。
今日の、地球社会における開発問題を、人類の運命を左右する深刻な課題であると認識するならば発展途上国や開発問題についての無知、偏見を取り除くことから始まる開発教育を、大いに広げなければならないことになる。
開発教育を広げていくためには、いくつかのステップが必要とされる。第一は、開発教育に関心をもつ人たちをできるだけ多く、しかも幅広く(地理的にも、領域的にも)顕在化させていくことである。顕在化させるというのは、関心をもつ人びとの存在をお互に認めあうということである。開発教育協議会にそういう人たちが加わってもらうようにすることも大切だし、また各地に開発教育活動を推進するための連絡協議体のようなものが作られ、そこに関心を持つ人たちが集まれるようにすることも必要だろう。
関心をもつ人びとのつながりの輪を広げていこうとする場合に、それぞれの関心の質や方向に、あまり枠を設けるべきではないだろう。それが少なくとも教育活動と結びついている関心であれば、できるだけ多くの人びとに関心を表明してもらう必要がある。 関心を表明した人びとが、そのことにより一歩でも二歩でも前進するきっかけをつかみうるようにすることが、同時に考えられなければならない。そのためには、各地での実践例をできるだけ多く掘りおこして、普及させることが必要である。
開発教育活動は定型となるような内容も方法も確立していない。また定型がありうるような教育活動でもないだろう。実践の場は、学校教育における教科学習やクラブ活動、社会教育における講座、体験学習などさまざまである。また、内容も、開発問題のある側面をとらえるもの、発展途上国についての個別学習を試みるもの、南北問題の構造をとらえようとするもの、わが国の国際協力を取りあげるもの、などと多様である。それが教育活動を意図しているものであるならば、場を問わず、また内容を問わず、できるだけ幅広く多くの実践例を集めて分析し、開発教育活動に関心をもつ人びとへの参考に供しなければなるまい。そういう実践例の集積によって、開発教育の必要性の認識も深められ、方法が理論的にも追求できるようになる。また実践者もそこから新たな展開への示唆が与えられ、実践への工夫が生まれ、そして、開発教育活動へ関心をもつ人びととのつながりの輪を広げていくことに役立とう。それが同時に、開発教育を深めていくことにもなるはずである。
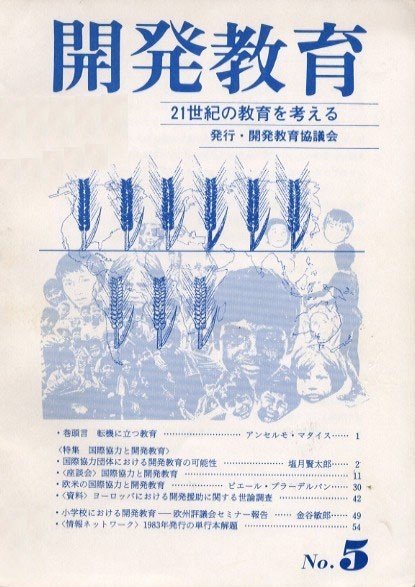
第5号(1985年)には金谷さんによる「小学校における開発教育-欧州評議会セミナー報告」が掲載されています。
3. 開発教育の展開 ― 深めていくこと
開発教育についての私見は冒頭にも記したが、理くつとしてはともかく、実践においてはきわめて多様な形態と方法がとられている。わが国の場合だけではなく、国際的にみてもそうである。それは開発教育の実践例を現時点で集めてみれば立証されよう。しかし、すでに指摘したとおり、開発教育の実践例のなかには開発教育と銘打たないものも多く包含されるはずである。たとえば、開発教育は国際理解教育のもっとも今日的な課題であると考えるが、国際理解教育の研究実践例の中に、開発教育が参考にしなければならない視点が数多く含まれている。例をあげてみる。
名古屋市教育センターが国際理解に関する研究に年次計画で取組み、その第5年次、昭和56年度のレポートを発行した。小学校5教科3領域、中学校4教科1領域における国際理解教育、特に人権の尊重と文化間の理解を狙った授業の実践的研究をまとめたものである。その中に、マレーシアについての発表会を少額5年生のゆとりの時間に開いたという言及がある。そのように開発問題や発展途上国を直接取りあげているかどうかにかかわりなく、この国際理解教育でいう人権尊重や異文化理解の視点は開発教育の視点でもある。だから体育科におけるチーム・ゲームの取組みが協力や他者へのいたわり、つまり人権尊重に結びつくという指摘は、開発教育の展開にとっても大切なものである。
南北問題を取りあげ、発展途上国の理解を糸口にする開発教育といっても、貧困、飢餓、経済格差などという課題領域、あるいは特定の発展途上国やその地域というトピックスを取りあげなくても、開発問題や発展途上国を正しく理解するために必要な基礎的心情や態度の形成に寄与しうるということである。開発教育と銘打たずに実践されているこの種の活動が、開発教育活動そのものを豊かにし、深めていることに異論はないだろう。
別の例として社会教育の場における開発教育を考えてみる。中央青少年団体連絡協議会が発行した「人類共存のために―開発教育ハンドブック」をひもといてみると、社会教育、特に青少年団体活動における事例がいくつも提示されている。
そこでは“開発教育に関連する活動”と慎重な表現をとっているが、(1)各種募金活動、物資の援助、人材の派遣、途上国でのワークキャンプなど、開発途上国に対する国際協力活動、(2)途上国への訪問、途上国からの招へい、国際キャンプ、留学生との交流、国際文通など、開発途上国の人びととの交流活動、(3)南北問題理解のためのゲームや体験学習、研究会、講座、セミナーなど、開発途上国や南北問題の理解のための学習活動、(4)途上国の留学生問題に関する活動、途上国との貿易に関する消費者運動など開発途上国における問題を解決するための運動、の4領域をあげている。
開発教育に関する活動とあるように、(3)を除くと、これらをそのまま開発教育活動と考えるには、開発教育を「教育」としてとらえるかぎりにおいては疑問が残る。しかし、これらが開発問題や発展途上国への関心を刺激し、学習への動機づけになるものであったり、あるいは学習活動を裏打ちする実践活動であったりすることには異論はない。したがって、ここで必要なのは、募金活動や発展途上国への旅行あるいは消費者運動が、どういうかたちで教育活動と結びつきうるのかという掘り下げである。
貧しい人びとに寄付をすることが、貧しい人びとの存在を容認している仕組みへの免罪符にならないのと同様に、豊かな人びとについては、金をだすことそのものが教育活動ではないことは自明である。その行為が教育活動に発展したり、教育活動の延長としてその行為が生じたりするようにするためには、その教育活動はどういうものでなければならないのだろうか。
これらの例から、開発教育活動を深め、掘り下げる必要がうかがわれる。教育活動としての掘り下げがきちんとなされないかぎり、開発教育は根無し草に終わったり、ためにする活動にすぎなくなるだろう。
開発教育活動を深めていくためには、第一に、学校教育や社会教育の分野で展開される開発教育活動の一つひとつが、教育活動としての吟味をうけ、点検されなければならない。
そのためには、学校教育においても、社会教育においても、多くの実践例が収集され、分析される必要がある。ここにおいて、開発教育の幅を広げる方向と内容を深めていく方向が交差し、相互補完的に、開発教育の展開に貢献することになる。抽象論ではなく、開発教育の多様な実践例が集められ、事例集として普及されていけば、それは開発教育を広めていくための力にも、掘り下げていくための参考にもなるのである。
第二に研究調査活動が必要である。集められた実践例そのものの検討もそうであろうし、各地の実践の評価、さらには開発教育理念の検討や外国事例との比較検討も、わが国における開発教育を深めていくためには欠くことができないものである。児童生徒の外国認識力の形成過程の研究や外国に関する意識調査なども、開発教育の推進に欠くことができない。
次に教材開発の課題がある。発展途上国の一般的紹介、ニュースやルポなどは比較的に多く市場に溢れているようにみえながら、開発教育のための教材不足が歎かれている。ひとつには、南北問題や発展途上国に関する既存の膨大な情報についてのクリアリングハウス的な機能がどこにもないので、個人で感知できる情報の範囲が限られ、情報不足という印象を与えている。映像情報も含む各種関連情報の所在だけでも定期的に把握しうる仕組みを設けることが必要であろう。
また既存情報そのものが教育活動の教材になるということは、ほとんどありえないということである。狙い、対象、場などに応じて加工された情報が、はじめて教材として利用できるものとなる。そのような開発教育のための各種教材の開発が、それざれの分野や対象別に試みられなければならない。教材開発の場合には、少なくとも利用者はだれか、前提となる知識あるいは経験にはどのようなものがあるのか、利用する目標とはなにか(なにを理解あるいは感得させたいのか)、利用する時間はどれくらいか、どういう利用の仕方(学習形態)をとるのか、などということが考慮にいれられなければならない。教材開発の普及が、開発教育を広げ深めていくうえでの大きな鍵となることは明らかである。
第四に指導者の養成研修である。開発教育に関心のある社会教育指導者や学校教師が、開発教育の理念、実践、教材、方法などについて研修をうけ、さらに研究協議をすすめる場が用意されなければならないだろう。新しい運動の展開は優れた人材を数多く用意することを必要とすることはいうまでもない。開発教育指導者の養成研修は、開発教育を広げ深めるために、もっとも早急に求められていることである。
以上、開発教育がこれから展開していく方向と、そのために必要なてだてのいくつかについて述べてみた。これらのてだてのすべてが開発教育協議会で実施できるものとは思えないし、また協議会は万能の実践組織であってもならないだろう。しかし、少なくともできるだけ多くの開発教育協議会の第一義的課題であろう。そして、そこに集まった人びとや団体の手によって、たとえば実践事例の収集、関連情報の収集、研究調査、教材開発、人材養成研修などが、個別にあるいは共同で行われ、その成果を多くの人が共有できるように連絡調整していくことが協議会にとって第二の課題となろう。大方のご検討の素材として私見を述べさせていただいた。■
(かなやとしお・本協議会理事)
※文中、一部、現在では不適切と思われる表現がありますが、当時の原稿のままで掲載しています。
機関誌『開発教育』創刊号(1983年5月発行)
・「開発教育協議会」結成の意義と役割(室靖/協議会代表理事)
・これからの開発教育の展開を考える(金谷敏郎)
・1983年度協議会活動への期待(渡辺忠)
・情報ネットワーク
http://www.dear.or.jp/books/656/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
