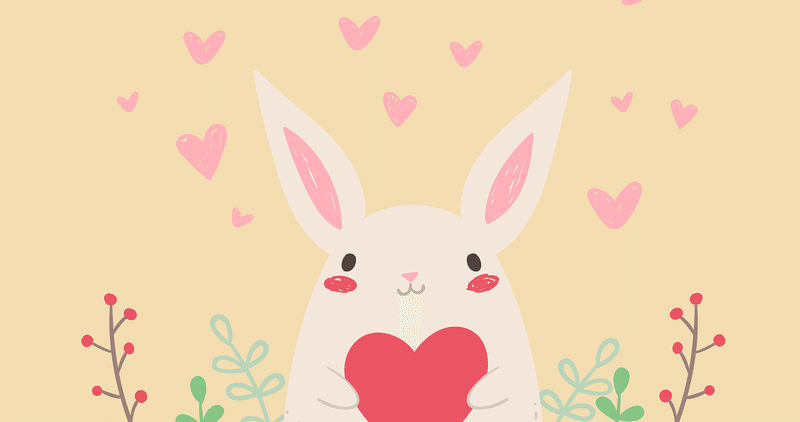
〈妄想掌編〉坂の上のおんなのこ。
ふいに思い立って、〈ひとの記事から派生した妄想を綴るマガジン〉をはじめました。まるっとフィクションですが、紹介記事の亜種みたいに思っていただけると嬉しいです。
基本無許可で妄想してしまうので、ご不快におもわれることがありましたら、速攻でご連絡ください。あっという間に削除いたします(._.)
■
長い坂を登りきったあたりで、香坂楓を見た。見たというか、目に入った。
目に入った、瞬間に、振り返った彼女と思いっきり目が合ってしまったので、あからさまに無視するか、一応なにかしらの反応をするかの選択に迫られ、祐希はとりいそぎ、ちょっとだけ上体を揺らした。見ようによっては会釈に見えなくもないような、また他の見ようによっては、自転車をひとこぎしたはずみの上下動に見えなくもないような、絶妙に微妙な揺れ具合だった。
あの絶妙に微妙なかんじが良かったのよね、と、のちに楓は打ち明けることになるのだけれど、とりあえず今のところは、ただすこし驚いたふうに目を見開いて、
「すごい汗」
と、言った。
うわ、すっげぇブシツケな女だな、と思ったんだよ、と、のちに祐希は打ち明けることになるのだけれど、それと同時に、こういう馬鹿直なかんじは嫌いではないな、とも思ったんだということは、のちになっても打ち明けなかった。馬鹿直という祐希独特のボキャブラリが、どうやら〈馬鹿みたいに率直〉なさまを示すらしいと楓が察するようになった頃にも、それからさらにずっとずっとあとにも。というのはそれとして、まあとりあえず今のところは、ただぽつんと、
「坂」
と答えた。
自宅と学校の位置関係上、どうしたって毎朝夕、この緩やかなだらだら坂をのぼってくだらねばならないのだし、夏というにはまだ早いけれど誰ももはや春とは思っていないこれくらいの季節ともなれば、よく言えば好代謝、もすこしぶっちゃけると汗っかきの祐希は、制服のシャツが透けて地肌が見えるくらい汗をかくのも毎朝夕のことだから。
「うん」
わかってる、とばかりに楓は肯き、わかってるなら言うなよ、とは言わずに祐希も肯き返す。4月の進級で同じクラスになって2ヶ月とすこし、顔と名前はぼんやりと把握できていたけれど、個人的に言葉を交わすのは初めて、なのではないかと、同時に思った。
「私は半分だから、ちょっとラッキー」
ここは自分も、〈わかってる〉風に、「うん」と肯くべきなのかもとも思ったけれど、正直目の前のポニーテール女子が言わんとしていることは十割わからなくて、
「…ンン?」
祐希の反応はまたしても絶妙に微妙に曖昧になった。相槌なのか疑問なのか半疑問なのか、ひょっとしたらただの息継ぎなのかさえさだかではない音声だった、と、のちに楓は語った。
「これ、うちだから」
息継ぎと判断して、そこで会話を打ち切っても良かったのだけれど、この絶妙に微妙なかんじは嫌いではないわ、と思ったから、楓は顎の先で坂のてっぺんに立つ建物を示した。
「ああ」
学校よりこっちサイドに住む生徒たちのほとんどは、徒歩にせよ自転車にせよ、このだらだら坂を毎朝夕登っておりなければならないのだけれど、坂のてっぺんに住んでいる香坂楓は、行きはくだりで帰りは登り、他の生徒の半分で済んでいるから、ちょっとだけラッキー、だと、言ったのだ。
…と、すぐにわかった祐希を、おお、ちょっとすごいなと、楓も祐希本人も思った。
「いい写真だよね」
「ん」
楓の生家である、とたった今顎で示された坂の上の写真館には、フロント部分のウインドウに、二十枚ほどの、さまざまなシチュエーションの家族写真で飾られていた。それらのどれを指して〈良い〉としたのか、祐希は言葉にする必要を感じなかったし、楓も問い返す必要を感じなかった。
「お父さん?」
「お母さん」
「へぇ」
それが、撮影者と楓との関係性を尋ねたのだということも、特に確認を要せずに伝わった。私たちの会話はエコよね、と、のちに楓は言うのだったけれど、エコって表現は違うと思うな、と、のちの祐希に珍しく否定されることになる。
「汗、かくからさ」
「うん」
「ここで一回止まるんだよ」
「うん」
思い出したように祐希は、制服の尻ポケットからタオル地のハンカチを取り出して、すでに乾きかけた汗をぬぐった。
このために毎朝夕、坂を登りきったところで自転車を止める。帰りがけには、ちょうど写真館のウィンドウが目に入る。
「なんか、いいなぁって」
「うん」
祐希の視線を追って、楓も肯く。
「なんか、いいよね」
「うん」
楓の視線が、正しい1枚の上で止まっているのを確認して、祐希も肯く。
「ずいぶん晩婚だったんだなぁ」
当然返ってくるつもりでいた、うん、という返答がなかったので、写真から楓に目を移すと、びっくりしたような、笑いをこらえているような、中途半端ゆえにややぶさいくになってしまった表情が、なんだかやけに好ましく思えた。
「キャプション」
「…ん?」
「読まないタイプ?」
キャプション。
言われてウインドウに目を戻すと、どの写真にも簡単な説明書きが付いている。
「あ」
ようやく気づいて声をあげると、こらえきれなくなったらしい楓が、とうとう小さく吹き出した。
「銀婚式?」
「銀婚式!」
ウエディングドレスとタキシードのカップルだから、結婚式だとばかり思っていた。
そうとわかってから見れば、なるほど、グレイヘアの男性も、それに寄り添う色白の細君も、ただただ満面の笑顔だ。新婚のふたりのようなぎこちなさがない。結婚式の写真なのに、結婚式の写真みたいな緊張感が皆無だから、なんだかいいな、と、思ったのだ。
毎夕坂を登るたび、そのあたりだけうっすら明るく見えた理由が、いきなりずいぶんくっきりとわかった。
「なるほど」
何がなるほどか、とは、楓は聞かなかった。さっきまでのニヤニヤ笑いもひっこめて、いつのまにかすこしだけ厳粛なおももちで。
「いつもがんばってくれてる奥さんに、もう一度ウエディングドレスを着せてあげたかったんだって」
「旦那さんが?」
「旦那さんが」
もう一度、なるほど、と言って、それからほんのすこし、なぜだか急激な緊張感を伴いながら、祐希は訊いた。
「銀婚式って、何年目?」
ああ、そうか、と、なぜだか急激な開放感とともに、楓は答えた。
「25年」
自分はおそらく、今目の前にいるこのひとと、その日を迎えることになる。
…って、そのとき確信したんだということは、のちになってもどちらも口にはしなかったけれど、たぶんお互いに知っていたのだと、たぶんお互いに、思ってもいるのだ。
(おしまい)
■
妄想元のすてき記事はこちらです。
このシリーズぜんぶすてきなんです。すき。お弁当(モン飯)シリーズと併せて読むと感慨もひとしおです。
■
みたいなことを、しばらくぽつぽつとやって行こうかな、とおもっております。
なんかこう、なんか…こう…〈むりせずマイペースで自分のスタイルで〉、noteのみなさんと交流したい、と、考え込んだら結果こんなになりました。我ながらなんでかアプローチが斜めからだなとはおもいますが、
…あいつ意外と照れ屋みたいだぜ、正面から感想とか言えないらしいぜ、くらいのイメージでご寛恕いただけたら、さいわいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
