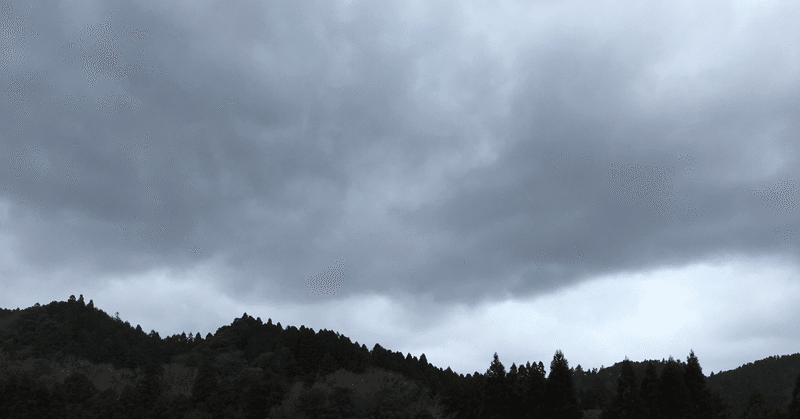
学びのデザイン=アート説
nicoと申します。
よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。
手順書があれば教えることができるのか?
夏季休暇の間に受け取ったメールに、講師が教えるための手順書が添付されたものがあったのです。
私は直感的に「このとおりやれば教えられるのか…?」と疑問を感じてしまいました。
これまでもトレーナーマニュアルと銘打って作成されたものが数多くあるのですが、どうも作成者の意図ほど活用されていないのです。
その理由は何なのでしょうか。
手順書だけではわからないこと
受講者がどのような状態に変化すればよいのか
そのために必要な受講生の感情の動きはどのようなものか
受講生の感情の動きを助けるために、講師は何をすべきか
つまり、教えるべきこととその手順が列記されているだけでは、足りないものが多いのだと思うのです。
私たちのような企業で、しかも営業部門を対象に教育を行なっている場合は、「知っている」「わかっている」だけではだめで、「できる」「やる」そして「成果を出す」というところまで持っていかなければなりません。
感情をデザインする
成果を出すために必要なのは、学びたいという意欲、学んでよかったという満足感、学んだことを試してみたいという意気込みの3つだと考えています。
これらの感情を起こさせるのが私たちの仕事である、と最近思うようになってきました。
もっとエモさに敏感にならなければならないです…
学びはアートなのかもしれない
例えば私は、始まりと終わりでは登場人物の何かが変化しているのが小説だと思っています。
その登場人物を受講者と考えたら、私たち教育の企画者は小説家ではありませんか。
絵画だとしたら。
音楽だとしたら。
運動だとしたら。
漫画だとしたら。
演劇だどしたら。
ダンスだとしたら。
演芸だどしたら。
詩だとしたら。
映画だとしたら。
学びの前後で、受講者の感情と行動をを変化させようと試みる私たちは、アーティストであるべきなのかもしれません。
プロモーターとファン
学びの企画者がアーティストなのだとしたら、参加者に届けるプロモーターが必要です。
そして、現在はファンやフォロワーがプロモートしているケースも多いですよね。
そう考えると、コンテンツそのものを増やすだけでなくファンやフォロワーを増やす活動も必要になります。
そういう意味で、YouTubeやSNSで行われていることを研究する必要があるし、できることは試してみるのも大切ですね。
これからの活動について、少し明確になりました。
お読みいただきありがとうございました。
ではでは。
よろしければサポートをお願いいたします!いただいたサポートは書籍の購入費として使わせていただきます。
