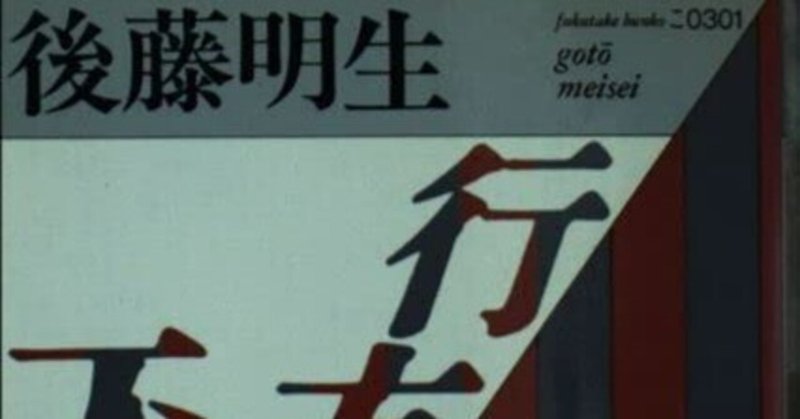
メルキド文庫~人生の一冊~(1)
第一回
後藤明生『行方不明』(福武文庫 一九八九)
沖鳥灯
私は愛知県の片隅で文芸同人誌を作っています。早いもので制作開始より十九年の歳月が経ちました。二十九歳の青年は四十七歳の中年になったわけです。チャップリンは名画『ライムライト』で「時間は最高の芸術家」と自身が扮する喜劇役者に言わせております。いまでも誤植や軽はずみな行動など失敗は絶えません。本企画であれ勢いで始めました。「躁転」という言葉があります。いやはや少しは自重を覚えたい。果たして人は時間によって成熟するものなのでしょうか?
さて本企画「メルキド文庫~人生の一冊~」は私の人生で強く印象に残った「一冊」を毎回ご紹介します。講談社文芸文庫の帯文「人生の光芒」(!)にあやかりました。朝日新聞の「私の一冊」でもありますかね。というわけで栄えある第一回は後藤明生『行方不明』です。では簡単に本の解説をします。
後藤の自選短篇集で五篇収録されています。順に「関係」(一九七一)「行方不明」(一九七三)「針目城」(一九八〇)「目には目」(一九八四)「鰐か鯨か」(一九八四)です。
「関係」は一九六二年の第一回文藝賞で佳作になりました。後藤は早稲田大学露文科在籍中に「赤と黒の記憶」で一九五五年の第四回学生小説コンクールに入選し、同年『文芸』に掲載。一九五五年は石原慎太郎『太陽の季節』が『文學界』(七月号)で発表されました。石原は本作で翌年一月芥川賞を受賞します。私は数年前に「赤と黒の記憶」を『関係』(皆美社 一九七一)で読みました。後藤は一九三二年四月四日の北朝鮮永興で生まれました。本作は北朝鮮のオンドルや葬儀、寄宿舎などの描写がありました。後藤の北朝鮮が舞台の短篇は他にも読みました。中でも「一通の長い母親の手紙」(『戦争文学17 帝国日本と朝鮮・樺太』 集英社 二〇一二)は印象に残っています。
私は後藤を定石通り『挾み撃ち』で入りました。次いで『首塚の上のアドバルーン』に挫折し、『行方不明』へ至ったわけです。本書は水道橋の古書店で百円で購入したと思います。水道橋には本書の版元福武書店の後継ベネッセコーポレーションがありました。二〇〇〇年だろうと記憶しています。まず「関係」の有名な冒頭「西野は北村に弱みを握られていると思っている」で心を鷲掴みにされました。ですが順当にあとあとバー「山猫」に興味津々になる「関係」を読み終えられませんでした。謎の電話や無料配布誌『Σ』、焼却炉のナタが鮮烈な「行方不明」に移ったように思います。とはいえ当時通信制大学二年生の私は中途で挫折しました。「関係」「行方不明」「目には目」「鰐か鯨か」は二〇〇二年の帰郷後に読みました。実は「針目城」だけ読んでおりません。本企画きっかけで改めて読んでみました。感想は最後に記したいと思います。
大学では映画研究会に在籍していました。二〇〇〇年夏「行方不明」という題の自主映画を撮りました。地元で一九九五年に笙野頼子『なにもしてない』の題名を借用した自主映画も撮っていました。この題名模倣は金井美恵子が映画の題名を借用することからの影響でした。いやはや軽率な学生でした。映画「行方不明」は夏の和田堀公園を男女四人がすれ違いながら彷徨するお話です。法桜祭で上映されて評価は芳しいものではありませんでした。サイレントなのがいけなかったようです。二〇〇〇年はラース・フォン・トリアーが流行していたので後藤チックな脱物語は受け入れ難かったのでしょう。というのは穿ちすぎで単に私の技術力のなさでした。
「目には目」は裁判や死刑制度のシリアスな笑いの短篇です。文学フリマ東京へ向かう新幹線で読みました。暗い気持ちになったことを覚えています。「鰐か鯨か」はドストエフスキー『鰐』とメルヴィル『白鯨』のお話が交錯する傑作。とくに「レヴィアタン」への言及が良い。一九九五年地元で「レヴィアタンへの挑戦」という自主映画を撮りました。支離滅裂なミュージックビデオ。評判は散々でしたが個人的に「レヴィアタン」への思い入れが強い。昨年の芥川賞作家砂川文次に「戦場のレヴィアタン」という短篇があります。ぜひ読んでみたいですね。ちなみに「レヴィアタン」というのは海の怪物です。
では最後に「針目城」の感想を述べます。貝原益軒(損軒)『筑前国続風土記』「針目城」の項にまつわるお話。「失われた主人公を探す」という後藤の小説論でもあります。終盤に益軒(甥の好古の手を借りている)の文章を現代語訳します。その中で後藤の注釈が挟まって脱線。原文を訳したり、文の中に他の文が接ぎ木されたりするのは『ドン・キホーテ』を彷彿とさせます。小島信夫『残光』で、人類が宇宙人に人類を説明する場合の手段として『ドン・キホーテ』を読ませるのが良いと述べていました。
現代日本文学を紹介する上で私は後藤明生を筆頭に挙げたいです。ゆえに本企画の始めに選んだというわけ。後藤は先述の通り一九三二年生まれ。石原慎太郎、江藤淳、ウンベルト・エーコ、大島渚、鈴木その子、フジコ・ヘミングと同年。筒井康隆、大江健三郎、古井由吉より年上です。むろん小島信夫は一九一五年生まれでさらに年上。ちなみに上皇(明仁)は一九三三年生まれ。後藤と上皇は同世代。何の意味もなさそうだが私は価値を見出したい。それが何なのかうまく言葉に出来ないのですが。『行方不明』は平成元年九月刊行。これも何の意味もなさそう。だからこそ。
以上で初回の「メルキド文庫~人生の一冊~」を終えます。書評というのは昔から馴染めず苦手な分野でした。本稿はふわふわとしたエッセイになりましたかね。今後の課題にしたいです。次回はカフカ『変身』(新潮文庫 高橋義孝訳)の予定。急遽変更もあります。よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
