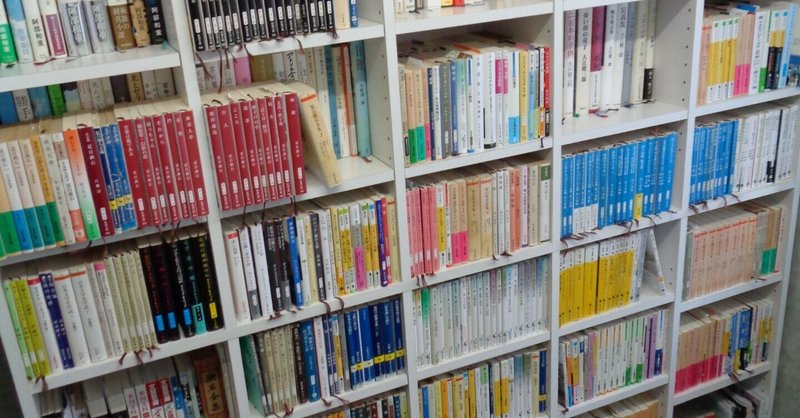
読書遍歴とは何か
作家の読書遍歴にとても興味がある。芥川賞や新人賞の受賞者インタビューで最も印象的なのは生い立ちや創作論ではなく読書遍歴だ。
本の雑誌社の「作家の読書道(みち)」というweb連載は単行本の既刊3冊を揃えるほどハマった。筒井康隆『漂流 本から本へ』(朝日新聞社 2011)は朝日新聞連載時(2009年4月5日~2010年7月25日)で愛読した。小島信夫「私の作家遍歴」(『小島信夫批評集成〈4〉』水声社)は以前より関心あるが絶版で高騰しており手が出ない。図書館で一度貸出したが読まなかった。
ドン・キホーテは「遍歴の騎士」と自称した。「遍歴」という言葉の響きは「学歴」「職歴」「性歴」などと違い含蓄がある。まさに筒井の「漂流」あるいは「漂泊」という趣きがうってつけだろう。「女性遍歴」だと一気に下世話になり食傷気味になるが。
戯れに私の読書遍歴を披瀝する誘惑に駆られる。千葉雅也の提唱する「欲望年表」ほど赤裸々な告白は控え、こと本に限って試みてみよう。手始めに私が生まれて上京するまでの21年間の読書遍歴を辿りたい。とはいえオーディオヴィジュアルに耽溺の幼少年時代であったため読書は概ね苦手だった。むしろ読書嫌いの人が参考にしてくれたら嬉しい。
ところで当ブログで「人生の一冊」という企画を打ち、一回で音沙汰なくなってしまった。「文学フリマ東京レポート1」の続編も公開していない。来夏創刊予定を公表のREBOX新書は一旦企画倒れになった。甚だお恥ずかしい限りだ。今回の「読書遍歴」はいったいどうなることやら。期待せずにお付き合いいただければ幸いだ。なお記憶曖昧なため正確さには著しく欠ける。ご了承ください。
1975年 生誕 二男 O型 双子座 市内在住作家:小谷剛(故人) 同郷作家:粕谷知世
1976年 1歳
1977年 2歳
1978年 3歳 桃太郎 浦島太郎 金太郎
1979年 4歳 動物・植物図鑑
1980年 5歳 怪獣・怪人図鑑
1981年 6歳 日本昔話
1982年 7歳 イソップ物語 グリム童話 アンデルセン
1983年 8歳 エルマーのぼうけん プロレス図鑑
1984年 9歳 ふくろねずみのビリーおじさん 失われた世界 ガリバー旅行記 ピノッキオの冒険
1985年 10歳 火吹き山の魔法使い ドラゴンの洞窟
1986年 11歳 サーカスの怪人 透明怪人 宇宙怪人
1987年 12歳 羅生門 ゲゲゲの鬼太郎 鬼太郎夜話
1988年 13歳 来訪者 車掌の本分 陰翳礼讃 孤島の冒険 ドラゴンボール
1989年 14歳 レプラコーンの涙 石巨人の迷宮 ユニコーンの探索 盗賊たちの狂詩曲 AKIRA
1990年 15歳 坊っちゃん 鼻・杜子春 人間失格 ウィリアム・ウィルソン 黒猫 アモンティリャードの酒樽 群衆の人 狂人日記(魯迅) 外套 鼻 機動警察パトレイバー 究極超人あ~る 電影少女
1991年 16歳 原始人 陰獣・孤島の鬼 アルジャーノンに花束を 二銭銅貨 鏡地獄 屋根裏の散歩者 人間椅子 虫 押絵と旅する男 乱歩打ち明け話 幻影の城主 蜃気楼 寺山修司詩集 家出のすすめ こころ もものかんづめ 童夢 ショート・ピース ハイウェイ・スター 気分はもう戦争 彼女の思い出 ヘンゼルとグレーテル さよならにっぽん 暗黒神話 とっても少年探検隊
1992年 17歳 小説アイダ バタイユの世界 朝のガスパール 文学がこんなにわかっていいかしら 夜歩く
1993年 18歳 ダブリン市民(姉妹 邂逅 アラビー エヴリン) パール街の少年たち 八十日間世界一周 トム・ソーヤの冒険 パスツール ロードス島戦記
1994年 19歳 変身 マダム・エドワルダ 三四郎 見るまえに跳べ 奇妙な仕事 グッド・バイ 道化の華 如是我聞
1995年 20歳 ペンギン村に陽は落ちて あのひと 星の王子さま 夢十夜 桜の森の満開の下 いずこへ 闇の絵巻 檸檬 櫻の木の下には ライ麦畑でつかまえて 一指導者の幼年時代 メルニボネの皇子 タイム・マシン(ロバート・アーサー) 蛾 ブラウンローの新聞 紫色のキノコ 文学じゃないかもしれない症候群 リアリズムの宿 無能の人 必殺するめ固め
1996年 21歳 痴人の愛 みずうみ 河童 歯車 或阿呆の一生 ソドム百二十日 69 だいじょうぶマイ・フレンド 母の大回転音頭(『母の発達』最終章) ゴーストバスターズ‐冒険小説‐(序章) ザラゴス 漂流教室 14歳 あどりぶシネ倶楽部 青い車
作成中に気づいたけど、今年3月の個人ブログと重複していた。
わたしの100冊 - 沖鳥灯のブログ (hatenablog.com)
記憶違いで読了年が前後している。次回があるとしたらリストではなく文章で読書遍歴を振り返りたい。
追伸
いつからか国際的作家に憧憬を抱くようになった。一日中家に籠って小説を書くと噂されるオルハン・パムクや凄惨な性描写で批判される国民的作家J・M・クッツェー、シネフィルで世界的自分探しの名手J・M・G・ル・クレジオなどだ。世界文学の現代作家に憧れは募るものの読み終えた本は少ない。訃報が伝えられたクンデラは『存在の耐えられない軽さ』と大江健三郎「人間の羊」評を読んで、『小説の技法』は読み止しだ。クンデラを読むと小説はヨーロッパの文化なのだなとつくづく高い壁の絶望と克己心が湧く。大江は日本をヨーロッパの辺境と表現した。大江の業績は日本文学を西洋文学に引けを取らない水準にしたことだろう。村上春樹の功績ではない。20世紀という小説が文化の中心だった時代は遠くなり、大江とクンデラが亡くなったいま小説の役割は経済的売上ではむろん計れず、国民文学の機能は失われた。いつだって危機の時代ではあるが、いまほど小説の危機はない。秘められた個人と家族の記憶、国土と社会の抑圧された歴史を見つけるために小説は生き残ってほしい。膨大な書籍の山に茫然自失としながら大切な本と一冊でも多く出会いたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
