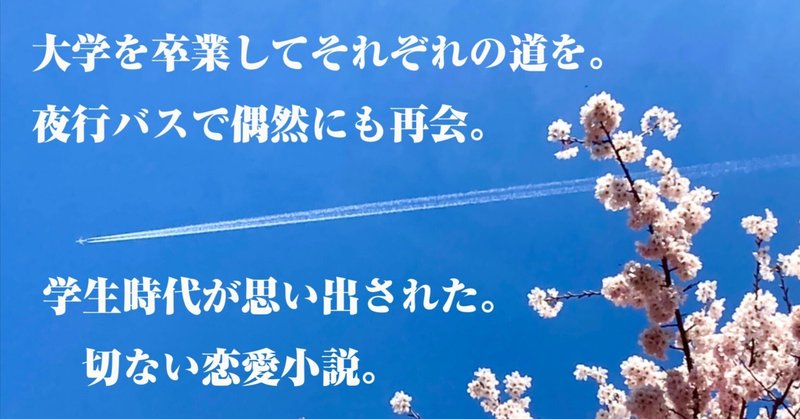
大きな玉ねぎの下で(7)
電波腕時計を外し、コーヒーカップの横に置いた。アポを取った時間に遅れないように、ここで少し心を落ち着かせて出版社へ行くことにした。この出版社へ持って来た小説原稿が入っている封筒をバッグから取り出したが、原稿は出さずに、封筒の表に書いた出版社名だけを確認して、バッグに戻した。
出版社の建物の前に立った。約束の時間まであと5分あった。エスカレーターで2階に上がると、正面に受付があった。受付窓口は一箇所ではなかった。多くの人が毎日、この受付にやってくるのだと思うと、ますます緊張感と不安感が高まった。
どこの受付に行けばよいかと戸惑っていると、一つの窓口から女性が声をかけてくれた。
「どなたとお待ち合わせでしょうか」
「はい、川染様と10時にお約束をしている納谷卓也と言います」
相手の名前を聞かれたのに自分の名前まで大きな声で言ってしまった。あまりにも大きな声に近くの人が振り向いた。それに気づき赤面した。受付の方はクスッと笑い、用紙を渡した。この女性もきっと嬉しいことがあったのだろう。口角を上げ嬉しそうに笑顔で接してくれた。
「この用紙に書ける部分だけで結構ですのでお書きいただけますか。そちらにあるテーブルをお使いください。川染をすぐにお呼びいたします」
とても丁寧でゆっくりした口調に、僕の焦る心が落ち着いてきた。テーブルで自分の名前や住所などを書いて、受付の方に渡そうとした時だった。
紺色のスーツ姿で背の高い男性が声をかけてきた。
「やぁ、君が納谷卓也さんだね。安納先生から伺っていますよ」
大学時代の恩師である安納先生が、出版社の知り合いを紹介してくれたおかげで僕は今ここにいることができている。
安納先生は、僕は教師になると思っていたらしいが、実家に帰ったとハガキで伝えると「本を読むチャンスだ。いっぱい読みなさい」と返信をくれた。それ以来、年に数回だが、季節の便りを書いてきた。
安納先生に「作家を目指します」とハガキを出したら、出版社の方を紹介してくれた。「ダメでもともとだ。届けてみなさい」と返信をくれたのだ。
安納先生は知り合いにも「作家を目指している教え子がいる」と伝えてくれていた。そして2つ目の出版社には安納先生の知人が連絡を取ってくれたのだ。もう一社は、勇気を出して、僕でアポをとった。
「ダメでもともとだから」「ダメモトだ。やってみよう」といつも口癖のように安納先生は学生に言っていた。ゼミの仲間も「ダメモト」という言葉が頭の中に打刻されるほど何度も聞いていた言葉だ。この言葉のおかげでいろいろなことに挑戦してきた仲間も多い。僕もこの言葉に背中を押され、出版社に来ることができたのかもしれない。
「始めまして、お忙しいところありがとうございます。納谷卓也と言います。よろしくお願いします」
川染さんはスーツの内ポケットから革製の名刺入れを取り出し、僕に名刺を差し出した。出版社名と役職、連絡先などが書かれてあった。僕も慌ててスーツの胸ポケットに入れてあった名刺入れを取り出し、手作りの名刺を差し出した。
名刺など使うことはないので、名刺入れは100均で買ったものだった。名刺には、表面に名前と裏面に連絡先しか印字されていない。肩書きがない名刺は、余白が多くさっぱりしている。それだけに名前が目立った。作成するときにあまりにもさっぱりしているので、「納谷卓也」という名前の横に「のうや たくや」とふりがなを添え、さらに、ローマ字で「NOUYA TAKUYA」と小さく書いた。
「納谷さんとは珍しいお名前ですね」
「はい、私も同じ名字の方には大学でもお会いしたことがありません」
「珍しいお名前は、印象深くていいですね」
川染さんは、ニコニコしながら、ロビーにあるテーブルに目をやった。空いているテーブルを見つけ案内してくれた。
「そちらのテーブルでお話を聞かせてください」
川染さんの落ち着いた言葉がロビーに響くように感じた。テーブルに着くと、それぞれの出版社に出す小説原稿を間違えないように表書きを確認してバッグから取り出し、テーブルの上に置いた。川染さんは、原稿を手に取る前に、どうして小説家になりたいと思ったのか、どんな小説を書きたいのかなどを聞いてきた。
僕は思わぬ質問に戸惑いながらも、学生時代からの話をした。教師になるか作家になるかと迷ったこと。実家の本屋でたくさんの本を読んでいたら、作家の人間性に触れることができたこと。僕も自分を表現する場として文字にしたいということなどを伝えた。
「納谷さん、それなら本にしなくても、今、はやりのブログでも自分の思いを表現し、多くの人に伝えることができますよ」
川染さんの言葉に、全くその通りだと思った。僕はなんのために小説を書きたいのだろうか。自分を表現する場として考えているのならブログでもいいのではないか。でも、僕は小説を書きたい。その思いが強いことは間違いない。僕の心の奥には小説を書く必要があると確信していながらも言葉として出てこなかった。
出版業界のこと、本になるまでの流れ、どれだけの本が1日に新しく出版され、書店に並ぶのか、そして「刺し」「ヒラ積み」などの用語も教えてくれた。どの話も僕には興味があった。出版社は本ができるまで、そして本ができてからのPR方法や書店での本の並べ方まで考えている。そういえば、新聞の一番下に本の紹介がよく載せられている。紹介のスペースもだが、新聞のどの面に載せるかで広告料も違うようだ。
実家の本屋で、僕は仕事らしきことをしているが、全く知らないことばかりだった。
夢中に話を聞いていて、気がつくとテーブルの上には、封筒に入れたままの小説原稿がそのままだった。このまま、受け取ってもらえないのかと心配になった。
「あのー、これが僕の書いた原稿です」
「あ、これですね。わかりました。確かに受け取りました」
川染さんはそう言いながら僕の差し出した厚めの封筒を受け取ってくれた。僕は立ち上がり、頭を深々と下げた。
「よろしくお願いします。数ページでも読んでいただけると嬉しいです」
今の僕にできる精一杯のことだった。
「納谷さん、読ませていただきます。珍しいお名前はいいですね。忘れることがないですから」
ちらっと腕時計を見た川染さんは次の用事がある感じだった。
「ありがとうございます」
「あ、そうそう。安納先生にもよろしく伝えてくださいね。また会いましょう」
「は、はい」
「じゃ、今日はここで」
「貴重な時間をありがとうございました」
その場で原稿を封筒から出して見てもらうことはできなかったが、「また会いましょう」という川染さんの言葉が嬉しくて、緊張感から解放された気持ちだった。
(一つ目の出版社を訪ねた卓也、一瞬だけ亜紀のことが頭から消えたが・・・。次回へ続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
