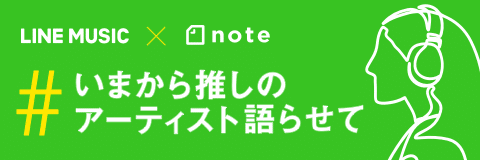小沢健二「アルペジオ(きっと魔法のトンネルの先)」について語らせてほしいんだ。
小沢健二について語りたい。しかし小沢健二そのものについて語ろうとすると、たぶん何も書くことができずに終わるだろう。だからここは小沢健二のカケラについて、フォーカスして語る方がいいのかもしれない。
月曜日、小沢健二のライブに行った。当たるわけないと思って興味半分で応募したのだが、はたして当たっていた。思わぬことで迷ったけれど(迷うな)新幹線に乗って向かうことにした。
僕は小沢健二について詳しくない。僕が音楽に興味を持ったとき、彼はすでに日本の音楽シーンから姿を消していた。それは煙のような消え方だったのか、爆発音とともに去ったのか、なんらかの事件とともに去ったのか、そのあたりのこともわからない。ただ気づいたときには、もうそこには小沢健二は存在していなかった。
まるで僕がちょうど角を曲がったときに、彼も通りの向こうの角を曲がり終えたところ、そんな感じだったかもしれない。
いま考えてみると、僕が平日に新幹線の中で味噌カツ弁当を食べ(980円だった)足をまあまあ大きめに開くチンピラ男のとなりの席に座って、新木場STUDIO COASTに向かったのは、ひとつの曲を聴くためだった。
それは「痛快ウキウキ通り」でもなければ、「ぼくらが旅に出る理由」でもない。「それはちょっと」でもなければ、「愛し愛されて生きるのさ」でもない。
僕が心をぎゅっとつかまれてしまったのは——つまり小沢健二を知ってしまったのは——アルペジオ(きっと魔法のトンネルの先)を聴いたからにほかならないのだ。
だから僕が小沢健二について何か語ろうと思うならば、それはこの「アルペジオ(きっと魔法のトンネルの先)」についてでしかないだろう。
僕はこの曲について、もうすでに与えられている見方ではない、自分の見方を提示する必要があると思う。
もしかしたら僕の解釈は、小沢健二が意図したこととは、まるっきり違う意味を持つかもしれない。けれども彼はまるで先まわりするみたいに、STUDIO COASTの舞台のうえからこう言ってくれた。
歌詞は不思議なもので、僕が歌った瞬間からみんなのものになる。ほんとに不思議なんだけど
と。
だから僕がこの美しい曲に、自分なりの解釈を与えたとしても、それはべつにおかしな話ではないのである。
では、始めたいと思う。

曲はアルペジオで始まる。曲が進行してゆくあいだ、このアルペジオはずっと鳴っている。たぶんだけれど小沢くんは、このアルペジオを最初に思いついたはずだ。記憶の中に潜ってゆくときに、ずっと寄り添ってくれている魔法の旋律。
この音が鳴っているとき、僕らは現在にはいない。そう。この音のつらなりは、僕らが過ごしたことのなかった過去へ、僕らの手を引いて連れて行ってくれる。
つづいて、シンセサイザーの音がかかってくる。まるで夜に雲がかかるように、ひらひらと浮かぶ音が、記憶の世界に現実感を持たせる。簡単なひとつの線に、細かな影を付けるだけで立体感が出るようなものだ。
そして確信的に、シンセの音が指一本ぶん足され、和音になった瞬間、この物語のストーリーが始まる。
幾千万も 灯る
都市の灯り
が
産み出す闇
に
隠れた
汚れた 川と
汚れた 僕らと
煌々と輝く大都会の街の光の中、その光が産み出す深い闇に、淀んでゴミが浮かぶ川と、「僕ら」なる存在が描き出される。
ここでいう僕らとは、つまり小沢くんと——ではなく、僕と彼女である。それはつまるところ、あなたと彼女でもある。僕らはすでにこの街の物語の中にいて、汚れた川の欄干に寄りかかり、街の灯りや月の様子をみているわけなのだ。
この時点で、この曲の圧倒的描写力に気づいたひとは多いだろう。アルペジオが鳴っているなと思っていたら、雲のようなのものがかかり、数秒のうちに僕らは自分のよごれっちまった心を抱えて、眩しすぎる都市の光が作る影の中にぽつんと立っているのだ。
「待ってくれ、ちょっと待って」
そんなふうに小沢くんに伝えるには、アルペジオのペースは一定すぎる。まるでメトロノームのように、天体を動きつづける星々のように、僕らは音楽というボートに乗って運ばれてゆくしかないのだ。
駒場図書館を後に
君が絵を描く
原宿へゆく
しばし君は
「消費する僕」と
「消費される僕」を
からかう
駒場図書館は東大の図書館であり、原宿で絵を描いているのは岡崎京子――だのなんだのと、ひとによってはデイヴィッド・カッパーフィールド的にあれこれ予備知識を持ち出してくるのかもしれない。
しかし僕にとって、そんな些細なことは問題ではない。とにかく僕は「僕の中にある図書館」をでて、原宿という文化の中心みたいなところにるんるんで向かうのだ。
すると彼女は僕のことを、あれこれ知的にからかってくる。僕はそのことになんだか笑ってしまうと、つまりはそういうことなのだ(それだけの話なのだ)。
このごろの
僕は弱いから
手を握って
友よ 強く
この言葉を聴くと、体の奥から自然と涙が溢れてくる。いつもは決して弱くないのだが、いまちょうど弱っているときというのは、誰にとっても存在する。自分が言ってることがまちがっていたとき、他者から責められているとき、何かを手から落として粉々に壊してしまったとき。
こういうときは誰にもそのそぶりを見せず、長くジョギングすることで解決したり、酒を飲んで忘れてしまったり、ただ部屋にひとりでいることを選びがちだ。
しかしこの曲では「弱っているから手を握って欲しい」と素直にいえる友がいる。それは僕らの人生には存在していないため(この世界にだけ存在しているため)僕はその手を握ってくれる友を呼ぶ声を聴いて、じんわり涙腺が緩んでしまうのだ。
でも 魔法の
トンネルの先
君と僕の
心を愛す
ひとがいる
本当だろうか
幻想だろうかと
思う
これが小沢くんと岡崎さんの話であるなら、トンネルとは創作活動を意味している気がする。音楽を作るとき、絵を描くとき、ふっと頭に浮かび上がる魔法の一瞬。その一瞬を幾度もつかんで——もちろんそこはトンネルの中のように暗い——彼らは創作活動を行う。
だからこの創作というトンネルを抜けて出口へと至ると、そこにはリスナーや読者がいて、「心を愛してもらえるのだ」と彼は歌っているのかもしれない。
もはや本当なのか幻想なのか、その区別もうまくつかないくらい、愛してもらえる瞬間があるはずなのだ、と。
僕の彼女は君を嫌う
君からのファックス隠す
雑誌記事も捨てる
その彼女は僕の古い友と結婚し
子供産み育て離婚したとか聞く
ここで世のカラオケ迎合体質への、小沢くんの一撃が走る。それはつまり薄暗い照明のカラオケボックスに入ってきた小沢健二が、テーブルのうえに「うりゃっ」と乗って、そのテーブルのうえのしなびたポテトやコークを蹴り飛ばすみたいな所業である。
そう。棒読みラップがここで唐突に挿入され、事実のスライドが僕らの脳内を突っ走ってゆく。本人ですらライブで歌いにくいだろうが(STUDIO COASTでも「あー歌詞忘れちゃった!」といって放り出したときは笑った)そんなことは彼には関係ない。
必要なものは必要な場所に置く。そしてこのあたりから、曲はヴァイオリン三重奏曲のような様相を呈してくる。
歌詞にも触れておくと、このほんの数秒の間に、およそ四半世紀が流れている。このあたりの技術は22歳の歌い手ではまねできない。膨大な時間をプレスする機械のうえに置き、極限まで圧縮して、さらっと曲に持ち込めるのは(しかも抑揚なしラップで!)このSo kakkoii 宇宙で小沢健二ただひとりだけなのだ。
初めてあった時の君
ベレー帽で 少し歳上で 言う
小沢くん
インタビューとかでは
何も本当のこと言ってないじゃない
三重奏の最期のひとり、二階堂ふみのクールな声が響き始める。その声はどこか冷めていて、小沢健二が過去に言われて、もっともぐっさり身体に突き刺さった言葉をそのまま言ってくれる。
「小沢くん
インタビューとかでは
何も本当のこと言ってないじゃない」
この言葉を彼はSTUDIO COASTでも何度もくり返していた。まるで壊れたラジオみたいに。何度も何度もこの場所をくり返し、そこから動こうとしない。おもちゃ売り場から動き出そうとしない子供のように、彼はこの場所から永遠に動かないかに思えた。
そして2時間が経過した。僕らはもう1,440回目の「小沢くんインタビューとかでは」を歌っており、半数のひとはもうスタジオに倒れていた。とまあそんなことになるくらいには(なってません)小沢くんにとってこの一文は大切なものなのだ。
それはつまり、人間たちがたどり着こうと思ってたどり着けない、完全なる理解へと接続される隘路への予感なのだ。
電話がかかってくる
それはとてもとても長い夜
声にせずに歌う歌詞が振動する
僕は全身全霊で歌い続ける
3行目。おい、ちょっと待って。リリック警察だ。「声にせずに歌う歌詞が振動する」? いくらなんでも、いくらなんでも散文がすぎる。
もう一度読む。
声にせずに歌う歌詞が振動する。
さらっと言い切ってるけど、この一連の歌詞の中でもっとも矛盾を孕んでいる。矛盾を妊娠している。矛盾が早めの破水を起こして、矛盾に満ちたタクシーで、矛盾に満ちた病院の、矛盾に満ちた救急外来にゆき、矛盾に満ちた幼子を産み落とすようなものだ(筆者はバカです)。
全身全霊で歌い続ける。
巻き戻すんだ、いますぐに!
声にせずに歌う歌詞が振動する。
僕は全身全霊で歌い続ける。
ものすごく早口で言い切っているが、ここには矛盾のサンドイッチが起きてる。
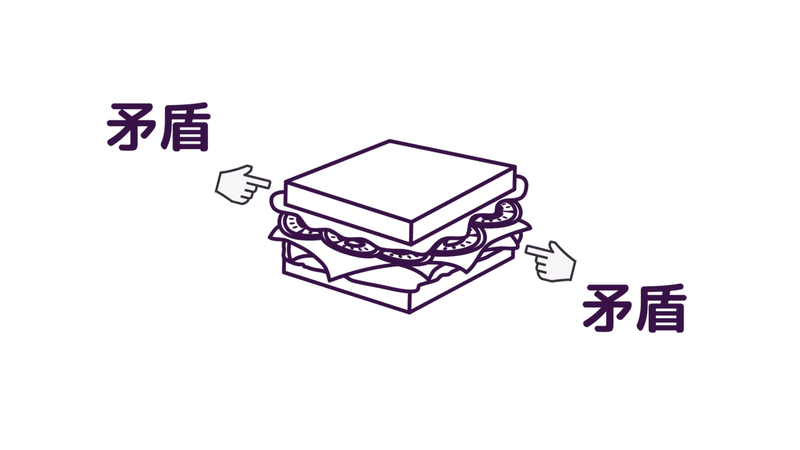
そしてだからこそ、だからこそ声にならない声が、爆音で僕らの耳を伝って心臓でスパーキングしてしまうのだ。
このとてつもなく難解な三重奏は、ようやくもとの小沢健二の歌唱に戻ってくる。まるでユリシーズでの主人公の冒険より長い、そして同時に短い、そんなオデッセイだった。
そう安心するのも0.2秒。僕がもっとも強く心臓をつかまれ、何者かにねじり上げられちぎられる言葉が耳に響く。
このごろは
目がみえないから
手を握って
友よ やさしく
こんなこと言えますか? このごろは目がみえないからって。そんな寂しくて美しい表現へと帰還するって、僕はいったい何を聞かされているんだろう?
でもわかる。全然何もみえない世界の、誰からもどこからも遠い世界で、たったひとり彼女だけが手を握ってくれることへの信頼。無垢な安心感。母なる者への懇願。
ここには何か特別尊いものが刻み込まれている。そう僕らはここへ来て確信に至るのだ。
でも 魔法の
トンネルの先
君と僕の
言葉を愛す
ひとがいる
本当の心は
本当の心へ
届く
本当の心とはなんだろう。たぶん本当の心というのは、相手への新雪みたいにピュアな信頼だろう。それは「愛」という名でもあり、「裏切らない」という行動でもあり、「信じる」という名前に姿を変えることもある。
本当の心で歌を創り絵を描けば、そこには本当の心でキャッチしてくれるひとたちがいる、彼はそう歌っているのではないだろうか。
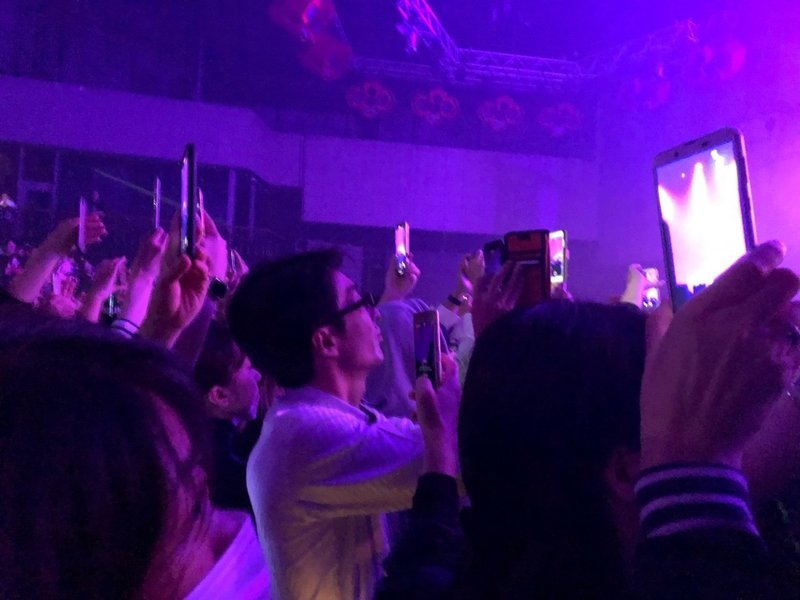
ここで旋律は金管に移り、暗い世界に黄金の瞬きが溢れてくる。雲間から希望が指すように。厚い雲を割った光の柱が世界を濡らす。
時々は
君だって弱いから
助け合うよ
森を進むこどもたちのように
手を握って
友よ 強く
これまでは自分ばっかりフォローされてた。すこし年上のベレー帽の君だから。でもそうだよな。君だって弱いときはある。だから今度はこちらから手を握るんだ。つまりこっちから握った手を、「離すなよ!」と彼はいっている。そう、ここでは立場が逆になっているのだ。
そして、この迷いの森をともに抜けよう。
ヘンゼルとグレーテルのように。
きっと 魔法の
トンネルの先
君と僕の
心を愛す
ひとがいる
汚れた川は
再生の海へと
届く
わずか3分37秒の旅。しかしこの尊い旅によって、汚れた川は再生の海へと接続され、ただただ浄化されてゆく。
日比谷公園の噴水が
春の空気に虹をかけ
「神は細部に宿る」って
君は遠くにいる僕に言う
僕は泣く
頬を撫でてゆく春の透明な空気に、虹が落ちている。もうここまで来ると、僕の知力や語彙力では意味が追いきれない。けれどたぶん、彼女はいつも僕がちょうど必要としている言葉を、世界から切り出すようにして端的に僕に提示してくれるひとなのだろう。
僕が僕よりも大切に思えるひと。相手はそんな人物であることがわかる。
下北沢珉亭
ご飯が炊かれ
麺が茹でられる
永遠
シェルター
出番を待つ若い詩人たちが
リハーサルを終えて出てくる
世界はこうして、アルペジオと歌声を響かせて、ゆっくりとテンポを落としてゆく。世界は回りつづける。僕らがいたことなんて、まるで嘘だったみたいに永遠に吸い込まれてゆく。
この記事が受賞したコンテスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?