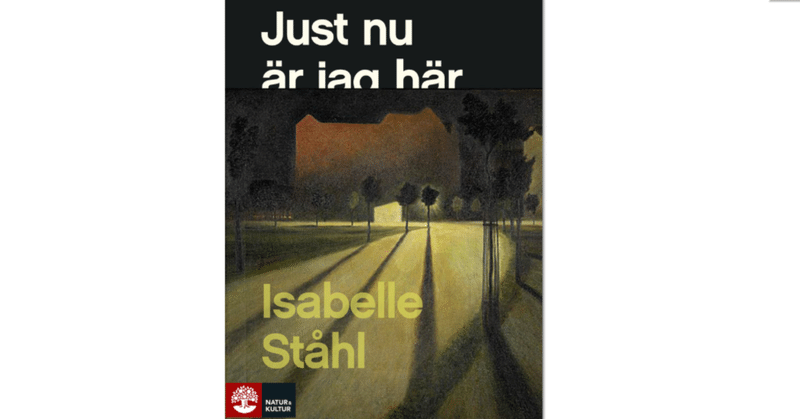
【書評】スウェーデン発、エキセントリックな女性の独特の時間の感覚、他人との距離感(久山葉子)
タイトル(原語) Just nu är jag här
タイトル(仮) わたしは今はここにいる
著者名(原語) Isabelle Ståhl
著者名(仮) イサベル・ストール
言語 スウェーデン語
発表年 2017年
ページ数 290ページ
出版社 Natur & Kultur
眠りにつくのは、この世でいちばん当たり前のことのようにも、世界いち難しいことのようにも思える。自分というすべてを脇にやり、身体から意識が消えるがままにする。この身体が自分のものではなくて、一時的に借りているだけみたいに。それは死ぬ練習のような感じもする。しばらくするとソフィアもやってきてベッドに横になった。そして服を着たまま眠ってしまった。
わたしは指輪のなくなった自分の薬指を見つめた。肉と骨。それだけ。わたしは手を伸ばし、ソフィアの顔に触れ、額の皮膚の下にある頭がい骨を感じた。これは人間。それ以上の何物でもない――。それがわたしの心の拠りどころなのだ。
これが、『わたしは今はここにいる』(仮題)の最後の十二行だ。主人公エリースの視点で綴られるこの作品は、どのページをめくっても、エキセントリックな主人公の感性が息苦しいほどに立ちこめている。彼女独特の時間の感覚、他人との距離感、そして冬の冷たさや夏の香りまでもが、読む者にぐさりと突き刺さってくるようだ。まるで彼女の身体に潜りこみ、彼女の五感と思考をもってこの世界を再体験するような感覚。衝撃的な読書体験になった。
主人公はストックホルム大学で哲学を専攻する二十代後半の女の子。生まれ育った地方都市の息苦しさから逃げるように都会に出たものの、そこでも異邦人のような気がしている。寂しさを紛らさせるために、出会い系アプリTinderで常に大勢の男性とつながり、毎晩のように夜遊びを繰り返し、男の家について行っては、一夜限りの関係を結んでいる。
昼間は大学で、何の不自由もなくストックホルムで育った年下の大学生たちを、教室の片隅から羨ましそうに眺めているエリース。その中でもエリースが心密かに憧れているのが美青年ヴィクトルだった。ひょんなことから彼と距離を縮め、信じられないことに恋人同士になる。しかしヴィクトルが自分に夢中になるにつれ、彼のことがますます知らない人のように思えるのだった。ついこの間まで遠くから見つめて憧れていた彼――しかし近づいたとたんに、ちがうものになってしまった。エリースはその感覚に恐怖すら感じ、トイレでひとり鎮静剤を飲む。
タイトルのとおり刹那的で、自滅的な生き方を選んでしまう若い主人公。どうしても他の人のように〝ちゃんとまとも〟に生きることができない。せっかく手に入れた幸せを、自分から壊してしまう。本文中に病名が出てくるわけではないが、明らかにパーソナリティ障害を抱えている。
正式な恋人として、一緒に暮らし始めた二人。ヴィクトルはハンサムで爽やかで、礼儀正しく育ちの良い青年だ。仕事でも将来有望で、料理も掃除も得意だし、マンションのインテリアにもこだわり、記念日には必ず素敵なレストランで食事をする。つまり読者からすると理想の結婚相手のような男性だ。しかしエリースはそんなヴィクトルに対する違和感が募るばかり。なぜシャツにアイロンをかけなきゃいけないの? なぜソファでだらだら食事しちゃいけないの? なぜ家じゅうにキャンドルを灯して、知り合いのカップルを呼んで、楽しそうに会話をしてディナーを食べなきゃいけないの? エリースは次第に息苦しくなり、薬の量が増えていく。素敵なレストランでプロポーズされたときは、二人とも幸せだった。とはいえエリースは、永遠の概念が彼と自分ではちがうことを認識している。彼女にとっての永遠はせいぜい五年くらいなのだ。それ以上先のことは、どうしても考えられない。
エリースのような女性はこれまで、よく言えば〝エキセントリックで芸術家肌の女性〟として描かれてきた。悪く言えば、〝精神的に不安定で、自滅するタイプ。不幸になるのは自業自得〟といったところか。どちらにしてもわたしから見ると、同じ女性でありながらも、なぜそういう行動に出るのかがさっぱり理解できない存在だった。しかし本作を読んで、一分一秒がこれほどまでに自分とはちがう感覚なのだと知った。世の中には色々な人がいるのだ。そこで現実に引き戻され、改めて、自分の価値観だけで相手を評価してはいけないと自らを戒めた。
子供の頃から、読書というのは、自分とはちがった環境に置かれた人の考え理解し、共感を身に着ける手段だった。とはいえ本によっては主人公に共感できなかったり、ミステリアスな存在のままに終わってしまうものも多くある。本書のように、新しい世界を垣間見る機会を与えてくれる本――そんな本に出逢ったときの感動は格別だ。
本作は、2017年にスウェーデンの権威ある文学賞アウグスト賞にノミネートされた。
(Yoko Kuyama)
**********************************
次回5月29日(水)は、セルボ貴子さんがフィンランドの本を紹介します。どうぞお楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
