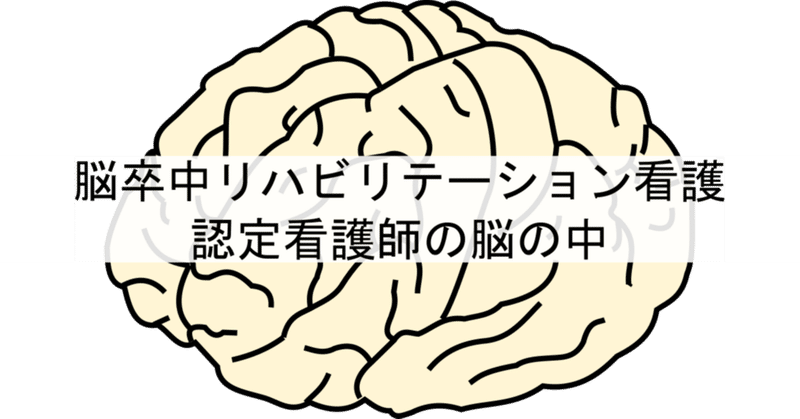
脳血管 #2-2 脳血管の解剖的・生理的特徴
脳血管の解剖学的特徴
①側副血行路
Willis動脈輪や眼動脈の構造などが代表的ですが、側副血行路を完備しています。頚部では前方に左右の内頚動脈と、後方に左右の椎骨動脈へと分かれていましたが、大脳底部でもう一度吻合して、Willis動脈輪をつくります。Willis動脈輪をつくることで、仮に1本の動脈が閉塞しても側副血行路で血流を補うことができ、脳梗塞に陥る危険性を回避できます。
脳実質内に入り込む穿通枝動脈は、他の動脈と吻合を持たない終末動脈であるため、穿通枝動脈が閉塞すると側副血行路で血流を補うことができません。、そのため、閉塞部より末梢は脳梗塞に陥ります。
②血管壁
脳の正常な動脈は、ほかの臓器の動脈と異なり、最外層にある外弾性板という保護膜を持っていません。また、中間層にある中膜筋層も比較的薄く、膠原線維が多い特徴があります。そのため、血管の内外からの損傷によって破綻をきたしやすい状態です。
老性変化や高血圧症によって、中膜の筋細胞が線維化します。さらに中膜だけではなく、内膜にも変化が生じ、血管壊死を引き起こします。血管壊死は、小動脈の動脈瘤を形成します。
③血液脳関門
血液脳関門は、脳の正常な機能維持のため、血液に混じって脳の中に侵入しようとする物質を制限して、有害物質から脳を守る重要な機能です。血液脳関門は、脳の毛細血管と脳組織の間にあります。
脳毛細血管の内皮細胞の一部には、隣接する内皮細胞との細胞間隙が極めて狭く、密着したような部位があります。ここは密接結合と呼ばれ、ある種の物質はこの部分に引っ掛かり脳への侵襲が制限されます。さらに、脳毛細血管は星細胞の樹上突起の先端にある終足で取り囲まれています。
こうした血管壁-髄膜-星細胞間の複雑なしくみは、必要な物質だけを神経細胞に取り込み、有害な物質は侵入を阻止するという、関門の役割を果たしています。
脳循環の調節
脳灌流圧と脳血管抵抗
脳血流量は健康成人で50~60ml/100g脳/分、脳酸素消費量は3.3~3.6ml/100g脳/分です。加齢とともに減少していきます。
この脳血流量の調節は、脳灌流圧と脳血管抵抗によって行われています。脳灌流圧とは、血液が脳内を一定の方向に流れるための頭蓋内圧と平均血圧の圧差を指します。「脳灌流圧=平均血圧-頭蓋内圧」という関係になります。血圧が上がるか頭蓋内圧が下がれば脳灌流圧は上がりますし、血圧が下がるか頭蓋内圧が上がれば脳灌流圧は下がります。
脳血流量と脳灌流圧、脳血管抵抗の関係は、「脳血流量=脳灌流圧÷脳血管抵抗」という関係になります。脳血流量と脳灌流圧は比例関係に、脳血流量と脳血管抵抗は反比例の関係になります。
しかし、血圧の変動によって脳血流量がすぐに変動するわけではありません例えば低血圧になってしまった場合に脳血流が低下し、脳虚血になる危険性があります。そうならないように、次に示す調節機能があります。
①神経調節機能
脳循環では、生理的な血圧変動に対して自動調節機能(autoregulation)という機能が働いています。この機能は、血圧に応じて血管が収縮したり拡張したりして、血圧の変動に対して脳血流を一定に保とうとします。このautoregulationが作動する平均動脈血圧は、下限が50mmHg、上限が160mmHgぐらいと考えられています。つまり、血圧が50~160mmHgの範囲においては脳血流は一定に保たれるのです。血管内圧変化に応じて、神経が血管を収縮させたり、拡張させたりして血圧を調節しています。
②化学調節機能
脳循環の調節には、脳代謝変化に対する化学調節があります。これはCO2とそれによるpH変化といった代謝的な要因による調節です。脳の機能が亢進し代謝が盛んになると、 CO2の産生が高まります。CO2は血管を拡張させるはたらきがあるので血流を増やします。脳への血流が増えることで、需要に見合った酸素を脳へ送ることができます。
脳の代謝亢進によって、酸素とエネルギーを消費し、二酸化炭素を産生します。二酸化炭素は血管中膜平滑筋細胞内に入り、その炭酸脱水酵素により水素イオンが増加します。水素イオンが増加によりpHが低下し、血管が拡張し、脳血流量が増加します。二酸化炭素自体が平滑筋に作用するわけではありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
