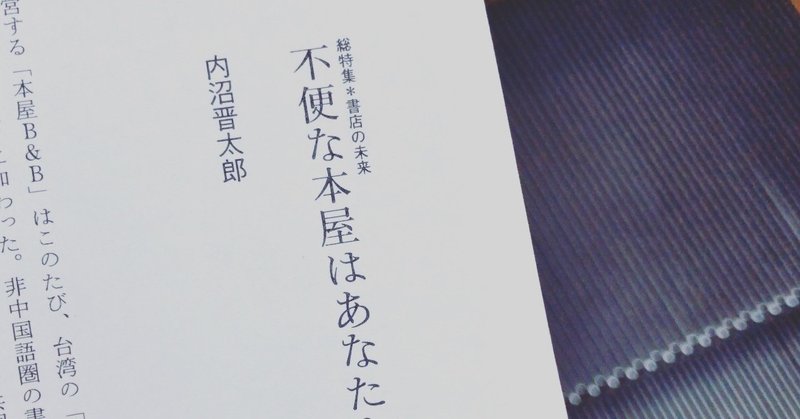
不便な本屋はあなたをハックしない(2)「泡」と「水」――フィルターバブルを洗い流す場所としての書店
「不便な本屋はあなたをハックしない」目次
(序)
(1)本屋としての筆者
(2)「泡」と「水」――フィルターバブルを洗い流す場所としての書店
(3)独立書店と独立出版社――「課題先進国」としての台湾、韓国、日本
(4)日本における二つの円――「大きな出版業界」と「小さな出版界隈」
(5)「大きな出版業界」のテクノロジーに、良心の種を植え付ける
(6)全体の未来よりも、個人としての希望を
※「不便な本屋はあなたをハックしない(序)」からお読みください。
何か知りたいことがあるとき、ある時代まで、私たちは書店や図書館に行った。けれどいまは、まず検索をするようになった。どんな些細なことについても、検索すればたちまち、いつかどこかで誰かの書いた情報が大量に出てくる。インターネットは巨大な一冊の本、あるいは巨大な図書館のようである。便利な時代だ。
同時に、インターネット上にあるのは、私たち人間がそのように検索エンジンを使ってたどり着ける情報ばかりではない。むしろ、それはいまやごく一部の情報にすぎない。誰かのメールやメッセージのやり取り、SNSでのクローズドな投稿、クラウドストレージに置かれた大量のファイル、ECサイトでの購買履歴をはじめとするあらゆるサービスの利用履歴、あらゆるスマートフォンのアプリケーション上でのデータや行動履歴など、膨大な情報がインターネット上に無数に存在している。
また、情報を生み出すのは、オンラインでの行動だけではない。ほとんどすべての人がGPSの入った端末を持ち歩き、キャッシュレスが浸透し、顔認識の技術が進み、IoT化が始まりだしたこの世界では、インターネット上だけでなくリアルでの行動までもが、本人が意図せず自然と生み出した情報となって、どこかに大量に蓄積されていく。
いまや人間によって書かれるもの、手作業によって記録されるものは、ごくわずかだ。意志をもって書かれるわけではないもの、自動で記録されるものが、途方もない量で存在している。サービス事業者の定める規約の範囲内で、いつか誰かに読まれるために、たしかにそれは記録されている。読む誰かとは多くの場合がAIであり、そのように読まれる情報は昨今ビッグデータと呼ばれることが多い。私たちの生活がテクノロジーに囲まれるほど、私たちのあらゆる行動が、誰かに読まれる対象となり得る。いわば、私たちは生きているだけで、一冊の著書も一文字のブログも書かないとしても、すでに巨大な本の一部を構成している。
このような時代を象徴し、かつ大量のユーザーとともに多くのデータを抱えているのが、GAFAとよばれる4つの企業だ。メディア情報学者の石田英敬は「Google、Apple、Facebook、Amazonという巨大企業のいずれもが、本や事典や図書館との密接な関係のもとに発達してきた 」と指摘している(*1)。各企業がこれまで手掛けてきたサービス、その思想や成り立ちからして、大量の情報を扱うようになったのは必然だったというわけだ。
AIによって読まれた私たちそれぞれの情報に基づいて、私たちが日々接する検索結果やタイムライン、消費行動は最適化されている。しかもそれは、個々にパーソナライズされている。2019年現在の私たちは、ただ世間一般に注目度の高い情報が流れてくるだけではなく、自分が現在いる場所の近隣の情報や、以前に閲覧したサイト、かつて購入した商品などと関連する内容の広告が表示される環境に、すっかり慣れてしまった。いわば、私たちは巨大な本の一部として読まれていると同時に、ひとりひとり違う、自分向けにフィルタリングされ、編集された巨大な本を読んでいる。読むものと読まれるものとの間は、相互に関係を見出され強化され続けている。精度が上がれば上がるほど、欲しい情報が向こうから勝手にやってくるようになり、どんどん心地よくなっていく。
しかしそれは、ただ便利で心地よいだけだろうか。筆者と同じ1980年生まれのインターネット活動家、イーライ・パリサーは、その環境を「フィルターバブル」と名付け、個人がその「泡」の中にいること、それらの情報を私企業に操らせることに警鐘を鳴らしている。パリサーによると、大きなターニングポイントはGoogleの公式ブログにてパーソナライズ検索が発表された2009年12月なので(*2)、その年をフィルターバブル元年とすると、今年で10年を迎えることになる。それは単に便利なだけでも、消費を促す広告を我慢すればよいだけでもない。
たとえば本稿の執筆中にも、Twitterで差別的な発言を繰り返していた有名な匿名アカウントの身元が判明し、それが日本年金機構の世田谷事務所長であったという事件が話題となった(*3)。彼がSNSを使い始める以前にどういう思想の持ち主であったかは定かではないが、少なくともSNS上で同種の発言に共鳴し、そうした情報を大量に摂取しているうちにさらに近しい情報が集まりやすくなるという「泡」の中で、自身も発言を繰り返しながら、ある種の確信を増していったことは想像に難くない。
そこにフェイクニュースの問題が重なる。「泡」の中にいるのが人間である以上、たとえ流れてくる情報がフェイクであっても、何度も繰り返して接触したものに好感を持ったり(ザイオンス効果)、事前に見聞きした情報に影響された行動をとったり(プライミング効果)、仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視しがちになったり(確証バイアス)といった性質から逃れきれない。それが一国の大統領選に影響を与えるほどの力を持つことは、もはや実証済みだ。
元来「テレビがこう言っていた」「週刊誌にこう書いてあった」という情報に影響を受けやすいタイプの人が、特に危険であることは言うまでもないだろう。しかし、テレビや週刊誌だけが存在していた時代に加えてやっかいなのは、あたかも偶然であるかのように、巧妙に情報を届けるような芸当ができてしまうところにある。その人に有益な情報のみを届けているように装って、ある種の消費を促したり、その思想に強い影響を与えたりすることが、本人に気づかれることなくできてしまう。むしろ、自分はリテラシーが高い、注意深く情報を得ているから大丈夫、と思っている人こそ、多かれ少なかれそれぞれの「泡」に閉じ込められている自覚をもつべきだ。
YNH (……)おそらく、21世紀を生きるにあたって知っておくべき最も重要な事実は、わたしたちがいまや「ハック可能な動物」だということです。
NT 人間をハックするとはどういう意味でしょうか。
YNH 身体や脳や思考といったレヴェルで、人のなかで起きていることを把握し、何をするか予測できるようになることです。人の気持ちがわかり、その先が予想できるなら、人の気持ちを改ざんしたり、操作したり、代替することだってできてしまいます。いまだ人間は完璧にハック可能だとは言えないし、100年前でもある程度のハックは可能だったでしょう。でも、現代とはレヴェルが違います。その分水嶺は、自分以上に自分のことを知っている誰かがいるかどうか、ということではないでしょうか。
ユヴァル・ノア・ハラリ+トリスタン・ハリス+ニコラス・トンプソン「人間はハックされる動物である」『WIRED』日本版 Vol.32 特集「DIGITAL WELL-BEING」(コンデナストジャパン)所収、P.39
私たちはもはや、簡単にハックされるようだ。「いいね!」した投稿や、クリックした広告、やり取りしたメッセージ、出かけた場所などのことを全部覚えていたりはしないし、その傾向から何が見いだされるのかなど、知る由もない。けれど「誰か」はそれを覚えていて、解析している。利用者どころか、管理者にさえ把握できないほどの、途方もない情報量に基づいた道具だ。そこに情報工学だけでなく生物工学的なテクノロジーが合わさると「身体や脳や思考といったレヴェル」に到達するという。私たちの生活にさらなる便利さ、さらなる快適さをもたらす一方で、その構造はもはや誰にもわからない、完璧なブラックボックスになっていく。
2018年、EUがGDPR(一般データ保護規則)を立法化したのは、GAFA以降のそうした流れに歯止めをかけるためだといえるだろう。メディア美学者の武邑光裕は、GDPRに関する自著の「おわりに」で、20世紀前半の有名な二つのディストピア小説(*4)を比較し「オーウェルではなくハクスリーが正しかった可能性について」30年以上前に警鐘を鳴らしていたニール・ポストマン『愉しみながら死んでいく』(*5)を挙げ、インターネット以降、その現実味がいっそう増していることを指摘している。
オーウェルは本を禁止しようとする独裁者を恐れた。ハクスリーは、本を読みたいと思う人が誰もいなくなり、本を禁止する理由がなくなる社会を恐れた。
オーウェルはわたしたちの情報を奪う者を恐れ、ハクスリーは、わたしたちに多くの情報を与え、人々が受動的な利己に還元されてしまう世界を恐れた。
オーウェルは真実がわたしたちに隠されることを恐れていた。ハクスリーは、わたしたちが真実とは無関係な情報の海に溺れてしまうことを恐れていた。
『1984年』が描いたのは、人々は痛みを負いながら制御されている世界だ。『すばらしい新世界』では、彼らは喜びを与えられることによって制御される。
オーウェルは、わたしたちが恐れるものがわたしたちを台無しにすると恐怖し、ハクスリーは、わたしたちが望むものがわたしたちを台無しにすると恐れた。
武邑光裕『さよなら、インターネット GDPRはネットとデータをどう変えるのか』(ダイヤモンド社、2018)P.224-225
未来の話には聞こえない。恐ろしいほど、現在進行形の話だ。私たちは既に、「自分以上に自分のことを知っている誰か」のつくりだす「泡」によって、多かれ少なかれ「受動的な利己に還元」され、「喜びを与えられることによって制御」されかけている。
自分の欲しそうなものが自動的に集まるのだから、もちろん気持ちがいい。個人としては「泡」に包まれているほうが幸福で、それを洗い流す必要などないようにも思える。けれど問題は、自分がハックされていることに気づきにくいことだ。もし意識的に情報を明け渡していたとしても、その構造がブラックボックスならば、そこに誰かのわずかな悪意が紛れ込んでも気づきようがない。
それでは「ハック可能な動物」である私たちはどのように、「自分以上に自分のことを知っている誰か」から身を守ればよいのか。憲法学者のキャス・サンスティーンは「エコーチェンバー(共鳴室)」、「インフォメーションコクーン(情報の繭)」、「デイリー・ミー(日刊・私)」といった概念を用いて、いち早く「泡」的なものの危険性に警鐘を鳴らしてきた研究者のひとりだ。サンスティーンは意外にも、建築・都市計画分野における古典中の古典である、ジェイン・ジェイコブス『アメリカ大都市の死と生』に着想を得たとしている(*6)。
サンスティーンは「歩道での触れ合い」を例に挙げながら、ジェイコブスが高く評価している都市の多様性、それを感じさせる街路や公園などの公共空間においては「エコーチェンバーを作るのはかなり難しく、人は選ぶつもりのなかった見解や情報とたびたび出会う」(*7)とし、個人が自らと異なる「他者」の見解にさらされることや、集合的な「共有経験」をもつことの重要性について書いている。
ここで、書店という空間について考えてみたい。誰でも自由に出入りすることができ、その店内を散歩し、買い物をせずに通り抜けることができる書店もまた、都市を構成する一要素であるといえる。同時に、そこに陳列されている本という物体は、知が凝縮された商品だ。研究者による長年の成果から、感情を動かす物語、消費を促す情報まで、あらゆるものが存在する。
そのように考えると、インターネットと同じく情報を扱う書店という空間は、人々をハックし「泡」を強化する場所にもなり得る一方、その手のテクノロジーから距離を取ることで、この時代を生きる人々を包む「泡」を薄めて洗い流すための、いわば「水」を得る場所として、重要な機能を果たし得るのではないか。
2019年現在、テクノロジーを駆使し世界一の売上を誇る書店は、言うまでもなくAmazonである。本を買うときに「あなたへのおすすめ」を参考にしている程度のことを、何を大袈裟にと思うだろうか。だがAmazonはいまや生鮮食品(Amazon Fresh)さえも扱う世界最大のオールジャンルの小売店であり、クラウドコンピューティングサービス(Amazon Web Service)でもトップシェアを誇りながら、利益のすべてをM&Aや研究開発に投資し、その内実はほとんど明かされない企業として知られる。いわば、多くのユーザーにとって「自分以上に自分のことを知っている誰か」の筆頭だ。ときにちょうど欲しいと思えるような本を、まるで偶然であるかのように薦めてくる。「泡」の書店の頂点に、Amazonがいる。
一方、たとえば筆者の経営する本屋B&Bにおいて、本の販売はアナログである。商品はスリップで管理されていて、POSレジさえも入っていない(7年経ってやっと、簡易なものの導入を検討しているところだ)。そこで売られている本は、インターネットとつながっていない、スタンドアローンの紙の束だ。誰かが選んで並べているものではあるが、それは誰かにパーソナライズされてはいない。そもそも著者がそこに何を書いているか、すべてを把握しているものは誰もいない。なるべく自分たちがいいと思える本を並べ、客に偶然の出会いを楽しんでほしいと考えている。
そのような書店を歩き回って紙の本を手に取れば、「自分以上に自分のことを知っている誰か」に知られることなく、「選ぶつもりのなかった見解や情報」と、およそ他のどんな場所よりも高い頻度で出会い、別の強い関心を持ったり、影響を受けたりすることができる。いつも似た情報にさらされ、知らずのうちにハックされかかっている人も、普段は自分のもとに届かない視点を、容易に手にすることができる。
リアル書店は、「水」を得るためのすぐれた場所になり得る。より踏み込んだ議論は後に回すとして、いったんテクノロジーの側から見える書店の姿としてこのような視点を提供した上で、続いては書店の側から現状を確認してみたいと思う。
*1 石田英敬「ハイパーコントロール社会について 文字学、資本主義、権力、そして自由」、石田英敬・東浩紀『新記号論 脳とメディアが出会うとき』(ゲンロン、2019) P.379
*2 イーライ・パリサー(著)井口耕二(訳)『フィルターバブル インターネットが隠していること』(早川書房、2019)十三頁。なお文庫化時に改題されており、初邦訳時のタイトルは『閉じこもるインターネット』(同社、2012)。
*3 「「ヘイトスピーチ」で更迭 年金機構・世田谷事務所長 | ハフポスト」https://www.huffingtonpost.jp/entry/news-ishido_jp_5c98336fe4b0a6329e184203
*4 ジョージ・オーウェル(著)高橋和久(訳)『1984年〔新訳版〕』(早川書房、2009)、原書初版は1949年刊行。オルダス・ハクスリー(著)大森望(訳)『すばらしい新世界〔新訳版〕』(早川書房、2017)、原書初版は1932年刊行。
*5 ニール・ポストマン(著)今井幹晴(訳)『愉しみながら死んでいく 思考停止をもたらすテレビの恐怖』(三一書房、2015)。原書初版は1985年。
*6 サンスティーンがこのテーマを扱う本は3冊あり、邦訳されているのは1冊目の『インターネットは民主主義の敵か』(毎日新聞社、2003)、および3冊目の『#リパブリック』(勁草書房、2019)。ジェイコブスに着想を得ていることは、どちらにも明記されている。
*7 キャス・サンスティーン(著)伊達尚美(訳)『#リパブリック』(勁草書房、2019) P.21
(3)独立書店と独立出版社――「課題先進国」としての台湾、韓国、日本 へ続く
初出:『ユリイカ 2019年6月臨時増刊号 総特集 書店の未来』
※上記は『ユリイカ』に寄稿した原稿「不便な本屋はあなたをハックしない」の一部です。2019年5月上旬に校了、5月下旬に出版されたものです。編集部の要望も踏まえ、しばらく間を空け順次の公開という形を取り、2019年8月にnoteでの全文公開が完了しました。
本稿以外にも多角的な視点で対談・インタビュー・論考などが多数掲載されておりますので、よろしければぜひ本誌をお手にとってご覧ください。
『ユリイカ 2019年6月臨時増刊号 総特集 書店の未来』
目次:【対談】田口久美子+宮台由美子/新井見枝香+花田菜々子【座談会 読書の学校】福嶋聡+百々典孝+中川和彦【未来の書店をつくる】坂上友紀/田尻久子/井上雅人/中川和彦/大井実/宇野爵/小林眞【わたしにとっての書店】高山宏/中原蒼二/新出/柴野京子/由井緑郎/佐藤健一【書店の過去・現在・未来】山﨑厚男/矢部潤子/清田善昭/小林浩【書店業界の未来】山下優/熊沢真/藤則幸男/富樫建/村井良二【海外から考える書店の未来】大原ケイ/内沼晋太郎
いただいたサポートは「本屋B&B」や「日記屋月日」の運営にあてさせていただきます。
