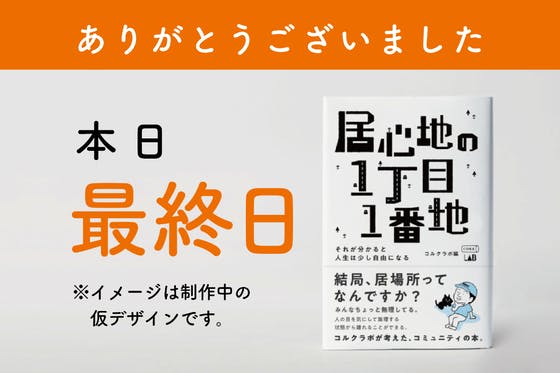「先生、高校辞めることにしました」
-----------------------------------------------------------------------------
忘れられないことばというのは、
いつか誰かに聞いてもらうまで胸にこびり付いて離れない。
でも、いつか聞いてもらってもそのことばをくれた相手のことを忘れることはあまりない。
忘れられないのは、ことばか、人か。
「二十歳の子がする目じゃない。寂しそう」
見透かすような、それでいて寄り添うような目を向けながらぼくにことばをくれた人。
しばらく言われたことばの意味も分からずぽかんとしていたぼく。
外から聞こえる土砂降りの雨の音よりも遠くに聞こえていた嗚咽が自分のものであるということに気づくのにもまたしばらく時間がかかった。
悲しみだけが涙の本質ではないと理解できるのは、先に向かって生きている者の特権だ。
欲しいものを手に入れるための手段としての獰猛な涙もあれば、
欲しいものを諦めた誰かの代わりに流す優しい涙もある。
どんな涙でも。
出し切った涙のあとに待っているものが本当の願いだと気付いたのは、わりに最近の話だ。
-----------------------------------------------------------------------------
◯先に生まれただけのぼく
「久しぶり、元気しとんね。あんたが教えてたあの女の子覚えと〜ね?◯◯ちゃんよ。この前ウチに急に遊びにきてくれたんよ。なんか、高校辞めるみたいなこと言いよんしゃーて。それを、あんたにどうしても報告したいって言って聞かんかったちゃん。あんたのLINE教えるまで帰らんって言い出したけん、勝手に教えたばい。(笑)あんたなら上手く対応できるやろ〜けん。近いうちに連絡あると思うけど、よろしく頼むばい」
二十歳の時。
家庭の事情が複雑だったり金銭的に困窮している中高生の学習のサポートを行うNPOにボランティアとして入っていた。
なぜ入ろうと思ったのかはうろ覚えだけど。
たぶん、自分ではどうすることもできない外部要因が不可抗力的に作用して将来の可能性を閉じざるを得ない10代の子たちに過去の自分を重ねたのだ。
今思えば。
当事者であるその子達の力になりあわよくば救うことで、ぼくの中にいる"救われたかった過去のぼく"を救いたかったのかもしれない。
だから、ぼくのエゴだ。
そのNPOの団体でお世話になっていた狸親父みたいなおじさんから久方ぶりにLINEをもらったので何事かと思って開けてみたら、ちょっと面倒くさそうな内容だった。
好々爺然とした彼のしたり顔が目に浮かびまたいつかどこかで一緒に飲みたいなと思いながら、
りょーかい、くそじじいとだけ返した。
本当に、彼の言った通り翌日すぐに連絡が来た。
「先生、久しぶり!あたしのこと覚えとー?」
久々、覚えてるよと返すと報告したいことがあるから夜電話したいとのことだった。
空いては、いる。
むしろ暇である。
でも、20代も半ばに差しかかろうとしている男と選挙権もない歳の女の子が夜中に電話するって客観的にいや社会的にどうなんだろうと考えながら、同時に彼女のことも思い出す。
年齢には不必要なくらい大人びた雰囲気を持った子というのが最初に抱いた印象だ。
当時のスタッフの間で「あの子は男性が怖いらしいから男性スタッフはあまり近寄らないように」という御触れが出ていたので、ぼくも挨拶くらいしかことばを交わしたことはなかった。
ところが、たまたま女性スタッフがほとんどいなかった日があり彼女への授業をぼくが担当することになったのだ。
授業の終わりに「ばりわかりやすかった!ありがとっ」と年相応の無邪気な笑顔を向けてくれた時は少し安心した。こんな顔もできる子なのかと。
その後、先出のおじさんの「あの子、あんたを担当にして欲しいらしけん。頼んだ!癖はあるけどあんたなら大丈夫やろ」という鶴の一声ならぬ狸の一声で彼女を担当することになったのだ。
授業の合間に話を聞いたりしていくうちに少しずつ彼女のご家庭の事情も知っていく。
家族の話をする時に浮かべる彼女のひどく、年齢に合わない他人事のような超越的な笑みは見覚えがあった。
複雑な家庭環境で育った、大人への階段を4段飛ばしくらいで駆け上がるよう急かされた人間のそれ。
身に覚えがあるといった方が正しいか。
そんなことを逡巡していると、返信がないことに不安を覚えたのかお願いしますと敬語でダメ押しするようにLINEが飛んで来たので、夜にこちらから電話するという旨を伝えた。
それにしても。
先生、と言われることになんだかものすごい抵抗があることに気づく。
よくよく考えてみると随分大層なことばだ、先生って。
◯学校では生き残れなかった彼女
「...............先生、高校辞めることにしました」
ひとしきり、
今は何をしてるのか日本には帰ってきたのか元気にしてるのかエトセトラ、、てんやわんやで根掘り葉堀りぼくの話を聞き出した後に、一息置いて意を決したように彼女は言った。
人間というのは本当に言いたいことを言うまでには時間がかかる生き物なんだと思う。
学校を辞める理由は、彼女のクラスの担任の先生をクラス全員でいじめるという状況に耐えきれず文字通り息ができなくなったから。
いじめられたからではなくいじめるということに耐えられなくなった、それも先生を。
担任の先生はとても優しい人で、怒ったりもせずただ悲しい顔で我慢して耐えていたそうだ。
生徒を傷つけるかもと思うと何も言えない、と保護者会で言っていたらしい。
生徒が先生をいじめるなんてことがあるんだと純粋にとても驚いたのだけれど、同時に彼女らしい理由だとも合点がいった。
思えば、彼女は初めて会った中学生の頃からうまく本音を言えない子だった。
当時ぼくが彼女に学習指導していた場で、そこに来ている子たちの中にもある種カーストのようなものは見え隠れしていた。
特に女の子たちの集団は顕著に階層ができており、ぼくを含む教える側の人間や狸親父にキツい言葉を浴びせて笑いを取るような行為を取る子も少なくはなかった。
そんなカースト上位にいるボスザルのような女の子たちと共に、彼女はいつも貼り付けたような笑顔でメンバーの一員としてそこにいた。
彼女の笑みはたまに泣いているようにも見えたのだけど、目を凝らしてみても涙は流れていなかった。
時折、彼女は本音を明かしてくれることもあった。
「みんなね、色々あるとよ。やけん、苛々するのが抑えられんっちゃん。みんなの気持ちもわかるし、友達やし、嫌われたくないけん、言えんこともある。でも、たまに疲れるっちゃん。」
そう言って、彼女はまた笑った。
ボスザルにもボスザルにならざるを得なかった歴史がきっとある。
他者への攻撃として外側に出すことでしか消化できないくらいの痛みがあったのだ。
自分一人で抱えきれなかった痛みは、その痛みを引き受け理解してくれそうなところに攻撃へと形を変えて向かっていく。
それにしても、思春期の女の子たち特有のあの歪な一体感はなんなのだろう。
疑似家族。疑似居場所。疑似恋愛。
どれも当てはまるような気もするし、すこし違うような気もする。
彼女が進学した女子高なんてそんな歪な関係性の宝庫だし、自分の身の置き所を見つけ生きていくためにきっとまたあの笑顔を纏っていたはずだ。
そんな場で生き残るには、彼女は少し繊細すぎたのだろう。
ごめんなさい、
色々お世話になったのに、本当にごめんなさい
先生にもあの場所にも本当に色々してもらったのにごめんなさい
画面越しから流れてくる彼女のごめんなさいという声をぼくはずっと聞いていた。
彼女はぼくに涙声でひたすらに謝り続けた。何かを懇願するように、懺悔するように。
ぼくに謝る必要なんて何もなかったし途中でそう伝えようかという考えも過ぎったんだけど、ただ黙って聞くことにした。
涙も想いも抑えてなきものにしてきた感情たちは一度全部出し切ったほうがいいんじゃないかと思ったのと、
なんだか彼女は何かに許されたかったのかもしれないと感じたから。
ひとしきり、
涙を流し終わったあと彼女は少し照れたように、いきなり泣きだしてごめんとぼくに言った。
気にしなくていい、と伝えると
「先生は、学校辞めるなって言わんと?」
と不思議そうな声で問いかけてきた。
確かに。
どう考えても高校は辞めないほうがいい。何か特別な才能や目標がない限り、高校を中退するメリットより高校を卒業して得られる社会的なメリットのほうが圧倒的に多いのは周知の事実だ。
地方で中卒。低学歴の世界。自己責任論。SNSで度々トレンドになる日本の溝は実際にある。
ぼくの周りにいる東京在住の友達にもそんな溝から僅かなチャンスを手繰り寄せ、死にものぐるいで這い出てきた奴は少なくない。ぼくもそうだ。
地方の田舎特有のコミュニティの中での常識感、手取り13万円もいかない給料、高校を辞めてホストかキャバクラに行った奴がなぜか一瞬勝ち組風その後転落。そんな環境から抜け出すために出来ることは何でもやってきた。
だから、わかる。高校には行っといた方がいい。チャンスが転がってくる数も角度も全然違う。チャンスをチャンスだと理解できる教養は必要だ。できれば大学にも行っておいたほうがいい。
これまで相談して彼女を辞めさせないように説得してきただろう大人たちが言ったことはおそらく全て正しい。絶対に。
当然、彼女もそれをわかっているはずで。ただ行かないという選択肢を選んだ未来に現実感がないだけだ。
行ったほうがいいとわかっているしその権利もあるのに選挙に行かない大人も当たり前に多く存在するように。
それでも絶対に辞めたらダメだなんてことは言えない。
ぼくも学校が嫌いで仕方がなかったから。実際に物凄くよく休んだし出欠日数ギリギリで卒業した。
学校が居心地がいいなんて思ったことはないし、中高から今も関係性が続いている友達なんて一人もいない。
社会的なある程度の信頼と少なからずの教養を得るためのメリット以外で学校に行く必要性は当時も今も感じていない。
そんな偏ったぼく個人の背景を踏まえて、これまで彼女の未来を考えていつか後悔しないように辞めないべきだと諭してきた大人たちと同じ道は踏まず、今の彼女のギリギリの心を正論で壊してしまわないように聴くという選択肢を取った。
何より惰性で辞めようとしてるのではなく、自分の心を大事にしようと考えた彼女の意思を曲げるようなことをしたくなかった。
それにもう彼女は自分の中で答えを明確に決めきってるんじゃないかとも思ったから。
全部、綺麗事かもしれないけれど。
概ねそんなようなことを伝えると、実はもう退学届も出し終えてしばらくは家の仕事を手伝いながら弟たちの面倒をみると彼女は言った。
そして、
「先生も、居場所がなかったん?」
と、ぼくに聞いた。
とにかく、
水商売とかは今は辞めておけ、仕事を探すとか何か困ったことがあったら信頼できる人を紹介する。
だから遠慮せずにぼくにできることがあったら言ってくれ。
彼女からの質問をそれとなく躱して大人っぽいことを伝え、電話を切ったのだけれど。
居場所がなかったのか、
彼女の声がぼくの中で反芻されていく。
問いの破片が胸に少しずつ刺さっていくような感覚に、電話を切ってからもしばらく身動きが取れなくなった。
彼女のまっすぐ過ぎる問いにより、断片的に記憶が手繰り寄せられていく。
◯学びとして生存戦略を獲得したぼく
「二十歳の子がする目じゃない。寂しそう。何があったの」
二十歳の時のとある企業のとある人事から寂しさを指摘された雨の降る夏の夜の記憶。
胸を貫かれたような感覚をくれた人は、彼女とそのとある人事くらいか。
当時はまさか、彼女とその人事がいずれ会うことになるなんて思いもしなかったのだけれど。
記憶の中では、何人も人がいる前で涙を抑えきれなくなったぼくがいた。
泣く、ぼくが。しかも、寂しいとか言われて。
切ったと思っていた涙腺の存在に驚かされた二十歳のぼくは、いつからこんな風になったんだろうと思い返しながらことばを紡いでいた。
二十歳は、はじめて彼女に会った歳でもある。
その時のぼくは、大切にしたかったはずの願いの片鱗に触れ始めた時期だったように思う。
本気で向き合ってくれる人とことばが、救われたかった自分の存在に気づかせてくれた。
*
「あいつ、ジャニーズジュニアらしい」
ぼくにとって二度目の不都合な転校は中学三年の時だった。
ようやく馴染み始めた私立の中学を辞めたのは家庭の経済的な要因があった故だ。
ぼくの意思ではなかったが親の懐事情を無視できるほど幼くもなかったし、そうですかとすぐに受け入れて感情の整理がつくほど大人でもなかったように思う。
転校先は地元の中学校。ガラが悪く荒れていると評判の。
転校初日は文字通り全校生徒がぼくを見にわざわざ教室に押しかけてきた。
晒される、ということばの意味をぼくはあの時にはじめて知った。
火のないところに煙は、とはよく言ったもので。
事実、芸能の事務所には入ってはいたがみんなが口を揃えて言う事務所ではなかった。
誰がそんなことを言い出したか知る由も無かったのだけれど、田舎の噂の立ち登りの速さは尋常じゃ無い。
噂というのは人類共通の娯楽だ。そして娯楽とはすなわち暇つぶしのことである。
ぼくはそんな暇つぶしの格好の的だった。
「おい、ジャニーズ」
そんな風に貶めるように揶揄することによって優越感を取ろうとする輩が三割。
ただ不躾に奇異な目線を向けて内輪で内緒話に勤しむ輩が三割。
上履きを隠したり机にジャニーズと落書きをして身内間で笑いを競い合っていた輩が三割。
その他、有象無象。
友だちはいなかったのかと聞かれたら。
いた、たぶん。
「おい、ジャニーズ。俺もジャニーズ入れてよ」
"友だち"と昼休みに教室で話をしていた時だった。
醜悪なにやけ面を引っさげて彼は机を蹴りながらぼくのところにやって来た。
いつもなら相手にしなかったのだけど、その時はなぜか。何かが切れたのか。
たぶん、君の顔じゃ無理だと思う
とぼくは言った。
あの時の場が凍りついた感覚は今でもよく覚えている。
ぼくにブサイク認定された彼は無表情で何も言わずに教室から出て行った。
10分くらいして、また"友だち"と談笑をしていたぼくの元に彼は帰って来た。
彼は彼の"友だち"を5,6人引き連れて。
「お前の"友だち"にちょっと用事あるけんさ」
と、彼はぼくの"友だち"に言った。
そう言われた時も、彼らがぼくの肩を掴んだ時も、ぼくの"友だち"はぼくに目を頑なに合わせなかった。
でも、ぼくと彼らが教室から出る瞬間だけ。
一瞬目は合った、と思う。たぶん。
そのあとのことは、あまりよくおぼえていない。
*
高校に入ってからも幾分マシにはなったが奇異な目線は続いた。
有難いことに、同じ中学出身の輩が噂を広めてくれたからだった。
学校に身の置き所もあまりなかったし、家に帰っても両親の紛争の仲介で夜が明ける。
普段は事務所のモデルの先輩方と遊ぶことの方が多かった。年も離れていたし、干渉されない感じがすごく楽で。
でも、ぼくは家族のことは嫌いではなかったから家に帰らない非行少年のようにはならなかった。
父と母の方がぼくより救われたい気持ちが強かったから、なんとかしたかったんだと思う。
でも、たまに一人の時間を渇望した。
誰の間にも立たなくいいい時間。
誰の目にも晒されない時間。
一人になることがぼくにとっては最高の娯楽だった。
そんな感じの中高を過ごして獲得したぼくの無意識に根付いた生存戦略は、
誰に見捨てられても、誰がいなくなっても
ひとりで生き残れるように強く賢くなること。
この生存戦略は、ぼくの痛みの結晶体だ。
強くなれば、守ってもらわずに済む。
賢くなれば、傷つかずに済む。
一人でいれば、もう一人にならなくて済む。
もし痛みの裏側にあるものが願いだとするならば、本当は。
誰かと繋がりたかった。
誰かに守って欲しかった。
誰かに助けて欲しかった。
本当は誰かといたいのに、一人になりたいぼくはこうして生まれた。
◯
もし"救われたかった過去のぼく"に居場所とは?と投げかけてみても、
綺麗事、としか返ってこないだろう。
今でも、居場所ということばについて考えようと頑張ってみてもいつも思考が止まってしまう。
ぽか〜ん、とどこか遠くにある美しい国の、日本語には翻訳できないことばのように感じる。
でも最近、そんな綺麗事を全力で作りあげようとしている居場所を知った。
コルクラボという名前だ。
どんなコミュニティかというと、愛のあるジャングルみたいだと個人的には思っている。
作家や漫画家、編集者もいれば人材紹介会社やベンチャーに勤める人、ニートからぼくのような猪口才まで多様な個性に富んだジャングルみたいな場所。
でも、弱肉強食とは程遠い。
"安全・安心"という前提の価値観を大切にしているからだ。
初期のコルクラボは"熱狂"という価値観を念頭に置いたことにより"熱狂疲れ"を感じて去った多くの人がいた過去があるらしい。
その際に、"熱狂"の前に"安全・安心"を確保する必要があるんじゃないかという価値観の見直しがコミュニティ内で行われたとのことだった。
強すぎる価値観は信念へと形を変える。
そして、信念を守ろうという意思が強すぎるとそのせいで崩壊してしまう人や環境もある。
だから、凝り固まりそうな信念を手放す勇気があるのも面白いコミュニティの条件のひとつだ。
そんな"安全・安心"を前提にしてコミュニティを運営してきた知見が詰まった本がでる。
学級の運営や組織の運営などに興味のある人は手にとってみてはどうだろうか。
個人的な見解だが、誰かの身を粉にした献身や犠牲の上に成り立った"安全・安心"を謳うコミュニティに未来はない。
ぼくの教え子の彼女の担任の先生は、うまくクラスを回そうという意識に本音が潰されてしまったようにぼくは捉えた。
きっと、自分のではなく、クラスの"安全・安心"を守るのに疲れていたはずだ。
優しい人こそ、まずは自分の好きな自分でいることや自分の居場所を分かることが必要不可欠だ。
本音をわかってもらうことを諦めてる人や、傷ついたことを傷ついたと言えなくなった人。
そんな人たちが主語を"私"にしても罪悪感を感じなくなる糸口が、この本から見つけることができるかもしれない。
コルクラボにも優しい人が多い。
てか、優しくない人をあんまりみたことがない。中にいて凄く感じる。
だから、もしかしたらコミュニティとして"安全・安心疲れ" に直面する時が来るかもしれないと思ったりもする。
それでも大丈夫なんじゃと思うのは、優しさの中に強さがある人もまたいるからだ。
強さとは、
自分をわかってもらう努力も人をわかろうとする努力も怠らないこと。
そして、ありがとうもごめんなさいも丁寧にできることだ。
だから何かにまたいつか直面しても、
互いの安全安心を知りあい
本音のことばを紡ぎあい
好きも嫌いも分かちあい
頼り頼られあい
そんな、いろんな"愛"で乗り越えていくんじゃないかと思う。
目を背けなかった真実を分かち合う強さを持った人たちが、居場所をまた進化させていくと思う。
その過程をもし生で見たかったら、暇な時にでもこっそりコルクラボに遊びに来たら良きである。
ぼくはたぶん端っこの方にいるので、声をかけてくれればうれしい。
P.S. 学校を辞めて生きていく彼女
最後にちょっと、教え子の彼女に触れておく。
「先生の知り合いにブライダル系の仕事しよる人とかおらん?」
電話で話をしてからそう時間を置かずに、また彼女からLINEが飛んできた。
ひとしきり、
我慢してきたことを親にも泣いてぶちまけたら親との仲もちょっと良くなったこと。
泣いてスッキリして色々考えてみたら昔ウェディングプランナーになりたいという夢を思い出したこと。
だから、そういった知り合いがいれば話を聞きたいので紹介して欲しいということなどまた矢継ぎ早に連絡をくれた。
そこで、二十歳のぼくの寂しさを指摘してくれたとある人事がブライダル系の企業の中の人だったのを思い出し相談してみたところ、彼女に会うことを快諾してくれた。
図らずも頼もしい偶然だ。
きっと寄り添いながらも彼女の現状に沿った適切な助言をしてくれるだろうと思ったが、彼女からの報告のLINEを見ると想像以上に彼女が前を向くための糸口をくれたようだった。
「緊張したけどほんとに話聞き行ってよかった!やっぱり夢やし諦めたくないけん、家のこと手伝いながら勉強して資格も取る!先生、ありがとっ」
大人びていない年相応の彼女の晴れやかな笑顔が脳裏に浮かぶ。
縁というのはこんな風に紡がれていくんだとどこか不思議な気持ちにもなった。
「てか、先生は夢あると?」
彼女からの真っ直ぐな質問を躱すのはもうやめようと思って、書きたい物語があると答えた。
小説家になりたいのかと聞かれたので、なんだか恥ずかしくなって少し曖昧にことばを紡ぐ自分に気づき、
こんな調子でうかうかしてたら彼女の勢いに追い抜かされることになるなとも思った。
ぼくも来月で四半世紀を生きたことになる。
年を重ねることで何かを諦めて、自分に対しての言い訳ばかりを上手にするわけにもいかないし。
教え子だった彼女の背中を追いかけるわけにもいかないのだ。
先に生きると書いて先生と読むのだから。
※この物語はノンフィクションです。実在の人物も場所もコルクラボも存在します。
この御恩は100万回生まれ変わっても忘れません。たぶん。