
アファンタジア.log (2024年04月)
🍅2024-04-05|#1
1/
最近、アファンタジア命名者(Zeman, 2015)によるアファンタジア10周年のレビュー論文が公開された。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-05|#2
2/
これと足並みを揃えるかのように、英米ニュースメディアのBBCとCNNの両方がアファンタジアに関する興味深いコンテンツを配信した。
BBC ⇒ https://www.bbc.com/news/health-68675976
CNN ⇒ https://www.cnn.com/2024/03/27/health/aphantasia-hyperphantasia-visualization-wellness
🍅2024-04-05|#3
3/
このことにより、英語を理解する世界中の地域/人々に、アファンタジアという用語およびそれを持つ人がどういった経験をしているのかの一例が、より広く知れ渡った。(アファンタジアをメシのタネにしている人にとっては朗報だろう)
🍅2024-04-05|#4
4/
これが良い結果をもたらすかそうでないかは自分には分からないが、個人的に懸念はある。例えばアファンタジアを扱う英語圏メディアでしばしば遭遇するフレーズのひとつに「家族の顔が浮かばないので悲しい/不安になる」というのがある。以降は完全に個人の空想だが、
🍅2024-04-05|#5
5/
家族との(ベタベタした)絆の深さが(実質的にあるいは建前的に)美徳化してそうな善良なる○○人的価値観にとって、「家族の顔が浮かばない」という内的現象は耳目を集めるウケのよいグッとくるエピソードに違いない。
🍅2024-04-05|#6
6/
「可哀想」「薄情」「信じられない」「愛情が足りない」「アイムソーリー」等々、いろいろな反応があるだろう。あとは察してほしい(空想ここまで)。
🍅2024-04-05|#7
7/
以降はあくまで自分(VVIQ=16)の場合だが、「家族の顔が浮かばない」からといって悲しんだり不安になるといったことは、これまでただの一度もない。そのような経験は自分にとって普通のことだし、「浮かぶ」人の経験と「浮かばない」自分の経験をネガティブな意味で比較したこともない。
🍅2024-04-05|#8
8/
心の中で視覚化されないからといって、虚無があるわけではない。記憶(SDAMを持つ自分の場合は主観的再体験を伴わない意味的記憶)や感情(同左)はあるし、外部媒体記録(写真など)もある。だが、言いたいのはそういうことではない。
🍅2024-04-05|#9
9/
そういった記憶や感情も、それが豊かであろうと希薄であろうと、いずれは霧散するのが世の常で、万物は流転し諸行は無常だ。どうということはない。誰もが経験するし誰もが死後を経験しない。話がズレてきたので終了。
🍅2024-04-05|#10
面白画像

🍅2024-04-05|#11
1/
先日、アファンタジアに関する最新論文が公開された。
和訳:アファンタジアと不随意のイメージ
表題:Aphantasia and involuntary imagery
著者:Raquel Krempel, Merlin Monzel
公開:2024年4月1日
https://doi.org/10.1016/j.concog.2024.103679
無料で読める要旨と序章だけを読んだ。以下に感想を記す。
🍅2024-04-05|#12
2/
アファンタジアはしばしば随意の視覚イメージ不在と定義される。随意(voluntary)とは自らの自由意志で意識的という意味であるから、
🍅2024-04-05|#13
3/
その逆の不随意(involuntary/spontaneous)すなわち意志によらず無意識的/自然発生的に起こる現象(例えば夢や幻覚や閃光)は、アファンタジアの定義とは関係ないとされ、多くの研究で無視されている。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-05|#14
4/
現状、ほとんどの研究は細部を省略した大雑把なアファンタジア定義しか持っておらず、随意のみに焦点をあてるのか?不随意の現象は無視していいのか?、イメージの不在のみに焦点をあてるのか?それとも複雑多様な希薄スペクトラムも含ませて範囲を広げたいのか?、
🍅2024-04-05|#15
5/
視覚イメージのみに焦点をあてるのか?他の多感覚イメージはどうなのか?、等々、多くの曖昧さや裾野の広がりを含んでいる。この件に関してはBlomkvistによる2022年の論文「Aphantasia: In search of a theory」に詳しい。
https://doi.org/10.1111/mila.12432
🍅2024-04-05|#16
6/
こういった状況において本研究は、まずは随意/不随意にかかわらず、視覚イメージの不在(または希薄)を特徴とする広範な現象をアファンタジアと関連付けて深掘りすべしと主張する。もっともな主張だと思う。
🍅2024-04-05|#17
7/
いち当事者として、アファンタジアという用語や概念の曖昧さには辟易しているので、緻密な議論を期待したい。2015年から本格的な研究がはじまったばかりのアファンタジアだが、次の10年はこのテーマに関する合意形成を期待したい。
🍅2024-04-05|#18
アファンタジアの研究はお世辞にも盛んとは言えない。何故か? 以降は個人の空想だが、「利益(地位・名誉・カネ)にならない」「他にやることがある」「興味がない」「ニーズがない」「地味」「(当事者が)日常で困ってない」「主観的体験だから」などが思いつく。つまり、優先度・重要度が低い。
🍅2024-04-06|#19
アファンタジアはリアル視覚認知に影響を及ぼす。これを「ディープ・アファンタジア」と名付ける。という論文を発見。眉唾?新たな事例?微妙なnaming?
Deep Aphantasia: a visual brain with minimal influence from priors or inhibitory feedback?(2024年4月5日)
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1374349
🍅2024-04-07|#20
1/
共感覚という現象がある。例えば、文字に色を感じたり、音に色を感じたりするそうだ。自分は共感覚に関する知識も経験もないので以降は凡人の空想だが、色(光)を感じるというのは視覚的な経験なのだろうか?
🍅2024-04-07|#21
2/
そうだとすると、その感じた色は視覚知覚(実際の目)で感じるのか? あるいは視覚イメージ(心の目)で感じるのか? それとも別の何かで感じるのか? どれなのか?
🍅2024-04-07|#22
3/
視覚知覚で感じるとしたらそれは幻覚の一種なのか? 視覚イメージで感じるとしたらそれは心的イメージなのか? いずれの現象も不随意の(無意識的で自然発生的な)反応なのか? 不随意だとしたらやはり幻覚的なものなのか?
🍅2024-04-07|#23
4/
等々、いろいろ気になるが、ここまでは前置きで本題はここから。自分は未経験だが、人類のほとんどは「何かを想像したとき、頭の中にその何かの視覚イメージを感じる」という経験が多少なりともあるそうだが、これって共感覚的な反応と似てると思った(おそらく見当違い)。
🍅2024-04-07|#24
5/
だって「視覚的な何かを想像したら、目の前に存在しなくても、心の中にそれの視覚的な感覚を感じる」んでしょ? 目の前にその事象がなくても多少なりとも心の目で脳内映像が見えるんでしょ? 実感しちゃうんでしょ? その意識(刺激)⇒感覚の連動(誘発)って共感覚に似てるじゃん。
🍅2024-04-07|#25
6/
で、アファンタジア(視覚イメージ不在)はこれがない、なんてことを考えた(おそらく的はずれ)。ちなみに先行研究によればアファンタジアの人が何らかの共感覚を持つことはあるそうだ。
🍅2024-04-09|#26
1/
以降はあくまで研究とは縁のない知的平民からの私見だが、
物語理解時の共感的反応における視空間的処理と心的イメージの関連性
細川亜佐子・北神慎司
https://doi.org/10.5265/jcogpsy.21.101
この論文で語られるアファンタジアに関する知見は、
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-09|#27
2/
アファンタジア当事者であった故Kendle氏による書籍からのものであり、それは学術研究というよりも、Kendle氏を含む多数の当事者らによる主観的体験記の列挙といった趣なので、根拠としては弱いかな?と個人的には思った。
🍅2024-04-09|#28
3/
なお、本論文が結論付けている「視空間的処理の活性化と心的イメージはそれぞれ独立したプロセスであることを支持する」の「視空間的処理」が何を示すのか学術素人の自分にはよく分からなかったが、それが空間や位置、距離などを把握する能力に関する処理のことだとしたら、
🍅2024-04-09|#29
4/
下記のアファンタジア研究の知見は、本論文の結論を支持するようにも思えた。
Quantifying aphantasia through drawing: Those without visual imagery show deficits in object but not spatial memory
Wilma A Bainbridge
https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.11.014 .
🍅2024-04-09|#30
5/
ちなみに自分はアファンタジア(VVIQ=16)ではあるが、空間の把握が求められる日常の課題で問題になったことはない(おそらく空間把握能力が人並みにある)。ただし、別のアファンタジア当事者の知人は道によく迷ったり場所を把握できないことがあるそうだ(おそらく空間把握能力が低い)。
🍅2024-04-10|#31
なぜ我々の知的文明は2015年までアファンタジアを発見できなかったのか?
https://www.reddit.com/r/Aphantasia/comments/1bzq70x/why_didnt_our_intelligent_civilization_discover/
古来、人が生きていくうえで視覚イメージがどうのこうのというのは、どーでもいいことだし、そもそも気づくに値する現象でもなかったが、近年ネットが浸透したおかげで自他の主観世界の違いに気づくようになった。
🍅2024-04-10|#32
1/
詳しくは知らないが、かつて1970年代に、視覚イメージの本質について認知心理学の界隈を二分する激しい論争(Kosslyn / Pylyshyn 論争)があったそうな。K氏「イメージとは実際の目と同じように心の目がみる絵的なもの」(まず絵ありき?)、P氏「いやいやイメージとは記憶された情報の
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-10|#33
2/
意味的な着想が心の目に見せる絵的な表現にすぎない」(まず意味ありき?)みたいな論争だったそうだが(適当です)、当時、先天的に視覚イメージ不在の人(最近の研究では1%、ニアを含めると4%の出現率)の話題がメインテーブルに載らなかったのは何故だろう? 研究者本人や知人の中にも
🍅2024-04-10|#34
3/
イメージ不在な人はいたんじゃないの? 研究者総数がさほど多くなかった? 気づかなかった? 1880年の英Galton文献もあるし、1973年にVVIQを開発した英Marksだってイメージ不在を(VVIQ理論上は)認識してたんじゃないの? なんで学術は2015年まで明示的に気づかん?
https://www.reshannereeder.com/objective-imagery-history
🍅2024-04-11|#35
目を閉じて目の前にあるものを1ミリも思い浮かべることさえできないなんて、本当にイライラします!アファンタジアには実際に良い点はあるのでしょうか?
https://www.reddit.com/r/Aphantasia/comments/1c0bq2a/i_get_really_upset_that_i_cant_even_close_my_eyes/
とくに良い点はないが、とくに悪い点もない。
🍅2024-04-11|#36
時効だから言うけど、過日、MRIに入って長めのタスク実施中に何度もウトウトした。MRIに長く入ると眠くなりますって伝えたのに、当然がんばってこなしてもらわないと的な空気だったから仕方ない。事後報告はしなかった。学術研究のfMRI実験で良いデータが得られないとしたら理由があるかもしれない。
🍅2024-04-11|#37
Deep Aphantasia的な事例だとしたら非常に興味深い。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-11|#38
ちなみに自分(視覚イメージ不在 VVIQ=16)はこの画像で人の顔を連想できるからDeep Aphantasia的なものは持っていないようだ。
🔗引用した投稿(添付画像に注目)を表示する
🔗この話題のスレッド全体を表示する
🍅2024-04-13|#39
1/
イメージ能力が低いアスリートのためのイメージトレーニング
2024年4月8日
https://doi.org/10.1080/10413200.2024.2337019
感想: 身体の動きや体感を心の中でイメージしたり、未来に向けて何らかのビジョンを心の中でイメージすることは、スポーツに限らずあらゆる分野で活用される能力だそうだ(←耳学問で知った
🍅2024-04-13|#40
2/
知識だが実感がないので憶測でしかない)。アファンタジアを持つ人はこのイメージ能力がない(あるいは一般より低いとされる)。ならば、自身が装備しないイメージ能力を前提とするトレーニングやカウンセリングは今すぐやめて、別の方法を模索すべきだろう。例えば、心的な感覚に頼れないなら
🍅2024-04-13|#41
3/
リアルな感覚のほうに焦点をあてたり、心的な感覚以外、例えば言語/論理/抽象を用いた思考や行為に焦点をあてる。また、パフォーマンスとアファンタジアを両立してる人が身につけているメソッドや習慣を真似る。最終的に何をやってもダメなら断捨離る。等々、先天的にアファンタジアを持つ人なら、
🍅2024-04-13|#42
4/
こういった対応を無意識のうちに会得している人も少なくないかもしれない。イメージ能力を扱うプロフェッショナル(例えばスポーツトレーナーや精神科カウンセラー)の場合、こういった知見を理解したうえでクライアントの特性に応じた戦略が求められていると思うが、現場はどうなってるんだろう。
🍅2024-04-13|#43
5/
現場と言えばもう一つ「教育」という大きな分野があるが、今回は詳しく触れない。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-13|#44
https://www.reddit.com/r/hyperphantasia/comments/1c1lipx/movielike_imagination_when_reading_novels/
こういうのを読むとほんと現生人類の脳(感性)って一種の魔法のように思う。
だって目の前に対象がないのに、それが鮮明に思い浮かぶなんて!

🍅2024-04-13|#45
Reddit のコミュニティー「r/Aphantasia」のユーザーである Tuikord さんのコメントは参考になるので毎回読んでる。
コメント ⇒ https://www.reddit.com/r/Aphantasia/comments/1c2ezbp/comment/kz9z5dd/

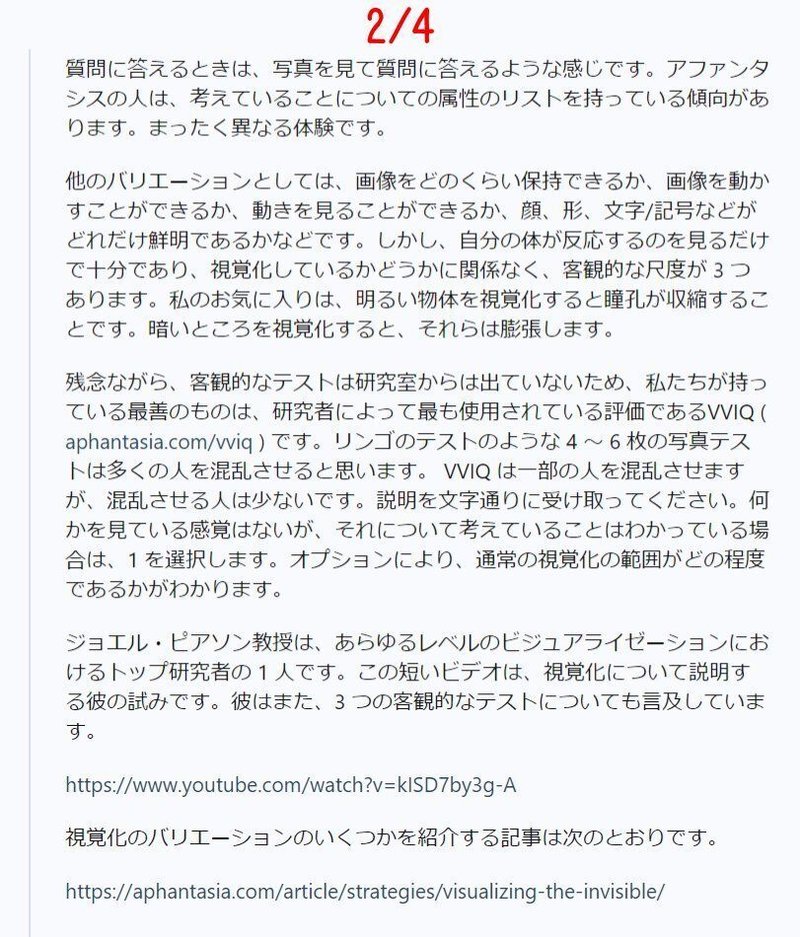


🍅2024-04-13|#46
心の中での視覚化や内言がなければ、人はどうやって考えるのでしょうか?
https://www.reddit.com/r/Aphantasia/comments/1c2pvym/comment/kzbr9l0/
FlightOfTheDiscords氏のコメントが面白い。自分もそうだ。心(潜在意識)は事象について「ただ知っている」を心(意識)に供給する感じ。自分はこれを着想/気配/情報/概念などと呼んでる。
🍅2024-04-13|#47
文章表現に関しても入力前に何も起こっておらず(思考してない)、入力と同時に着想され媒体に言葉(思考)が構成(表出)されるという感じ。しばしば心的感覚でもなく内的言語(非音声)でもない非記号化思考な感じ。これもよく分かる。
FlightOfTheDiscords氏のコメント ⇒ https://www.reddit.com/r/Aphantasia/comments/1c2pvym/comment/kzbr9l0/
🍅2024-04-15|#48
1/
SDAM(先天的な自伝的記憶重度欠落)を説明するのは難しい。あくまで自分の場合が、端的に言うと、随意に浮かべる過去の自分の経験に関する思い出の絶対量が極めて少なく、浮かんだとしても詳細が希薄で短い箇条書き的な意味的着想がぽつぽつ供給されるだけ。
🍅2024-04-15|#49
2/
外部刺激や内部着想から連想される不随意の思い出に関してもほぼ同様で、一般的とされる心的タイムトラベル(心の中で思い出が擬似的に再現され、当時経験した情景/感覚/感情などが心に浮かぶ主観的体験)は一度も経験したことがない。
🍅2024-04-15|#50
3/
そんな感じだから成人までの記憶はほぼ全部ない(よほど印象に残った事象の短い意味的記憶くらい)。主観体感的には成人までの自分の存在/自我/記憶は99.9%以上消失してる(あるいは意識に浮上しない)。大人になり結婚した後は多少の思い出が増えたもののやはり同じ傾向で、
🍅2024-04-15|#51
4/
思い出すという行為は短い意味的着想の列挙でしかなく、過去の感覚/感情/状況など何もかもが短い着想(抽象だったり言葉だったり)に圧縮される。こんな人生だが、SDAMに由来してこれまで日常や仕事(IT技術系)で問題になったことはないし、主観的に問題と思ったこともない。
🍅2024-04-15|#52
5/
SDAMは、他者や社会に対して自分が果たす責任/役割/機能には影響しない。その点はアファンタジア(先天的に随意の心的イメージ不在)も同じ。なんら問題ない。
🍅2024-04-15|#53
1/
あくまで私見だが、アファンタジアという心的経験を持つ人が、まったく異なる別の知覚経験を持っていたとして、その二つの経験に関連があるとみなして、「これを Deep Aphantasia と名付ける」と主張されても、私的には「え?」としか思わない。ものすごく極端で異質な話をするが、
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-15|#54
2/
Aphantasia を持つ私が「『ちいかわ』を見て可愛いを経験する人は多いようだが、私には中年のオヤジにしか見えず、『ちいかわ』を見ても可愛いを経験しない」、「この私の知覚経験を Deep Aphantasia と名付ける」と主張したとして、
🍅2024-04-15|#55
3/
Aphantasia を持つ多くの人に「VVIQ『ちいかわ』版」のアンケートをとったとして「『ちいかわ』を見ても可愛いを経験しない」が有意に出現したら、それは私の主張した Deep Aphantasia が妥当である証明になるのだろうか。そもそも Deep Aphantasia という言葉が抽象的すぎるし、
🍅2024-04-15|#56
4/
「それって Aphantasia と関係あるの?」「単に『ちいかわ』がオヤジに見える錯覚じゃね? 好み(予測)の問題じゃね?」とも言える。なお、この論文に記されているローレン・N・ブイヤー氏の独特な経験を、Aphantasia(VVIQ=16)及びMulti-Sensory Aphantasia を持つ私は経験しなかった。
🍅2024-04-15|#57
面白画像

🍅2024-04-15|#58
面白画像

🍅2024-04-16|#59
自伝的記憶の知見まとめ(2022年)をナナメ読み。とても勉強になった。後ほど再読。
https://jstage.jst.go.jp/article/jcogpsy/19/2/19_39/_pdf/-char/ja
アファンタジア(心的イメージ欠如)やSDAM(心的タイムトラベル欠如、自伝的記憶欠如)についての記述はなかった。
SDAM ⇒ https://sdamstudy.weebly.com/what-is-sdam.html
SDAM(例) ⇒ https://twitter.com/no_minds_eye/status/1779527302965338244
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-17|#60
1/
視覚的な心的イメージが全く存在しないこと、および自伝的記憶が著しく欠落していることについて、他者とに違いに気付いたのは20世紀末頃だった。アファンタジア(視覚イメージ欠如)という固有名の存在に気付いたのは2020年頃、SDAM(自伝的記憶欠落)という固有名に気付いたのは2022年だった。
🍅2024-04-17|#61
2/
直近10年間に研究されたアファンタジアの知見で、個人的にインパクトがあったのは次のとおり。
- 視覚的な心的イメージの欠如をアファンタジアと呼ぶことが提唱された(2015年)。
- 視覚以外の他の感覚(聴覚等)でも心的イメージの欠如があることが示唆された。
🍅2024-04-17|#62
3/
- アファンタジアと自伝的記憶欠落の関連が示唆された。
- 自伝的記憶の著しい欠落をSDAMと呼ぶことが提唱された(2015年)。
- 過去の記憶のみならず未来の想像にも影響することが示唆された。
- 視覚イメージが欠如しているにもかかわらず空間把握能力は機能していることが示唆された。
🍅2024-04-17|#63
4/
- アファンタジアは精神障害の条件を満たさないという意見に一定の合意が集まった。
- アファンタジアを客観的に測定する試みの研究がはじまった。
🍅2024-04-17|#64
5/
- ある研究(Wright et al., 2024)によれば、限定条件下において、視覚イメージのスペクトラム各層の出現率は、不在0.9%(VVIQ=16、Aphantasia)、希薄3.3%(VVIQ=17~32、Hypophantasia)、一般89.7%(VVIQ=33~74、Typical Imager)、過剰6.1%(VVIQ=75~80、Hyperphantasia)と推定された。
🍅2024-04-18|#65
理研の脳科学研究センターがアファンタジアの研究をはじめてから1~2年は経過してると思うが、その後はどうなったのだろう? 成果はいつ確認できるのだろう? 進捗が不明だし、Xの公式アカウントも停滞してる。
https://twitter.com/ishikirabo
https://research-er.jp/researchers/view/960901
🍅2024-04-18|#66
自分の知る限りの話だと、国内でアファンタジアを研究するチームは二つある。一つは理研、もう一つは福島大学の研究者が主導するチーム。福島チームは昨年の7月に論文を発表したが、その後はどうなったのだろう?
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-18|#67
あくまで私見だが、海外のアファンタジア研究と比べて、日本の研究はユニークな視点や成果がない。一部に教育分野とアファンタジアを絡めたテーマもあるようだが、個人的にこのテーマは██だと思う。
🍅2024-04-20|#68
1/
アファンタジアでない人(つまり随意の心的視覚イメージが浮かぶ人)は、時と場所を選ばず常に浮かぶのだろうか。例えば体調によって浮かばなかったり、対象に興味がない場合は浮かばないといったことはあるのだろうか。イメージを浮かべる能力はスペクトラム(人それぞれ)だから、
🍅2024-04-20|#69
2/
おそらくそういう人もいるんだとは思う。だとすると、その人は「浮かぶ」と「浮かばない」の両方を体験してるわけで、アファンタジアの人が持つ「浮かばない」という体験がどんなものかも理解できるのではないだろうか。主観的体験を一つしか持ってない人(例えば極アファンタジアの人)は、
🍅2024-04-20|#70
3/
比較対象が内部にないため比較不可だが、主観的体験を二つ以上持ってる人は一個人内で比較が可能ではないのだろうか(後天性アファンタジアがこれにあたる)。そういった視点からの研究はあるのだろうか(見たことないが)。
🍅2024-04-20|#71
1/
カナダ・マキュアン大学の学生763人にアファンタジアを測定したそうな。
結果、無イメージは0.5%、無+低イメージは2%、高+過イメージは8%、過イメージは2%と推定された。
概ね先行研究の報告と一致。低イメージ以下は、感情的な反応性が高く、物体/空間イメージと心的回転の能力が低かったそうな。
🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-04-20|#72
2/
日本の研究(Takahashi et al., 2023)では無イメージ(極アファンタジア)は0.07%と報告されたが、他国の研究と比べると大きく外れてる。まさか日本人だけ極アファが少ないなんてことはないと思うので測定エラーだろうか。
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1174873
🍅2024-04-21|#73
ディズニー映画でキャラクター・デザインや作画監督を務めた伝説的クリエーターのグレン・キーン氏(https://w.wiki/6Rx4)は、アファンタジア(脳内でイメージの視覚化を持たない)であることが知られている。
添付画像は氏の描いたアリエル(リトル・マーメイド)の初期スケッチ。
🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-04-21|#74
グレン・キーン氏とアファンタジアについてはここに詳しい。
https://theconversation.com/the-art-of-aphantasia-how-mind-blind-artists-create-without-being-able-to-visualise-162566
氏が絵を描く過程も面白い。
https://www.youtube.com/watch?v=0M254urId8w
https://www.youtube.com/results?search_query="glen+keane"
氏はアファンタジアであるから脳内に視覚イメージは存在しないが、描こうとしている対象を緻密に言語化してる様が興味深い。
🍅2024-04-21|#75
1/
極アファンタジア(脳内でイメージが視覚化されない)を持つ人は、その対極にいる極ハイパーファンタジア(脳内でイメージの視覚化が過剰)に関心を持つことがある。
https://www.theguardian.com/science/2024/apr/20/like-a-film-in-my-mind-hyperphantasia-and-the-quest-to-understand-vivid-imaginations?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
極アファ民がこれまでの人生で僅かでも経験したことのない脳内イメージを、
🍅2024-04-21|#76
2/
極ハイパー民は日々過剰なほど経験しているためだ。極ハイパー民の内的世界という未知に興味がある。以降は空想だが、極アファ民と極ハイパー民の違いは脳内イメージだけではない。おそらく現実(つまり世界、つまり人生)を観る感性も大きく異なる。極ハイパー民は目の前の対象を観ると同時に、
🍅2024-04-21|#77
3/
脳内に浮かぶ(時空を超えた)対象も観ることがあるが(←経験したことないので憶測)、極アファ民は目の前の現実そのものだけを観る(他の時空は観ない)。この経験の差は、その人の現実世界への接し方や人生観に大きく作用するに違いない。この差を嘆く人もいるが、個人的には尊い。
🍅2024-04-22|#78
1/
2021年7月より理研CBSに在籍のハクワン・ラウ氏が、今年後半に日本を離れる予定だそうな。
氏が率いる研究室(意識/心象/幻視などを研究)は来年まで運営する予定だそうだが、この研究室(@ishikirabo)はアファンタジアも扱ってい(る|た)。これに関して何らかの成果は公表されるのだろうか。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-22|#79
2/
海外のアファンタジア研究は論文数(10年で2桁?)から察するにローカルなネタだと思うが、国内ではさらに人気がなく、今回理研が抜けるとしたら国内でアファンタジアを研究する主たる主体は福島チームのみになるのではないか。
個人的にこの状況は██████。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-23|#80
面白画像(おそらく、アファンタジア ⇒ 画像生成AI開発会社SDの元CEOエマドもそれを持ってる ⇒ 反生成AI界隈でエマドは蛇蝎のごとく嫌われており犯罪者扱い ⇒ おまえはエマドと同じじゃ、ということなのだろう。当てこすり表現にアファンタジア使ってて草)
画像一覧 ⇒ https://twitter.com/search?q=面白画像 from%3Ano_minds_eye&src=typed_qu&f=live

🍅2024-04-23|#81
1/
クオリアという概念があるのは知っていたが、これまであまり深く知ろうとしなかった、理由はちょっと言いづらいのだが(そして完全に偏見だが)、テレビに出演したり各所でよく炎上してるモジャモジャの方が、クオリアを専門としているようで、
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-23|#82
2/
その方の言ってることと、その方のキャラクターが被ってしまい、なんとなく避けてきた。だが、そういうのはもうよして、この分野の豊かさや面白さに接してみようと思う。いま、このページにあるYouTube動画を観ている。とても面白い。
https://qualia-structure.jp/
🍅2024-04-23|#83
1/
いま、この動画を見終わった。
動画 ⇒ https://youtu.be/T4DDsWfk3Wg
クオリア(意識の中身)についての動画だ。アファンタジアについても言及されている。この動画の中で「関係性でクオリアを理解」というアプローチがあった。とても面白い。動画を見終わって、動画の内容とは全然別の話題になるが、
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-23|#84
2/
「関係性」というキーワードに触発されて次のようなことを考えた。
以前から考えていたことだが(そして車輪の再発明だろうが)、知識とは信念(○○は○○であるということを信じる主観的な意志)のことで、体系とは信念のネットワーク(構造)だと思う。
🍅2024-04-23|#85
3/
個々の信念(点)や、複数の信念の意味的/論理的な繋がり(線)は日々アップデートされ姿を変えてゆく。たまに、信念や主観を軽視し、客観云々や科学的云々というスタイルを見かけるが、細部を分解すればそこ(客観)には「信」の積み重ねがある。
🍅2024-04-23|#86
4/
ある人が神秘的現象(信仰を含む)やオカルトを信じるのも、科学者がデータ(先述の知識の説明を参照)を根拠に何かに迫る行為も、その根底をなす基盤は「信」と「繋がり(即ち関係性)」という意味で同じだと思う(それがどれだけの人から支持されているかは別として)。
🍅2024-04-23|#87
5/
「信」は豊かな人生の源泉になることもあれば、「信じ切る」と狂気に走ることもある。それくらい「信」の力は強く、人も世界も変えてしまう。戦争になることもある。
🍅2024-04-23|#88
6/
蛇足だが、楳図かずお氏が1970年代に描いた「漂流教室」という伝説的超超超名作漫画がある。ネタバレになるから詳しくは述べないが、ラストシーンで夜空を見るあの目に「信」の究極の形があると思う。
https://www.mangazenkan.com/items/10140011/
🍅2024-04-23|#89
1/
名前などの「言い間違い」の件、自分の家族にも同じタイプがいる。脳内で漢字の字面(つまり図形)が視覚化されるらしく、音訓の読みを間違えたり、異なる漢字に差し替えられて言い間違ったりするらしい。同じ要領で記憶のすげ替え(偽記憶)もたまにみられる。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-23|#90
2/
以前、政治家の麻生氏がよく言い間違いをしていたが、彼もこのタイプじゃないかと家族は言ってた。自分はというと脳内に視覚イメージが浮かぶことは常に一切ないから(アファンタジア)、言葉を発する際のリズム(音韻?)のようなもので発語してるから、あまり言い間違えない。
🍅2024-04-23|#91
3/
それでもたまに間違えることはある。よくニュースでアクセルとブレーキを間違えて事故を起こしたというのがあるが、あれと同じで「A」といったつもりなのに発語は「B」になっていて、すぐに自分で気づくか指摘されて気づく。
🍅2024-04-23|#92
4/
それと、冬は「さむさむさむ」、夏は「あつあつあつ」と言うのがクセになってると、なぜか冬の寒いときに「あつあつあつ」と自動発語してしまい(このとき思考しておらず条件反射的に発語してる)、俺何言ってんだ?となることがたまにある。
🍅2024-04-24|#93
1/
僕はアファンタジアなのか ⇒ https://scrapbox.io/sta/%E5%83%95%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B
非常に興味深い。自分はVVIQ=16(下限)の「無イメージ」なので常に何も浮かばないから迷うことがない(アファンタジア自認の主観的確信度が高い)。 一方で、
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-24|#94
2/
VVIQ=17~80(上限)は「低イメージ ⇒ 一般イメージ ⇒ 高イメージ ⇒ 過イメージ」のアナログ連続体(スペクトラム)だからデジタル化できず迷うと思う。
https://twitter.com/no_minds_eye/status/1769371818849144884
🍅2024-04-24|#95
1/
ある実験(下記)によれば、ネオンカラー錯視が生じる動画と生じない動画の二種類をマウスに見せたところ、錯視が生じる動画のときはマウスの瞳孔が開き、錯視が生じない動画のときは瞳孔に反応がなかったそうな。つまりマウスは錯視を経験しているらしいことが示唆されたそうな。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-24|#96
2/
どこかで聞いた話だなと思ったら、アファンタジア(心的視覚イメージ不全)の研究で知られるPearson氏らが似たようなことをやってた。
https://doi.org/10.7554/eLife.72484
氏らの研究(2022年)によれば、人々に明るい画像と暗い画像の心的視覚イメージを目を開けながら想起してもらうように指示したところ、
🍅2024-04-24|#97
3/
非アファ民らの瞳孔は散大や収縮の反応を示したのに対して、アファ民らの瞳孔にはさして変化が見られなかったそうな。つまりアファ民に心的視覚イメージが無い/低いことが示唆されたそうな。光に対する瞳孔の反応は無意識の反応であり主観に依存しておらず客観性があると考えられているそうな。
🍅2024-04-25|#98
1/
まさにアファンタジア(というより内的経験全般)の弱点はここなのだろう。そもそも主観だし、当事者の内観や表現が各人各様で、懐疑者(@Neuro_Skeptic)が疑うのは当然といえる。なんだけど、同じ屁理屈で非アファンタジアの存在も疑えちゃうという笑。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-25|#99
2/
ちなみに、自分的には Deep Aphantasia という名称に「え?」と思った。なんでわざわざ Aphantasia と関連付けるの?しかもなんで Deep なの?的な。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-26|#100
1/
クオリア構造を研究していらっしゃる土谷尚嗣さん(@NaoTsuchiya)の動画。34分55秒から「科学と主観について」。自分は学術や研究に全く縁の無い一般モブだが、めっちゃ共感した。
⇒ https://youtu.be/bs4c9UK3RN0?t=2095
こちらも面白い。
⇒ https://youtu.be/Llf03zMeIr4?t=1272
🍅2024-04-26|#101
2/
下記はアファンタジアの文脈(例)だが、おそらく各所でこういった空気感がある中、至極当然の道理を研究者の方に言ってもらえること自体個人的には嬉しくて、
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-26|#102
3/
こういうことの積み重ねが科学(下記参照)の豊かさや発展に貢献するんだなと思う。とにかくこの土谷さん(https://youtu.be/JL5R1IvsclE?t=27)、妙に魅力があってワクワクさせてくれる。
🔗引用した投稿を表示する
🍅2024-04-26|#103
1/
アファンタジアにおける心的回転は遅いがより正確であり、認知戦略の違いと関連している(2024/04/23)
Slower but more accurate mental rotation performance in aphantasia linked to differences in cognitive strategies
Lachlan Kay, Rebecca Keogh, Joel Pearson
https://doi.org/10.1016/j.concog.2024.103694
🍅2024-04-26|#104
2/
自分の場合だが、視覚知覚(実際の目)および視覚イメージ(心の目⇒これはアファンタジアの場合は無い)からの刺激の有無に関わらず独立した能力として空間や位置を認識する能力がある。論文にもあったが「正解は知っているが、どうやって知っているのかわからない」という表現がしっくりくる。
🍅2024-04-27|#105
頭の中で視覚化(あるいは視覚的な想像力)が制限されている人には、少なくとも3つのタイプがある。
【1】アファンタジア(脳内視覚化不全)を持つ人。
【2】視覚劣位の認知特性を持つ人。
【3】ビジュアル・シンカー(視覚思考者)以外の人。

🍅2024-04-27|#106
タイプ1(アファンタジア)は、心的視覚化の機能がない(あるいは不十分)という話。例えるならハードウェア(I/O)やドライバといった下位レイヤーの話。※あくまで比喩です。
🍅2024-04-27|#107
タイプ2(視覚劣位の認知特性)およびタイプ3(ビジュアル・シンカー以外/視覚思考者以外)は、視覚的思考の活用がない(あるいは限られている)という話。例えるならソフトウェア(OS/アプリ)やそれを操作するユーザースキルといった上位レイヤーの話。※あくまで比喩です。
🍅2024-04-28|#108
最近、こんなのをよく見かける。いずれも主観的報告。 1. 認知特性(視覚/聴覚/言語) 2. ビジュアル・シンカー(視覚/言語) 3. MBTI(16タイプ性格診断) 4. エニアグラム(9タイプ性格診断) 5. 占い(血液型、12星座、etc) 6. アファンタジア(脳内で随意の視覚イメージ欠如) (続く)
🍅2024-04-28|#109
(続き) 我田引水だが、分類するとこんな感じ。 1. 認知特性【習慣 or ファッション】 2. ビジュアル・シンカー【同上】 3. MBTI ⇒【習慣 or アクセサリー】 4. エニアグラム【同上】 5. 占い【エンタメ】 6. アファンタジア【先天性の場合はおそらく脳機能の話だが主観的体験の科学的証明は困難】
🍅2024-04-29|#110
面白画像
「どんぐり倶楽部」という子育て理論(?)がある。https://reonreon.com/index.html
視覚イメージを再現したり操作する「視考力」こそ、人生で本当に必要な万能の絶対基礎学力だそうで、本も出版してる。https://amazon.co.jp/dp/4794216270
理念はこうだ(⇒ 添付画像参照)
感想「・・・・・」

🍅2024-04-30|#111
1/
先月、アファンタジア研究の第一人者である Zeman によるレビュー論文が出版された。
内容は、アファンタジアが命名された2015年から2024年までの10年間に出版されたアファンタジア論文群の総まとめとなっており、これまでに積まれた数々の知見を俯瞰するには最適な資料となっている。(続く)
🍅2024-04-30|#112
2/
アファンタジアについてまったく知識がない人でも、この論文をざっと読めば、これまでの背景や最新情報までを容易に把握できるので非常にオススメである。
論文原文 ⇒ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661324000342
EOF
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
