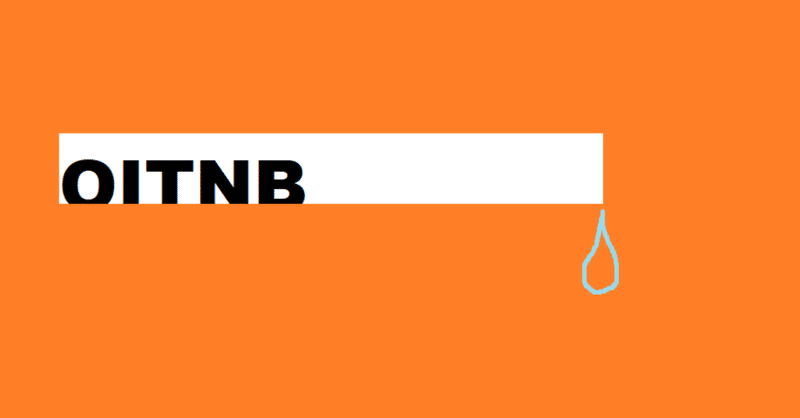
「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」の涙たち
大人になると泣かなくなる。映画やドラマ、漫画や演劇など、日常から少し離れた場所で涙することはあっても、普段は滅多に泣かなくなった。
仕事が大変でも泣いている暇などないし、このところ泣いた記憶がない。もちろん、感情からでなく身体的な痛みで自然と出る涙はある。大人も子どもも転ぶし、ふとした時にぶつける足の小指とか、何故にこんなにも痛い?と思う。涙が出る。
一方で感情からの涙はご無沙汰だ。まぁまぁ生きてきて、自分との折り合いがある程度つくようになったことも大きいだろう。哀しんだり後悔する前に、そうなる予想がつくのだ。だからその前に行動に移す。無理のない程度に、やり残しはしない。平坦なようで色々ある日々の中、その術を学んできたのだとも言える。書いていると、まるで泣かない言い訳のために行動をしているような気分になってきた。
大人になると泣かなくなる。私はそう書いた。でも、本当にそうだろうか?確かに、頻度は減っていくのかもしれない。でも、実際に流れるだけでない涙をカウントするとしたら?涙を流す瞬間と、ぴったり同じ気持ちになる時があるとしたら?気付かないうちに押し殺しているだけで、心の中では号泣しているとたら?
そう考えてみると、私は、まだまだ泣き虫だ。
Netflixのオリジナル・シリーズである「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック(原題:Orange Is the New Black)」が完結した。全7シーズン。
このドラマは、今まで観たドラマの中で一番泣き虫なドラマだった。涙の数は目に見えるものだけではない。心では泣き叫びながら、ぐっと堪える涙も含めての印象だ。そして私は観ながら、憶えていられないくらい、数えきれないほどに、泣いた。そして、忘れられないドラマだと、観終わった今、思っているところだ。
舞台は女子刑務所なので、登場人物は受刑者たち。薬物の売り上げ金を運んでいたパイパーが入所することになる。入所先の刑務所には、元恋人・アレックスも服役中だ。新入所者の証であるオレンジ色の囚人服を着て入所するパイパーは、ブロンドの白人で、学歴もある。アメリカ社会で多数派とされ優遇されている彼女も、刑務所に入ればただの受刑者。寧ろ目の敵にされる。
刑務所というのはひとつの社会であると思わされる。観ていると本当に色々な人物がいるし、同じ人種の中にも貧富の差があったり、誰かの母親がいたり、宗教もセクシュアリティだって、本当にバラバラだ。多数派も少数派も無い刑務所では、一般的な社会よりも、ある意味個々の存在自体が浮き彫りになるといえるかもしれない。そうなればひとつに括ることなど不可能だ。自由も可能性も制限された受刑者たちと自分には、はっきり言って違うことの方が多い。それでもこの物語が私の胸を打つのには理由がある。そこには、様々な種類の涙が流れているからだ。
・悔しい涙
この涙は一番多かったかもしれない。理不尽なことが多過ぎる。でもそれが現実なのだ。痛いくらいに。何度も心の中で言った。「わかるよ、でも、どうして?何とかならない?」
不当な扱いを受けるメインキャラクターたちはみんな、抗議しようとする。でも逆らおうとすると、看守から違反を取ると脅されてしまう。入所中の態度は刑期にも関わってくるので、受刑者にとって重要なことだ。力のある看守や刑務所側の人間が力をかざすのは力のない受刑者であり、その上彼女たちの弱いところを見て突いてくるのだ。
その権力の刃は、本来守られるべきである受刑者たちの、基本的な人間としての権利をもズタズタにする。その様な関係を続けていると、人と人との関りとは呼べなくなっていき、受刑者たちの鬱憤は溜まるばかり。そりゃ涙も枯れるよ、と思う。でも、みんな心では悔し涙を流しているに違いない。特にシーズン7では、不法移民たちの収容の様子も描かれ、絶望が塗り重ねられる。つらい。つらくて、嫌で、悔しかった。
・哀しい涙
受刑者たちの溜まった鬱憤は、やがて爆発する。それは、ただ怒りからではない。哀しさからだった。
受刑者は罪こそ犯したものの、人間である。そして本作で言えば、女性たちだ。刑務所で働く看守からすれば、彼女たちを管理し、所内の治安を守ることが仕事になる。そうしているうちに、受刑者たちを人間でなく、女性でなく、受刑者としてしか見られなくなっていく。仕事の姿勢としては、何も間違っていないかもしれない。けれども、受刑者が人間であるということを忘れてしまったら、看守は受刑者の何を見るのだろうか?所内にいるのは、罪を犯した人間たちだ。“受刑者”は、ただの名前に過ぎない。ただの名前だけを見て、何がわかるというのだろう?
仕事を全うする看守と、人間であり、女性である受刑者たちでは、圧倒的な力の差がある。しかし、“受刑者”という名前だけを見ることに慣れると、その差をも忘れてしまうのだ。その無意識の忘却がもたらした悲劇は、受刑者の命を奪うことだった。明るく楽しい人柄の、所内で愛するひとに出会った彼女の人生は、無自覚にふるわれた力により、途絶えてしまった。
この哀しい事件は、受刑者たちに声を与えた。当然、全員が同じ意見ではない。看守の責任を問うひと、その他の不当な権力をかざす刑務所側の人間を責めるひと、事実を世に伝えるべきだともがくひと…。そこに共通しているのは、今の刑務所のあり方を問う、という点だ。もっと言えば、刑務所と受刑者の関係性への問いかけであると言えるだろう。暴動に発展させた受刑者たちの声は、所内での看守と受刑者の力関係を逆転させることになる。しかしそれも、長くは続かない。
彼女が死んだ時、私も哀しかった。正直に言えば、わんわん泣いた。彼女と仲の良かった受刑者たちと同じように、沢山泣いた。不在が寂しくて、腹が立った。そしてそれ以上に哀しかった。生まれるべき悲劇だとはどうしても思えなかった。それでも、この哀しみが受刑者たちの力となったことも事実だ。声を上げ、その声の届く先が明るいものでなかったとしても。
・幸福の涙
本作の場合は、幸福と呼ぶには大袈裟かもしれない。でも、敢えてそう書かせてもらう。私は、彼女たちの幸福をどうしたって願ってしまうからだ。受刑者には、幸福になる権利がない。そんなことは絶対にない、と言いたいから。
入所したことで、彼女たちはみな傷ついている。罪そのものの傷もあれば、入所してからの扱いによる傷もある。所内で新しく人間関係が生まれれば、そこにも傷が付きまとうだろう。もしかしたら、所外の人々よりも、彼女たちは傷に敏感かもしれない。そして知っている。傷を完全に癒すことは不可能でも、手を差し伸べ、それ以上深くならないよう、包むことは出来ると。
メインキャラクターたちは、何故罪を犯したのか、どういう生い立ちなのかも描かれる。当たり前だけれど、何の理由もなく入所しているひとは居ない。誰ひとりとして同じひとは居ないと痛感しながら、互いに寄り添って、困難な入所生活に向き合っていく。
時には奇跡のような幸福な瞬間が訪れる時もある。そんな時、彼女たちは笑っている。きっと泣きたい気持ちで。私はそんな彼女たちの笑顔を見て、泣いた。彼女たちの笑顔は最高だ。自分であることを祝福している。犯した罪を受け入れながら、今の自分に出来ることのために、必死に戦い、立ち向かっている。人間は心から行動する姿を見ると、その溢れる光が眩しく、泣いてしまうのかもしれない。
笑える場面も沢山あるけれど、つらく苦しいことも多い本作。感動しながらも、ずっしり重いものを受け取ったりと忙しい。最終シーズンでは、正直いつもより幸福な涙が増えるかな?と期待していた。でも、そんなことはなかった。容赦なしだ。希望が差すかも、と思うと、その寸前で暗雲が覆う。なかなか幸福は訪れず、哀しみも多い。
それでも、彼女たちは笑っていた。裏で沢山の涙を流しながらも、その笑顔には希望が詰まっている。どんな悔しさも、哀しみも、晴れやかにしてしまう力のある笑顔。私は、「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」を観て、沢山泣いた。悔しくて哀しくて、嬉しくて泣いた。彼女たちを大すきになった。彼女たちの生きる、そして自分の生きる社会について、あれこれ考えた。きっと答えが出なくても、これからも考え続けるだろう。今の自分のことを。これからのあれこれを。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
