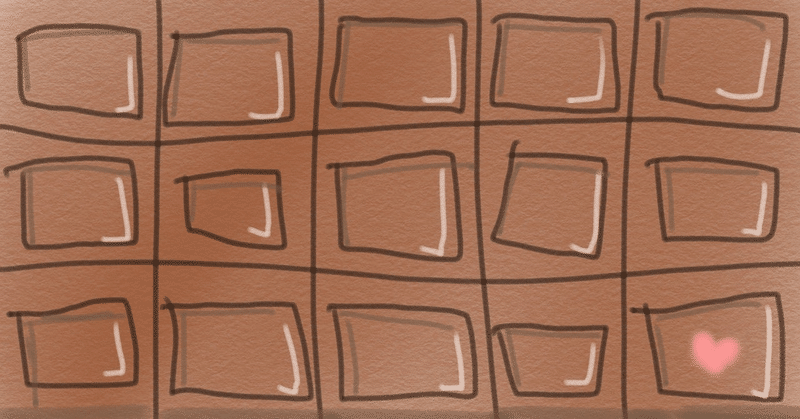
想い人に魔法をかけるチョコ
私は初潮が遅かった。
中1になれば大体の女子はソレが来ていて、トイレでナプキンを貸し借りする現場を何度も目撃した。でも私は中2になってもソレが来なかった。
心配した母親は私を病院へ連れて行った。先生は「15歳を過ぎても来なかったらまた来てください」とだけ言った。あと1年も待たなければならなかった。心はどんどん大人びて来たのに身体がそれに伴わないのは、なんというか、長距離走で同級生たちにどんどん抜かされ離され取り返しのつかない差が生まれているようで、私は家に帰って自分の未来を案じ家族の前で泣いた。
母は泣いている私を抱きしめながら囁いた。
「一回だけ、魔法の力を借りてみよう」
私は母が何を言っているのか全く見当もつかなくて「からかってるの?」と怒った。すると母は年代物の本棚、それは引き戸がガラスになっていて開ける時に必ず「キーッ」と嫌な音を立てるのだが、その誰も開けない本棚の奥の方から古いノートを出して来て、あるページを開き、私に見せた。
「お母さん、実は魔法の勉強したことあるの」
「へ、えぇぇ?」
「イギリスには魔法教室みたいなのがあってね、そこで魔法の薬の作り方を習ったの。ここにレシピをメモしてあるからちょっと試してみよっか」
母はその薬を作るのに必要らしい草花やドライハーブやらを集めて来てキッチンで嗅いだことのない匂いの液体を作り、私に飲ませた。
1ヶ月後。ソレは突然やってきて、私のお気に入りの下着に赤いシミを作った。
その日から、私は母の魔法ノートの存在に囚われた。他にどんな魔法の薬が作れるのか母に何度聞いても「あなたにはまだ早い、いずれ教えてあげる」としか答えてくれない。それで、母が不在の隙を見計らい、私はそのノートを盗み出した。
全て母の手書きで、しかも筆記体の英語で書かれていたから読むのに苦労した。というか、殆ど読めなかった。でもあるページで、タイトルのように大きく書かれた文字に私は反応した。
"Love Potion"
"Love"の四文字を私は無意識のうちに探していたのだと思う。電子辞書で意味を調べるとそれは「惚れ薬」という意味だった。私は興奮して、近所の図書館に行ってそのページをコピーした。
私には小学校の頃からずっと片思いしている男子がいた。ここではJ君と呼ぶことにする。彼は毎年リレーの選手に選ばれるような運動神経抜群な子で、それでいて勉強もよくできて小6の時は生徒会長をやっていた。私と彼は小3の時からずっとクラスメイトで、給食に私の嫌いなしいたけが出れば先に取って食べてくれたり、筆記用具を忘れればすぐに気付いて貸してくれたり、学芸会で照明係をした私に「照明を当てる角度が絶妙で台詞を言いやすかった」と褒めてくれたり、とにかく優しかった。彼は小学校で一番の人気者で、女子も男子もみんなJ君のことが好きだった。
でも中学に入ると少し状況は変わった。私の中学は主に二つの小学校が集まって一学年を構成するのだが、隣の学校にも凄い人気者がいたのだ。入学前の下見の日、J君を含めた私の同級生たちは皆、隣の小学校出身のT君が教室に現れるや否や一瞬で圧倒された。
T君はJ君と雰囲気が全然違った。まず、T君は顔のパーツがしっかりしていて大人みたいな顔をしていた。J君はどちらかというと目鼻立ちが小ぶりなベビーフェイスだったので、そこがまず大きな違いだった。T君は真面目そうなJ君と違い、少し不良っぽかった。彼とつるんで目立ちたい男子や彼を狙う女子に囲まれ、いつも群れを作っていた。J君のように勉強は得意でなかったが、先生、特に女性教師から好かれていたようで、噂では内申点がテストの点数の割にかなり高かったらしい。小学校の時にJ君を好きだった女子も、結構な数でT君に鞍替えした。だから中学の一番人気はT君だった。でも、私は変わらずずっとJ君が好きだった。
前置きが随分長くなってしまったが、今書こうとしている話は私が中2の時のバレンタインに起きたひと騒動、忘れられない思い出だ。
タイトルを見れば薄々お気付きと思うのだが、私は母の魔法レシピにあった惚れ薬を、J君にあげるチョコに入れたのだ。魔法の力に頼って、J君に私を好きになってもらおうと画策したのだ。
今でもよく覚えているのは材料集めにかなり難儀したこと。まずレシピの文字を解読して翻訳する作業が大変だった。今のように何でも簡単に調べられる道具もないし、郊外に住んでいたので買い物も都心に行かなければならない。だから、材料を全部集めるのに1ヶ月以上かかった。
チョコ、というか惚れ薬を作るタイミングも難しかった。秘密裏で計画を遂行したかったので、深夜や早朝に作って家族に見つかる危険を恐れたし、かと言って魔法の話を人に知られてはいけない気がして友達にも相談できなかった。色々検討した結果、私はバレンタイン前日に学校をズル早退して家に誰もいないうちに作る、という方法を取ることにした。
2時間目の終わりに急に具合が悪くなったふりをして、保健室へ行き、保健の先生に帰宅する旨を伝えた。普段真面目に生活していたからか、思っていたよりもすんなり計画は成功した。
家に帰って、用意していた材料を全部キッチンに並べ、既にボロボロになったレシピを見ながら惚れ薬を作り、湯煎したチョコにそれを混ぜた。
その日は夜も眠れないほど興奮した。背徳感というのか、生まれて初めて悪いことをしている気分だった。それでも、小心者の私はチョコに告白のメッセージをつけることは出来なくて、確か自分の名前と「もし良ければ食べてください」くらいのことしか書かなかった。
バレンタイン当日。彼に直接渡すのはどう考えても出来そうになく、私は朝一番に学校に行って彼の机の中にチョコをそっと忍ばせた。
一人二人と学生が登校し始め、私は朝から自習している風を装いずっと机の上の問題集に集中した。ただもう恥ずかしすぎて前を見ることもできなかったのだ。教室が騒がしくなってきた頃、誰かが肩を叩くので、私は顔を上げた。そこには優しく微笑むJ君がいた。私は卒倒しそうになった。
「ここ、俺の席」
「え?」
「そっか、xxさん昨日早退したもんね。席替えしたんだよ」
「!!!」
「座席表、あっちに貼ってあるよ」
私は机の上に広げていた問題集やら筆記用具を慌ててリュックの中にぶち込み、黒板の横に貼られた小さな紙を見に行った。確かに、私の席は窓側に変わっていた。そしてその瞬間、やっと私は自分のしでかした大変なミスに気づいた。
《チョコ!!!》
朝チョコを入れた机に視線をやると、T君がちょうど大あくびをしながら椅子に座ったところだった。全身から血の気が引いた。まさに、血液が全て吸い取られたように私は真っ青になって硬直した。T君は机の中に道具を入れながら中に入っていた私の箱に気づき、それをチラッと見るとすぐ元の場所に戻した。
《一巻の終わりだ…》
教室の前で青白くなって突っ立っている私を見た友人が「ちょっと!なんで学校来たの!」とか言いながら私を保健室へ連れて行った。保健の先生は私にいじめがないかとか悩みはないかとか伺うような質問をした。今日も帰る?とも聞かれたが、本当に具合が悪い時は家に帰る気力も湧かないことがわかった。私は2時間目が終わるまで保健室のベッドで横になった。
ベッドの上で、私はこの危機をどう潜り抜けるか一生懸命考えた。あらゆる馬鹿馬鹿しい方法も考えたが、結局、正直に謝って返してもらうのがベストだという結論に行き着いた。いつも人に囲まれているT君に話しかけるには、チャイムが鳴ってから先生が教室に来るまでの時間しかない。私はT君が椅子に座るのを確認すると彼の横にしゃがんで小声で話しかけた。
「T君、あのさ、机の中に入れてたものなんだけど…」
「あ、ご馳走様。美味しかったよ」
「え...?食べたの?」
「うん、小腹空いてたらから助かったわ。サンキュー」
教室の扉がガラガラと開く音がして私は自分の席に戻った。授業中ずっと、母の魔法レシピがくだらない子供騙しの嘘っぱちであることを祈って祈って祈りまくった。そして、多分私以外からも何十個もチョコを貰うであろうT君にとって、私のチョコが七夕のローソクもらい(※)で集まったお菓子の一つくらいの存在であることを願った。
昼休みだったかトイレ休憩の時だっか忘れたが、教室に人が沢山いる時にJ君にチョコを渡しに来た女の子がいた。クラスの男子がJ君に「ヒューヒュー!モテる男はツラいぜぇ!」みたいなことを言って冷やかし、J君が恥ずかしそうに「うるせーよ」とそのチョコをリュックに入れたのを見た時は私は本気で泣きそうになった。折角、1ヶ月以上前から準備していたのに、チョコひとつ渡せず2月14日を終えてしまうとは。
そしてやはり思った通り、T君の元には先輩後輩含め色んなクラスから女子たちがやって来た。担任は職員室から大きな紙袋を持って来て彼に渡した。チョコは紙袋に溢れんばかりだった。
「これお前ひとりで食べるのかよー」
「無理無理、食べれるわけない。好きなの取ってっていいよ」
「おいおい、女子に怒られるぞ」
放課後、T君は大きな紙袋を下げてサッカー部の部室へ行った。私に何か変な行動を起こすこともなく、あの魔法の薬は大した効き目がなかったようだった。私は胸を撫で下ろし、いつも通り音楽室へ向かい、J君にチョコを渡せなかった悔しさを練習にぶつけた。
部活が終わると外は真っ暗で、雪もちらついていた。私は靴箱の前でJ君にばったり会った。
「おっす、おつかれ」
「あ、おつかれ」
「わー、今日寒そうだなー」
「確かマイナス10度とかなんだよね、今日」
「そりゃ寒いわ」
いつも通り私の目を見て優しく笑ってくれるJ君を見て、今日一日の緊張からやっと解放された気がした。私はコートのフードを被り、友達にもらったチロルチョコをポケットから2つ取り出した。
「はい、これ1コあげる」
「おっ、チロルだ」
「私も、ほら、同じの持ってるの」
「ん、ありがと」
「バレンタイン…だしね」
「ははは、そっか。じゃあ来月クッキー持って来るよ、俺が焼いたやつ」
私たちは笑いあって、なんだかとてもいい雰囲気で別れた。なんだ、こんな簡単なことだったんだ。どうして魔法に頼ろうとしたり、机の中に入れておこうなんて考えたんだろう。私は反省しつつ、J君にチョコを渡せたことが嬉しくて、時々ニヤニヤと笑いながら暗い雪道をキュッキュッと音を立てて歩いた。
……さて。
私の中学時代の淡い初恋の思い出はここまで。J君はホワイトデーに約束通りクッキーをくれ、私たちは結構仲良しになった。彼が私の部活の演奏会に来てくれたり、私が彼の試合を見に行ったり、そういう付き合い方はしたけど、まだとてもウブだった私たちは彼氏彼女の関係とかそういうのはまだ遠くて、卒業式に別れてからは成人式まで顔を合わせることもなかった。
あれから10年以上の月日が経った。
そして私は、なんと、T君と結ばれた。
魔法が効いたのか?いや、大人になった私はもう魔法のことは信じていない。だって、あんなレシピでそんな効果のある薬が作れるのなら私は今頃億万長者だし、世界中の女性が大好きな推しに惚れ薬入りのチョコを贈るかもしれないし、あんな薬でスターがその辺の女の子を好きになったら…って、そんなの陳腐すぎて映画にもならない。
では、私とT君の間に何があったのか。
あのバレンタインの翌日、T君は学校を休んだ。体調が悪いとかで、担任は「チョコの食べ過ぎだな」と冗談を言ってみんなを笑わせたが、私は笑えないどころかまた血の気が引いて3日連続で保健室に連れて行かれた。
ここにはちょっと書けないのだけど、惚れ薬の材料はお花とかハーブとかそんな可愛らしいものばかりではなくて、なかなかスゴイものが入っていた。だから、これは絶対に私のチョコのせいで体調が悪くなったんだと直感した。
家に帰り、私は母に自分のしたことを正直に話し、彼の体調を治す薬がないか尋ねた。母は呆れたように笑い、それに合う薬はないけど、魔法を解くには林檎が効くらしいと教えてくれた。
その翌日は土曜日だった。T君の体調を確認する術もなく、私はスーパーで林檎を10個くらい買い、住所録片手に彼の家へ向かった。彼の親は理容室をしていると噂で聞いていたので、家はすぐに見つかった。
店にはおじさんのお客が数人いた。T君とよく似た父親らしき人が、この場に似つかわしくない私を見つけ「どうしたの?」と聞いた。
「xx中学のT君のお父さんですか?」
「うん。お友達かい?」
「はい。あの…T君、体調、どうですか?」
「ああ、もうだいぶ良くなってたよ。呼んでくるかい?」
「あ、いえ…私、T君にちょっと、手作りのお菓子をあげたんですけど、もしかしてそれのせいで具合悪くなったんじゃないかと心配で…あの、これ、どうぞT君と召し上がってください」
私はT君のお父さんに強引に袋を渡し、急いで店を出た。背後からお父さんが私を呼び止める声が聞こえたが、私は後ろを振り返らず逃げるように走って帰った。
月曜日の朝、T君は教室にいた。彼の周りにはいつも通り人が沢山いて、チョコの食べ過ぎか?毒でも盛られたのか?などとからかわれていて、私は元気そうに笑うT君を遠くから眺め安堵した。
朝の会が終わった時だった。T君は私の席までやって来て、私と目も合わせず「具合悪くなったの、xxのせいじゃないからあんまり気にしないで」と言った。いつも堂々としているT君の恥ずかしそうな顔を初めて見て、その時すごくキュンとしたのを覚えている。でも私たちはそれっきりだった。
その後もT君はずっと人気者のままだった。今振り返ってみても、彼以上にモテる人に私は会ったことがない。
高校に上がると、中学の頃の記憶はポラロイド写真が色褪せるように日々薄れて行った。バレンタインが近づくとこの恥ずかしい失敗を思い出すこともあったが、歳を重ねるごとに思い出すことすらなくなった。
月日は経ち、27歳の時、私は勤めていた東京の会社で精神的に病んでしまい、会社を辞め、数年ぶりに地元に帰った。故郷に錦を飾りたかったのに、無職のニートで見慣れた景色の街へ戻るのは辛かった。
家からほとんど出ず、くだらないテレビ番組や韓流ドラマをただぼーっと見るだけの毎日を過ごした。ある日、私は鏡に映る自分の姿があまりにも酷いことに気付き、ガツンと一発殴られやっと目が覚めたような気分になった。とても天気が良くて、外に積もった雪の一粒一粒がキラキラと輝いているような日だった。私は家にあった情報誌で近所の美容室を探し、初回◯%オフの文字につられてすぐ予約を入れた。都心まで出かけられる状態に戻すため、とりあえず近場で自分の姿をマシにしようと思ったのだ。
クーポン代わりになる情報誌の切れ端を持って美容室の方へ歩いて行くと、過去の記憶が少しずつ蘇った。私の予約した美容室は、あの日林檎を持って訪ねたT君の家だった。
おじさんしかいなかったあの理容室はとてもオシャレな美容室に生まれ変わっていて、店に入るとだいぶ落ち着いた印象のT君がいた。クーポンを使う初回客の私には若い美容師がついたが、T君と目が合うと、彼も私を思い出したように反応した。
T君は私の髪をブローしてくれた。鏡ごしにお互いの笑顔を見ながら、昔の話や知っている人の近況なんかについて話した。笑い合って話すような仲では決してなかったのに、10年以上の歳月が私たちを十分に大人にしたらしかった。そして彼は今も変わらず、いや、前にも増して魅力的だった。
「僕ね、xxにずっと聞きたいことがあったんだよね」
T君は唐突にそんなことを言った。
「なに?」
「なんで僕にチョコくれたの?」
「あ...あぁ」
「あれ、告白のつもりだった?」
「うーん、それは…あはは」
「僕のこと好きだったんでしょ?なのに全然話しかけても来ないし。あれ以来、僕、女の人って難しいなって軽い人間不信になったんだよ」
「あはは…だよね…ごめんなさい」
「すみません、店長」と、私の髪を切った美容師が彼を呼びに来た。きっと彼の客が来たのだろう。彼は「じゃあまた後で」と言ってドライヤーをその若い美容師に渡した。
帰り際に彼は自分の連絡先を書いた紙を渡して「さっきの続き、話し足りないからメールして」と言った。私たちは週1くらいでお酒を飲みに行く仲になり、付き合うことになり、ついには結婚することになった。
…ちなみに、T君にはあのチョコの秘密は話していない。だからあのことを知っているのは私の母と、今これを読んでいるあなただけだ。
最終的に惚れ薬を飲ませた相手と結ばれた私だが、あのチョコに効果があったとはやはり思っていない。でも、チョコを渡す勇気、リンゴを家にまで持っていった勇気に魔法の力が宿ったのかもしれない。だから私は、来たる2月14日をドキドキして待つ女の子に「きっとそのチョコにも魔法の力があるはず」と言いたいのだ。
誰かを想う皆さんに素敵な恋の魔法が舞い降りますように。
fin.
(※100%フィクションです)
(※ローソクもらい: 北海道では旧暦に近い8/7に七夕を祝うのですが、その日子供たちは集団でハロウィンのように歌を歌いながら近所を回り蝋燭やお菓子を貰います。最近はやらないみたいだけど)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
