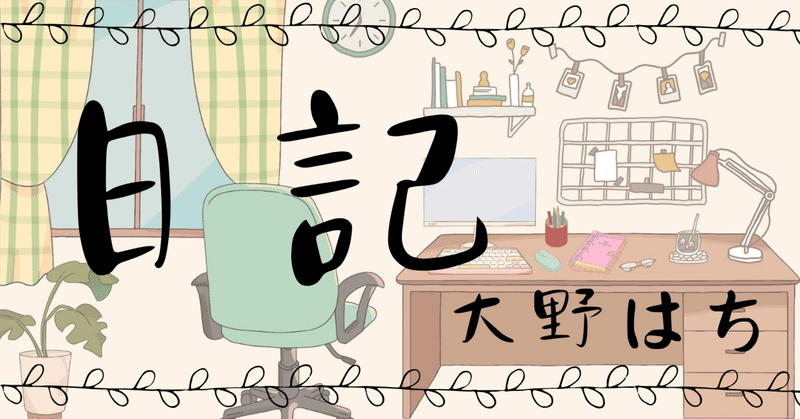
【日記】ザザンとガガンと蛇の足
ザザンとガガンと鬼の指、読んで頂けましたか?
ゆきのまちで最後の長編賞となった作品、せっかくなので公開してみました。
個人的に、自分の創作のターニングポイントとなるような重要なお話です。蛇足ではありますがちょっと語ってみようと思います。
このお話は東北を襲った天明の飢饉をベースにしています。といっても史実を細々突っ込まれたくなくてボカしておりますが、はっきりとモデルにした時代はそこです。
(なんなら日本風の異世界と思ってもらっても……という逃げ)
物語の後半で、村人に「癸卯か?」と聞くシーンがありますが、天明の飢饉が1782年壬寅に始まっているため、今はその翌年である1783年の癸卯か?と聞いているわけです。
当時、庶民は和暦である天明〇年などをあまり使っていませんでした。使っていたのは干支、つまり十干十子です。昔の和暦はちょくちょく改暦されていたので、使いにくかったのですね。
例えば文化元年の1804年に「天明二年の時にさぁ」と言われても何年前だかわかりにくいんです。二十一年前なんですが、間に寛政と享和を挟んでますしね。
平成を挟んでいるだけの令和の今でさえ、昭和〇年が何年前かすぐにはわからないのと同じような感じでしょうか。
なので六十年で一巡する干支が一般庶民にとって使いやすく、広く浸透していました。それを受けてのあの台詞です。
それ以外のところはまだしも、ここについてはちょっと解説をしないと伝わらないかも…と思ったのでまず第一に書かせてもらいました。
さて、このお話は飢饉に見舞われた双子の兄弟が雪山で鬼に遭遇し、その役割を継承するお話です。東北の民であれば子供の頃に地域学習の一環として飢饉について学ぶかと思います。私の住んでた地域でも飢饉は地続きの過去であり、作中でモデルにした石碑も存在します。餓死万霊等供養塔(がしばんれいとうくようとう)といいます。
石碑の内容が一部削り取られているのも本当です。内容は…お察し下さい。
兄弟は山へ逃げ、洞窟の中にある鍋の中身を食べ、鬼と共に一冬を過ごします。即ち「その世界のものを食べると帰れない」という黄泉戸喫が行われました。
そして長い一冬が、干支が一巡する六十年に相当していたという浦島太郎的展開に至ります。そしてザンガの後釜を双子が担います。なので、割と基本的で古典的な物語ベースに則っております。
今までの私はなるべく奇をてらってやろうとか、読者を驚かせてやろうとか肩肘張っていたところがあったのですが、このお話は出来るだけシンプルに書きたいという気持ちがありました。
でも、何か仕掛けてやりたい欲はまぁまぁあったのであちこちに深読みできる余地は残しております。謎解き気分で読んでもらえれば嬉しいな。
ザンガというキャラクターは私なりの神様感です。神様は人間のことなど微塵も気にしておりません。言葉も使いません。ただ人間が神様に静かに寄り添い、その流れを理解するだけなのです。津波や吹雪や雪崩など、自然の厳しい東北で生まれ育ってきたからこそ「神様に見つからないように生きる」「神様に殺されないように生きる」という価値観が染みついているのかもしれません。
他にも、指の先端を失って鬼の角のような爪が生えてくる場面ですが、これは父がモデルです。子供の頃に脱穀機に指を挟んでしまって、鉛筆の芯のような爪になってしまっていました。爪切りは使えないので、やすりでコリコリ削っていたのを思い出します。
今読み返すといろいろ気になる点はありますが、今後の創作のためにも書き上げられて本当に良かったです。新作も書かねばなぁ……と、ぼんやり決意して長すぎた蛇足を閉じようと思います。読んで頂いてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
