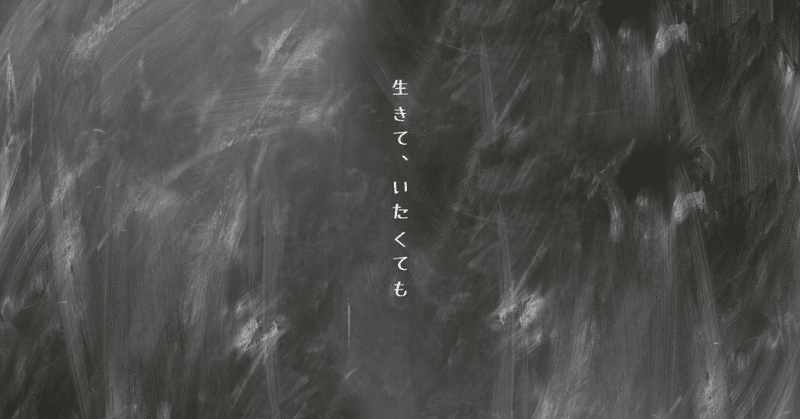
生きて、いたくても――Oct#17
三上は芸術に対して常に、新しい形、新しい表現を模索していた。
アートは常に独自的且つ、コンセプチュアルである必要に迫られていると、三上はそう考えている。美しいものならそこら中にあるし、技術は作品の因子でなく作者の側面だ。星岡さんとはやや反する形の思想だった。
「だから、『風景だけの』風景画とか、『人物だけの』人物画とかは、習作でもなければ描かないんです。この前の静物画も一緒で、同じ描くにしても、何か違うものがないといけない。それは、自分に対してもそう。過去の自分と同じものを見たくないし、描きたくない。勿論その時々で、自分の中の流行や傾向はありますけど、後で絶対に、その流れを堰き止める為の石を置くんです。行き場がなくなれば、必ずどこかから溢れ出す。新しい水路を作る。……それで駄目だった時、枯れてしまった時が、終わりなんだろうな、って」
その話を、三上は意識して僕にしたのだろう。
「既存の自分を壊す事が、既存の芸術を壊す事。それが、私の持論なんです」
――過去の自分と同じものを見たくない。僕だって、今までの自分と同じ光景が映され続ける世界を脱したくて、既存の自分を壊したくて、今。
その先にあるもの。
新しい世界に辿り着くには、新しい自分になる事。
彼女は、真っすぐに僕を見ていた。
三上の注文は、出来るだけサラサラの塩、両面に色のある折り紙またはそれに準ずる紙、そして側面にデザインが施されたペイパー・カップ――紙コップだった。
一見、関連を見出せない、シュルレアリスム的な並びの品々。見事に日用品だ。そこに何かしらの意味を持たせるのは、先人が開いて来た芸術の道にも同系がある。
翌日の放課後、早速そのアイテムを求めて、偶見と電車に乗った。向かう先は、常時人で賑わう、一帯の中心地。駅舎もそれだけ大きく、各方面へ接続する一〇本前後の線路が並ぶ。偶見はよく知った街の様で、率先して僕の前に立ってくれた。
三上が別の作業をしている間に、僕と偶見が三つのアイテムを入手する役目を引き受けた。一人でもよさそうに思えるけれど、二人の方が意見や判断力の広がりが期待出来る――そして僕単体の問題として「デザインが施された紙コップ」なんてものを買い求める先が分からない ――事もあって、共同での買いものになった。
勿論普通の、白色のものなら適当な場所に行けば僕にだって買える。だけど、三上に出された条件が細かい。「キャラクターやロゴ・文字などではなく、ある程度凝った『らしい』デザインや意匠が割合全面に施されていて、地の白い部分は残っていても構わないけれど、それが『空白』らしくないもの」と言う厳しい設定だ。コップの規格も統一が必要事項。
最初は旨意が掴みかねたけれど、偶見に連れられて色々な店を回ると、側面下部に影絵の様な黒い街が描かれ、上部が空白のままになったデザインのものなどは幾つも散見された。「こう言う事だよ」と偶見が言う。ストライプなどデザイン上の白が可で、日本画的な余白のあるものが不可と言う解釈でよさそうだ。その真意は分からないけれど。
どこへ進んでも雑踏に行き当たる。僕はこんな所に来る事すら珍しいのに、一人では絶対に入らないし入れない様な店を、回遊魚みたいに偶見は次から次へと渡り歩いて行く。
「向こうに雑貨屋さんあるんだ」
「あ、何かありそう。ここ寄ってみていい?」
「次、オークルの方行ってみようよ」
迷う素振りも全くない。周辺の地理や商業施設の大まかなフロアー・マップ、店の名前まで様々な情報を網羅していて、慣れた感じを、少し羨ましいと思う。
偶見一人ではなく、僕のセンスも参考にしたいと言う名目は一応あったけれど、何せ彼女が好きなのはデザインの大家、アルフォンス・ミュシャなのだ。僕から見ても、その選択に間違いはなかった。そもそも女子とは、元からそんなものじゃないだろうか。
「はー、楽しかった。紙コップ探しで盛り上がれると思わなかったや。普段買わないし」
「うん、そうだね。意外な時間の使い方だった。……ちょっと、疲れたけど」
一六時も後数分で終わる頃、百貨店の中にあるファッション・フロアー内のカフェで、僕たちは少憩していた。それにすら僕は驚いている。ファッションに関連したフロアーは四、五階分あるけれど、その全てに一つずつ、そして全て違うカフェが入っているのだ。必要性と関連性を疑う。生産性も。
買った紙コップの数、総計七五個。意外と値段の上下差が激しく、同じ五〇〇円で五〇個入りのものもあれば、一二個しか買えないものまである。安ければ一〇〇個で三〇〇円程度だ。三上に渡された――断ったし、受け取る際にも腰が引けたけれど、支出の多い企画を立てた私の責任だと持たされた――額でこそ収まってはいるものの、高が紙コップだとは馬鹿に出来ない失費をしている。……端から見たら馬鹿だろうけど。
「七五って数字、何か意味あるの?」偶見がカプチーノを一口飲んで言う。
「多分だけど、アラン・カプロウのオマージュだと思う」
カプロウは、「ハプニング」と呼ばれる活動の創始となった「六つのパートからなる一八のハプニングス」と言う催しを実行した芸術家だ。七五人の人間に手紙を送り、参加者として協力を仰いだその最初の「ハプニング」は、パフォーマンス・アートの隆盛に大きな影響を与えた。オマージュ、とまでは行かなくても、僕が想起出来る程度にはメタファーだ。
三上に一つだけ、踏み込んだ質問をされた。「復讐したい相手の人数は」。昨日、喫茶店で解散し、僕が帰宅した後に届いたメイルでの話だ。それは間違いなくこの計画には重要な情報で、僕は正直に答えた。特に標的としたいのは三人。もう少し欲を掻いて、裾野まで範囲を広げていいのなら五人。或いはそれが絡んでいるのかも知れないけれど、公倍数にしたって七五は多いし、数としてもやや半端だ。僕の推察は、外れてはいないだろう。
ぬるくなってしまったアメリカン・ブレンドを飲み干したのを合図に、僕たちは店を後にした。コップ以外も買いものは既に全て済ませて、袋の中だ。
「宮下君、これからどうする? もう帰る?」僕の顔を覗き込む様にして、偶見が尋ねる。
「まあ、別件はないしね」
「んーとさ、そうじゃなくって……」歯切れの悪い返答をしたかと思うと、焦れったそうに続けた。「折角だから、ちょっと遊んで行かない? こっからは活動抜き。あたしと宮下君の、普通の交遊として」
「……え、っと、うん。それは全然、いいけど」
全然いい……けれど、そんな事は全く考えていなかった。あくまで買い出しと言う刷り込みがあったし、そもそも、遊ぶと言う発想が僕には乏しい。所持金に余裕があれば休日に美術展へ行ったりするし、そうでなくとも、大型の書店にでも行けば、立ち読みなどしなくとも優に二時間はまず過ごせる。見て回るだけでも楽しいものだ。本や作者に敬意を払う意味で、必ず買って読むと言う概念だけを持った僕に、立ち読みの文化は元々ないけれど。
ただそれは趣味の一環で、遊んでいるのとは違う。僕はそう言う「遊び」に弱かった。だから偶見に「どこか行きたい所ある?」と問われても、何一つとして目的地は浮かばない。
「偶見の好きな所でいいよ。好奇心とか興味とかは強い方だから、或る程度どこに行っても、楽しめると思う」
「本当? えっとね、行きたい所あったんだよね。宮下君となら尚更」
僕となら、尚更? そんなスポットなんてあるものなのだろうか。疑問に思った僕が五分程歩いて連れて来られたのは、すぐ近くにある、また別の百貨店だった。
そこでは、古くなった本館建て替えによる翌年からの一時休業で、全館に渡って売り尽くしセイルが行われていた。その中には絵画や工芸品など、普段は値下げ対象にならないものまでが含まれていて、それがフェアーとして、丸々ワン・フロアーを使い切って展開されていた。また全てが売りものなので、どれも値段の書かれたパネルが取りつけられており、末尾に多くのゼロを伴って示される額の印象も相俟ってどこか威厳があった。客層も普通の美術展とは違う。僕たちの様な若者は、同年代に絞らず多少の上下差を見ても居ない。大抵が雰囲気からして風格を感じるご老人や、質のよさそうな衣服で整えた、上品な中年の方々などだ。既に商談をしている姿も見られる。場違いな思いに身を浸している傍ら、偶見はどこ吹く風だった。
「日本画家の作品が多いかもね。宮下君、日本で誰か好きな人居る?」
「……東山魁夷かな。ああ、あそこにリトグラフがあるね。あの空気感は、固有のものだと思う。川端龍子とか、竹内栖鳳なんかも好きだよ」
基本的には近代辺りの芸術家が、洋の東西を問わず、一番好きだ。何にしても古きの技術的な世界と比べると、感性的なものも強く合わさってその先へ枝を伸ばしていると思う。
「デュシャン好きって言うから、もっと別の人想像してたけど。結構正統派なんだね」
「うん、日本の絵には、独特のよさがあると思うし。偶見は?」
「あたし? あたしは……」そこで少しの考える間を置いた。「二世・五姓田芳柳かな」
奇襲の様な返答だった。僕はその名前を知らない。知らないままで言うのは見当違いな節もあるけれど、それでもメジャーな画家ではなさそうに思えた。
「風景も綺麗に描く人なんだけど、人物がいいの。表情。何て言ったっけな……戦国武将に纏わるエピソード主題の絵なんだけどね、その表情見ると」そして、予想外の事を言った。「何かね、嬉しくなっちゃうんだ」
「嬉しい?」あまり、絵画を見た感想として聞かない言葉だ。
「その武将、笑わない人だったんだけど、飼ってる猿の仕草がおかしくて、思わず笑うって言う話なの。あ、だから『一笑図』だ。『何とかかんとか一笑図』。部下の兵士が見た最初で最後の笑顔って言われてるんだけど、それが本当に自然で、無意識に出た笑みなんだなぁって。この人、ちゃんと笑ってるって思える絵なの。それが、嬉しい」
説明を聞いてみると、胸の中で熱伝導の様にゆっくりと広がって、同じ感覚を少し共有出来た気がした。題名に覚えはないし、実際にその絵を見た事もないと思う。だけどきっと、いい絵に相違ない。そして、それを「嬉しい」と表現出来る彼女の事も、素直に称讃したい。
「うん、それ、凄くいい感想だ」
「ふふん」偶見から変な声が漏れる。「そう言う顔だよ、宮下君」
「え、何が?」
「今、とってもいい顔だった。ちゃんと笑ってた」
「……僕、そんなに笑わなかったかな、今まで」
「うーん、ふっと笑う事は結構あったと思うよ、今のもそんな感じだったし」だけど、と続ける。「その顔見たら、本当にいいと思ってくれたんだな、って分かった。ありがと」
「うん、本当に、いいと思った」
「だからさ、あたしは、そう言う風に、もっと笑って欲しい。ちゃんと笑える時が、機会が、もっと増えて欲しい」
そう言った彼女の微笑みに、少し窺う様なニュアンスが含まれているのを察した。
「今更だけど、宮下君はいいの? ……あんな復讐で、さ。そこに関しては、宮下君の中の問題じゃん。ちゃんと『復讐』になるのかな、気が済むのかな、って」
「他の選択肢だって、数あるだろうけど……これ以上のものは、きっとない。寧ろ、復讐に対する最大限の解釈だよ。僕の身の丈にも、よく合ってる。……それに、こんな事言うのもどうかと思うけど、復讐だって分からなければ、仕返しだってされないからね。そして、多分」いや、絶対に。「とても、楽しいと思うんだ」
「……あたしも、絶対、楽しいと思う」
「だからまずは、やってみたい。何も変わらないって事は、ないと思うから」
僕の言葉に、彼女は頷いてくれた。
その表情は、心から同意してくれたのが分かる、ちゃんとした笑顔になっていた。
