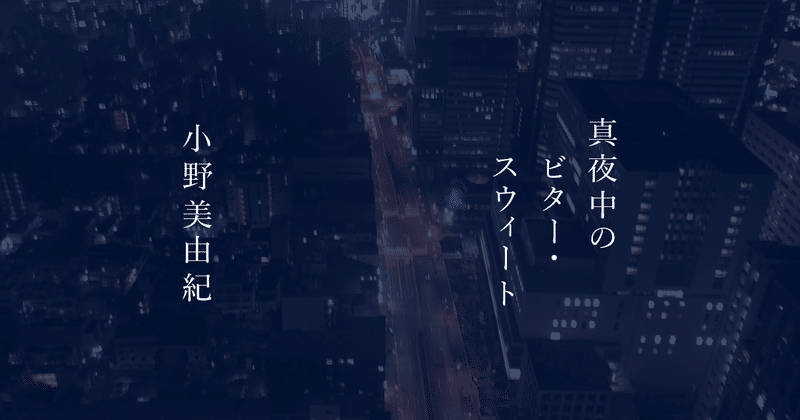月夜のビター・スウィート
会社からの帰り道、トボトボと暗い路地を歩いていた。
今日はバレンタインだ。華やかに飾り付けられた駅前の繁華街とは違い、人気のない住宅街はうら寂しい。
空には銀紙を貼り付けたような月が出ている。
「渡せなかったなあ」
いや。渡せるはずもないのだ。先輩は結婚している。加えてうちの会社はバレンタイン禁止だし、そうでなくたって、私があの人には渡すのはおかしい。
好きになる前は会社の人を、それも既婚者を好きになるなんて、馬鹿げたことだと思っていたし、恋に恋するタイプでもない。そんな私がよりによって、気付いた気づいたら一番好きになってはいけない相手を好きになっていたなんて、神様は本当に不公平だ。
叶わないということはよくわかってる。そんな度胸もない。
カバンの中で、行き場を失ったチョコレートが虚しい音を立てている。毎年毎年、渡せない、ということを確認するためだけの儀式。叶わない、叶えてはいけないと自分に言い聞かせるためだけの。行き場のない思いは、どんな食べ物よりも苦い。
「ねえ、確かめてみたくない?」
突然、前方から声をかけられて、私は顔をあげた。
上空に浮かぶ銀色の月のクレーターから、ウサギが顔を覗かせていた。
「毎年、飽きもせずによくやるよねえ」
シルクハットを被ったウサギは皮肉げな笑みを浮かべて私を見下ろしている。
ムッとした。月の兎ごときに、複雑な事情ってもんのある人間の恋に口を挟まれたくない。
しかし、ウサギは身を乗り出すと、するするーっと何かを垂らした。
赤い糸の先に、何かがついている。掴んでたぐり寄せると紙コップだった。
「あのね、今から、君が一番話したい人と、電話を繋いであげる。ただし、つなぐのは機械の電話じゃない。人間ってのは不便だね。本音さえ伝えられやしないのに、通信手段ばっかり発達させるんだから」
ウサギは得意そうに言う。
「この電話が通じるのは、相手の心だよ。その人の顔を思い浮かべて、つながるように念じてみて」
私は糸電話を耳に当てた。はたから見たらバカみたいに見えるかもしれないけど、幸い、暗い住宅街には誰もいない。
白い空洞の奥からは、潮騒のような、自分の血流の音みたいな、不思議なざわめきが聞こえる。
そのうち、その向こうからコール音が聞こえてきた。
RRRR、RRRR ……
「はい」
聞き慣れたあの人の声が耳のすぐ近くで聞こえたとき、私はびっくりして紙コップを取り落としそうになった。
「もしもし」
仕事中、何千回と聞いたはずの「もしもし」。
少しゆったりとした、あの人独特のトーン。
「…あの」
もつれる舌を動かして、やっとのことで声を出した。心臓が耳の近くに移動してきたみたいに大きな音を立てる。
「かけてくれるの、待ってたよ」
やがて、淡い笑いを含んだ優しい声が響いた。
あの人だ。間違いない。
「待ってた、って言うのはずるいかな。こちらから、かけるべきところをごめんなさい」
電話の向こうは静まり返っていて、彼がどこにいるのかは分からない。まるで、月の裏側の”静かの海”から通話しているみたいだ。
私は思い切って言った。
「先輩、好きです」
ずっと言いたくて、言えなかった言葉。
最初に仕事を教えてくれたときから、ずっと。
「私、あなたのことがずっと好きです。けど、どうこうなるつもりもないんです」
途端に涙が溢れ出した。
そうなのだ。どうこうなる気はない。行き場のない思いを確かめて、飲み下すしかない、だから余計に苦しいのだ。
「先輩が奥さんを大事にしているのは誰よりも知ってます。子供のこと、嬉しそうに話すあなたのそばにいて、ああ、私もこういう家族を持ちたいなあ、っていつも思うんです」
するするとほどけた本心が、赤い糸を伝ってゆく。
「だから、余計に苦しいんです。私の気持ちはいけないもののような気がして」
先輩は答えない。溢れる気持ちだけ、止める堰を知らずにぽろぽろとこぼれてゆく。
そのうち、
「ありがとう」
少し掠れた声が、耳に押し当てたコップの底から届いた。
「君の気持ちは知っていた。毎年この日になると、そわそわして、俺と目も合わせてくれなくなる。次の日には真っ赤に目を腫らしてるし。……最初は勘違いかと思ったんだ。けど」
「そんなとこまで見られてたんですか」
「メンター、だからなあ」
少しの空白ののち、彼は言った。
「僕も君が好きだよ」
受話器にかじりついた。なりふりなんて構ってられない。嗚咽のからまる喉から、声を振り絞る。
「一度だけでいいんです」
人生で、決して口になんてしないと思っていた言葉。
「一度でいいから、抱きしめて欲しいんです。現実で」
沈黙の中、かすかに耳元の空気が揺らいで、先輩が首を振るのがわかった。
「ごめん、それはできない」
「なんで!」
「君を幸せにしたいから」
完敗だった。
胸元を濡らすこの涙と同じくらいに、はっきりと私の心を敗北が浸した。
彼の強さに、私のちっぽけな心は到底勝てない。
「君の幸せを、先輩として、男として、一人の大人として、誰よりも願っています」
さっきより丸みを帯びた彼の声が、人差し指で押したピアノのキーのように、強くはっきりと胸に響く。
「だから、俺のことは忘れてください。来年からは、別の相手にチョコレート、買ってやってくれ。君を俺よりもずっと、幸せにしてくれる男に」
「……わかりました」
私は言った。
「けど、私、きっとこれから先もずっと、先輩のことを思って、毎年チョコレート、買います」
向こうで先輩が、声をつまらせるのがわかった。
「私も、先輩の幸せを、ずっと願ってるから」
「…ありがとう」
そこで電話は切れた。私は一人、月明かりとともに、路地に取り残された。
カバンを開け、包装紙に包まれた小さな箱を取り出す。リボンをほどき、紙を剥がして蓋を開けると、ふわん、と甘やかなショコラの香りが漂った。
綺麗に並んだ一粒を、そっと取り出して口に含む。
甘いはずのそれは、私の知るどんなものより苦くて、しょっぱくて、涙が止まった後もなかなか溶けずに舌の上に残るその味を、私はいつまでも味わっていた。
このお話はフミナーズさんで毎月一回掲載している小説連載「真夜中の戯言」の2月回「真夜中のビター・スウィート」の別バージョンです。2つ編集者さんに提出してどちらを採用するか決めてもらいました。全く異なる後味を味わえる、採用された方のショートストーリーはこちら。
ありがとうございます。