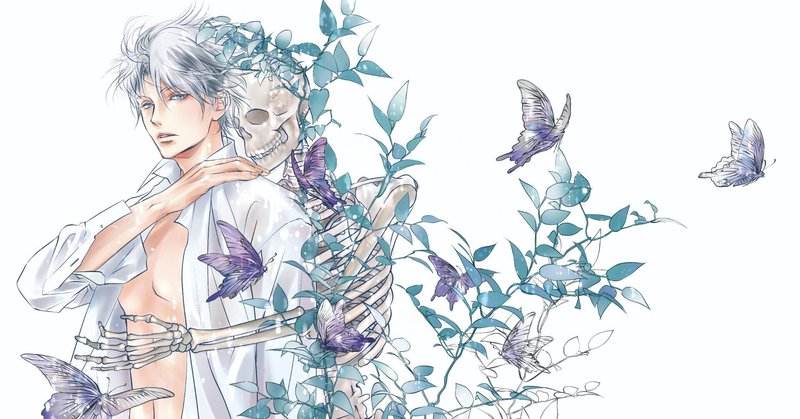
ストロベリームーン
★2024/2/25 発行 メリーバッドエンドなBL短編集【人でなしの恋わずらい】収録作品。全年齢対象です。
ストロベリームーンってのはピンク色をした満月のことだと、ずっと思っていた。
六月の満月を指す俗称だと知ったのは、つい先日のことだ。
アメリカ先住民の風習に由来するものらしく、月の色とは関係がないらしい。
アメリカ合衆国の北、カナダとの国境付近にある五大湖の西側に暮らすオジブワ族は、農耕や狩猟が困難な森林地帯を生活の場としている。おもに野生の木の実や種子を採集する暮らしを送ってきたことから、その時々に採れる季節のものを月の呼び名とした。そのなかのひとつが、ストロベリームーンなのだという。
すなわち、イチゴの収穫時期に昇る月のことなのだ。
正しい由来を知っても、僕のなかでは『ストロベリームーン=ピンク色の月』だ。
長いあいだ持ち続けてしまった思い込みや刷り込みは、そうそう簡単に変えられるものじゃない。
そういう意味で今夜の月は、自分的に正真正銘のストロベリームーンだった。僕の真正面に、作りものみたいにでっかい桃色の月が、ぼーんと浮かんでいる。
ちなみに国立天文台のホームページには、月が赤く見える理由が載っている。地平線、もしくは水平線に近いときに、赤っぽく見えやすくなるそうだ。
たしかに今夜の月は、やたら地上に近い。
近辺に高い建造物や山がなく、空気も澄んでいるこの場所だからこその光景なのだろう。
自分の身体が宙に浮き、すぐ間近で月を眺めているような心地がした。長時間の移動のせいか妙な浮遊感があって、なんだか足下がおぼつかない。
新幹線ひかり号から乗り継いだ在来線は、二両編成の、鮮やかな朱色の普通列車だった。
これがなんと、キハ40系。
昭和五十年代半ばに製造された旧国鉄時代最後のディーゼルエンジン車で、【撮り鉄】と呼ばれるマニアが数人、ホームでカメラを構えていた。
キハがホームに入ってくると、撮り鉄たちの興奮度とカメラのシャッター音がすさまじくなる。
擦り切れたベルベットの座席に座り、木の匂いがするレトロな列車に揺られること一時間あまり。
目的の駅に到着する頃には、すっかり暗くなっていた。
屋根もない小さなホームでピンク色の月を見あげていた僕は、はっと我に返り、無人の改札を通って古びた駅舎を出る。
駅前には人っ子ひとり、いなかった。
まだ夜の八時前だというのに、真新しいコンビニ以外、通りのすべての店はシャッターを降ろしている。それらのシャッターには錆が浮いていて、看板は傾き、軒先に貼られたテントも色褪せたり、破れたりしていた。
想像していた以上に寂れた場所だった。
ひと昔前は観光客でごった返していたなんて、とても信じられない。
――僕だったら……こんなところで暮らしていけるかな……。
知らず知らず、ため息が出る。
ここからは徒歩だ。
教えられた通りの道順をたどれば、十五分ほどで須藤兄弟が住む家に着く。
須藤兄弟は一卵性双生児だ。
兄が『ナル兄』こと成章で、弟が浩怜。
兄のニックネームがナル兄で統一されているのとは対照的に、弟のほうはヒロくん、ヒロヒロ、ヒロリン、サトポンなどなどバラエティに富んでいる。
見ためはそっくりでも成章は実直、浩怜は「ふにゃっ」とした、捉えどころのない弄られキャラだった。会うのは六年ぶりだけど、きっと、変わってはいないはずだ。
シャッター通りを抜けると住宅街だった。
が、小綺麗な家が並んでいるのはほんの五十メートルほどで、その先には古い木造民家が軒を連ねている。屋根が傾いた家や、朽ちた廃屋もあった。
やがて街灯がまばらになり、空き地や雑木林が目立ちはじめる。
(ほんとに、この道でいいのか……?)
胸のあたりがザワザワした。
進行方向の上空には、まるで道しるべみたいにピンクの満月が浮かんでいて、僕は気を取り直して歩き出す。
やがて、灯りのともった一軒家が見えてきた。
きっとあの家だ。
安堵して、自然と歩調が速くなる。
もう二度と、彼らに会うつもりなんてなかったのに――。
須藤兄弟の家は、端的に表現するなら『サザエさんの家』だった。
まわりをブロック塀で囲まれた、スレート屋根の平屋だ。
向かって右手の奥に屋根付きのガレージがあり、1980年代のものらしき古いメルセデス・ベンツが停まっていた。いまはこういうネオ・クラシックな自動車が、お洒落な大人たちに人気らしい。
色褪せた木製の門扉を開け、これまたレトロな玄関の前に立つ。
格子の木枠に磨りガラスが嵌まった、いまどき珍しい木製の引き戸だった。軒先には、乳白色の傘を被った裸電球が取り付けられている。
ここだけ、昭和で時間が止まっていた。
「いらっしゃい、開人。久しぶりだね。道、迷わなかった?」
薄暗い玄関で出迎えてくれたのは、兄の成章だった。
浩怜とまったく同じ顔だけど、僕にはすぐに成章だとわかる。
だから、心臓が騒ぐことはない。
彼はスリムなチノパンに、パリッとしたモノトーンのボーダーTシャツを合わせていた。
普段着だからそんなに高価な服じゃないのだろうけど、イケメンは何を着てもさまになる。うらやましい限りだ。
「びっくりしただろ、ド田舎で。いまじゃゴーストタウンになりかけてるけど、俺たちが子供の頃は、けっこう賑わってたんだ。旅館や飲食店もたくさんあった」
軋む狭い廊下を、二人で前後に並んで歩く。
「まあ、こんなとこでも住めば都だよ。静かだし、空気はいいし、のんびりしてるし」
「だろうね。月がめちゃくちゃ綺麗だった」
「ああ、今夜はあれだ、何だっけ? そうそう、スーパームーンってやつ」
そう言いながら成章は、廊下とダイニング・キッチンを隔てた引き戸を開ける。
きききっ、と耳障りな音がした。
「――ヒロ、開人、来たぞ」
こちらに背中を向けているパーカーの、鮮やかなターコイズブルーが視野に飛び込んできた。
僕は一瞬、息を止めて固まってしまう。
彼に会いたくて会いたくて、たまらずに泣いた夜もあったはずなのに、いますぐ逃げ出してしまいたいような気持ちになる。
成章の複製が、こちらを振り向いた。
六年ぶりに会う想い人が、何度あきらめようとしても、あきらめきれなかった愛おしい人が、そこにいる。
須藤兄弟と親しくなったのは、中学一年の二学期だ。
僕の通っていた市立中学校は、山を削って造られた新興住宅団地のなかにあり、当時もまだ三学期制だった。
東京からの転校生、それも双子のイケメンがやって来て、三学年あわせて六クラス、全校生徒百三十九人しかいない学校中が騒然となったのを覚えている。
二人とも顔がいいうえに勉強もでき、性格も気さく――とくれば、当然モテまくった。女子にも男子にも、他校の生徒にも。
兄の成章はスポーツ万能で、唯一の運動部だった硬式テニス部を、創立以来はじめての県大会に導いた。
けれど弟の浩怜は喘息に悩まされていて、地方に引っ越してきたのも空気のいい環境を求めてのことだと、本人が話してくれた。
ときおり授業中に発作を起こす浩怜を介抱し、保健室まで送り届けるのは保健委員だった僕の役割で、庇護する対象だった彼の存在が日ごとに大きく特別なものになっていくのを、どうすることもできなかった。
僕は浩怜への想いを、ひた隠しに隠し通した。
まったく同じ顔をしているのに、どうして兄の成章に対しては友情と憧れ以外の感情を抱けないのか――自分でも不思議でしかたなかった。
「今日はすき焼きパーティーだよ、開人。嬉しいだろ?」
調理台で野菜を切っていた浩怜は、開口一番、そう言った。
六年のブランクも、別れ際にみごとに僕を振ったことも、すっかり忘れてしまったかのような、ごく自然な笑顔で。
「ちょっと散らかってるけど、ま、気にせず座ってよ」
僕は、椅子の上にあった雑誌やコピー紙をどかそうとして持ちあげた。持ったはいいが、どこに置けばいいのかわからない。
「ああ、ごめん。それ、渡して」
おろおろしていると、さっと成章の手が伸びてくる。
須藤兄弟のサザエさんの家は、そこそこ散らかっていて、適度な生活感があった。
いい感じだ。典型的な田舎の家だったけれど、あちらこちらに彼らのセンスの良さが見え隠れする。
この台所にある古い木製のテーブルと椅子と食器棚は、おそらく北欧のヴィンテージだ。
オーガニックな雰囲気の照明はルイスポールセン。
天井や壁紙も新しく張り替えられていて、モダンなインテリアと古い日本家屋が違和感なく融合していた。
懐かしくて、心地よくて、いつまでも居たくなる。そんな家だ。
六年前、地元の公立大学を卒業した僕は、東京の会社に就職して実家を出た。
浩怜も僕と同じ大学の芸術学部に籍を置いていたが、入学後に持病の喘息が悪化し、中退せざるを得なくなった。
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症――好酸球という白血球の一種が増加して全身の細い血管に炎症が生じ、神経、皮膚、筋肉、内臓の障害がみられる病気だった。喘息やアレルギー性鼻炎を持つ患者の一部が、ごくまれに発症するらしい。
「なんで、こんな訳わかんないクソ長い名前の病気になっちまったんだろ? 寿限無寿限無かよ? おれ、いまだに覚えられなくてさ、病名訊かれたら困るんだよな」
そう言って笑う浩怜は夢をあきらめることなく、通信制の大学に入り直してデザインを学び、在宅で仕事をはじめる。
そののち、京都の大学を卒業した成章と、二人でデザイン事務所を設立して軌道に乗せ、祖父母が他界したあと空き家になっていたこの家に拠点を移したのだ。
東京に発つ前日、僕は浩怜に会った。会って、自分の気持ちを彼に伝えた。
玉砕することはわかりきっていたし、十年近く続いた友情も、この日を境に終わるだろうと覚悟した。
待ち受けるのはバッドエンド一択の愚行だ。
けれど、独りで墓場まで抱え込んでいくには、あまりにも僕の想いは深く、大きくなりすぎてしまっていた。
明日からは離ればなれだ。たぶん、もう二度と、須藤兄弟に会うこともない。
開き直った勢いに任せて告白すると、
「……ごめん、開人。おれ、好きな人がいるんだ」
軽蔑も罵倒もせず、浩怜はそう言って、緊張で固まっていた僕に頭を下げた。
「……元気そうだな、ヒロ。よかった」
ダイニング・テーブルの椅子に座った僕は、鍋の支度をしている浩怜に声をかける。
「うん、最近、調子がいいんだ。こっちに移って正解だった」
「たしかに環境はいいみたいだけど、病院、近くにあるのか? 通院、大変なんじゃ……」
「平気、平気。車で三十分くらいかな、隣町に大学病院があるんだ。いい先生が揃ってる。だから、ここに来ようって決めたんだから」
「そうなんだ」
僕はほっとする。
同時に、なんだか哀しくなった。
浩怜も成章も、本当だったら、こんな寂れた場所でひっそりと暮らしているような人間じゃない。
もっともっと華やかな場所で、自由に羽ばたいて生きるのがふさわしいのに――。
「うわっ、ヒロ! 卵、ないじゃん! ビールもぜんぜん足りないし!」
冷蔵庫を開けた成章が叫ぶ。
「えー、ナル兄、買ってきてくれてたんじゃないの?」
「今日は体調がいいから買い物に行ってくるっつったの、おまえじゃないか。何やってんだよ」
「え~、うっそぉ~」
浩怜は『どれどれ』といった風に、成章の後ろから冷蔵庫のなかを覗き込む。
「あーらら、ほんとだ。肉と野菜を調達したら安心して忘れてたよ。買ってこなきゃ。吉田さんの店、まだ開いてるかな」
「電話してみろよ。ダメなら駅前のコンビニだ」
「うん」
浩怜がスマホを耳に当て、話しはじめる。
「ナル兄、吉田さん、店開けて待っててくれるって」
「じゃ、すぐ行かなきゃ。開人、悪いけど留守番しててくれるかな。三十分はかからないと思う。冷蔵庫にビールがあるから、適当にやってて」
「わかった。二人とも、気をつけて」
「あ、ビールのほかに何か飲みたいもの、ある?」
浩怜が僕に訊く。
「う~ん、すき焼きなら、赤ワインがあると嬉しいかな。辛口のやつ」
この辺には美味いワインを置いてる店なんてないだろうな、と思いつつ、僕は言った。
「オッケー。吉田さんとこ、老舗の酒屋で通販もやってるから、けっこう品揃えがいいんだ。期待してて」
浩怜と成章は先を争うようにして、勝手口から外に出ていく。
ああ、いい光景だな、と思う。中学時代に戻ったみたいだ。
不覚にも、泣きそうになる。
二人を見送った直後、テーブルの上に車のキーが置かれてあるのに気づいた。
ほんとに浩怜も成章も忘れっぽい。
僕はキーを取りあげると、三和土にあった古いサンダルをつっかけ、二人を追いかけて勝手口を出る。
奥のガレージにはベンツが停まっていた。人の姿はなく、徒歩で行ったらしい。
でも、それにしては奇妙だった。
彼らの姿がどこにも見えない。
僕がキーを持って勝手口を出るまでにかかった時間は、せいぜい十秒かそこらだった。
だから、家の前かすぐ近くに、まだ二人はいるはずなのだ。幽霊のように、いきなり消えたりしない限りは――。
上空には、さっきよりも色鮮やかになったストロベリームーンが浮かんでいた。可愛らしいピンク色ではなく、赤に近いサーモンピンクで、何となく毒々しい。
初夏の生暖かい風が、玄関横に植えられた金木犀の葉を揺らした。まだ夜は浅いのに、漆黒の闇がべっとりと肌に張りついてくる。
ふと気になって、僕は、ガレージの車を見た。
チナブルーと呼ばれる、くすんだ水色のボンネットとフロントガラスに、うっすら砂埃がたまっている。ここに来たときは気づかなかった。
眼を凝らす。
運転席と助手席に、人のかたちをした影が見えた。
何かに導かれるように、僕は、ゆっくりと車に近づいていく。
運転席側の窓には、砂埃がほとんど付着していなかった。そしてなぜか、窓を囲むように内側からテープで目張りがしてある。
覗き込むと、暗い車内が赤っぽい月灯りに照らされて、ぼんやりと浮かびあがった。
人間が――正確に言うなら、『人間だったもの』がふたつ、折り重なるようにして、そこにあった。
顔も身体も茶色っぽく膨張していて、最初はこれがいったい何なのか、わからなかった。人間だと認識できたのは、服装に見覚えがあったからだ。
僕を玄関で出迎えてくれた成章が着ていたのと同じ、白と黒のボーダーTシャツ。
その隣りに見えるのは、台所で野菜を切っていた浩怜の、ターコイズブルーの半袖パーカーだ。
それらが、何を意味しているのか――。
理解できるまで、僕は当分のあいだ、ぼんやりとその場に立ち尽くしていた。
もう須藤兄弟には会わないと決めていた僕がここに来たのは、浩怜が悪性リンパ腫で、余命がいくばくもないと知らされたからだ。
浩怜は、ぎりぎりまでこの家で、通常通りの生活を送ることを望んだ。
そして成章も、弟の選択を受け入れた。
だから、今回は僕が浩怜に会う、本当に最後の機会だったのだ。
最後だったのに――。
本当に最後だったのに、どうして待っていてくれなかったんだ。
明るく頑張り屋だったヒロに、いったい何があったんだろう? 賢くて、しっかり者のナル兄のはずが、どうしちまったんだよ?
おまえたちは強かったじゃないか。強くて、誰よりも美しくて、誰よりも輝いていたじゃないか。
こんな最期を、おまえたちは本当に望んでいたのか? それなら、二人で静かに眠っていればよかったじゃないか。
どうして、六年も会っていなかった僕を呼んだんだ?
浩怜も成章も、腐った肉の塊になり果ててしまって、何も答えてはくれない。車のなかで、お互いを庇うように寄り添っているだけだ。
混乱が、次第にやるせない怒りへと変わっていく。
なぜ、僕を呼んだ? なぜ、僕を巻き込んだ? 何をしてほしかったんだ? こんなになってしまったんじゃ、もう、どうにもならないのに――。
『ごめん、開人……』
耳もとで、浩怜が囁く声がした。
振り返っても誰もいない。
『……ごめん、開人。おれ、好きな人がいるんだ』
浩怜の声が、六年前と同じ台詞をくり返す。
僕は、すべてを悟った。
――そうか。おまえの好きな人は、ナル兄だったのか。
見あげた赤い月がぼやけていく。頬に温かいものが伝い、流れていく。
僕は踵を返してガレージを出た。勝手口の引き戸を開け、家に入る。
警察に知らせなくてはいけない。
そのために呼ばれたのだという気がした。きっと二人とも、自分たちがこれ以上醜くならないうちに、見つけてほしかったのだ。
台所は、暖かな光で満たされていた。
テーブルに卓上コンロが置かれ、その横にパック詰めにされた牛肉が重ねられている。
三人分の箸とグラスも並べてあった。
調理台には、すでに準備された野菜や豆腐が入った大きなボウルが置かれてあって、まな板の上に、ついさっきまで浩怜が切っていた白ネギが転がっている。
僕は、木のテーブルに触れてみた。
続いて椅子の背に。
それから、グラスに。
確かな手触りがあって、この光景が夢ではなく、現実なのだと教えてくれる。
――なんだ。ヒロもナル兄も、ちゃんと生きてるじゃないか。生きて、この家で生活しているじゃないか。こっちが現実で、本物なんだ。さっきのあれはきっと、赤い月と疲れが見せた幻だったんだ。
僕は自分に言いきかせる。
――きっとそうだ。もう一度、ガレージに行って確かめればいい。そうすれば、すべて解決する。
けれど、足は床に張りついたまま、少しも動かない。
「行ってはいけない」と、頭のなかで声がした。
テーブルに置かれた手が震える。
背中が、ぞわりと冷たくなる。
不安に潰されそうになって立ちすくんでいると、いきなり、勝手口の戸がガラリと開いた。
「ただいま!」
両手にエコバッグを下げた浩怜と成章が、帰ってきた。
「地ビールの新しいやつが入っててさ、買いすぎちゃったよ。一人最低三本、ノルマな」
どさどさとテーブルに置かれたエコバッグから、アルミ缶や瓶に詰められたビールが次々に出てくる。
「これ、おすすめ。ヨモギ入りのIPA。珍しいだろ。こっちはペールエールだけど、香りがウッディで凄くいいんだ」
成章がテーブルにビールを並べ、浩怜はワインのボトルを「ほい」と僕に差し出す。
「吉田さんの保証つきワインだよ。二千本限定のレアものメルロー。九州にある小さなワイナリーが作ってるんだって」
ボトルを受け取ろうとしても、身体が動かなかった。
いったい、この家で何が起こっているのか。
何が真実で、何が嘘なのか――頭のなかはぐちゃぐちゃで、自分が眼にしているものを何ひとつ信用できない。
「ヒロ……あの、さっき……」
僕は、喉から絞り出すようにして声を発した。
全身の筋肉という筋肉が固まってしまったみたいで、短い言葉を発声することさえ思い通りにならない。
ガレージで――言いかけた僕を、成章が遮った。
「さあ、始めようか、すき焼きパーティ」
僕は、何も話せなくなった。
声を出そうとするたびに、喉の奥に何かが詰まったようになる。
わかっていた。
声を出せば、話してしまうからだ。ガレージで見たものを。
尋ねてしまうからだ。なぜ浩怜と成章が、ここにこうして生きているのかを。
テーブルに着いた僕の前で、香ばしい匂いをさせた牛肉がぐつぐつと湯気を立てている。成章が食器棚からワイングラスを取り出して、浩怜がルビー色のワインをつぎ分ける。
「はい、これは開人のね。あ、卵、忘れてるじゃん」
僕の前には、いつの間にか赤ワインがそそがれたグラスと、生卵が入った深皿が置かれてあった。
黄泉戸喫。
死者に勧められた食物を口にしてしまうと、肉体を持って生きる生者の世界には二度と戻れない。永遠に煉獄をさまよって、生きることも、死ぬこともできなくなる。
何のために――。
僕はまた、同じことを考える。
何のために、僕はここに、二人に呼ばれたのだろう。
いや、もしかして。
彼らを呼んだのは、僕のほうなのか。
いつまでも浩怜に執着していた、僕の心が呼び寄せたのか――。
「じゃ、いっただきま~す」
浩怜が肉にかぶりつく。
成章は優雅にワインを飲みながら、野菜と肉を鍋に投入する。
「ほら、食べなよ、開人。なんでぼーっとしてんの?」
浩怜の、成章の、四つの眼が、僕をじっと見つめている。
彼らは、選べと言っているのだ。
逃げるのか。それとも、自分たちとともに、ここに残るのか――。
玄関横の金木犀の葉が、ざわざわと風に揺れる音がする。
僕は眼を逸らした。
流しの上にある窓の磨りガラスが、ピンク色に染まっていた。
暗い夜空にはまだ、あの大きなストロベリームーンが浮かんでいて、ベンツのなかに横たわった二人にも同じ光が降りそそいでいるのだろう。
逃げるという選択肢は、僕のなかから完全に消えていた。
わかってしまったのだ。
警察に知らせたら、この家を出てしまったら、もう二度と、ここには戻れない。僕の大切なものがすべて、永遠に失われてしまう。
こうして、この暖かな食卓を、ずっと囲んでいられるのなら。
愛おしい浩怜のそばに、ずっと居られるのなら。
僕は、震える手を伸ばしてワイングラスを持ち、ゆっくりと口に運ぶ。
浩怜の眼が、きらりと光る。
成章の唇に、微笑が浮かぶ。
舌の上に、ワインの芳醇な香りが拡がった。
END
★文学フリマ広島6(2024/2/25)にあわせて発行した同人誌【人でなしの恋わずらい】のなかの一作です。
青城硝子さんの表紙イラストをはじめ、装丁がほんとに綺麗な本なので、ぜひ、お手に取ってみてください。
【架空ストア】で通販しています。(R15指定です)
最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございました。 著作を読んでくださることが、わたしにとっては最高のサポートになります。どうぞ、よろしくお願いします。
