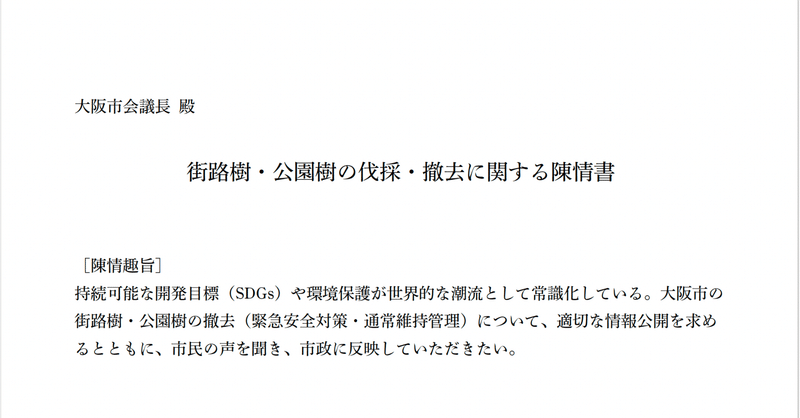
初めての陳情書提出(2023年2月1日付)
大阪市議会・議長宛てに陳情書を提出しました。
陳情は委員会で審査され、結論 (採択・不採択)が出されます。
締切は【2023年2月7日(火)】。
●陳情質疑の議事録を追記しました(2024年1月15日)。

街路樹・公園樹の伐採・撤去に関する陳情書
[陳情趣旨]
持続可能な開発目標(SDGs)や環境保護が世界的な潮流として常識化している。大阪市の街路樹・公園樹の撤去(緊急安全対策・通常維持管理)について、適切な情報公開を求めるとともに、市民の声を聞き、市政に反映していただきたい。
[陳情項目]
1. 市内全ての街路樹・公園樹の伐採計画について、各樹木一本ごとをマッピングした地図および撤去理由を市ホームページ、区の広報紙に公開し、市民への周知を図ること
2. 通常維持管理費の「剪定費用」「伐採費用」「処分費用」等の各項目について、年度ごとに(平成24年度から令和4年度まで)内訳を示し公開すること
3. 樹木の管理において強い剪定を繰り返したことで樹勢が弱り、伐採を免れない例がある。倒木・幹折れ・伐採を誘発する管理をしていないか、検証・報告・公開すること
4. 景観がよくないブツ切り剪定を見直し、樹形を維持しながら維持管理すること
5. パブリックコメントの募集や住民説明会など市民の声を聞く機会を設け、それを反映できる行政をおこなうこと
2023年2月1日
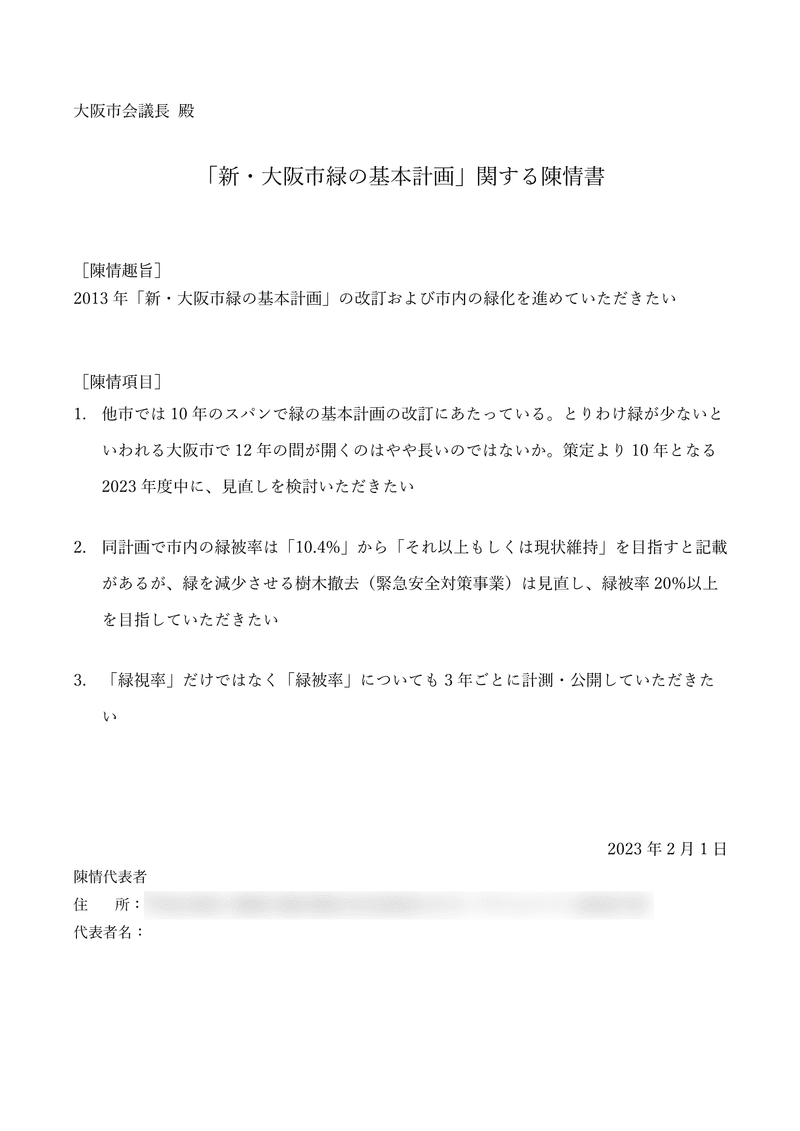
「新・大阪市緑の基本計画」関する陳情書
[陳情趣旨]
2013年「新・大阪市緑の基本計画」の改訂および市内の緑化を進めていただきたい
[陳情項目]
1. 他市では10年のスパンで緑の基本計画の改訂にあたっている。とりわけ緑が少ないといわれる大阪市で12年の間が開くのはやや長いのではないか。策定より10年となる2023年度中に、見直しを検討いただきたい
2. 同計画で市内の緑被率は「10.4%」から「それ以上もしくは現状維持」を目指すと記載があるが、緑を減少させる樹木撤去(緊急安全対策事業)は見直し、緑被率20%以上を目指していただきたい
3. 「緑視率」だけではなく「緑被率」についても3年ごとに計測・公開していただきたい
2023年2月1日
■陳情が審査された「大阪市会建設港湾委員会」(2023年2月17日)の議事録
●陳情に対する大阪市の見解(建設局長)
続きまして、陳情第9号、街路樹・公園樹の伐採・撤去に関する陳情書について見解を申し上げます。
陳情の趣旨は、街路樹・公園樹の撤去について、適切な情報公開並びに市民の声を聞き、市政に反映することを求めるものでございます。
陳情項目の1点目は、街路樹・公園樹の安全対策事業における具体的な実施箇所や撤去理由について、市民への周知を求めるものでございます。
大阪市では、過去に植えた樹木が大木化・老木化し、長年の管理の中で街路樹では樹勢の衰えや通行障害、視距阻害など安全な道路交通に支障を来すおそれがあり、また公園樹では、樹勢の衰えのほか、民有地への越境、公園施設の損壊など安全に支障を来すおそれがそれぞれ生じておりました。
そこで、市民の安全・安心を確保するため、これらの樹木を撤去し、必要に応じて成長の緩やかな樹木等に植え替える安全対策事業に、平成30年度から令和6年度まで取り組むこととしております。
安全対策事業の実施に当たりましては、予定箇所など事前に地域の方々へ説明するとともに、撤去する個々の樹木に貼り紙で撤去の理由などを掲示し、お知らせしております。
さらに、この2月からは予定箇所についてホームページへの公開も始めたところであり、引き続き、市民の皆様への丁寧な周知に努めてまいります。
陳情項目の2点目、3点目、4点目は、樹木の維持管理において剪定方法の見直しや情報公開を求めるものでございます。
日常の樹木の維持管理に当たりましては、限られた予算の中で安全の確保にも十分考慮しながら、植えられている環境や樹種に応じた剪定を行っております。また、樹木の維持管理の在り方につきましては、現在、様々な観点から検討しているところでございます。
なお、公文書の保存期間内にある情報につきましては、請求がございましたら適宜対応してまいります。
陳情項目の5点目は、これらの施策について市民の声を聞き、それを行政に反映させることを求めるものでございます。
街路樹や公園樹は地域住民にとって身近な緑であることから、安全・安心を確保する施策の必要性について引き続き情報発信を行い、市民の皆様の様々な意見をお聞きしながら丁寧な説明に努めてまいります。
続きまして、陳情第10号、「新・大阪市緑の基本計画」に関する陳情書について見解を申し上げます。
陳情の趣旨は、2013年度策定の新・大阪市緑の基本計画の改定及び市内の緑化を進めていただきたいというものでございます。
陳情項目の1点目は、現行の新・大阪市緑の基本計画が策定より10年となる2023年度中の見直し検討を求めるものでございます。
現行の新・大阪市緑の基本計画は、本市の緑のまちづくりを推進するための緑とオープンスペースの総合計画で、2013年に策定し、計画期間は2025年度までとなっております。計画期間は、広域計画である大阪府のみどりの大阪推進計画と整合を図り設定したものであり、計画期間が終了する2025年の緑の基本計画の改定を目指し、現在、みどりのまちづくり審議会での議論を開始しているところでございます。
陳情項目の2点目は、安全対策事業による樹木撤去の見直しと緑被率の向上を求めるものでございます。
高密な都市化が進み市内全域が市街化されている本市では、現行計画の緑被率の目標設定を現状もしくはそれ以上となるよう努めていくとしております。次期基本計画で用いる指標につきましては、今後、審議会での議論を踏まえ検討してまいります。
なお、安全対策事業につきましては、市民の安全・安心を確保する観点から必要な事業であり、樹木撤去をした上で、必要に応じ成長の緩やかな樹木に更新していくこととしております。
陳情の第3点目は、緑被率の3年ごとの計測・公開を求めるものでございます。
現行計画では、実感できる緑のまちづくりを推進するため、うめきたや大阪駅前、淀屋橋や御堂筋といった大阪の顔となる場所など市内8か所において、目に見える範囲に占める緑の量の割合を示す緑視率を共有指標として設定し、3年ごとに公開することとしております。今後、緑の基本計画の改定作業の中で、市民の皆様にとって分かりやすい情報の発信についても議論してまいります。
◆片山一歩委員
大阪維新の会の片山一歩でございます。
私のほうからは、陳情第9号、街路樹・公園樹の伐採・撤去に関する陳情書につきましてお伺いいたします。
陳情では、安全対策事業に係る樹木の撤去において、きちんと情報を公開し、市民の声を聞きながら進めることが求められております。
安全対策事業は、大木化や老木化が進み、倒木などにより市民の安全に支障を及ぼすおそれのある樹木について撤去、更新を行うものと聞いておりますが、平成30年に発生した台風21号では健全な樹木でさえ公園に隣接する家屋や車両等の市民の財産に多大な被害があったことが記憶に新しいところであり、市民の安全・安心を確保する上で重要な事業であると認識しております。
昨年度も我が会派において街路樹・公園樹の安全対策事業について質疑を行ってきましたが、改めて、これまで取り組んでいるこの安全対策事業の概要についてお伺いいたします。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えします。
建設局では、市民の安全・安心を確保するため、平成30年度から街路樹・公園樹の安全対策事業に取り組んでいます。本事業では、樹木を撤去した後は都市の貴重な緑を確保するためできる限り植え替えることとしており、街路樹では交差点の見通しを遮る場所、公園樹では家屋に隣接する場所など市民生活の安全・安心に支障を来す場所でない限り、新たな樹木を植栽しています。
本事業の取組状況についてですが、まず街路樹については、平成30年度から令和2年度までの3年間、長年の管理の中で樹勢が衰えてきた樹木や通行障害など安全な道路交通に支障が生じている緊急性の高い高木、約9,000本を対象に撤去、更新を行ってきました。
更新に当たりましては、約9,000本のうち約2,000本は成長の緩やかな高木に植え替え、残りの約7,000本は、樹木により見通しが悪くなることで安全上支障が生じないように、約8万5,000株の低木に植え替えました。
引き続き、令和4年度から6年度までの3年間、樹木の根が舗装や縁石を持ち上げる根上がりなど根の成長不良を起こし、近い将来安全な道路交通に支障を来すおそれのある高木など約3,000本と、主に生活道路において成長が著しく早く通行障害などが発生しやすい低木約1万3,000平方メートルを対象に、撤去、更新を行っております。
次に、公園樹においては、令和2年度から5年度までの4年間、樹勢が衰えてきたものや民有地への越境、公園施設の損壊など公園内外の安全に支障を来すおそれのある高木約7,000本を対象に撤去、更新を行っております。
現在実施中の安全対策事業においても可能な限り高木や低木への植え替えを行うこととしており、引き続き、市民の皆様に丁寧な説明を行いながら進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
◆片山一歩委員 今回の安全対策事業の趣旨やその目的はよく分かりました。今回、撤去することがクローズアップされているようで、事業期間中、約9,000本の撤去のうち約2,000本は高木に植え替え、残りの約7,000本は安全上支障が生じないよう約8万5,000株の低木に植え替えたということで、撤去しただけではなく、植え替えも可能な限り行ってきているということをお聞きいたしました。
ただ、今回の陳情や先日の毎日新聞での報道にもあるように、市民の方々は撤去に関し十分に御理解をいただけていないように感じる部分がございます。そもそも撤去をするとした判断基準はどのようなものであったか、改めてお伺いいたします。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えします。
まず、公園樹における撤去の判断基準としまして3つの視点がございます。1つ目は、樹勢の衰えを判断する「樹木の健全度」で、枯れや腐りなど生育状態に支障がある樹木を対象としています。2つ目は、例えばヒマラヤスギなど根が浅く倒木しやすい樹種など樹木の特性を踏まえ、樹種で判断しています。3つ目は植栽環境等でございまして、民有地への越境や植栽密度が高いもの、また、現状もしくは将来的に施設を損壊するおそれのある樹木などを対象としています。これら3つの視点を基に撤去対象樹木を選定しております。
次に、街路樹における撤去の判断基準としましては、先行して平成30年度から令和2年度に実施いたしました安全対策事業におきましては、長年の管理の中で、樹勢が衰えてきたことや通行障害など安全な道路交通に支障が生じているものを撤去対象として最優先に取り組んでまいりました。
また、引き続き今年度から実施しております安全対策事業における街路樹の撤去の判断基準としましては、大木化により通行障害のおそれのある樹木を中心に取り組んでおります。以上でございます。
◆片山一歩委員 安全対策事業は、市民の安全・安心を確保する意味でも大変重要な事業であることから、陳情にもありますように、より丁寧に地域の方々に説明しながら事業を推進してほしいというふうに考えております。
先日の毎日新聞の報道では、撤去予定樹木1本ごとに貼り紙を掲示しているとあるが、2週間ほどの掲示の後、撤去作業に入っていると書かれてありました。先ほどの答弁で市民に丁寧に説明するとのことでありましたが、もう少し掲示期間を長く取る必要があるのではないかと考えます。
加えて、市のホームページを充実させるなど、市民に分かりやすく発信していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回、貼り紙の周知期間が短いというお声もいただいていることから、今後、できる限り周知期間を長く取り、さらに丁寧な説明に努めたいと考えております。
また、市のホームページについては、この2月から予定箇所を示した地図を御覧いただけるようにいたしました。令和5年度からは、地域への説明のタイミングに合わせ、撤去予定樹木の樹種名や本数、撤去理由を市のホームページへ掲載するなど、事業の内容をより分かりやすく伝えられるようにしていきたいと考えております。また、市のホームページにおきまして、撤去前の写真を充実させるなどにより、撤去理由を市民に分かりやすく御理解いただけるように改善していきたいと考えております。
現地での貼り紙の掲示期間を長く取ることやホームページを充実させることなど様々な手法を活用するとともに、市民からの問合せに対しても丁寧に説明させていただきたいと考えております。以上でございます。
◆片山一歩委員 市民への周知は改善していくということなので、よろしくお願いいたします。
さて、先日の毎日新聞の記事では、街路樹と公園樹の維持管理について、「住民側は、予算が抑え込まれて管理が不十分になり、伐採ありきで進めているのではないかと疑いの目を向ける」という形で報道されております。改めて、今回の安全対策事業の目的を確認したいと思います。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
街路樹・公園樹は、長年の管理の中で街路樹では樹勢の衰えや通行障害など安全な道路交通に支障を来すおそれが、また公園樹では、樹勢の衰えのほか民有地への越境や公園施設の損壊など、市民の安全・安心に支障を来すおそれが生じてきております。
安全対策事業は、これらの樹木を撤去し、可能な限り成長の緩やかな高木や安全上支障が生じない低木に植え替えるなど、市民の安全・安心の確保を目的とした事業でございます。以上でございます。
◆片山一歩委員 樹木の撤去について、予算が原因ではなく、安全・安心を確保するために取り組んでいる事業であるという説明でした。
繰り返しにはなりますが、事業の目的や趣旨を市民の方に理解していただき、引き続き丁寧に事業を進めていってほしいと思います。
さて、陳情では日常の維持管理に関する要望もありました。先ほどの局長からの見解では、樹木の維持管理の在り方について検討しているところであると説明されておりますが、どのようなことを検討しているのか、お伺いいたします。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
街路樹や公園樹の維持管理におきまして、樹木の剪定は樹木の骨格を形づくり、健全な成長を促す上で重要な作業となります。
特に街路樹においては、安全な道路交通に支障を来さないよう、道路構造令に基づく歩道や車道の建築限界の確保、また電力線や建築物などとの離隔を取って道路交通の安全を確保するためにも、また信号や標識を隠さないようにするためにも樹木の剪定が必要となっております。
また、公園樹におきましては、公園に隣接する民家付近などにおいては越境することのないように、公園出入口付近においては視認性を確保するためにも樹木の剪定が必要となっております。
これらの剪定は、限られた予算の中、安全の確保に十分配慮しながら、植栽された環境や樹木の樹種などに応じて行っております。また、過去に植えてきました樹木が大木化・老木化し、長年の管理の中で市民の安全・安心に影響を及ぼすおそれが生じてきたため、平成30年度から安全対策事業として短期集中的に撤去・更新を行っているところでございますが、今後は樹木の状態に応じて計画的に樹木の撤去・更新を実施していく必要があると考えております。
そういった状況を踏まえ、安全・安心の観点はもとより、景観への配慮、ライフサイクルコストなど様々な観点から、今後の樹木の剪定や撤去・更新の在り方について現在検討しているところでございます。以上でございます。
◆片山一歩委員 長年、家の前にあった木が切られるということは本当に寂しい思いをされることも分かりますが、このように先ほどから説明がありますように、今後とも市民の方々に丁寧な説明をしながら事業を進めていっていただきたいというふうに考えます。そのように要望いたしまして、以上で私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。
◆長岡ゆりこ委員(注:配付資料は下部に掲載)
陳情第9号、10号及び16号にも関連をいたしまして、大阪の緑ですね、とりわけ公園樹・街路樹を守ってほしい、慈しんでほしいという思いが出されていると受け止めまして、この3点で質疑をさせていただきたいと思います。
実は、私の地元の東淀川区でも、お顔を見てお話を聞ける人たちの間でも、そして市政アンケートを取りましたらその中からも、街路樹が根こそぎ取られてしまってショックだと、別の木が植えられると思ったら塞がれてしまったと、そういうなぜですかという声が多くの方たちから上がっているということです。
SNS上でも、大阪城公園の樹木が1,200本伐採されたことを皮切りに、大阪における公園樹・街路樹の伐採に対して市民の皆さんの不満の声というのは多数上がってるのかなと思います。木を切る改革とやゆまでされるという状況になっているわけです。
数日前にはネットニュース、毎日新聞のことも言っていただいた方もいらっしゃいましたけれど、「街路樹伐採、募る不信」というそういう見出しも出ていたかなというふうに思いますので、公園樹・街路樹の伐採問題、非常に市民の関心が高まっていると思います。
多くの市民の、なぜそんなに木を切るのかという疑問と、守ってほしい、緑を増やしてほしいという疑問と思いにお応えするのが大阪市かなというふうに思うんですけれど、ほかの委員からもありましたけれど、この木が切られていってるのには理由があるというふうに思います。安全対策事業という名前が聞こえてきますけれども、そもそもどういったものなのか、概要や目的について説明をして、現状で伐採対象となっているのは何本なのかということをちょっと重複しますけれども教えてください。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
平成30年度から令和2年度までの3年間で実施しました街路樹安全対策事業は、長年の管理の中で樹勢が衰えてきた樹木や、通行障害、視距阻害といった安全な道路交通に支障が生じている樹木など緊急性の高い高木を対象に、約9,000本の撤去・更新を行ってきました。
引き続き令和4年度から6年度までの3年間に実施している同事業は、樹木の根が舗装や縁石を持ち上げる根上がりなどの根の成長不良を起こし、近い将来安全な道路交通に支障を来すおそれがある高木などを対象に、約3,000本の撤去・更新を予定しています。
また、公園樹安全対策事業については、令和2年度から5年度までの4年間実施いたしまして、樹勢が衰え倒木や枝折れなど安全な公園利用に支障を来すおそれのあるものをはじめ、公園に隣接する民有地への越境、樹木の根により縁石や擁壁、舗装などを持ち上げる公園施設の損壊など公園内外の安全に支障を来すおそれがある高木を対象に、約7,000本の撤去・更新を予定しております。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 全部合わせると約1万9,000本ということだというふうに思います。とんでもない数の樹木を切り倒すという計画になっているわけです。今、令和4年度ですので、街路樹と公園樹、両方の伐採計画が重なっている中で、あっちでもこっちでも木が切られてると、そういう声が上がってきているということだと思うんです。
また、高木の本数を言っていただきまして、低木も平米で1万3,000平米でしたか、切ってるよということもありましたけれど、そんなに切らなければならないのかということが、今日は素朴な疑問を連発しますけど、素朴な疑問なわけです。
伐採・撤去される樹木というのは、今いろいろと理由はありましたけれど、判定する基準というのがあると思うんですよね。その木がこういう理由であかんのやという判定基準というのは、市民に納得する理由がなければ、やっぱり何でこの木切っちゃったのということからは逃れられないということになっています。判断基準について教えていただいてもよろしいでしょうか。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
まず、公園樹における撤去の判断基準としまして3つの視点がございます。
1つ目は、樹勢の衰えを判断する樹木の健全度で、枯れや腐りなど生育状態に支障がある樹木を対象としています。2つ目は、根が浅く倒木しやすい樹種など、樹木の特性を踏まえ樹種で判断しています。3つ目は植栽環境等で、民有地への越境や植栽密度が高いもの、また、現状もしくは将来的に施設を損壊するおそれのある樹木などを対象とします。これら3つの視点を基に撤去対象樹木を選定しております。
次に、街路樹における撤去の判断基準としましては、先行して平成30年度から令和2年度に実施いたしました安全対策事業におきましては、長年の管理の中で樹勢が衰えてきたことや通行障害、視距障害など安全な道路交通に支障が生じている緊急性の高いものとし、引き続き今年度から実施しております安全対策事業における街路樹の判断基準としましては、大木化により通行障害のおそれのある樹木を中心に取り組んでおります。撤去した箇所は、支障のない限り原則、高木や低木への植え替えを行っております。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 3つの判断基準と街路樹について教えていただきましたけれど、安全対策ということですから、本当に中が枯れてしまったりしてすぐに倒木のおそれがあるというもの、どうしても撤去しなければいけないものまで全部切るなと言ってるわけではないんですけれど、ただ、本当に1万9,000本全部切らなあかんのかということが市民の皆さんの本当に心が痛いという、そういうお声だというふうに思いますので、こういった質疑をさせていただいてるんですけれど、樹種についてはヒマラヤスギとか、名前が挙がったらもうヒマラヤスギは全部撤去するという、そういうことになっていて、その理由についてもちょっと伺ったらよかったんですが、今日はちょっと置いときますけれど、健全度については、いろいろ健全度だけじゃなく、今言った3つの指標なんだというふうに思うんですけれど、いろいろな段階で調査をして判定しているということをヒアリングの中で教えていただきました。
1つ目には、造園系のコンサルさんがまず樹木の判定をして、これはもう絶対切らなあかんと判定する。2つ目が、その造園コンサルさんが樹木医さんに依頼をして、どうですかと判定してもらう。3つ目が、公園事務所が植栽環境とかそういったもので撤去を決めると、この3つの段階があるというふうに教えていただいたんですけど、資料を見ていただきたいんですけれど、城北公園の図面が出てきます。これ、情報公開請求をされた方からこういう各公園の伐採計画書というのがあるんですよと教えていただいて、私のほうでも取得をしたものなんですけれど、伐採対象の樹木がある全ての公園のこういった計画書というのがあるということです。
城北公園から東側という部分なんですけれど、先ほどの判断基準3段階別に見ると、まずA、Bと書いてるところ、造園コンサルさんが判断したA、Bというのが即撤去。2番目に、樹木医さんに判定してねと言ったのが数字です。伐採しようと選ばれたのが丸がついてるやつです。公園事務所が判定したのが平仮名で、ここだったら、分かりにくいかもしれませんけど、「あいうえお」といってずっとこちら側の左側には「に」までありますので、22本あるということになります。ですので、数字のほうは10まで丸がついていますから、合計34本の樹木が撤去されるよということが記載をされているわけなんです。
これ、すごい見方が難しくて3回教えてもらってようやく分かったということなんですけど、城北公園東側だけで34本根こそぎ取っちゃおうという、そういう計画になっています。それは公園利用者さんや地域住民の皆さんも驚くぞということになるわけですね。
今回ちょっとこれが3つとも書いてあったんで分かりやすかったんで例を出しましたけど、全部の公園、ちょっとお載せできなかったんですけど、各伐採計画書を細かく見ますと、例えば伐採理由が高さ10メートル以上という項目だけに丸がついてるのに伐採するのかというような疑問が出されたりとか、我が家の近所の小松公園というのが東淀川区にあるんですけど、24本しか木がないのに8本切ると、3分の1切っちゃうと。そのうち6本が間引きと書いてあるんですよ。間引かないでも邪魔になってないなと思ったり、間引きって危ないからという理由と違うなとか、いろいろ思いがよぎるということになっております。
そして伐採理由が、植栽環境の項目では、例えば公園内にある縁石ですね。こっちに土のところがあって、こっちに木が生えててちょっと縁石があって、それが根上がりになったらそれは伐採するというんですよ。縁石をちょっと動かしてあげたら、木がゆっくり根っこが張れるようにしてあげたら、公園の中ですからいいんじゃないかと思うものも、伐採だということになっているというのが、本当に切らなきゃいけないのかという住民の皆さんの思いにここがつながっているわけですね。細かく見ていけば切らずに守るという選択肢がありそうだぞという、そういうことになっております。
極めつきは、今日載せたらよかったんですけど、すみません。淀川区西中島東公園のタブノキという木があるんですけど、そこには伐採理由が何と書いてあるかというと、伐採を行うための通路確保のためと書いてあるんですよ。そのためにこの木を伐採するのという話なんですね。伐採のための伐採が行われていると。やっぱり伐採ありきだったんじゃないかと、許されないんじゃないかという理由で伐採される木があるんだということが、本当に木を守るという視点を持ってもらいたいということにつながるわけですね。
関係各所、このことで市民の皆さん、いっぱい動いてますので、いろんな情報が寄せられるんですけど、街路樹に関しては通行障害が一番だということなんですけれど、通行障害で信号を隠している木の枝を切るというのだったら分かるんですけど、そこの街路樹を全部切るというのが本当に必要なのかということなんですよ。工夫できるんじゃないですかということが寄せられています。
ちょっと紹介しますね。信号や標識の位置をちょっと変える。電灯の位置を工夫する。電線が引っかかってるんだったら電線のほうにカバーをつけるというのは関電さんに相談したらできるそうですので、そういうことも考えられる。道路側にも対策を取ることができるんじゃないのと。関係各所と調整して互いに工夫をすれば、木を切らなくてもいい、ちょっとこの枝を払うとか、そういうケースだってあるんじゃないかと。現在は街路樹が全ての責任をかぶって伐採されていると。これでSDGsと言えるのかと、こういう声があるわけです。
どの木を伐採するのか、今、理由があってこの木を伐採しようと、こういうふうに決めていってると思うんですけど、いつするか、なぜするかという周知について、先ほどもちょっと出されていましたけれど、どのように実施しているか教えてください。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
安全対策事業の実施に当たりましては、事業の趣旨や目的については市ホームページで公表するとともに、これまで各区の地域活動協議会や町会、公園愛護会などに対し事業予定箇所などについて説明させていただいております。また、撤去予定樹木1本ごとに貼り紙を掲示し、撤去の理由や撤去時期並びに復旧方法について周知させていただくとともに、貼り紙に示しておりますQRコードを通じて安全対策事業の趣旨や目的などを御確認いただけるようにしております。
さらに、樹木を撤去・更新することに対して、より広く市民の皆様に周知を行うため、今年の2月から市のホームページで予定箇所を示した地図を御覧いただけるようにいたしました。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 ありがとうございます。
一本一本に理由と期日を書いたお知らせを貼ってるというんですけど、ちょっと資料の2枚目のほうを見ていただきたいんですけど、これ陳情者の方が出されているビラなんですが、上から2つ目の問題②のところの写真がその貼り紙なんですけれど、このお知らせが実際貼られて、市民の皆さんにどんな印象を与えているかということをもう少し考えていただきたいと思うんです。これ、本当にいわゆる白羽の矢が立つというやつですよ。次のいけにえはおまえだという印象です。もうこれを見ただけで心臓がきゅっとなる、そういう思いをさせている紙になっているんだということを知っていただきたいんですよ。
今おっしゃった陳情の方のビラの2のところの括弧書きにもありましたけれど、ホームページにアップしていただいているというほうを資料3につけておきました。これ、さっき城北公園があったので、その周辺の旭区の地図になってるんですけど、これがホームページで見られて、この公園には伐採される木がありますよということが分かるようになったんです。だから、おまえだ、白羽の矢だというのもそれはそれでやり方かもしれませんけれども、こういった自分の家の近くの公園どうかなといったときに、ここで城北公園、クリックしたらここに飛べるというふうにしてもらえないかなというふうに思うんですよね。この木が伐採対象になっていますよといったら見に行って、何でやと、結構元気やんかといったら市に問い合わせて、この木、元気そうやけど何でなのということが市民の皆さんが聞けるようにしていただけないかなというふうに、切らないでほしい、守ってほしいという市民の願いに少しでも寄り添って、いや本当にこれ、外側は元気そうに見えるけど中は腐ってるんですよと、樹木医さんがもうあかんと言ってましたということだったら、そういう説明がちゃんとなされるように、市民の皆さんの思いに応えていただきたいというふうに思います。
その上で、これまで安全対策事業ということで切る話ばかりしてましたので、切る話だけじゃなくて植え替えもしておられるということですので、伐採・撤去を進めてきた上で植え替えしてきた分というのがどういう実績なのか、今、実績が分かる令和2年までの9,000本の分でも構いませんので、植え替えはどのくらいだったかというのを教えていただきたいと思います。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
樹木を撤去しました後は、都市の貴重な緑を確保するため、成長の緩やかな樹種や低木に変更してできる限り植え替えをすることとしております。
また、街路樹においては、平成30年度から令和2年度までの3年間に先行して実施いたしました安全対策事業におきましては、対象としました約9,000本のうち約2,000本は高木への植え替えを行い、残りの約7,000本は、視距阻害など安全に支障がないように約8万5,000株の低木に植え替えました。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 ありがとうございます。
ちょっと本数で言われたので増えてるかなと思うけど、低木に変わったりとかしていて、質疑調整をしてるときは約6割とおっしゃってたと思うので、高木に植え替えたのは約2,000本で、低木には約8万5,000株ほどやったよという、そういうことですよね。面積的には6割とおっしゃってませんでしたか。そういった形です。
高い木を植えて、取ってしまって植え替えていくということが乱暴なんだということはちょっと後で述べさせてもらいたいと思っていたので、植え替えについてです。
高木を約9,000本切り倒して約2,000本を植えるということなんですけれど、公園緑化部緑化課の皆さんに、危機管理室じゃないのでやっぱり木を大事にしてもらいたい、緑を増やしてもらいたいということ、緑化に力を入れてほしいということは本当にお願いしたいと今日思ってたんですよ。だから、本当に一つには切り倒さないということが一番なんだというふうに思うんですけど、緑化を安全対策で切るほうの話が先に出るんじゃなくて、やっぱり増やしていくよという、そういうことをしていっていただきたいというのが要望なんですね。
もう一枚資料をつけてあるんですけれど、こちらは此花区の伝法公園の先ほどの--これ公園事務所によってすごい様式が違って、本当に見比べるのが大変なんですけど--さっきと同じものなんですけど、伝法公園では11本、「あ」から「さ」まで伐採対象になってるんですけど、特記事項のところを皆さん見てください。これ、樹木が歩道に毎年越境して強剪定、強い剪定をしてきたから、樹木が傷んで樹形が維持できないので撤去するということなんです。
これがまたもう一つ陳情の皆さん、市民の皆さんから出されているもので、大阪市は本当に樹木を剪定する、枝を払うときにもう少し大事にしてほしいということが言われているわけです。陳情にもさっきのビラにも指摘がされておりましたけれども、この剪定作業についてちょっと話を移していきたいんですけど、日常の維持管理の中で強剪定というのが行われているというのは本当に心が痛いんですけれど、どのような考えに基づいて剪定作業をしているのか、教えていただきたいというふうに思います。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
街路樹や公園樹の維持管理におきまして樹木の剪定は、樹木の骨格を形づくり健全な成長を促す上で重要な作業となります。特に街路樹におきましては、安全な道路交通に支障を来さないよう、道路構造令に基づく歩道や車道における建築限界の確保、また電力線や建築物などとの離隔を取って道路交通の安全を確保するためにも、さらに信号や標識が隠れないようにするためにも樹木の剪定が必要となっております。
公園樹においては隣接する民家などに越境することのないように、また、公園出入口付近においては出会い頭の事故を防ぐために視認性を確保する目的で、樹木の剪定が必要となっております。
これらの剪定は、限られた予算の中、安全の確保に十分配慮しながら、植樹された環境や樹木の樹種などに応じて剪定を行っております。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 ありがとうございます。
いろいろと配慮する点はあるんでしょうけれども、予算の話が出ました。予算の範囲でということなんでしょうけれども、丁寧な剪定をするには一定の費用もかかってくるというのは当たり前のことかなというふうに思います。でも、市民の財産である樹木の維持こそが本当に緑化課さんの仕事かなと、予算を使うべきところかなと。切るほうは切ってしまえばそれで終わりですけれど、守っていくことに力をつけていきたいというふうに思うわけですね。伐採のための伐採というのはやめて、丁寧な維持で樹木を守るほうに予算の切替えをしていかなきゃいけないんじゃないのかなと思います。
この予算について陳情でも出されておりますよね。伐採したり撤去したりする費用の内訳を教えてほしいと言われたけれども、それが出てこないという中で、どういった対応をしていただけるのか、そういった内訳を示してもらえるのかということを教えていただきたいと思います。
◎澤建設局公園緑化部緑化課長 お答えいたします。
事業の実施に当たりまして、安全対策事業の趣旨や目的など、これまでも市民の皆様に広く知っていただく必要がある情報につきましては、市のホームページにおきまして適宜発信させていただいており、また、この2月からは発信する情報も充実させております。
一方で、今回の陳情で言われております維持管理費用の内訳につきましては、完了した全ての街路樹維持工事と公園樹維持工事の設計書の明細から集計する必要があるため、公開につきましては情報公開制度に基づき対応させていただきます。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 情報公開するから自分で計算せえということなのかもしれないんですけど、これだけ伐採されたり撤去されたり枝も強剪定されたりという中で、どれだけのお金を使ってちゃんとやってくれてるのかというのが市民の関心の高いところであれば、それは市民に公開するべき情報のほうにカウントしてもいいんじゃないのかなというふうに思います。
大変だからやらないということは責任逃れというふうになりますので、きちんと情報を整理して公開するのが、聞かれたら公開ということでも、一個一個足すのもそっちでやってねという公開の仕方ではないんじゃないかなということも要望させていただきたいと思うんです。市民の皆さんが知りたい情報が市民の皆さんにとって必要な情報、今、毎日新聞でも予算のことがどうなのかということが言われていて、それは違うかもしれないし、大阪市がちゃんと数字を出していればそのことでみんながしゃべれるということになりますので、きちんと情報提示をしてほしいというふうに思います。
そして、公園緑化部緑化課ということで、緑化をしてほしいんだということを申し上げてまいりましたけれど、大阪に緑を増やそうよということなんですよ、つまりはね。伐採の本数は具体的に数値ががんがんと出ておりますけれど、緑を増やしていくという先のポジティブなほうの具体的な目標というのは設定されているのかなというふうに思います。設定されてたら教えてほしいし、新・緑の基本計画というのがあります。陳情の中でも聞かれています。緑化の指標として緑被率とか緑視率とか書いてありますけれど、そういったものがどんなものなのかということも含めて教えてください。
◎木下建設局公園緑化部調整課長 お答えいたします。
緑視率は、目に見える範囲に占める緑の割合を表すもので、市民の方が実感できる緑の量を表す指標でございます。
新・大阪市緑の基本計画では、うめきたや大阪駅前、淀屋橋や御堂筋といった大阪の顔となる場所など8か所において、実感できる緑の現状について分かりやすく情報発信し、市民の皆さんと共有する指標として緑視率を設定し、3年ごとに計測し公開するとしたものでございます。
また、緑被率は市内における緑で覆われている面積の割合を表す指標となっております。本計画では、樹木・樹林や芝生地、屋上の緑など多様な緑全体で市内をどの程度覆われているかを示す指標として緑被率を設定し、計画期間終了時に計測し公開することとしたものでございます。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 指摘されている、緑被率というものをもうちょっと、2012年、この制定以来計測していないということを指摘されているというふうに思うんですけれど、見解表明のところで樹木撤去についてはほぼ影響しないんだということがあったかなというふうに思うんですけれど、街路樹・公園樹を1万9,000本も伐採してしまって本当にほぼ影響しないのかなということが分からないから、ちゃんと測ってほしいということだと思うんですね。
横浜市でも名古屋市でも5年ごとに緑被率というのは出されています。ホームページでぱっと見られるんですよ。そして、木が生えている樹林地、あと草原とか芝の草地、農地など内訳がちゃんと出されていて、緑が増えてないということを受け止めようということで、ちゃんと減ってるけど情報公開しています。その上でどうしようか、緑を増やしていかなきゃいけないということをやっぱり市民の目線でもやっていこうということをされているわけですよ。
緑視率については、駅を上がったところで緑、たくさんあるなという、これはいろんなところのホームページとかも見ましたけれど、緑が少ないけど多く見せようということなんですよ。駅は緑が少ないけど、緑が多いと感じてる人が多いのはなぜかというところから生まれた緑視率ですよね。だから、梅田の駅前を上がって緑が多いなと思っても、家の近くでがんがん木を切られてたら緑視率って上がってないというふうに市民は思うんだということもちゃんと受け止めていただきたいと思うわけです。
だから、木を切る計画のほうは本数もばっちり決めてがんがん進めている大阪市ですけれど、増やしていくほうの計画ですね。今、緑被率、緑視率の指標はありましたけど、増やしていくほうの計画というのをどのぐらい具体的な数値を持って進めておられるのか、緑の創出ですね。どう考えているのか教えてください。
◎木下建設局公園緑化部調整課長 お答えいたします。
高密な都市化が進み既に市域全域が市街化されている本市においては、緑やオープンスペースの量を大きく増やしていくことが難しい状況で、都市における緑の確保には、市民、事業者、行政など多様な主体により、地表面だけでなく屋上や壁面も含めた多様な緑の保全と創出が重要となってまいります。
中でも緑の保全につきましては、安全・安心・快適な市民生活を確保するため都市の緑を適正に維持管理することが重要となっており、公園樹・街路樹の安全対策事業を実施しております。
みどりの魅力あふれる大都市・大阪を基本理念に掲げる新・大阪市緑の基本計画の考え方を継承しつつ、今後のみどりのまちづくりについては検討を始めているところでございます。以上でございます。
◆長岡ゆりこ委員 今後だということなんですよね。計画がもうちょっとしたら更新されるからということなのかもしれないんですけど、今おっしゃったように、都市部だから緑を増やすのって難しいんですよ。それはほかの政令指定都市だって、減っていってるという現実を受け止めてどうにかしようと思っているわけですよね。だから、増やすのが難しいんだから、切らなくていい木は切らないほうがやっぱりいいということを考え直していただきたいなということにつながるわけですよ。
樹木というのは人間よりずっと長生きですよね。鶴見区の阿遅速雄神社というところにある天然記念物の大クスノキは樹齢1,000年だそうですよ。東成区の八王子神社御旅所のクスノキは1,300年だそうですよ。つまり、今植えた木が急には育たないということですよね。それはもう皆さん御承知のとおりです。だからこそ、寿命の短い人間が勝手にがんがん切っていいものじゃないんじゃないでしょうか。長期的視野で樹木を守って命をつなげていくことが本当に必要なときだというふうに思います。
本当に危険なのか、本当に守れないのか、切らなくて済む方法はないのかということを立ち止まって考えていただきたいというふうに思います。本日指摘させていただいただけでも、切らずに守るという選択肢ができそうな木、たくさんあったんじゃないかなというふうに思うんです。住民の皆さんの近くの並木や樹木に対する愛着、先ほどの靱公園のところでも出ていた愛着ですよ。丁寧に寄り添う公園緑化部であってほしいなと思っています。
やっぱりいろんなところが緑を増やすこと、頑張っています。東京都建設局では街路樹診断等マニュアルというのがあって、そこに住民合意形成のことが載っています。これ、すごく参考になると思います。ステークホルダーというそうですよ。
横浜市は、街路樹による良好な景観の創出・育成事業といって、いきいき街路樹事業という通称にしてますけど、美しい樹形にするという、そういうことを取組にして、それをまちの売りにしようということもされています。ホームページで見られます。是非参考にしていただいて、がんがん木を切るのはちょっと一旦立ち止まって、切る木を選ぶ。これ切るか、これ切るかという視点じゃなくて、この木をどうやったら守れるか、そういう視点に立って市民の財産である樹木を守っていただくように強く要望いたしまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
(注)長岡氏配付資料




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
