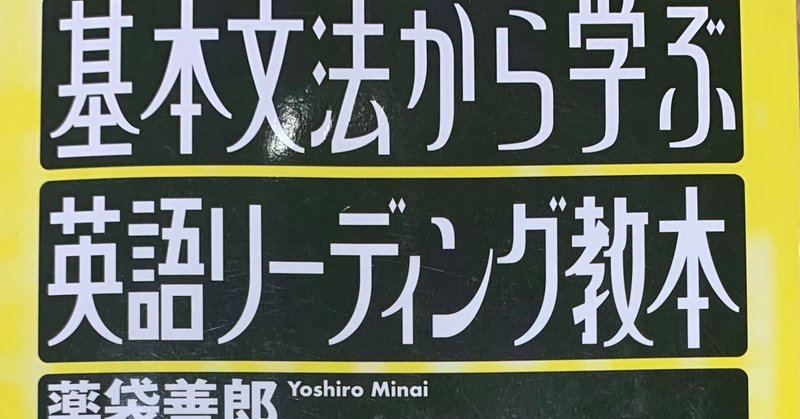
『黄リー教』をやったからこそ分かる多読の効用と、黄リー教で学習する意義
先日も書かせていただいたとおり、今『基本文法から学ぶ英語リーディング』通称「黄リー教」を使って英語を学習しています。
この記事の中で、僕は「黄リー教」がいかに英語学習に、とりわけ英語リーディングにおいて効果的か、ということを少々あつく述べました。
僕は黄リー教を始めるまではずっと「多読」こそが英語力を引き上げる最善の方法だと思っていました。もちろん今も、多読が僕の中で重要な学習法であることには変わりがありません。41歳で取り立ててスキルも特技もなかったこの僕がほぼ多読のみで英検一級に合格し、英語コーチとして、新しい第二の人生を歩み始めることができたんですから。
それくらい、多読というのは効率的かつ素晴らしい英語習得法で、僕にとってかけがえのない学習法の一つである、ということなんです。
でも、多読が僕にとって優れた学習法だったからこそ「黄リー教」の意義と、本書を使って学ぶことの価値にも気づくことが出来たんだ、と思っています。
「黄リー教」は「英文を読めるようにしてくれるもの」で「文法知識の拡大」のためのものではない。
僕たちは、英語を考える時に「英文法」に拘泥しがちです。つまり「英文法がわかれば、英語はわかるようになる」と考えがちだということです。
もちろん、英文法がわかれば、英語はわかるようになります。でも、正確に言うと「英文法を知っていて、かつその文法を運用できるようになれば英語が分かるようになる」なんです。ここを勘違いされている人が結構いらっしゃるように思います。
僕たちは、悲しいかな英文法の「知識」と、その知識を使ってパズルのような英語のテスト問題を解くことを学校教育を通じて訓練されてきたせいで、つまり「英文法を知っていれば高得点が取れるテストという仕組み」にどっぷりと浸かっていたせいで、文法ができることを=英語ができることと勘違いしてしまう傾向があるんです。
英語は、英文法の知識を実際に使って英語を読んだり聞いたりすることによって初めて「できるようになる」のであって、文法を知っているだけでは「文法クイズで高得点を取れる日本語話者」にとどまったままです。
「黄リー教」は「文法知識としての英語」と「実用レベルの英文法」の両者を架橋してくれるものです。そこに気づくためにはある程度の英語経験が必要だろうと思います。逆に、文法クイズを問いたり、TOEICや英検に合格することが英語力の全てだと考えている方には、このことをご理解いただくのは難しいかも知れない、とも思います。
「黄リー教」は「英文法知識を量的に拡大してくれるものではなく」「文法的な了解事項を使って英語を読めるようにしてくれるもの」です。
でも、多く日本人英語学習者にとって、英語力は残念ながら「テストで高い点数が取れること」を意味しています。ここの認識のずれが「黄リー教」への正当な評価に対する障壁となっています。
だからもし、あなたが「とりあえず文法をなんとかしたい!」とか「TOEICで高得点を取りたい」人なのなら、手に取るのは黄リー教ではありません。別の文法書なり参考書を手に取るべきでしょう。
テニスがやりたいんだったらテニスのラケットを購入しなければいけません。「かっこいいから」「軽そうだから」と言ってバドミントンのラケットを購入してテニスの練習や試合に臨むのは個人の勝手ですが、「なんだこんなものでテニスボールが打ち返せるか!」とラケットメーカーに食って掛かるのは、お門違いというものです(そもそもルール違反かも知れないし)。
あ、でももしあなたがTOEIC800点代後半とかの人で、900点オーバーという一大アチーブメントを前に足踏みを余儀なくされている人だったり、満点を目指してリーディングパート対策に精進している人(僕です)だとしたら、黄リー教はひょっとすると、とんでもない福音になるかも知れません。
英語が読めるようになってどうなるというのか?という意見に対して
多読をしていたときからずっと聞こえてきていた「アンチ多読」の声の代表的なものが「英語が読めるようになったからと言って、どうやって英語ができるようになるというのか?」というものでした。
この意見には一応一理あるとは思っています。なにせ世界には文字を読むことができない人が山程いらっしゃるからです。そういう人でも英語は喋れる。なら、読めたからといって英語ができるようになるとは言えないんじゃないか、と。
そういう例はさておき(←いっぱい「英語を聞いているから」に決まっています)フィリピン・セブ島に移住した2017年12月以降、語学学校のスタッフとしてそれなりの数の英語学習者の方を拝見してきて思うのは「英語が読める人は、英語を話したり聞けたりするようになるのが早い」という事実です。
これにはほとんど全くと言っていいほど例外がありません。
もちろん、読めるだけで話せない、という人は山ほどいます。でも、読める人というのは「話す訓練をしていない」「話すことに慣れていない」だけで、英語の背後にある法則、英語を律しているルールというものはある程度理解しておられる場合が多いです。当然ですよね、読めるんだから。
だからボキャブラリーを増やし、セブに来てある程度まとまった期間集中して英語を話す訓練をすれば、あれよあれよという間に英語が話せるようになっていきます。「英語が読める=英語が分かっているから」です。
でも、英語が読めない・英語の正しい読み方を知らない人は、英語が読める人のはるか後方からレースをスタートすることを余儀なくされます。結果、1ヶ月なり3ヶ月後に現れてくる留学の成果には明確な差が生じます。この差ははっきり言って残酷なくらい絶望的です。
「読めない人」が3ヶ月後もなお「I is like feeling good today!(「今日はとっても気分がいいです」の意)」だとか「You are like baseball?(「あなたは野球が好きなのですか?」の意)」とか言っている一方で、英語がもともと「読める人」というのは、軽やかに先生との会話を楽しみ、セブ島での生活をエンジョイし、なんなら現地で友達まで作って日本に帰っていかれます。
読める人というのは正確な英文法知識を駆使して英語を理解できる人で、つまり先の話のようにその知識を自分がアウトプットする英語にきちんと応用できる可能性が既に高い人なのですから、話せるようになるのは時間の問題です。
そして繰り返しになりますが、黄リー教は「英語が読めるようになる」ためのものです。文法知識は文法書で学習すればいいですが、そこで得た知識を英語の「ちゃんとした読み方」に転換していく手段の一つとして黄リー教は大変示唆に富んだ、興味深い視点を提供してくれている学習参考書なんですね。
文法や読解法を知らなくても、英語はできるようになる
ただ、だからといって黄リー教をやらないと英語が読めるようにならない、英語ができるようにならないというつもりもありません。
その辺りのお話は昨日の繰り返しになるのでここでは深堀りしませんが、英語に大量に触れることで、英語の背後にある法則に「なんとなく」気づくことができるようにはなります。
多読・多聴と言った経験を沢山積み重ねるタイプの英語学習法が目指すのはそこです。人間というのは、一見ランダムに生起しているかのように見える現象の背後に知らず識らずのうちに法則とかルールを見出していくことができる生き物なんです。
そうして知らず識らずのうちに「知覚系の動詞は目的語の後ろに補語を取る傾向がある」ということに気づいていく。なんとなく、ある種の動詞の目的語の後ろには補語がないと気持ち悪く感じる様になる。
あるいは、あるべき場所に目的語としての名詞がないのが気持ち悪いとか、一つの文章の中に現在形の動作は二つ現れるはずがないとか、英語を律する様々な法則を、意識的無意識的に感じ取って、少しずつ正確に読めるようになっていくんです。
というようなことを、たかだか英語学学士に過ぎないこの僕が自信を持って主張できるのは、間違いなく「黄リー教」が、僕が英語を読む時の脳内プロセスを余すところなく一言一句言語化してくれているからに他なりません。
黄リー教を読むまではずっと、自分がどうして多読でこんなに英語を読めるようになったのかが不思議で仕方ありませんでした。でも黄リー教を一周終えた今ははっきりということができるんです。僕は知らず識らずのうちに、英語の背後にある「品詞・働き・活用」の相関関係の中に、薄っすらとした法則性を見つけ出していたからなんだ、と。文法的知識の拡大によって英語ができるようになったんじゃないんです。
大切なことなのでもう一度いいますが、僕が無意識に気づいていたのは「文法」と言うよりはむしろ「英語の品詞・働き・活用の相関関係」だったんです(それを文法という、という意見は大筋では認めます)。
「副詞が形容詞を修飾するときは前から」という基礎的な文法知識は「この語がこの語の前に来るのは、なんか違う」という形でおぼろげに知覚されていきますし、「この動詞がここに来ているからには、このあとに本物の動詞が来るはず」ということが分かっている人にとっては、関係代名詞の理解なんて造作も無いことです。
そうやって「英語が読める様になっていく」のが「多読」の効用です。じゃあ黄リー教は必要ないんじゃ?という議論にまた戻って行きそうですが、ここらへんでもう一つのエピソードをご紹介しておきます。
先に「ルール」がわかっておいたほうが英語が頭に入ってきやすい人が一定数いる
僕がセブ島で英語学校のお仕事に携わっていた頃、定期的に一緒にカフェに行って英語を教えさせていただいていた方がいました。コロナで帰国を余儀なくされた方ですが、とても優秀な方で、現地で「アクセンチュア」という、世界的に有名な企業の採用試験に合格され、就職することが決まっていたんです。
元々理系の方だったようで優秀な方には違いなかったんですが、何故か英語はからっきしだめだった、と言います。そんなご自身を変えたかったのか、はたまたそのあふれる可能性に一度きりの人生をかけてみかったのか定かではありませんでしたが、とにかくそれまでの安定したお仕事を捨てて、その方はフィリピンに来られたのでした。そりゃあ応援したくなるというものです。
この方がはっきりと仰っていたのが「自分は先にルールとか法則とかから学ぶほうが頭に入ってきやすい」ということで、だから英文法を一生懸命勉強されていたんです。僕もその頃には英文法のそれなりのことは理解して説明できるようになっていましたから、よくカフェで、コーヒーおごって貰う代わりに文法をレクチャーさせていただきました。
スマートな方だったので、英文法を習得されるのはあまり造作ないことでしたし、実際に教えさせてもらっていても、知識の習得がとてもスムーズなので教え甲斐がありました。
が、残念なことに、なかなか話せるようにはならなかったんですね。英語環境にいて、文法はこんなにできるのに、どうしてだろう?語彙力かも知れない(事実、そんなにボキャブラリーが豊かだとは思いませんでした)、あるいは単に話すという経験がたらないだけなのかも知れない。でも、どれもいまいち説得力に欠ける仮説でした。
でも今ならはっきりと言うことができます。僕が彼女に勧めるべきは、英語の背後にあるルールを徹底的に解説してくれる「黄リー教」だったんです。
おそらく、この本のような本質的な英文読解法を好む方というのは結構な割合でいらっしゃると思います。それはコーチングをしていても思います。今僕のクライエントさんは渋谷にある、飛ぶ鳥を落とす勢いのIT企業さんですが、特にエンジニア系の人は「ルールがきちんとしている」ことを非常に好まれます。国際企業なので、開発系の方は普段から英語を使って外国人のエンジニアの方とお仕事をされているのですが、英語は文法知識を駆使しつつも「なんとなく」感を抱えながら喋っていると言います。
もっとちゃんとしたルールを知りたい。技術系の皆さんは割とそうおっしゃいます。まだ実際におすすめしたことはないけれど、この本が向いている人は実は結構いるかも知れない、ということです。
僕は幸い「多読」で、黄リー教が示してくれている英語のバックグラウンド法則に気づくことができましたが、そうでない人にも、「黄リー教」という手段があるんだ、ということはもっと大々的に言ってみてもいいと思っています。
この記事が気に入っていただけましたら、サポートしていただけると嬉しいです😆今後の励みになります!よろしくお願いします!
