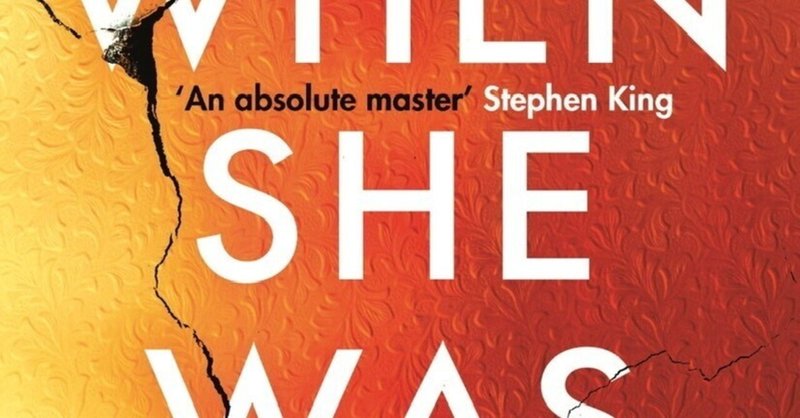
【洋書多読】When She was Good(163冊目)
『When She was Good』(Michael Robotham著)を読了しました。
本書は心理系のサイコサスペンスで、大変評価の高い同著者の『Good Girl Bad Girl』の続編にあたります。
概要
統合失調症の兄を持つ犯罪心理心理カウンセラーであるCyrus Havenと、猟奇的な殺人現場で発見されたEvieという少女との出会いが前作のお話の中心でしたが、今回は、ある事件をきっかけに徐々に明らかになっていくEvieの幼少時代、暗い過去が中心です。
物語は前作同様CyrusとEvieの語りのChapterが交互に登場する形で進んでいきます。最初のうちは、二つのバラバラなお話が並行して進んできますし、登場人物も多いので読みにくいかもしれません。
しかしながら、徐々にその二人の物語が接近し始めます。そしてその辺りからストーリー展開が一気に加速していって最後までハラハラの連続という感じ。
ボリューム的にはちょっと多く感じますが、とにかくこの著者の本は話の展開が面白いので、一気にハマって読めてしまいます。おすすめです。
YL:6.5 総語数:約80,000語
前作(YL:6.0)と同様、基本的に英文はそんなに難解な言い回しはありません。とても素直な英語で読みやすいと思います。特に情景描写などは、英検とかIELTSのような、あまり修辞的でないシンプルな英文が淡々と続いていきます。
なので、英語のそのものは難しくありません。でも、やはり大人が読むペーパーバックなので、英単語はそれなりに難解です。具体的には英検1級レベル、TOEICも900点台をコンスタントに超えてくるレベルの語彙力がないと難しいと思います。
前作よりもより、単語が難しいと感じたので、少し高めのYL:6.5としました。
文字数はおよそ80,000語で、これは標準的なペーパーバックの長さだと思います。ちなみに文字数のソースは、タイトルを入れる文字数をカウントしてくれる以下のサイトです。
余談ですが
本書には、主人公であるCyrusが精神科病院に入院する兄を尋ねるシーンが登場します。
Cyrusのお兄さんはいわゆる「重大な犯罪行為を犯した心神喪失者」で、一般の精神科とは違う、日本でいうところの「司法精神病棟」に入院しています。
僕は41歳で仕事を辞めて海外に出るまで日本の精神科病院で「ソーシャルワーカー」として患者様の社会復帰の相談に応じる国家資格専門職として勤務していたのですが、本書では日本とイギリスの精神科病院、とりわけ司法精神科病院の違いを垣間見ることができて興味深かったです。
それからこれも余談なんですが、僕がこれまで読んだ洋書に登場する「ソーシャルワーカー」ってだいたい悪者というか、あまりいい描かれ方をしていません。堅物で、融通がきかなくて官僚的、みたいな。大体そんな感じ。
で、そんなソーシャルワーカーに対比して、人間的で、暖かい、親身になって患者さんのカウンセリングに当たる臨床心理士、みたいな。いわば引き立て役っぽい感じなんですね。
ま、日本の小説読んでたら、そもそも「ソーシャルワーカー」自体がでてこないので、まだ取り扱われているだけでもマシなのかもだけど、ちょっと不満と言えば不満です。
気になった表現集
1.out of one's league
「〜にとっては高嶺の花である」とか、自分にとっては不釣り合いなくらいレベルが高い何かを表す表現です。異性だけでなく、仕事のタスクとか学業とか、とにかく自分にはレベルが高すぎて手が出ない、と言いたい時に使える表現です。
2.People tend to talk at me, rather than to me.
talk at meは「一方的に話す」の意味ですので、上の文章は「私に話しかけると言うよりは、一方的に話しがちだ」となります。
3.have one's face on
上に〜の顔を持つ=『化粧をする』のようです。そのすぐ後ろに「You don't need make-up for me」(私のために化粧する必要はないよ) という文章が続いているので、そう推測しました。
4.set A up with B
AにBを(紹介目的で)合わせる、引き合わせる、などの意味があるようです。Cyrusの親友が彼をディナーに招待する時に、このセリフを言います。
5.Leave off
「止めなさい」「いい加減にしなさい」です。
6.take it upon oneself
〜する役割を自ら引き受ける。take on が「(きつい仕事などを)引き受ける」という英検一級頻出熟語です。
7.don't have a pot to piss in
「小便をするためのポット(便器?)もない」という直訳ですが「極端に貧乏である」ことを表すイディオムだそうです。
8.hung up on
「〜にこだわっている、夢中になっている」「〜に恋煩いをしている」です。
9.a born 名詞
You are a born diplomat. という文章で出てきました。bornを形容詞として使っているのが珍しいと思いました。意味は「生まれながらの(名詞)」で、ここでは「あなたは生まれつきの外交官だ」という意味です。
10.stands to reason
It stands to reason.の主語が省略された形でよく用いられ「道理にかなっている」「理屈にあっている」という意味です。
11.Not that I'm aware of
「私の知っている限りでは」。TOEIC頻出のフレーズですね。
12.reception
「携帯の電波」の意味でよく使われていました。結構普通に言うのかな?シグナルとかじゃないのか?"The moment you get reception, please call me"みたいな感じです。
この記事が気に入っていただけましたら、サポートしていただけると嬉しいです😆今後の励みになります!よろしくお願いします!
