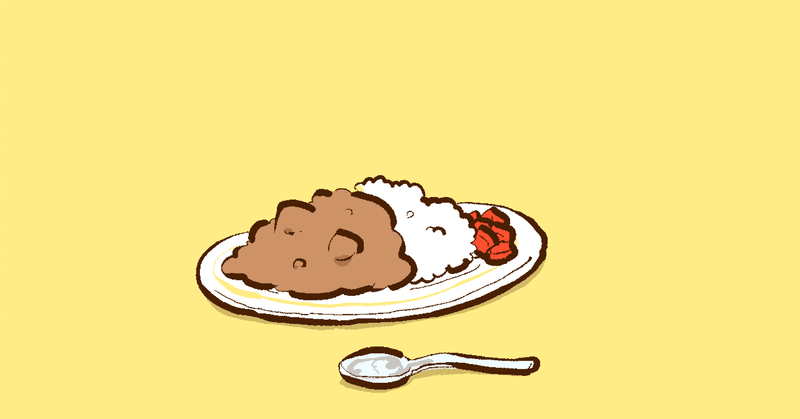
カレーは味噌汁である
ある日、カレーを作っていて、ふと疑問に思った。なぜ、(少なくとも当時の)大方の市販のカレールーのレシピには、具材を炒めて少し煮込んだ後、いったん火を止めてから、ルーを割り入れると、書いてあるのか。いったん火を止めることに何か意味があるのか。いったん火を止めてから割り入れないと、ルーが溶けなかったりでもするのか。試しに、いったん火を止めずに、単に弱火にして(強火のままでは焦げ付いてしまうから)ルーを割り入れてみても、いったん火を止めた時と同様、ルーは溶けていくし、味も特段変わらない。
ではなぜ、レシピにはわざわざ「いったん」火を止めてからルーを割り入れると書いてあるのか。
ある日、味噌汁を作ろうと、味噌を容器から取り、味噌漉しにいれ、鍋がかかった火を止めた瞬間、はたと気づいた。これは、カレールーの溶かし方と同じではないか! というより、カレールーの溶かし方が、味噌の溶き方と同じ、つまり前者が後者を真似しているのではないか、と気付いたのだ。
日本で固形ルーを最初に発明した製造業者には、諸説がある(たぶんどのメーカーも、この世紀の大発明を自社の手柄にしたいのだろう)。はたして発明当初のレシピが、現在同様「いったん」火を止めるレシピだったかどうかはわからない。
しかし、おそらくは日本の家庭にカレーライス(ないしライスカレー)を普及させるのに、それまでの調理法――西洋料理のソースづくりのレシピをベースにした調理法――が当時の主婦(おそらく「主夫」は少なかったろう)には複雑で面倒であったので、それを簡略化し、手軽に家庭でも作ってもらうために、作り慣れた味噌汁の作り方を模倣して作ることができるよう、「いったん」火を止めてから(味噌同様に)カレールーを入れ、溶かし、汁に馴染ませるようにしたのではなかったか。その「名残り」が今現在のレシピにもそのまま受け継がれているのではないか。だから、「カレーは味噌汁である」と言いうるのではないか。
しかし、味噌汁のレシピと違う点もある。もちろん、(味噌汁同様)ルーを溶かしてすぐ食べても食べられないことはないだろうが、おそらくこなれた味にはなっていないだろう。普通レシピには、20〜30分くらい煮込む、と書いてある。せっかく「いったん」火を落としてルーを入れたのに、(味噌汁と違って)また火を点け直し、煮込んでいくのだ!
私は人生で、(もちろんルーを使わずにゼロからスパイスを炒めて作ったことも何回もあったが)、市販のルーを使ったカレーも何百、何千回と作ってきたことだろう。
私は、カレーに限らず、料理の基本をフランス留学中に習得した。1980年代当時まだインターネットなど普及していなかったので、和食や日本の家庭料理のレシピは、母に日本から料理本を送ってもらい、それを参照していた。
日本のカレールーは、パリの日本食料品店に行けば(日本の3〜4倍の価格がしたが)手に入った。私は、その「貴重な」ルーを使い、日本風カレーライスを何度か作ってみた。しかし、どうも箱に書いてあるレシピ通りに作っても、大概肉がパサつき硬くて美味しくできない。そこでレシピに書いてある以上の時間、煮込んでみる。(肉の種類にもよるが)1時間煮込んでもパサパサ、1時間半でもパサパサ、ようやく2時間の峠を超えると、急に柔らかくなり始め、しっとりとその肉独特の旨味が出てくる。牛肉などは(部位にもよるが)2時間半くらいがベストのようだ。(それ以上煮込むと逆に柔らかくなりすぎて解体してしまう)。
もちろん、その間、たえず弱火で煮込み続けるため、5〜10分おきにヘラで底の方からかき混ぜねばならない。私はよく、食卓で論文を読んだりしながら、気長にかき混ぜていた。
ところが、次に新たな問題が起きた。レシピ通り、最初に肉と一緒に野菜類を炒めて2時間〜2時間半煮込むと、肉はいい感じに柔らかくなるのだが、野菜類がほとんど溶けて跡形もなくなってしまうのだ。特にジャガイモが全部溶けてしまうと、ルーに非常にとろみはつくのだが、変にざらついた舌触りになり、美味しくないのだ。
そこで、レシピ通りに最初から肉と一緒に炒めることなく、仕上がりから逆算して、その野菜が一番美味しく煮込まれそうな時間を推し測って時間差とともに投入していくと、それぞれの具材がベストな状態で煮込まれて、仕上がっていく。そうして、フランスで、市販のルーを使いながらも、それなりに自分でも満足し、客人たちも堪能できるようなカレーライスを作っていた。
ところが、である。日本に帰ってきて(ちなみにフランス留学以前、私はカレーライスすら作ったことがなかった)、「同じ」食材を使ってフランス同様の順番と時間差で投入し、2時間〜2時間半かけて煮込むと、なぜかフランスでは煮崩れなかった肉、野菜が跡形もなく溶けてしまうのだ。う〜〜ん、なぜだろう…。
もちろん、カレーのみならず、他の煮込み料理も同様の結果だったので、至った結論は、「同じ」肉、「同じ」ジャガイモ、「同じ」にんじんに見えても、フランスと日本とでは、その繊維の質、細胞(膜)の頑丈さ、含まれた水分量などが違い、おそらく日本の肉や野菜の方が相対的・総体的に「弱い」ために、フランスの食材と同じ時間煮込んでしまうと、跡形もなく溶解してしまうのではないか、ということだった。
逆に、日本の食材は(煮込み料理の場合)、美味しさのピークがかなり早めにやってくる。牛肉は、1時間半程度、鶏肉だと40分〜1時間程度、ジャガイモだと20〜30分程度(メークインで)。それ以上煮込むと、どんどんと形が崩れ、やがてドロドロに溶けてしまう。
たかが、カレーのような、ある意味でシンプルな煮込み料理でも、食材の元々の質、育てられ方などが違うと、こうもレシピが変わってくる。まさに比較文学論ならぬ比較料理論。もちろん、フランス、日本以外の国、地域の食材を使えば、またレシピも変わっていくだろう。それがまた、「料理」の面白み、醍醐味でもある。「レシピ」通りに作れば必ずしもベストな結果が生まれるとはかぎらない。目の前にある食材の質如何、場合によってはそれを取り巻く気候・環境、自分そしてゲストたちの体調なども、瞬間的・直感的に「読み取り」ながら、その日その場でのベストなパフォーマンスを生み出していく。自然と人間との、即興的コ・クリエーション。だから、料理、たかが(?)カレーライスづくりでも、毎回毎回面白いのだ。
中央アジアの超絶美味たち
ユーラシア大陸横断の旅
13年前、パリに1年間滞在していた時、私は国内外、旅を重ねた。国外は、前述のように、オランダ、スイス、そしてベルギー、ドイツなど。滞在終了間際には、インドにも3週間ほど旅をした。
だが、最大かつ最も波乱に満ちた旅は、やはりパリから上海までの陸路での横断であろう。
私は、幼い時から、日本地図・世界地図を眺めるともなく眺めるのが好きだった。特に、地図を眺めながら「辺境」にはいったい何があるのだろう、どんな人たちがどんな生活をしているのだろうと、想像をめぐらすのが好きだった。日本地図では、樺太(当時はそういう表記だった)や対馬や知床半島。世界地図では、グリーンランドやカナダの北部、そして何よりもユーラシア大陸の真ん中あたり、都市や町もまばらで、鉄道網も途絶していたり、氷河や砂漠に覆われていたり…。少年の「ロマン」を否が応でも刺激する、それらは謎に包まれた「空白」地帯だった。
今回、パリに1年滞在する前から、私は漠然とユーラシア大陸を横断してみたい欲望に駆られていた。それが少年時代からの「夢」の一つであり、(すでに50歳を迎えんとしていたが)この機を逃すとおそらく一生機会は訪れないだろうという気がしていた。
そして、いよいよパリに暮らし始めてから、その「機」がどんどん熟していき、ついに断行する意を固め、必要な装備を買い求め、旅程を組み立て、各国の入国ビザを取りに奔走した。
ガイドブックを見比べながらいくつかコースを考えたが、身の安全を第一に、コースを綿密に計画立てた。まずパリからイスタンブールまで二泊三日夜行列車を乗り継ぎ、何週間かトルコ国内をめぐった後、グルジア(今は「ジョージア」と呼ばれる)、アゼルバイジャン、(カスピ海を船で渡り)カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、中国。そして上海から東京というルートを考えた。基本全て陸路(たまには水路)、すなわち鉄道かバスか(乗合)タクシーか徒歩。(結局、ちょうどトルコをめぐっていた時、ロシアがグルジアを侵攻したため、入国できなくなり、トルコからアゼルバイジャンまでは空路となった。)
2ヶ月余りをかけ、無事、どころか、波乱の連続だったが、なんとかパリから上海までユーラシア大陸を横断した。
旅の途上、実にさまざまな、予期せぬことだらけであったが、数ある収穫のうち最大の収穫の一つは、やはりユーラシア大陸の大きさを肌身で実感したことだろう。幼い頃から地図上で想像をめぐらすしかなかった、大「空白」地帯。そこにも、人々は暮らし、車は走り、携帯もつながり、しかし、予想だにしなかった発見、体験も数多くした。地図で何度となく見た世界最大の湖「カスピ海」でまさか自分が泳ごうとは、そこまでの旅の最中でさえ全く予期しなかった。
食の衝撃
食における発見、驚きも、予想をはるかに超える位相で数多くあった。それらを網羅していると、何十ページも必要としてしまうので、その中でも特に印象の残る、今でも強烈な衝撃とともに甦るいくつかの出来事だけ、ご紹介しよう。
カザフスタン最大の都市、アルマタイ。文字通り、ユーラシア大陸のど真ん中に位置する。そのせいか、大陸のはじからはじまで、北欧からはては日本までの、あらゆる「血」が何千年、いや何千万年と混じり合い、ありとあらゆる組み合わせ、混淆が、人々の容姿からだけでも伺える。モンゴル系のある人たちは「韓国人」や「中国人」以上に、日本の街角にいそうな「日本人」にそっくりだ。そうかと思うと、透明に近いブロンドの女性たちもいる。遺伝子的交配のおかげなのか、かなり美形の男女が多い。モンゴル系の顔立ちの人たちも、メリハリの利いた体形をしている。
食もまた、同様だ。私は、文房具などを買いに街に出た。そしてたまたまかなり大規模なスーパーに出会った。入ってみると、予想以上に(この旅で最も)「高級な」品揃えとディスプレイだ。さしずめ大型の「成城石井」といった風情である。
それにしても、食料品、特に酒類、惣菜などが「大陸」的に豊か、それこそ「ユーラシア」の食文化の展示場のようだった。ビール売り場は圧巻だ。ユーラシア大陸を横断するかのように、巨大な棚は、左からポルトガルに始まり、各国のさまざまなビールが東西の順に整然と並べられ、右端は「スーパードライ」で終わる。隣にはチョーヤの梅酒まである。惣菜も、日本の寿司、韓国の味付け海苔から饅頭(ここらでは「マントゥ」というらしい)を経由して、北欧風のニシンのマリネまである。私は、迷った挙句、北欧風ニシンのマリネ、ハンバーグのようなもの、韓国風春雨サラダのようなもの、とパンを買う。
スーパーを出て、しばらく歩くと、交差点でなぜか日本語で「高崎ハム」と書いたトラックが止まっている、というオチまでついた。
翌日は、中央バザールに行ってみる。ここもまた、「成城石井」とは別な意味で圧巻である。今まで世界中でいろんな市場を見てきたが、これは三本の指に入るだろう。たとえば、馬肉コーナーなら、馬肉売りが店頭に馬の部位をぶら下げ、その同じような陳列=店が何軒も続いている。買う人はどうやって選ぶのだろうかと思うほど。プレゼンテーションの仕方もどの店もほとんど同じ。肉、野菜、果物から始まって(魚は、やはりユーラシア大陸のど真ん中のせいかスモークか塩漬けしかなかった)、スパイス売り、朝鮮漬物店(だけでも30~40軒)。その青果市場を、雑貨市場が取り囲む。いろいろと買いたい欲望に駆られるが、買っても食べきれないのと、ホテルから遠いので、諦めざるをえなかった。
食材の驚異的な質
それにしても、中央アジアの食材は驚異的だ。フランスのそれも、当時の日本に比べれば、肉、野菜、果物ともに、はるかに風味が濃く「健康的」なものが多かったが、ここの肉、野菜、果物の味、「健康さ」は、フランスのそれをさらにはるかに凌ぐ。
宿泊したホテルの目の前に、小ぢんまりしたバザールがあったが、その前の路上では、生産者らしき人たちが素朴な風情で自分たちの作った野菜や果物を売っている。私は試しに、あるうら若き男性からイチゴを500グラム買ってみた。大小不揃いだが真っ赤なイチゴを紙袋に無造作に入れてくれる。ホテルは、通りを渡ってすぐなのだが、部屋に着くまでに袋の中身の下半分が自重で潰れて、果汁が滴っている…!それほどまでに完熟なのだ!その一つを口に入れた瞬間、今まで味わったことのない濃度と甘みに全身が打ち震えた。太陽のエネルギーと大地のミネラルがものの見事に凝縮された、まさに「奇跡のイチゴ」だった!(ニューヨークのデリやスーパーで売っている「イチゴ」など、もしアルマタイの人たちが口に入れたら即座に吐き出すだろう!)
あるいは、隣国ウズベキスタンの、世界遺産にもなっているサマルカンド。そのバザールやレストランでも、食材の濃厚さに見舞われたが、なかでも最も鮮烈な衝撃を被ったのが、宿泊したB&Bの朝食だった。ここらあたりの「パン」は、インド同様「ナン」というが、直径30センチくらいの円形で、かなりの厚みがあり、それがいたるところで売られている。B&Bの朝食でも、もちろん、それが出たが、インドのナンとちがい、ナポリのピザ生地のもちもち感をさらにもちもちにしたような粘り気に、これまた太陽のエネルギーと大地のミネラルをたっぷり吸い込んだ小麦の濃厚な味が口いっぱいに広がり、しかも爽やかにクミンまで香る。今まで世界中で食べた、小麦粉を発酵させて焼いたもののうちで、まさに「最高峰」である。これまた見事な甘味の手作りのイチゴジャムが添えられているが、それさえ全く必要のないほど、これ自身で「完結した」美味しさのナン=パンである。(これに匹敵する「完結さ」は、新潟は五泉市で祖父が作っていた新米くらいであろう。それもまた、おかずが全く必要のない、それ自体で「完璧な」食べ物だった。)それに、目玉焼き! こんな目玉焼き=卵も今まで食べたことがない。塩さえ全く必要のない、こちらも「完結した」、「自立した」味だ。「調理」する必要さえない、食材自体が完璧に「立っている」!
あるいは、ウズベキスタンの首都、タシケント。宿の近くに屋台が多く出ていたが、たまたま入った一軒で、注文したピラフ! 中央アジアでは、よく油で炒めた米、すなわちピラフ(タシケントでは「プロフ」というが)をよく食べるのだが、隣席の人が食べていたピラフの様子に興味を強く引かれ、(言葉が通じないので)指差しながら同じものをくれと店員さんに頼んだ。目の前に運ばれてきたものは、なんといっさい具のない素(す)のピラフ!それだけでも驚きだが(同様な驚きは、イタリアでやはり隣席の男性二人組が美味しそうに食べていたトッピングのない素のピザを見た時以来だ)、それを一口、口に入れた途端、先のナン同様の衝撃に襲われる。炒め加減といい、味加減といい(おそらく油と塩だけ)、ほぐれ具合といい、もちろん米自体の旨みといい、油で炒めた米ではこれ以上ありえないほどの、やはり「完璧な」フライドライスであった。
食の「アイデンティティ」とは?
加えて、また別な屋台で食べたいくつかの麺料理。それらはまさに、人種の混淆同様、ユーラシア大陸の端から端までの食(麺)文化が、何万年、何十万年と混淆した結果、とりあえず21世紀の今、ここタシケントでとっている姿形なのであろう。
これまたホテル近くの、屋台風の店。写真と値段が壁に貼ってあるので、注文もしやすい。これまで食べようと思っていたが、なかなか出会えなかった念願の麺料理「ラグマン」を頼む。予想より汁が少なく、ソースが多めのパスタという風情だが、麺は明らかに日本の「うどん」そのもの。「うどん」という麺のルーツはここにあるのか、と思うほど(実際そうかもしれない)「うどん」である。ソース=汁はしかし、トマト味! つまり「ラグマン」は、日本からイタリアまでの麺料理が、この皿一点に凝縮されたようで、眩暈すら覚える。いや、逆に、「ラグマン」こそ、「パスタ」や「うどん」のルーツなのかもしれない。古に、ここらあたりから、シルクロードを通って、ユーラシアの西の端でいつしか「パスタ」になり、東の端で「うどん」になっただけなのかもしれない。
翌日は、同じ店=屋台で、写真では焼きそば風に映っているものを注文する。出てきてびっくり、何と「つけ麺」そのものなのだ! スープは鶏だしが効いていて絶品。比して、麺は残念ながら少し延び気味で今一つ。でも、このスープに日本のちぢれ麺を入れたら、さぞ絶品の「ラーメン」になること、請け合いである。
これら絶品の料理を食しながら、ふと思う。いったい食の「アイデンティティ」とは何だろう? 例えば、「パスタ」や「ピザ」は今やイタリア料理の(国内外ともに)アイデンティティを構成する重要なアイテムだが、その由来はおそらくこのあたりだろうし(しかもイタリアに普及したのは中世以降のことだという)、今や少なくとも「外国人」から見て「日本料理」の代名詞の一つである「天ぷら」も、もちろんポルトガル由来だし。日本の「うどん」も、もしかすると、本当にこのラグマンがルーツなのかもしれないし…。
生の素材は、流通が発達していない時代にあってはほとんどが地産地消であったろうが、それを調理する調味料・香辛料や技術は外来でありうる。また、実は素材にしても、原産は外来であったりすることが多い。有名な例では、今やヨーロッパの食材の基本中の基本であるトマトやジャガイモでさえ、新大陸発見によりもたらされたものだという。
そうしてみると、食的「アイデンティティ」は須らく相対化され根拠がないように思えるが、かといって、ある国、ある地方に行った時、食の“特異性”を感じることも事実ではないか。その“特異性”は地産の素材に負うことが多いものの、それを調理する調味料、そして技術にも多くを負っているのではないか。地産素材の独特のクオリティとそれを調理する技術の妙が相俟って、その地の食の“特異性”を形成しているのではないか。
カザフスタンやウズベキスタンにいると、ややもすると自分がすでに見知っていた国の食の「アイデンティティ」を形成しているものの変奏ないしアレンジにしか映らない料理が、実はそんなことはなく、「アイデンティティ」と思えるものさえも元々は“特異性”の一つにすぎなく、その「変奏」や「アレンジ」に見えるものもまたそれ自体が一つの立派な“特異性”なのではないだろうか。
一見日本の「うどん」とイタリアの「パスタ」のアレンジにしか見えなかったラグマンも、従ってこの地に特有な“特異性”なのであり、もしかするとそれどころか日本やイタリアに中国から麺文化が伝わるずっと以前からこの地ではこうした麺料理を食べていた可能性だってあるのだ。ラグマンを食べて覚えた眩暈は、もしかすると自分がこれまで抱懐していた食の「アイデンティティ」にかんする遠近法が、突如崩壊したからかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
