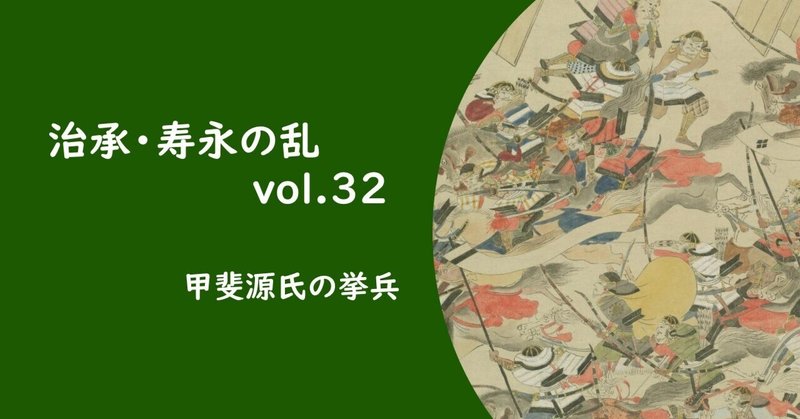
【治承・寿永の乱 vol.32】 甲斐源氏の挙兵
甲斐源氏の本格的な挙兵
治承4年9月10日(『吾妻鏡』)。
甲斐国(今の山梨県)の武田信義、その子・一条忠頼以下の軍勢は隣国・信濃国(今の長野県)へ侵攻しました。
前回の安田義定を中心とするグループに次いで、武田信義を中心とするグループもついに兵を挙げたのです。いよいよ甲斐源氏の本格的な挙兵です。
その甲斐源氏に対する敵は菅冠者という人物。
ですが、この菅冠者、残念ながらどのような人物かわかっていません。
『吾妻鏡』によれば、信濃国伊那郡大田切郷(今の長野県宮田村大田切・駒ケ根市赤穂付近)を本拠地とする者だそうですが、なぜこの時信義たちのターゲットになったのか定かではありません。
『吾妻鏡』には菅冠者が平家に味方する者だったから、甲斐源氏としては頼朝のもとへ向かう前に後顧の憂いを断っておきたかったからと出陣理由も述べていますが、これはまったくアテになりません。
なぜなら『吾妻鏡』はあくまでも「頼朝中心主義」ですので、最初から甲斐源氏を頼朝の下に置いている書き方をしているからです。
この頃の甲斐源氏は頼朝よりも勢力が大きく、この段階でわざわざ頼朝の傘下になって得るメリットがほとんどありません。上総国の上総広常のように勢力を持ちながら頼朝に味方した者もいましたが、それは頼朝に味方することでメリットがあったからです。つまり、この甲斐源氏による信濃出兵は頼朝とは関係ない独自の軍事行動と考えたほうが良さそうです。
これまでも何例かお話ししてきましたが、この治承・寿永の乱は在地の武士同士の対立が争乱の原動力の1つになっているので、やはりここでも甲斐源氏と菅冠者との間に何か対立することがあったのかと想定されるのですが、この菅冠者の拠った伊那郡大田切郷と甲斐源氏の甲斐国とはやや離れており、なんらかの利権をめぐって直接対立することはあまりないように思えます。
しかし、ここで『吾妻鏡』はある寺社勢力を登場させて、なぜ信義たちが信濃へ出兵したのかをうかがわせる手がかりになりそうなものを与えてくれてます。
そのある寺社勢力とは諏訪上宮です。
信濃出兵は諏訪上宮の要請だった?
この諏訪上宮というのは、諏訪大社の上社のことを指していて、甲斐や伊那郡と境を接する諏方郡にあり、諏訪大社は武神・建御名方命を祭神とする格式高い神社として、この頃すでに武士たちの信仰を集めていました。
『吾妻鏡』にこんな話が載っています。
武田信義・一条忠頼ら一行は、昨夜(9月9日夜)諏訪上宮の庵沢付近に宿をとりました。するとそこへ深夜、一人の女性が申し上げたいことがあると陣を訪ねてきたのです。
応対した一条忠頼は怪しみながらも、囲炉裏の近くに招いて話を聞いてみることにしました。
女性は話します。
「私は諏訪上宮の大祝(≒宮司〔その神社の長〕)篤光の妻です。夫の使いとして参りました。
夫・篤光は源家のために心をこめて祈祷するために、社殿に籠もることすでに3日、家にも戻らずにいたしましたところ、ついに夢の中で神のお告げを得たのです。梶葉紋の直垂を着て、葦毛の馬に騎乗した勇者一人が、源家の味方といって西の方へ向けて鞭を揚げたのです。これはひとえに諏訪の大明神がお示しになられたことです。どうしてこれを頼みにしないことがありましょうか。夢から覚めたのちに夫自らがご報告に参らねばならないところですが、まだ社殿にて祈祷を致しておりますゆえ、この私を遣わしたのです」
これを聞いた一条忠頼は、諏訪の大明神への信仰をいよいよ篤くして、野剣一腰と腹巻一領をこの妻に与えたそうです。
さて、ここで改めて甲斐源氏がなぜ信濃へ出陣したのかを考えてみると、諏訪上社は菅冠者となんらかの対立をしていて、甲斐源氏に介入を要請した、つまり助太刀を頼んだという構図がみえてきます。
この後、甲斐源氏は菅冠者の拠る大田切城に迫り、菅冠者は戦わずして館に火を放って自害し滅亡しますが、この時甲斐源氏は諏訪明神の加護に感謝して信濃国伊那郡の平出(今の上伊那郡辰野町平出)、宮所(今の上伊那郡辰野町大字伊那富宮所付近)の2郷を上社に、竜市(今の上伊那郡辰野町辰野付近と推定)の1郷を諏訪下社に寄進しています。

これらのことから、この平出郷・宮所郷・竜市郷などがあった今の辰野町付近の利権をめぐって諏訪上社と菅冠者が対立していた可能性が考えられるのです。この頃の甲斐源氏はまだ信濃国に所領なり利権を有していた可能性は低いと見て、これらの各郷は菅冠者の所管する郷だったのではないでしょうか。
しかし、なにせ頼れる確たる史料が私の見つけられる範囲にはなく、『吾妻鏡』の記述のみからの推測なので、このままではこれは単なる想像になってしまうことをあらかじめ断っておきます。

諏訪明神の思し召し?
ちなみにですが、甲斐源氏はこの戦勝に際して、同じ諏訪大明神を祀る社ということで諏訪下宮(下社)にも土地を寄進したのですが、この時不思議なできごとがあったことを『吾妻鏡』は記しています。
せっかくなので紹介しておきます。
甲斐源氏は諏訪下社に竜市郷を寄進する旨の寄進状を書かせましたが、執筆者は誤って竜市郷の他に「岡仁谷郷(今の長野県岡谷市付近?)」という郷も書き加えてしまいました。
間違えた寄進状ではいけないということで書き直させますが、何度書き直しても岡仁谷郷を書き加えてしまうのです。
ただ、この岡仁谷郷という地名はみな知らず、一体どこのことかわかりません。そこで地元の古老に尋ねたところ、岡仁谷という地名があることが判明。そこで武田信義や一条忠頼らは気がつきます。これは上宮と下宮に優劣はないという諏訪明神の思し召しであると。
そして、竜市と岡仁谷の2郷を寄進する旨の寄進状を下宮に送り、甲斐源氏の者たちは改めて諏訪明神の霊験あらたかなるを感じて、ますます信仰を篤くし、両宮を敬って礼拝しました。
この話をどう見るか、またなぜこの話を『吾妻鏡』が収録したのか、大変興味深いところですが、確たることはわかりません。
しかし、当時諏訪下社(下宮)の祝(≒宮司)は金刺盛澄(諏訪盛澄とも)という人で、彼は神官でありながら武士でもありました。治承・寿永の乱では源義仲(木曾義仲)に従って活躍をしており、また、義仲を聟に取ったという話もあります(『諏訪大明神絵詞』)ので、甲斐源氏としては源義仲ら木曾勢との無用な衝突を避けるねらいがあったか、この頃から木曾勢と連携していた可能性があるという見方ができそうです。
(源義仲の話はまたいずれしますね)
また、上社(上宮)の大祝は先ほど登場した諏訪篤光で、下社(下宮)の祝は金刺(諏訪)盛澄ということで篤光も盛澄も同じ諏訪氏を名乗ってるんですが、両者の関係がよくわかっていません。
かなり前の時代に分かれた別系統の諏訪氏とも、もともと違う氏族ながら共通して諏訪明神を祀る古代豪族同士とも考えられ、いずれにしても、この当時は上社系諏訪氏と下社系諏訪氏のそれぞれ独立した勢力であったことをうかがわせます。そのため、上宮と下宮に等しく土地を寄進することで、上宮と下宮の無用の対立も避ける思惑もあったのかもしれません。
北条時政の来訪
さて、甲斐源氏は菅冠者を滅ぼしたのち、信濃国の敵対勢力(『吾妻鏡』には平家に志を寄せる者と記述)をも多く駆逐して、甲斐国へと戻りました。
そして9月14日夜。甲斐源氏軍は甲斐国の逸見山(場所不明です。谷戸城付近か清光寺付近と推定)に到着。そこで宿を取って一息つきましたが、その翌朝、ある人物が逸見山を訪れます。
その人物とは、あの北条時政です。
『吾妻鏡』では頼朝の仰せを伝えにやってきたということになっていますが、その仰せの趣というのが時政と甲斐源氏が協力して信濃国へと出陣し、降伏する者は早くこれを引き連れ、おごって反抗する者はただちに討つようにというものでした。
お話ししてきた通り、もうこの時すでに甲斐源氏は信濃国での戦を終えている段階ですので、この命令にはとても違和感があります。
そうです、この記述は甲斐源氏の信濃出兵が頼朝の意向に沿うものであって、その命令が伝わる前に甲斐源氏は先立って命令を履行していた体にすることで『吾妻鏡』特有のクセを遺憾なく発揮させていると考えられるのです。
(参考)
上杉和彦 『戦争の日本史6 源平の争乱』 吉川弘文館 2007年
川合 康 『日本中世の歴史3 源平の内乱と公武政権』 吉川弘文館 2009年
五味文彦・本郷和人編 『現代語訳 吾妻鏡 1頼朝の挙兵』 吉川弘文館 2007年
関幸彦・野口実編 『吾妻鏡必携』 吉川弘文館 2008年
石井進 『日本の歴史7 鎌倉幕府』 中央公論社 1965年
黒板勝美編 『新訂増補 国史大系 (普及版) 吾妻鏡 第一』 吉川弘文館 1968年山梨県 『山梨県史 通史編2 中世』 山梨日日新聞社 2007年
塙保己一編 「諏訪大明神絵詞」『続群書類従 第3輯下 神祇部』 続群書類従完成会 1976年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。
