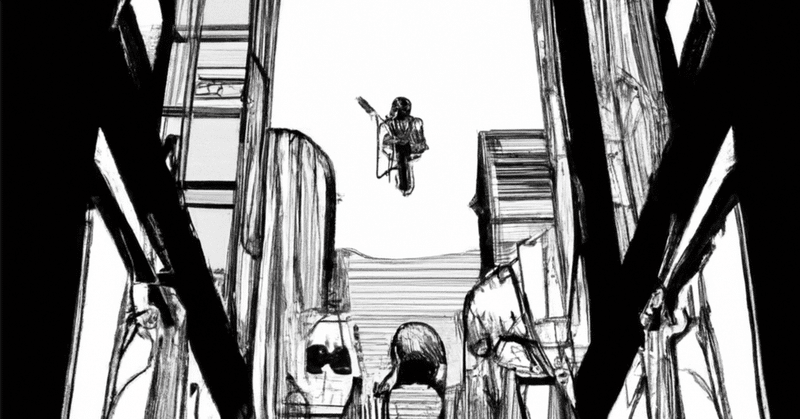
BFC4決勝進出ファイター決定&ファイターをジャッジ
決勝進出ファイターは以下の2名に決定いたしました。
草野理恵子「雰囲気しりとり」
冬乃くじ「あいがん」
準決勝ジャッジ
冬木草華
岡田麻沙
白湯ささみ
虹ノ先だりあ
採点表

準決勝ファイターをジャッジ
冬木草華
準決勝作品をジャッジするにあたり基本的には採点方法、勝ち抜けともに一回戦のものを踏襲しています。
・個別評
「雰囲気しりとり」 草野理恵子 4点
本作は【】で囲われた二つの単語と()で囲われた五七五の川柳、そして上記ふたつの要素を含んだ詩の四つの連作になっている。この評内では順に①~④とする。前作においてもあったように、()とその後に続く詩は完全な対応はしていないが、それによって起こるのはイメージとその奥行きの拡大だ。今作においては、さらにそこに【】で、例えば②の冒頭には①に含まれていた単語がピックアップされ、②内において【】の単語が完全な引用ではなく要素として使用されている。まさにタイトル通りの雰囲気でのしりとりになる。本作を最後まで読めばわかることであるが、①の【】については、④から単語を選出しており、それによって①と④が接続され、円環としての構造を見せる。
本作の内容においては、①冒頭から「地球最後の日」、②「青い血」「世界の終わり」③「装甲車」「防弾ガラス」④「死んだ時頭につけるやつ」「死ねないね」とあるように使用される語句にはダークな印象がちらつくが決して読み口としては暗くならない。それは、「私たち」が常に交歓をしているように思えるからで、①の「クラスの女子全員」でトイレに寝ころぶシーンや、②の「ターコイズブルー」のユーモア、③での「装甲車」と「音楽隊」のふれあい、④の「看護師ごっこ」がそれぞれにおいて楽天とした雰囲気を与えている。④は、後半に進むにつれて陰りを見せるが、ここで円環の構造が読者を再び冒頭へと回帰させる。円環の構造が読み手に再読の要請を可能とするのだ。しかし円環という形式は諸刃の剣であり、おさまりの良さ、構成美を思わせるが、同時に作品を終わらせることの逃避ともうつる。最後の【】は冒頭で示されているのだから、読み手への親切にしてもやりすぎに思え、構造への意識がにじみでてくどいように思えてしまった。
「バス停山」 宮月中 5点
降りる気配もないのに一つのバス停ごとに停車するバスに乗った人々とその事情が描かれる本作は、一行空きで視点が変わる三人称の形式をとっている。登場人物それぞれが目的地へ着く=バスを降りる=ボタンを押す、ことになにかしらの思いを抱いている。最後まで読めばわかることだが、「悠」の「バス停山」という姥捨て山に似た話への対抗策からバスは毎度停車していたことが判明する。これによって同乗者には、「悠」の意図せぬ効果を引き起こしているように思える。「誠二」は入院中の自己中心的に思える父に会うことを遅滞させられ、それによって少しは気持ちが落ち着いていくかもしれない。「希美」は母の呪縛から自分を解放したが、それでもまだ、その姿を見せたことがなく、またその呪いに「対抗する」言葉を「まだ持ち合わせていな」いが、このバスに乗っている間に手に入れられるかもしれない。刑務官である「幸一」は「ボタンを押」すことにとりつかれていたが、思索に時間を使用できるようになり、あるいはその意味を見つけられるかもしれない。
本作は情報提示の順序が肝となっており、毎度の停車の理由は結末部において知らされることで、物語は巻き戻され、駆動していく。バスが停車する場面で始まり、バスが停車を予告して終わるこの作品においても、偶然だろうが循環の構成が浮き上がって見える。いら立っていたはずの運転手が「優しい声」でアナウンスをするのも冒頭に還っていく合図かもしれない。幾分メタ的な視点で考えると、本作は複数の登場人物が順々に語り終え、その後姿を見せなくなるというのはバスになぞらえればひとりひとり降りているようだ。そうして、そのバス停となっているのは、ひとりの語りの最終段落と次の語り手の最初の段落に登場する言葉だ。「誠二」と「希美」なら「一番前」の席について、「希美」と「幸一」なら「親切」が、「幸一」と「悠」なら「ボタン」が。それぞれが、バトンを渡すようにそれらの言葉を受け渡し、語りをつないでいる。いつまでも目的地に着かず、本来のルートを外れていると思われるバスが、毎度停止することの恐怖が消えた後も残り続けることで、深みを増している。
「編纂員の夜勤」 奈良原生織 4点
本作はタイトルの通り二人の編纂員「マヌカ」と「トバ」のある日の夜勤を切り取った作品だが、長編小説の序章と言われても不思議はないほどに描かれていない部分の世界さえ見せるほど作品として強度がある。それは、ひとつひとつの設定の細やかさによるところが大きいだろう。「想像力」を「国が買い取る」という世界で、トラブル発覚のきっかけが、「ID」の供給数が夢を見るせいで増え、サーバーの稼働率が上昇するはずなのになぜか供給数が少ない、というのもすんなり理解できるし、その後のサーバーが過冷却になるというのもリアリティを担保している。徴収されている「ID」がなにに使われているのか、あえて提示されないことで作品に奥行きを生む。しかし本作の最も大きな魅力は、その作品世界を下地にして「マヌカ」と「トバ」の関係性にクローズアップしていることだろう。ふたりの関係性は最初の会話における軽妙で裏表のない言葉のやりとりから、ふたりが互いに心を開いていることが読者に伝わってくる。大勢のユーザーが契約を解除するシーンは作品が加速していきそうな場面ではあるが、「マヌカ」と「トバ」は「絵しりとり」をしている。このゆるさ。思わず頬が緩む。「絵しりとり」をするふたりには、「想像力」を徴収されているいないの違いがありながら、平等に行えているように見えるのは、「トバ」の絵がへたくそだからなのだろうか。思い出すことにすら「想像力」の徴収を受けるならば、それも難しいような気もして、その点が疑問として残った。が、結末部における、「マヌカの笑顔は夜に似合わない」と思いつつ、それでもその笑顔を夜にしか見られないことに「トバ」は不満を抱いたりしないし、きっとわざわざ昼に会おうとも言わないだろう。絶妙な関係性を見事に表現しきっている。「絵しりとり」の箇所は気になるが、それ以外に特段目立って気になる箇所は見受けられなかった。が、他作品と比較するとすこしインパクトに欠けた。
「あいがん」 冬乃くじ 5点
「わたし」が「空き家」と出会うところから始まる本作は、「わたし」が母と暮らしていたころへ遡り、そうして再び現在へ還っていくまでが描かれる。本作で重要となるのが、「箱」のモチーフであり、そのひとつの空間におけるルール、秩序といったものだ。まだ母と暮らしていたころの「わたし」は、母の許可なしに犬との接触も許されず、犬に向ける視線を「わたし」にも向けている。それには「ゆきのすけ」が関わっているようで、この人物は「わたし」の兄あるいはそれに近しいような存在だろう。「ゆきのすけ」の一件があったことで、「わたし」は犬同様に縛られる。母が絶対の「家」。そこから出る「わたし」を最初止めようとしたのは、母には母の秩序があり、それには「わたし」が不可欠だったからだろう。「わたし」が母の部屋から犬の骨を盗むのは、骨それ自体が実在を証明するものであるからで、それがあれば、いないことにはならないからだ。「わたし」は恋人にも同じような思いを抱く。だが、それはもともと「わたし」にあった考えというよりは、母にあったものだ。だから海洋散骨を嫌がるし、部屋には犬の祭壇まで拵えている。それが同じ家で過ごしていた者のルールになっているのだ。ただそれとは別のルールもある。「わたし」が犬の肋骨をとったときに思う自分の都合で犬を人間の社会のルールに従わせていたこと。犬には犬の社会があるはずなのに。恋人との子供を作るのが怖いのは、自分が持つルールに子供を従わせることになるからでもあり、この社会という箱のもとでルールに従って生きていってもらうことになるからだ。だから「わたし」はそれに反抗するように「一人しか住んではいけないワンルーム」という箱で恋人とふたり暮らす。大きくなった「空き家」は白い箱だけ食べていたのに黒い箱も食べるようになった。清濁併せむように、聖なる純とした存在から、より「わたし」に近い存在となる。黒と白、どちらも知っている存在に。「空き家」の中での「わたし」は裸で、母とも親しく接する。まるで胎内めぐりのように、純な存在としてふたりは出会いなおす。「わたし」だってもともとは母のおなかの中にいた存在なのだ。だから声が聞こえない。それでも微笑んでいるのがわかるのは、同じ身体でつながっているからだろうか。煙に飛び込んだ「わたし」は、暗闇に白い箱を見る。焼かれる前のまだ純粋なそれを。きれいに割り切れないからこそ、暗くても、白くもあれる。げっぷの音は、「わたし」がそれを認められたからかもしれない。平和や希望の花言葉を持つ「ひなぎく」を育てる母には未だかつての影が見える。「わたし」の「スマホ」という箱にたまり続ける写真が、それを証明するかのように。簡単には割り切れない感情や母との関係性を描き切ったその手腕には感服する。
・勝ち抜け評
点数は記載の通り。「バス停山」と「あいがん」が5点である。四作品どれもほとんど拮抗していたが、ほんとうに少し、鼻の先の差で点数が低くなったりしているだけだ。「雰囲気しりとり」は前作に引き続き言葉がどの作品よりもいきいきして見えたし、「編纂員の夜勤」は掌編からそれ以上の大きな世界を感じさせられた。けれど、勝ち抜けには選べなかった。「バス停山」と「あいがん」両作とも書かれている言葉以上を読み手に働きかける力があり、一回戦の作品とは異なる方法で戦いに挑んでいた。また、どちらも掬いきれなかったという印象を強く感じるほど底の知れない作品だった。しかし、その中でもより作品にジャッジとして負けたと感じた、冬乃くじ「あいがん」を勝ち抜けとする。
「雰囲気しりとり」草野理恵子 4
「バス停山」宮月中 5
「編纂員の夜勤」奈良原生織 4
「あいがん」冬乃くじ 5 〇
岡田麻沙
採点のしくみはない。書かれたものを判じるために必要な距離まで、作品から遠ざかることができなかった。読者として「くらった」と感じた箇所を一発とカウントする。部分も全体もなべて一発とみなす。結果は以下。

経緯を記す。最初に私の視点を突き崩してきたのは「バス停山」だ。次に「編纂員の夜勤」で迷子になった。「あいがん」で情緒をやられ、「雰囲気しりとり」で退路を断たれた。この順に評を置く。
宮月中「バス停山」 4点
本作は定点からの安易な読みを退け、読者としてバスに同乗することをそっと促す。だが読むほどにたたらを踏む。「彼」は「希美」になり、苛立ちは親切に転じ、それもすぐに失せ、押し損ねた指先は誰かのチャンスに代わり、祖父との時間を奪いもする。温度を持たぬボタンに倫理は介在しない。これを「構造に善悪は宿らない」と読むこともできる。
しかし、「一段高い席」にいるかぎり「独り」であるならば、読者として低い席に座りなおす必要があるのではないか。さらに腰を落とす。すべての登場人物に与えられた死角が寿ぎのように見えてくる。「バッサリと切り落とした」髪をまだ知られずにいる時間は気高く、罰と救いの間でさまよう心はあえいでおり、「みんなにはおりてほしい」という願いの裏には孤独がある。押され続ける降車ボタンは無機質な結節点であることをやめ、生の有限性を示す警告に姿を変える。錯綜するまなざしを追ううちに、作品から見つめ返されたのだと気づく。席を立つタイミングを失い、バスの中に取り残される。
奈良原生織「編纂員の夜勤」 4点
緊迫した状況と対照的に、ゆったりと据えられた余白が「図書館」へと誘う。提示されるのは不可視の領域。想像力を奪われた人々が捉える世界そのもののように、得られる情報は限られている。本作を読むのは、暗闇で目をこらすのに似ている。わからなさのなかで、グラシン紙の質感や、本棚に挟まれた空間の狭さが、そのものとしてふいに顔を見せる。随所に散らばる「二」と呼び合うのは螺旋。「左右の大きな耳」もまた螺旋を内包する器官だ。生き物じみて感じられるこの「図書館」は、冷却され、電源を落とされ、死にゆく過程のように見える。ここにきて、「トバ」が「マヌカ」に寄せる想いが、ごく淡く描き出される。見通しの悪い場所にかすかなものが置かれ、読みが無限に広がっていく。
サーベルタイガーのことがいつまでも心に残る。巨大な犬歯を持つ絶滅種がここに描かれたことについて何度も考えたが、解釈は訪れなかった。ただ繰り返し思い出す。祈りのように。
冬乃くじ「あいがん」 5点
対となるものが互いを喰らい合いながら凄まじい速度で移動していく。箱を喰らう空き家は生を喰らう生であると同時に、制度を喰らう制度をも連想させ、無限の入れ子構造が立ち現れる。犬の心臓とシロナガスクジラの心臓は異なるリズムで脈打ち、「隣り合う細胞のよう」に共生することの儚さを仄めかす。キク科の多年草であるひなぎくは死者への手向けのようでいて、それ自体が「生き物」でもある。化粧箱から肋骨を取り出す指は灰にまみれるが、生き延びるために必要な儀式だったことが示される。肉片から骨が盗まれ、解体としての死が前景化する。
死んだら地球に混ざりたいという言葉が胸を打つ。斬り結ぶ他者としてではなく、ひとつであることができぬものか、と自問しながら読む。しかし「わたし」は消滅を望まない。自由に触れることは許されなかった犬の「欠片」をポケットに忍ばせ、眼前の「恋人」にいつか訪れるであろう死をまなざすことで呼吸を続ける。白い箱は黒い箱に転じ、「わたし」の体もまた煤に覆われる。生々しい感情を描きながらも、断罪の手つきはここにない。生き延びること、その両義性だけが示される。高度な乱れ打ちのなかに、呪いと祝福が共存する。
草野理恵子「雰囲気しりとり」 5点 ★勝ち抜け
本作は幻視を誘う呪具だ。瞬きと永遠の間に肉体がある。「落下」と「窓」は、逆説的に窓外のすべてを射程に入れ、その永続性は詩のパート全体を貫く過去形により補強される。俳句は現在形。色褪せぬ一瞬のまなざしとして楔を打ち込む。これらを肉が紐帯する。普遍的な身体感覚を追ううち、「人が降る」場所までたどり着く。そして「世界が傾」く。降下のさなかに訪れる無重力状態のように、隔てられていたはずの言葉と言葉が手を取り合う。続いて、触覚の氾濫。風とワンピース、タイツと膝、てのひらと液体の対比に粟立つ。皮膚感覚が誘うのはしかし、装甲車から防弾ガラスを経て乳歯へと至る道だ。意味を逃れた声としての歌は風と呼応し、個と全体が入れ子になる。最後に時間が手渡される。ごっこ遊びの過去から、「手や足が溢れる」未来へ。過去形の未来は終わりなき反復へと落下/上昇していく。抹消のしぐさが形成する円環のなかに、読者は閉じ込められ、解き放たれる。読んでも読んでも、自分はまだこれを読んでいる途中だと予感させられる。果てしない詩情。
準決勝の四作を前に、読むことそのものを退けてしまいたい衝動に何度も駆られた。読めたような気がした作品に見つめ返され、解釈以前の祈りに出会い、情報として集約できない感情を引きずり出された。騙し騙し身を投じるなかで、ある作品に対し、いっさい心が動かなくなった。「雰囲気しりとり」だ。自分が本作を恐れいてることを知った。佐々木中の言葉を以下に引く。
読めるわけがないんだ。他人が書いたものなんて読めるわけがない。読めちゃったら気が狂ってしまうよ。(中略)書くということ、読むということは無意識に接続するということである。だからカフカの小説を読むということは、半ばカフカの夢を自分の夢として見てしまうということです。ならば、そこで「自然な自己制御」が働いて当然でしょう。
本なんて読めません。読めたら気が狂ってしまいます。しかし、そのことだけが、それだけが読むということなのです。
読み捨てることによって生きながらえることもある。大いに心当たりがある。それでも今回は、「読めない」と呟いた、この場所に立っていたい。「雰囲気しりとり」を勝ち抜け作品とする。
「雰囲気しりとり」草野理恵子 5 〇
「バス停山」宮月中 4
「編纂員の夜勤」奈良原生織 4
「あいがん」冬乃くじ 5
白湯ささみ
ルール確認。一回戦と同じくミニトーナメント方式によるジャッジを行う。まず掲載順に二作品ずつA・Bブロックに分かれて対戦する。次に両ブロックの勝者同士で決勝戦を行い、優勝者を決める。
採点方式は「五点満点の防衛戦」。はじめにすべての作品の持ち点を五点とする。初戦で負けた側は二点を失い、勝った側は五点をキープする。続く決勝戦では、負けた側が一点を失う。終了時には五点が一作品(勝ち抜け)、四点が一作品、三点が二作品となる。
各戦において勝敗を分けるポイントは都度変化する。「この組み合わせだからこそ」浮上したベン図の重なる要素を【鍵】にして作品を読み解き、より強いと判定したものを勝者とする。真の決勝戦への切符を手にするのは誰か。これよりトーナメントを開始する。
準決勝Aブロック 『雰囲気しりとり』VS『バス停山』
鍵は【モラトリアム】。どちらの作品にも「終わり」の到来を予期する人物が、それぞれの猶予期間を過ごす様子が描かれている。
『雰囲気しりとり』は、任意のキーワードの語尾ではなく「雰囲気」を引き継ぐことで、詩作の過程を遊戯になぞらえた連作散文詩だ。()内の川柳は、後に続く詩の内容を端的にあらわした要約になっており、読者への水先案内として機能している。
四章に分かれた川柳と詩の世界を移動する「私」は、その日が「地球最後の日」であることを知っている。終末の気配はすべての章に通底しており、「爆発」「雷鳴」「世界の終わり」「血」「装甲車」「死」「(水)鉄砲」「落下する人」などの言葉によって、不穏な情景が次々と立ち上がる。にもかかわらず、本作にはどこか楽観的で開放的な空気が漂っている。
少女たちは地球最後の日にも冗談を言って笑い、授業中に居眠りをし、草むらで歌をうたう。事態が最も深刻化する四章においてさえも、お揃いの「ピンクのエプロン」を着け、同じ色の「きれいな雲」がたなびく空を見つめる「私」の眼は絶望の色に染まってはいない。そして場面は冒頭の【窓&落ちる】へと循環し、終末は繰り延べされる。ループする時空の中でモラトリアムを遊び続ける「私」の姿には希望が託されているように思える。
『バス停山』はバスの車内に乗り合わせた四人の人物の内面を描いた密室劇である。誠二は死期の近い父との面会を億劫に感じ、彼が姥捨て山の話を息子の悠に教えたときと「同じ目をしている」。悠は姥捨てとバス停を聞き違えたために「バスの終点で誰かが捨てられる」という空想に囚われ、終点に着く前に他の乗客を降ろそうと停車ボタンを押し続ける。希美は過干渉の母との対決の時を先延ばしにしたがっていて、悠の行動を「親切」だと感じる。三人にとってバスの停車回数が増えることは、乗車時間の終わりと共にやってくる不快や恐怖から一時的に逃れるためのモラトリアムの延長を意味する。そして四人目の乗客・幸一は「ボタンを押す」という行為そのものにモラトリアムを見出している。刑務官として働く幸一は、「ボタンひとつで他人の生死を決めてしまった」という罪悪感と向き合う時間を先延ばしにするためにボタンを押し続ける。しかし悠に先を越されたことで猶予期間は終わり、彼はその事実が「罰なのか、救いなのか」自問する。
停車場に停まるバスのように視点を移動させながら四者四様の事情や思惑を描き出す展開は自然で、伏線回収も鮮やかだった。反面、読者が自由に想像や解釈をふくらませる余白が少なく、物語全体が終わりに向けて小さくまとまっていくような印象を受けた。一方、『雰囲気しりとり』には終わらないモラトリアムと広大な想像の余白があり、「もっとこの世界に留まっていたい」と感じさせる魔力がある。よって、『雰囲気しりとり』を勝者とする。
準決勝Bブロック 『編纂員の夜勤』VS『あいがん』
鍵は【抑圧と抵抗】。
『編纂員の夜勤』の舞台は、市民の想像力が徴収され、IDで管理されるディストピアだ。ある夜、人々の想像の自由を抑圧する政府への抵抗として「ユーザーの一斉解約」が行われる。想像データサーバーの編纂員・マヌカとトバは、現場対応に追われつつ、仕事の合間に「絵しりとり」で遊ぶ。「絵しりとり」にも想像力は必要となるため、ここにも「ただ徴収されるくらいなら、自発的に遊んだほうがマシだ」という小さな抵抗意識が見てとれる。さらに、実は想像力の徴収を免れていることを隠しているトバが、今後プロパガンダを仕掛けた抵抗勢力と結びつくキーパーソンになるのではないかという予感もある。
設定もキャラクターも魅力的で、続きを読みたくさせる引力があった。しかし、作品の根幹を担う概念の説明が不足しているために、読みながらちょくちょく疑問や混乱が生じてしまった。思考回路のどのレベルまでを「想像」と呼んでいるのか?「連想」や「追想」も徴収対象のようだが、そうなると日常生活や会話もほとんど不可能にならないか?「想像力を奪われる世界」を読者がリアルに想像するには、「想像」という行為に関する詳細な分析と解説が必須と思われるが、それらの情報を盛り込むには六枚の紙幅は狭すぎたのではないだろうか。
『あいがん』には、娘を抑圧する母と、母に抵抗する娘の姿が描かれている。愛を免罪符に対象を所有・支配しようとする母にとって、娘は自立した他者ではなく、物言わぬ犬やひなぎくと同列の愛玩物だ。しかしそんな母から逃れようともがく「わたし」もまた、対等なはずの恋人やいつか生まれるかもしれない子どもに対して、犬へのそれと同じ眼差しを向ける。
「わたし」は恋人と新しい「家庭」を作ることに忌避感を抱いている。「家」は母の象徴であり、抑圧と抵抗の歴史を内包した忌むべき黒い箱だ。殺鼠剤が撒かれた場所で犬を遊ばせることと同様に、危険や苦悩に満ちた世界に子どもを産み落とすことを「こわい」と思う「わたし」は、さらに犬の骨を盗んだときと同様に、恋人の骨を所有して「一人で生きていく」ことを夢想する。白い骨を媒介にして取り出される死者の記憶は、「わたし」の内側からほとばしる愛を一方的に注入するための白い箱となる。それは母が「わたし」に求めた関係と相似だ。知らず知らずのうちに抑圧する側の思考をトレースしてしまう「わたし」の意識は、次の瞬間「散骨」のイメージへ飛ぶ。散骨は「家」の墓に入ること、母と同じ人生を歩むことへの抵抗をあらわしている。このように抑圧と抵抗をめぐる「わたし」の葛藤は作中のあらゆる物や情景に投影され、融合と分裂を繰り返す。本作を読んだときに読者の中に生じる混乱は、設定上の穴や説明不足から来るものではなく、作者が緻密な計算のもとに創造した「混乱に満ちた作品世界」に嵌められていることの証左だ。よって、『あいがん』を勝者とする。
決勝戦 『雰囲気しりとり』VS『あいがん』
鍵は【箱庭】。六枚という小さな「箱」の中に言葉をめいっぱい詰め込む。これは他のファイターたちも目指してきたことだ。しかしそこに特殊な仕掛けを作ると、言葉の力が最大化され、六枚の何倍もの広さや深さをもつ箱庭世界が顕現する。
『雰囲気しりとり』は「雰囲気」「しりとり」「ループ」の三要素を用いて六枚の枠を破っている。「雰囲気」とは本来言語化できないものだ。辞書によれば「その場所や、そこにいる人たちが自然に作り出している、ある感じ。」一言では説明できない「感じ」を読者に伝達するには、「その場所」の情景や、「そこにいる人たち」の姿を描くしかない。それこそが詩だ。二つの言葉の組み合わせを元に詩を作り、完成した詩から別の二つの言葉を取り出して新たな詩を作る工程を繰り返すのが雰囲気しりとりの遊び方である。たとえキーワードが同じでも生まれる詩はいつも違うし、取り出せる言葉の組み合わせの数だけ作品世界は増殖する。
「地球最後の日」を繰り返しているはずの「私」が「今日はなぜかみんな仲が良かった」「まさかそのまま看護師になると思わなかった」などの感想を持つのは、ループするたびに世界が変貌しているためだ。新たに生まれ続ける詩から詩へと移動しながら、「私」は点在する。学校のトイレに、教室に、道端に、草むらに、装甲車の中に、屋上に。そしてそれぞれの場所で新しい体験をし、新しい言葉と出会う。そこには無数の世界線が存在し、しりとりは永久に続いていく。
言葉が外側にまとう「雰囲気」によって世界を拡張した『雰囲気しりとり』に対し、『あいがん』は言葉の内側に含まれる「意味」によって重層的な世界を形作っている。例えば「空き家」。空っぽの家、不在の家というモチーフは、実家から逃げた「わたし」と母親との関係や、かつてそこで飼われていた犬の死、恋人と新たな家庭を築くことへの不安などを包括する象徴になっている。成長した空き家の内部に入った「わたし」は、不思議の国のアリスさながら白黒、愛憎、生死のイメージ渦巻く世界に翻弄される。
タイトルから想起される「愛玩」はペットや物に対して使う言葉で、相手を人格のない「愛の入れ物」として見ていることを示している。だが果たしてそれを「贋」の愛だと言い切れるだろうか。歪な形であっても愛は確かに「含」まれているし、私たちは誰かを愛したいと「願」うことをやめられない。同族の箱を食らい続けて成長する空き家の姿は、愛の共食いをする人間の姿と重なる。相似の構図やイメージを持つ言葉を何層にも重ね合わせ、緻密に織り上げた本作は、ひとつひとつの言葉の要素を深掘りし、読み解いていく楽しみを与えてくれた。
しかし、『雰囲気しりとり』はもう一段突き抜けている。読者に「詩の作り方」を教えているからだ。詩はこうやって作るんだよ。一緒に遊ぼうよ。しりとりしようよ。私には作者がそう言っているように感じられた。自らの創作過程を開示し、読者の創作意欲を触発する作品との出会いは、過去のBFCすべてを思い返しても初めてだった。よって、優勝は『雰囲気しりとり』。
『雰囲気しりとり』5点★
『バス停山』3点
『編纂員の夜勤』3点
『あいがん』4点
虹ノ先だりあ
はーい!虹ノ先だりあです(はぁと)。準決勝もかわいくジャッジしちゃいますよ?!準決勝のかわいい4作品をジャッジする上でだりあは考えました。BFCのスケジュールってかわいくないです……。だがそれこそがBFC、この過酷さの中で輝くものを拾い上げることがジャッジの使命と考える。ともに駆け抜ける他に選択肢はない。
■ジャッジ(作品順)
「雰囲気しりとり」 草野理恵子
冒頭から堂々と仕掛けてきた大胆さがよい。「【→窓&落ちる→】」は即座に意味を理解できないものの、タイトルの「しりとり」と、続く作品の形から構造を徐々に理解させ、最終的に円環としたことでその意味を回収した。円環ではなく螺旋で、次の詩はまた別の作品という読みもできるが、「【→窓&落ちる→】(最後の日トイレが綺麗で失禁す)」は、舞台が地球最後の日であり、ラストが終末の予兆であることから、「雰囲気しりとり」の始まりと終わりを担う結び目と解釈した。作品群を束ねるのは、穏やかで不安定な世界と、そこに生きる少女たちである。世界は損なわれる。それが絶対のルールとしてある。
トイレの床が綺麗すぎて寝転ぶという日常から逸脱する遊戯性、ターコイズブルーが蛸 is ブルーに変わる軽やかさ、草原にいる音楽隊のすぐ側を通る装甲車の不穏さ、看護師ごっこが本物に変わる残酷性。これらの特性はすべての詩の中に姿を変えて忍び込んでいる。【】で括られた言葉以外も他の詩に侵入しているのだ。トイレで見た足は蛸の足に、絡まった草に取られた足に、校舎に溢れる足に引き継がれる。横たわる動作も同様に。さらに拡張すれば、水のイメージはトイレと失禁→青い血→草の汁と血→水鉄砲と点滴へと繋がっている。いくつもの糸が作品に通っており、読みの多様性を高めている。
しかし一方で、各詩の距離が近すぎることは疑問としてある。ターコイズブルーの驚きがあったゆえに、装甲車、野戦病院、世界の終わりという連なりを惜しく感じた。だが作品の統一感を強めたと取ることもできる。本作の鮮烈さは間違いなく4作品中1番である。
青空を眺める幸福さの中で世界が終わっていくかわいい4点です。
「バス停山」 宮月中
バス停山という愉快なタイトルが姥捨山の言葉遊びであると気づいたときの不気味さ。バスに乗る人々は、全員が苦いものを抱えている。老親を対象にした姥捨山よりも広い射程を持つ負の土地として「バス停山」は提示された。バス車内という空間の、席、ボタンという要素によって、各キャラクターの背景が呼び起こされる。
それぞれのキャラクターの苦痛は、家族や仕事という生活の一部としてあり、バスの運行のように、生活に組み込まれている。その生活を保留にするのが、悠の子供らしい勘違いから生まれた想像である。おそらくは姥という言葉を知らないために作り出されたバス停山という想像は、降車ボタンによる妨害として現実世界に作用する。バスが目的地に到着しないことにより、生活への帰還は先延ばしにされ続け、その状態が保たれたまま作品は終わる。今日だけは、乗客が日常に辿り着くことは永遠にない。
2つの読みを提示することができる。バス停山はそれぞれが降りた先の日常を指すものとして読める。そこにある苦痛との遭遇は決定されており、キャラクターたちはいずれ、それぞれのバス停山で苦痛と向き合うことになっている。
一方で、バス停山という想像が現実になったという読みがある。トンネルに入ったとき、幸一は「駅前行きのバスがこんな道を通っただろうか」と思い、実際に「バスはダムの上を渡り、あたりに人家が見えなく」なる。病院、実家、駅前という目的地にしては道のりが不穏だ。そして、悠の想像に基づくバス停山では誰かが捨てられることになっている。「次、止まります」の優しい声が、悠の優しさと呼応しているが、バス停山への到着を告げる予兆でもある。どちらの読みにせよ、バス停山へ少しずつ近づいている。
キャラクターの悩みがややありがちな点は気になるが、描写はうまく、また、カモフラージュにもなっている。
わたしたちの生活はバス停山で降りた先のものかもしれないかわいい4点です。
「編纂員の夜勤」 奈良原生織
未来社会で国民は想像を徴収されている。おそらく現在の図書館、そして本はすでに失われているようだ。想像の徴収は厳しくなっており、夢も、過去を思い出すことも、未来の予想も取り立てられている。いくつかの謎がある。想像データを使う目的は何か。絵しりとりにおける想像は徴収されないのか。労働生産性のために想像を徴収しているのに、それで支払われる金銭のため労働が減っているのはよいのか、など。これらのために、本作を読むにはいくつかのアプローチが発生する。作中の要素を拾い上げてこの未来社会がどういうものかを「想像」するとか。現実の何かを反映していると「想像」してみるとか。
そういった読みを含みながら、何よりもまず、この作品は未来社会での夜勤小説としてある。マヌカはシステム以前の世界の図書館、想像の集積所に愛着を持つ人である。それを懐かしみながら、現在の社会に依存して生きている。トバはシステムの外にいながらシステムに与する、所属と承認を求める異物である。彼はおそらく頭頂葉の損傷によって絵がうまく描けない。だが、マヌカはその絵を笑って受け入れる。想像の徴収を免れているトバと、徴収されないほどささやかな想像力を駆使するマヌカの間に絵しりとりが成立する。この均衡によって、社会の混乱の中で穏やかに幕が閉じる。だが、2人の感情はトバの一方通行でしかない。という、夜勤の一幕を描いたSF作品として本作を読んだ。
前述した通りに、読み方を惑わせるものがある。想像力を奪われていないわたしたち読者は、作品の書かれていない部分を想像するべきか。それが狙いと読めるほどには仕掛けが作られているとは言い難く、謎の見せ方は読む上でノイズになっている。わからなさを楽しむものと言い切ることもできず、調整不足と判断した。想像データをめぐる描写の不足により、ありがちな管理社会像に陥ってしまったことと、SF仕事小説としての面白さが十分に高められていないことは指摘しなければならない。しかし不穏な社会でのささやかな営みを掬い上げたことを評価したい。
システムはいつだって間違っているのかもしれないけれど、そこで生きていくしかないかわいい3点です。
「あいがん」 冬乃くじ
「サトゥルヌスの子ら」評で、わたしは「意図は十分汲み取れるが、敵対する父の描写に不足があり、余計な読みが介入する隙がある」という旨の指摘をした。「あいがん」においてその点は完全に払拭されている。害をなす母、母から受けた傷、主人公自身も加害者であった可能性を可能な限り描いている。犬に対して主人公が抱く罪悪感は、絶対的なディスコミュニケーションにより裏付けられ、それは主人公を傷つける母との関係にも結びつく。話せないゆえに起こるディスコミュニケーションと、話せるのにも関わらず起こるディスコミュニケーションが対置される。空き家は不在の犬の象徴としてあり、同時に家として母との生活、恋人との生活に繋がる。ある存在と共に暮らすことへの憧憬とその困難さが白と黒に担わされ、さらに白は棺に、黒は喪に服すことに移行する。骨を盗むという行為が、身勝手さと愛着が同居した行為の象徴として配置され、同時に、愛する存在が生きていた過去と死んでしまう未来を繋ぐ。このような仕組みを用いて、混乱を抱えた主人公を中心に据えながら、母の支配、犬の死というふたつの軸とその周辺をまとめ上げている。愛することと支配の関係を「愛玩」と言い切るには迷いがあり「あいがん」と名付けたのかもしれない。最後の母からのひなぎくの写真をどう受け止めるか。喪失の埋め方、弔い、手をかける相手を必要とする性分の現れ、相手を繋ぎ止める呪い、あるいは和解の兆し。そういったものが渾然となって、主人公の内面と呼応している。2人はいくつかの点で似通っているために。何にも決着をつけられない。そうあるほかない。作者がどれほど自身を削って書いたかという点では4作品中で抜きん出ている。 オルタナを標榜するBFCでこの作品に勝ち点をつけることのためらいはなくはない。だが徹底して人物の内面を描いた様は圧倒するものがあり、非常に優れていると評価する他ない。ただただとってもかわいい5点です。
■配点
「雰囲気しりとり」 草野理恵子 4
「バス停山」 宮月中 4
「編纂員の夜勤」 奈良原生織 3
「あいがん」 冬乃くじ 5 ◎勝ち抜け
※作品の権利は各々の作者に帰属します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
