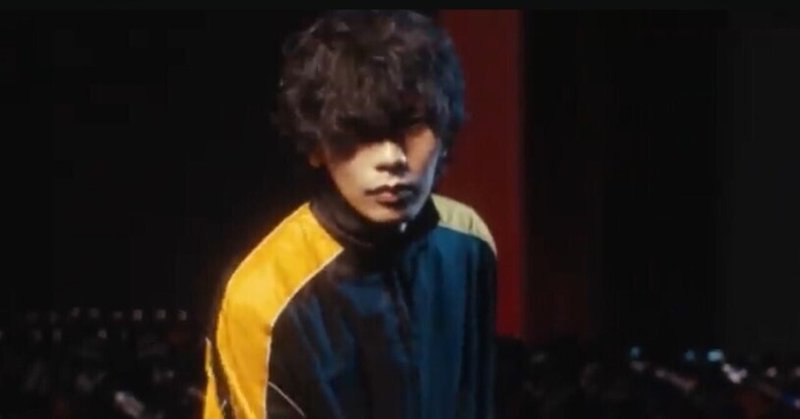
好きな曲を紹介してみる。(米津玄師KICK BACK編)
こんにちはー。初投稿失礼します。PeDeと申します。初投稿なので軽く自己紹介です。
普段はボーカロイドという音声合成ソフトを使ってオリジナル曲を作ってYoutubeやニコニコ動画にあげています(ボカロ曲とか言ったりします。)リンクを貼るのでよければ聞いていってくださいねー。ブログとインスタとツイッターはしているので何となく仕様がわかるのですが、noteは完全に初めてなので読みにくい文章だったらすいません。笑
気長にお付き合いよろしくお願いします。笑
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43230241?ref=nicoiphone_other
さて、自己紹介はこの辺りにしまして。笑
上の通り、私はボカロ曲を作るのが好きなのですが、せっかく作った曲をなるべくたくさんの方に聞いてほしいと思うもので、流行りの曲を自分なりに解釈してポイントをまとめるのです。
今回は米津玄師さんのKICK BACKという曲の見どころ紹介したいと思いますー。
YouTubeのリンクを貼るので一緒に流しながら見てくれると嬉しいですね。笑
まず冒頭のチェンソーを引くSEからの、ベースリフですね。これいいですよね。笑
このリフはRadioheadというイギリスのバンドのParanoid Androidという曲の間奏の2分5秒あたりのリフをオマージュしたものだと思います。この曲は97年にリリースされたRadiohead3枚目のアルバム収録曲なのですが、このアルバムがきっかけで彼らの音楽性がロック系のサウンドからシンセ系のオルタナっぽさが出ていくんです。(諸説あります。笑) 要するに過渡期ってやつですね。こういった前衛的な曲のリフをイントロからズドンで出してくるあたり痺れますよねー。笑
さらにディストーション系のエフェクトをきつめに利かせていて冒頭からバチバチ感全開です。笑
さてベースリフ2周、からのエレキーギターで駆け上がるようなフィル、からの歌い出しイントロ始まりですが何と言っても印象的なのは、努力未來a beautiful star、という歌詞ですね。
これは以降この曲中で随所に散りばめられており、とてもとても印象的なフレーズだと思います。というか私はそうです。笑
これは米津さん本人がおっしゃっていたことなので間違いありませんが、モーニング娘。さんの、そうだ! We're ALIVE という曲のフレーズなんですね。この曲は2002年のシングルで、私はモーニング娘。さんにあまり詳しくはないのですが、恐らく入れ替わりの激しいアイドル業界の不安定さとその中でも客に向けては明るい部分を見せる若い女の子特有の揺らぎのようなものが、KICK BACKという始めから終わりにかけて、いい意味で破壊的な曲のポテンシャルを最大に引き出していると思います。
また先ほどのベースリフ然り、MVのアメコミ系の雰囲気然り、最近の90年代文化のファッションなどにおけるリバイバル的な流行というのを自身の曲にきちんと取り入れています。音楽的な鋭い感覚やその理屈を勉強されていることはもちろんのことだと思いますが、大衆的な流行とのバランス感覚のよさというのはポップスを作る上で非常に重要な感覚であると考えます。
続きです、
イントロが開けて怪しげなベースフィルからAメロですね。このAメロ、私含め多くのボカロPは曲を作る時2回似たような歌メロを入れることが多いのですが、一周でさっさと終わってしまいます。笑
米津さんは元々、ハチと言う名前で活動されていたボカロPさんなのでこう言った手癖のようなものは誰しも悪い意味で残ってしまいがちですが、そんなのお構い無しです。日々、進化されているようです。笑
続いて、だっだっだっっだだーー〜んでもの凄い荒い転調をかましてきます。(めちゃめちゃ褒めてます。笑)
説明できるほど知識がないのもありますが、こんな転調の仕方はポップスの曲では普通はあまりしません。最高です。
続きます、
誰だ、誰だ頭の中呼びかける声はー、の後にギターで歌メロをなぞるのですが、これは常田さんの手癖全開な感じがして良いです。King Gnuの曲中のソロとかでよく見かけます。vinylとか全開ですね。3分23秒あたりからです。
はい。この曲、King Gnuのギターをされています常田大輝さんが編曲に入っているんですね。常田さんの作る楽曲は特にロック系において90年代くらいのバンドに影響を受けられている印象があります。だから冒頭のゴリゴリディストーションリフだったんですねー。笑
続きます、
あれがほしいこれがほしいと歌っているー、からのまた転調してBメロ、幸せになりたーい、楽して生きていたーい、この手に掴みたーい、あなたのその腕の中ー、で凄い回数転調してます。もはや転調しすぎてキーという概念が存在しないような演出を狙っているのかなと思います。
作曲者が転調する時は曲に展開をつけることを目的にしていることが多いと思います。つまり、明るくしたり、暗くしたりを狙って出せるというわけですね。
この曲は元々、チェンソーマンの主題歌として提供されたものなのですが、このチェンソーマンという漫画は作者の藤本タツキ先生から始まり、とにかくぶっ飛んだストーリー展開です。ファイアパンチという漫画は藤本先生の別作品なのですが、ストーリー中盤までこれ完結させる気あるのだろうかと心配になるくらいに破茶滅茶ですが、終盤にかけて何となく人って結局そういうものだよなと思わせてくれる謎の読後感があるので大好きなのですが、きっとこう言ったあたりを反映しているのかもしれません。つまり漫画の終盤を曲で言うサビとするなら、今はサビ前に対応していると言うことです。笑
続きます、
散々転調しまくっての満を持してのサビです。笑
ハッピーで埋め尽くしてー、のサビです。圧倒的にかっこいい。笑
サビに転調するのは最近のポップスではセオリーみたいなところがあると思いますが、通常はサビ前でこれだけ転調を繰り返すと言うことはありません。なぜかというと日本のポップスはサビを主軸に置いて曲作りをするという傾向にあるからです。そのサビを立たせるための手段としての転調であり、下手な転調をしすぎるとサビに入った時にメインがぼやけてしまいがちだからです。
要するに、大トロを食べる前にガリで口をリセットしたほうが大トロを味わえると言うことです。ガリを食べすぎると普通は意味わからなくなります、笑
しかし、この辺りを成立させてくるのが流石の米津先生です。転調をサビ前に繰り返している分普通のポップスよりもサビが光ります。流石としか言いようが無いですね。ガリ職人でしょうか?笑
またサビのドラムが大好きです。何拍子なんでしょうかねこれは。笑
この曲の速さはbpmと言う曲の速さを表す単位で200あたりなのでかなり早めの部類になるのですが、16ビートと言ってめちゃくちゃ早くドラムを叩いてる所にさらにさらに規則性を持って変なタイミングで叩くという離れ技をしているところが前衛的でいいです。好きです。自分なら安全に8ビートの四つ打ちくらいに逃げてると思います。サビ前までふざけまくってサビで大衆受けするメロディーやビートにすると言うのはよくあるのですが、この曲ではそう言ったことはしません。
ヤンキーがおばあちゃんに優しいムーブで好感度が上がるのがセオリーだとすると、この曲はヤンキーがおばあちゃんとブレイクダンスしてるみたいな感じです。笑
続きます、
努力未來a beautiful starなんか忘れちゃってんだぁ、でフォール気味で1番が終わって2番頭のベースリフに続きます。
ポイントはフォールしている所です。ほんとにそうか?みたいな歯切れの悪さを意図的に残しているものと思います。これが2番への契機になっています。この後しばらく1番と同じような展開が続きますが人生2周目みたいな落ち着きが感じられます。
しかし、やまない雨はないより先にその傘をくれよ、からの、あれがほしいこれが欲しい全てほしいただ虚しい、で尻上がりに展開をつけます。そしてオーケストラアレンジに急に変わります。これは何か人生論のような悟りを開いたふうな感覚がします。1番ラストのフォールがここで解決しているように感じます。
1番でしっちゃかめっちゃかなことをしてきたけども、1番ラストでとりあえずの結論は出します。でも何となく腑に落ちない感覚がモヤモヤとあって、でもここのオーケストラで何かがストンと落ちたような気にさせてくれます。藤本タツキ先生のチェンソーマンという作品への深いリスペクトを感じます。
ラッキーで埋め尽くしてー、からは手拍子っぽいビートの取り方に変わり、今までと違い音数を減らされており、芯のぶれない印象を受けます。
I love you貶してー、奪ってー、笑ってくれマイハニー、と続きます。
ここもフォール気味に歌われており不安な感じを予感させますが
努力未來a beautiful star,努力未來a beautiful star,努力未來a beautiful star
と3回目で強めの歌い方をしているところが悟りを開いた強さで跳ね返していく印象ですごく好きです。
またこの時コード進行がかなり特徴的でクリシェという低い音が少しずつ下がっていくコード進行が使われているのですが、これが12回連続で使われています。はい。ありえないです。笑
私が自作曲内でクリシェを使う時は4連続くらいで使います。これが普通なのです。流石です。笑
クリシェをうまく使えば何だか話がうまく解決しきれないと言うような浮遊感が生まれ次の展開や元の展開に戻りやすくなると言う特徴があります。また音の種類は12種類で構成されており、12回クリシェを使うと言うことは一周回って元に戻ると言うことになります。いろいろな困難を乗り越えて原点回帰という印象です。
続きます、
ハッピー、ラッキー、こんにちはベイベー、と続いて以降は1番で見かけたような展開であり安定した印象で曲が終わります。
以上になります。
めちゃくちゃ長くなっちゃいました。笑
この記事を作るにあたって改めて曲を何度か聞き直しましたが、やっぱり天才なんだなって思いましたし、生意気ですが自分もいつかこんな素晴らしいものが作れるようになりたいなとも思いました。
今回は触れませんでしたがチェンソーマンのアニメopバージョンもいいですよね。私は映画にあまり詳しくないのですがいろいろな映画のパロディが使われているようです。よければツイッター、インスタなどで教えて下さい。
リンク貼っときますね。笑
では長い間、お付き合いありがとうございました。
最後まで読んでいただいた方ありがとうございました。
インスタで読んだ本の紹介をしています。よければ覗いてくださいね。
インスタ
https://www.instagram.com/pede_book?igsh=dHBxMTJydDB3dzI5&utm_source=qr
X,Twitter
https://x.com/voazffzycs76271?s=21
TikTok
https://www.tiktok.com/@pede138?_t=8k4KOBDru9n&_r=1
YouTube
https://youtube.com/@pede207?si=Bvp7r9Bnerv4rVGZ
YouTubeサブ
https://youtube.com/@pede-io8wq?si=HTy8rmFO2X9M0BwP
ニコニコ動画
https://www.nicovideo.jp/user/130166470?ref=nicoiphone_other
日常ブログ
https://basumykino.wordpress.com
ホームページ
PeDe portfolio
https://pedevochomepage.my.canva.site/vocal-wtve
note
PeDe|note#ブログ、#TOEIC、#ボカロ、#日常、#ボカロp、#楽曲解説
- アーティストの意図やメッセージを紹介する視点から、楽曲解説を行う。楽曲に込められた思いや背景について詳しく説明し、読者に深い理解を提供する。
- 楽曲の魅力や特徴を紹介する視点から、楽曲解説を行う。独自の音楽要素やアーティストの特長に焦点を当て、読者に興味を引く情報を提供する。
- 歌詞やメロディーの意味を探る視点から、楽曲解説を行う。歌詞の隠喩や象徴的な表現、メロディーの伝える感情などについて解説し、読者に新たな視点を与える。
- 楽曲のジャンルやスタイルの変遷を追う視点から、楽曲解説を行う。その楽曲が属する音楽の流れや変化に焦点を当て、読者に音楽の歴史的背景を理解させる。
- 楽曲を取り巻く社会的な影響や現代のトレンドについて考察する視点から、楽曲解説を行う。楽曲が放つメッセージが社会や時代の状況とどのように関連しているのかを解説し、読者に洞察を与える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
